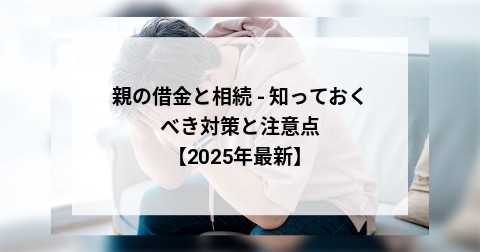相続放棄と限定承認の違いは?それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説
相続とは、人が亡くなったときに発生する財産や権利義務の承継を指します。
相続では、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの方法があり、相続財産の内容や相続人の事情に応じて有利な選択ができるようになっています。
どの方法を選択するかによって、相続人が負う責任や権利が変わってくるため、それぞれの違いをしっかりと理解しておくことが重要です。
本記事では、相続における「相続放棄」と「限定承認」という2つの選択肢について、それぞれの違いやメリット・デメリットなどを詳しく解説します。
|
■この記事を要約すると ・相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があるが、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続するか放棄するか、プラス財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐなどの違いがある。 ・限定承認は相続人全員で申請する必要があり、相続放棄に比べて手続きが複雑で、時間や費用もかかる。 ・限定承認と相続放棄は、いずれも3ヵ月という短い期間で財産を把握し、手続きをしなければならないため、早急に「プラスマイナスの財産を正確に把握すること」「相続人同士で話し合うこと」が重要 |
単純承認とは?
相続が生じたときに、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することを「単純承認」といいます。
預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナス財産も、すべてそのまま相続することになります。
自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月の間に何もしなければ、自動的に単純承認したことになります。法律で定められた一定の行為を行った場合も、単純承認とみなされるため注意が必要です。
相続放棄とは?
被相続人の財産を一切引き継がないという方法です。プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄することになり、被相続人の借金などの負債を支払う義務を負うことはありません。
相続放棄をするには、放棄する相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。相続放棄が認められると、最初から相続人ではなかったものとみなされます。
限定承認とは?
被相続人のプラス財産の範囲内で、マイナスの財産も引き継ぐという方法です。相続した財産で負債を支払える場合はその範囲内で返済すればよく、もし負債が相続財産を上回る場合は、超過分を支払う必要はありません。
限定承認をするには、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続人全員で合意し、家庭裁判所に限定承認申述書を提出する必要があります。限定承認は、相続財産の全体像が不明な場合や、負債を支払っても財産が残る可能性がある場合に有効な選択肢となります。
限定承認にするか、相続放棄にするか
相続放棄と限定承認は、どちらも被相続人の負債から身を守るための制度ですが、それぞれに適したケースがあります。相続人の置かれている状況や、被相続人の財産状況などを考慮し、どちらを選択するのが適切か判断する必要があります。
限定承認を選択すべきケース
どうしても相続したい財産がある場合
相続財産の中に自宅や思い出の品・家宝など、どうしても相続したい財産がある場合、限定承認を選択することで、その財産を相続できる可能性があります。
相続放棄を選択すべきケース
明らかに負債の方が多い場合
明らかに相続財産に負債の方が多い場合の選択肢ではあるのですが、債務の額が不明なときであっても、相続放棄をする期間を延長しすることで、延長期間内に精力的に遺産調査を行い、放棄か否かを決断することもできます。
被相続人や他の相続人と疎遠で関わりたくない
被相続人と長年連絡を取っていなかった、関係が良好でなかったなど、被相続人の財産状況をよく知らない場合、相続放棄を選択するケースがあります。
弁護士や司法書士の依頼など費用がかかることは避けたい
限定承認は、相続放棄に比べて手続きが複雑で、専門家への依頼が必要となるケースも多いため、費用がかかる可能性があります。手続きにかかる費用を抑えたい場合は、相続放棄という選択肢もあります。
限定承認のメリット・デメリット
メリット
負債を負わずに済む
限定承認ではプラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続します。プラスの財産を超えたマイナスの財産は相続する必要がありません。
そのため、相続財産調査で判明していなかった債務について、あとから請求がきたとしても、プラス財産の範囲内での清算とできるため、相続人が安心して選択できるのが大きなメリットです。
先買権の行使ができる
相続放棄を行った場合は、財産の中に自宅が含まれているとその自宅まで相続できなくなります。なので、マイナスの財産の方が多くても、自宅だけは相続したいという方も少なくありません。
このような場合には、限定承認を利用すると自宅などの必要な財産を残すことができます。
自宅や自社株など必要な財産だけ取得したい相続人は「先買権」という優先的に購入することができる権利を使用すれば、必要な財産のみ取得することができるのも限定承認のメリットです。
デメリット
相続人全員で、家庭裁判所に申述しなければならない
限定承認は、必ず相続人全員が家庭裁判所に申立をする必要があります。
全員の意見が一致しないと申立ができないという点は大きなデメリットです。相続人同士の仲が悪いときは、利用が難しくなります。
みなし譲渡所得税がかかる場合がある
みなし譲渡所得課税とは、土地などの資産を譲渡した場合、その資産を取得したときの価格から現在の価格への値上がり益に所得税が課されるといった制度です。
被相続人がある1000万円で取得した土地の時価が1500万円になっていたような場合に、限定承認をすると、差額の500万円は、みなし譲渡所得となり、所得税がかかることになります。
手続きが複雑で時間もかかる
限定承認の手続きは非常に複雑で、時間がかかります。まず、3か月の熟慮期間内に「遺産目録」などを作成し家庭裁判所に相続人全員で申述しないといけません。さらに家庭裁判所から限定承認が受理された後も、相続人の中から選任された相続財産管理人が限定承認した旨の公告を行う、法律にしたがって競売や債務の返済をする、などたくさんの手間がかかります。
相続放棄のメリット・デメリット
メリット
借金などのマイナスの遺産を引き継がなくてもよい
相続放棄は、特に亡くなった人が多額の借金を負っていた場合に効果的です。借金などの負債を一切相続せずに済むため、マイナスの財産を引き継ぐ事態を回避できます。
相続トラブルに関わらずに済む
遺産をめぐる親族間の争い、いわゆる「争族」に巻き込まれたくない場合にも、相続放棄が有力な選択肢となるでしょう。、相続に関わる揉め事や権利関係から離れられるのもメリットといえます。
相続に関連して親族間で揉め事が生じた場合、相続人でなくなれば一切関係なくなりますし、連絡自体も受けなくて済むようになります。
遺産分割の手間が省ける
遺産分割を行う際には、協議・合意書面の作成・名義変更手続きなどに多くの手間がかかります。協議不成立の場合は調停や審判など面倒なことにも対応したりする必要があります。
相続放棄をすればこれらの手続きに対応する必要がなくなり、相続手続きの手間が省けるという点もメリットです。
デメリット
すべての資産を相続できない
相続放棄をすると相続権が失われ、被相続人の資産や負債などは一切相続することができません。
欲しいと思っていた財産をもらえなくなるほか、資産額が負債額を上回っている資産超過の場合、経済的な損失となってしまう点には注意が必要です。
相続放棄すると撤回や取り消しはできない
相続放棄は、一度裁判所に申述書などを提出すると、原則として撤回できません。
ほかの相続人から「財産はない」と言われていたのに実はあった場合や、「勘違いして相続放棄してしまった」というような場合でも、撤回や取消ができないこともあります。
ただし例外的に、錯誤・詐欺・強迫によって相続放棄をした場合などには、相続放棄の申述を取り消すことが可能です。
全員が相続放棄したら相続財産管理人を選任しないといけないことがある
相続人が全員相続放棄したときに「相続不動産」が残っていたら注意が必要です。この場合、元の相続人(相続放棄した人)に不動産の「管理義務」が課されます。
相続財産の管理義務を免れるには、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てる必要があります。
相続財産管理人を選任する際に、引き継ぐべき被相続人の現金・預貯金がない場合や非常に少ない場合には、100万円程度の予納金が必要となるケースが多いです。
死亡保険金や死亡退職金の非課税枠が使えない
死亡保険金や死亡退職金は相続税の課税対象となりますが、相続税には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。
相続放棄をしても死亡保険金や死亡退職金を受け取ることはできるものの、上記の非課税枠が適用されません。
したがって、相続放棄することで多くの相続税がかかってしまうおそれがあります。
まとめ
限定承認は、相続財産のうち、故人のプラスの財産の限度で借金を引き継ぐという相続の方法です。
手続きが複雑で、ほとんど利用されていない相続方法ですが、場合によっては非常に役立ちます。
「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの相続方法をしっかりと確認し、あなたが相続人になったときにどれが一番合っている相続方法か見極めることが重要です。
限定承認の手続きは複雑ですので、借金がある相続が起きそうな場合は、財産目録を作り、財産(プラスの財産)と借金(マイナスの財産)をきちんと把握しておくことと、被相続人とこまめに意思疎通をしておくことをおすすめします。