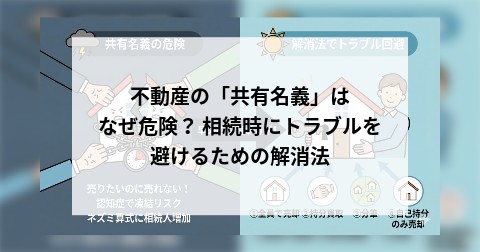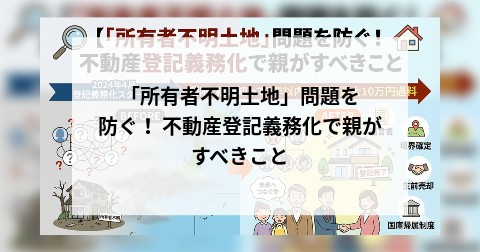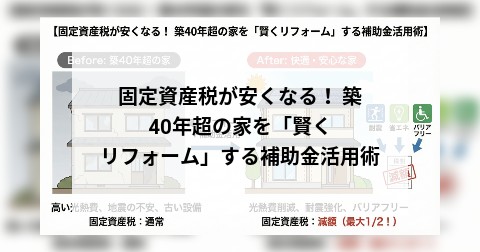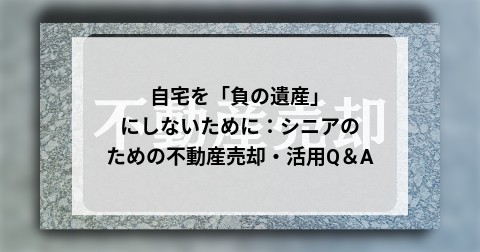不動産の生前贈与のメリット・デメリットとは?
自らが所有する不動産を、自身の生きている間に配偶者や子どもなどに贈与する「生前贈与」を検討されている方は多いと思います。土地や建物のような不動産の生前贈与を行えば、自分が希望する人物に土地や建物などの財産を渡せます。
今回は不動産の生前贈与に関するメリット・デメリットや費用・税金などの注意点をご紹介します。

|
■この記事を要約すると ・不動産を生前贈与することで相続税を抑えることができる可能性があるが、生前贈与のメリット・デメリットを正しく認識しておかないと節税どころか税額が増えてしまうため、贈与の仕組みや性質を十分に理解しておく必要がある。 ・不動産の登録免許税・不動産取得税の税率は意外と高いので予め理解しておく ・不動産の生前贈与では分割贈与にリスクがあったり、親子間でも贈与契約書を作成しておくなど注意点がいくつかあります。 |
不動産を生前贈与するメリット
・任意のタイミングで希望の相手に確実に不動産を継承できる
・控除等を活用することで、相続税の節税につながる場合がある。
・短期間で贈与が終えられる
・認知症対策になる
任意のタイミングで希望の相手に確実に不動産を継承できる
自分が所有している土地を任意のタイミングで配偶者や子どもなど自身の希望する相手に贈与できるのが大きなメリットの一つです。
例えば子どもが結婚してマイホームを建てたいと思ったとき、親が所有している土地を贈与することも可能です。
控除等を活用することで、相続税の節税につながる場合がある。
将来値上がりしそうな土地や家賃収入がある土地を生前贈与することで相続税を抑えることができる可能性があります。
例えば現在(贈与時)3,000万円の土地が、仮に30年後(相続時)には5,000万円になりそうと予測される場合、単純に相続税の課税対象となる財産の差額が2,000万円もあるため、少ないうちに早めに手放しておくという方法です
相続税と贈与税では税率が違うものの、他の財産額によっては値上がりした後に相続税を収めるより、今のうちに贈与して贈与税を支払ってしまった方が税金が安くなる可能性があります。
短期間で贈与が終えられる
不動産の生前贈与は比較的短期間で完了するのも、メリットのひとつです。
贈与者と受贈者が不動産の贈与契約を締結して、直ちに法務局で名義変更を行えば、1ヶ月以内に手続きを終えることも可能です。
相続となると、残された相続人は、土地以外の財産も含めて誰がどのくらい相続するのか(遺産分割)を確定させないと、土地の相続手続き自体ができません。
・認知症対策になる
認知症によって不動産所有者の判断能力が低下すると、基本的に不動産の売買や名義変更が本人ではできなくなります。このような状況を避けるためにも、不動産所有者である親に十分な判断能力があるうちに、贈与しておけば、万が一の際も受贈者が自由に扱えるので認知症対策としてもメリットはあります。
不動産を生前贈与するデメリット
・贈与税やその他の税金がかかる
・贈与後7年以内に贈与者が亡くなると相続税が発生する
贈与税やその他の税金がかかる
不動産を生前贈与すると相続税を節税できる一方で、登記費用や贈与税、不動産取得税などの金銭的負担が大きくなることがデメリットとして挙げられます。
贈与税は、年間110万円以内の贈与であれば発生しません。しかし、土地の価額が110万円以下ということは通常ないため、贈与税の大きな負担が発生すると考えられます。
贈与後7年以内に贈与者が亡くなると相続税が発生する
贈与から7年以上経過する前に贈与者が亡くなった場合、実質的にその資産の移譲は贈与ではなく相続であるとみなされ、相続税が発生します。これは暦年課税方式でも適用されます。
ただし、直系尊属から教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税分などについては、相続税の課税価格には加算されません。
不動産の生前贈与にかかる税金・費用と計算方法
不動産を生前贈与するうえで必ず把握しておきたいのが、贈与時にかかる税金です。生前贈与の際にかかる税金は不動産取得税、登録免許税、贈与税の3つです。それぞれの税金の内容と計算方法を見ていきましょう。
不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を入手した際に課せられる税金です。不動産取得税の計算方法は次のとおりです。
【不動産取得税=固定資産税評価額(不動産価格) × 税率】
|
土地 |
家屋 | |
| 住宅 | 住宅以外 | |
| 3% | 3% | 4% |
不動産取得税の計算は、固定資産税評価額に法定の税率をかける方法で算出します。土地については特例があり、宅地の場合、評価額を2分の1にして計算します。居住用不動産を贈与によって取得した場合、一定の条件を満たせばさらに軽減を受けられる可能性があります。
不動産取得税は地方税に該当するため、不動産の存在する都道府県に納付することになります。
都道府県により、別途税率などが規定されていることもありますので、購入の際は確認をしましょう。
登録免許税
登録免許税は、土地の名義変更の登記の際にかかります。税額の計算式は以下の通りです。
【登録免許税 = 固定資産税評価額 × 2%】
【例】
AさんはBさんから贈与された不動産(4,000万円)の名義変更を行うため、登記手続きを行った。
登録免許税=4,000万円×2%=80万円
贈与税
贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの間に贈与により取得した財産に対して課される税金ですが、その計算方法には暦年課税制度と相続時精算課税制度の2つがあります。
暦年課税制度
年間110万円以上の財産の贈与があった場合に贈与税が発生します。暦年課税の計算式は以下の通りです。
【贈与税=( 贈与額 -110万円 )× 税率 】
贈与税の税率は、贈与額から基礎控除の110万円を引いた残額の大きさに応じて変化します。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 200万円超400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円超600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円超1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,000万円超1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 3,000万円超4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
相続時精算課税
相続時精算課税では、1人の贈与者ごとに、贈与財産額の累計で2,500万円までの特別控除が設定されており、2,500万円を超えた贈与額部分にのみ贈与税が課されます。つまり、2,500万円までは贈与税が課されないということです。
これを使用すると、2,500万円を超えた分に関してのみ、一律で20%の贈与税がかかります。
ただし、相続時精算課税の対象になった贈与財産は、その財産を贈与した者が死亡した際、その贈与者の相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。これを「贈与財産の相続財産への持ち戻し」といいます。2,500万円の特別控除枠部分に贈与税は課されないのですが、代わりに相続税が課されることになるというわけです。
例えば、相続時精算課税を用いて父から子に2,500万円の不動産を贈与していた場合、贈与した年に、子に贈与税は課税されません。しかし、その後、父が死亡したときに、2,500万円が相続財産に加算され、相続税の課税対象とされます。
つまり、相続時精算課税を適用して贈与をしても、贈与税または相続税を単純に「節税」する効果は限定されることとなります。
土地を生前贈与する際の注意点
分割贈与のリスクを理解しておく
土地などの不動産は、所有権を分割して相手に一部だけ贈与することもできます。この手法により贈与税の基礎控除の110万円を超えない範囲で、毎年少しずつ不動産を贈与することもできます。しかし、まとまった額をあえて毎年110万円ずつに分けて贈与した場合、その合計額に贈与税がかかる可能性があります。
贈与後3年以内に贈与者が亡くなると相続税が発生
相続が発生した時、相続開始前3年以内におこなわれた生前贈与は相続財産に加算されるという制度があります。2024年1月1日からは、生前贈与加算の対象が相続開始前7年以内の贈与までと税制改正されました。生前贈与して間もなく亡くなった場合、相続対策として生前贈与したつもりでも、相続財産に加算されてしまいうことになりますので注意が必要です。
相続の場合は登録免許税の税率が異なる
不動産を贈与した場合の登録免許税が2%であるのに対し、相続で不動産を取得した場合は免税措置によって0.4%に減少します。
元々不動産が高額の資産であることを考慮すると、数%の差であっても金額としては大きな額になることを留意しておきましょう。
必ず贈与契約書を作成する
贈与は贈与者と受贈者双方の合意があって初めて成立します。それは親子間や家族間といった密接な関係であっても例外ではありません。
双方の合意があったことを公的に証明するためにも、親子間や家族間であっても必ず贈与契約書は作成しておきましょう。
不動産の生前贈与が向いているケース
将来の価値が確実に上がる土地
相続税と贈与税は、相続または贈与した時点のその不動産(資産)の価値を元に、納付すべき税額が算出されます。
したがって将来値上げが見込まれる不動産の場合、値上がり前に生前贈与により納付する贈与税の方が、将来納めるはずだった相続税より金額が安くなる可能性があります。
賃貸マンションなどの物件
家賃収入が入り続けると相続時の財産が増えてしまうため、賃貸マンションなどの物件は早めに贈与した方が相続税対策として有効です。特に中古マンションの場合は、贈与税や不動産取得税、登録免許税に軽減措置があるため、建物だけの贈与でも有効な相続税対策になります。
婚姻期間が20年以上の夫婦
婚姻期間が20年以上である夫婦の場合、「配偶者控除の特例制度」を適用できます。この特例を利用することで、自らが居住する住宅に関しては最高2,000万円まで贈与税を控除できます。
このとき年間110万円の基礎控除も適用されるので、合計で2,110万円までは贈与税が課せられないことになります。
まとめ
土地の生前贈与は、贈与税の制度や特例を活用し、タイミングを見極めて生前贈与を行うことで、結果的に将来の相続税の節税につながる場合があります。
ただし一般的には相続税より贈与税の方が高くなりやすい傾向にあるため、生前贈与を検討している際は、必ず専門家に相談してください。