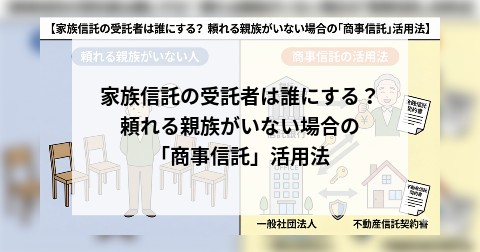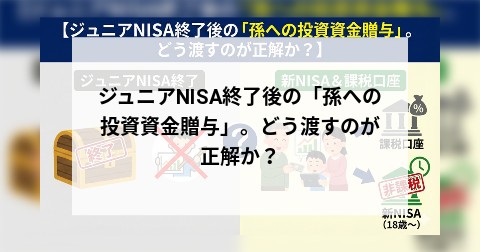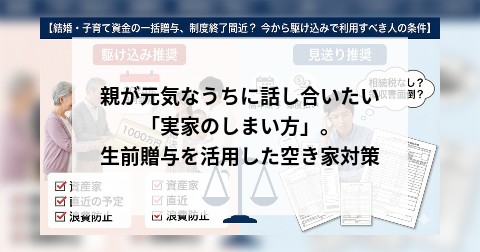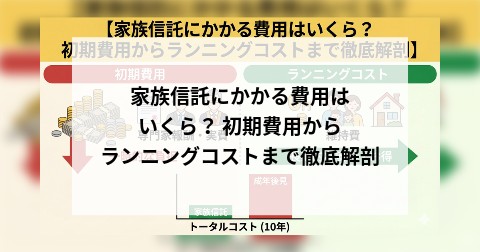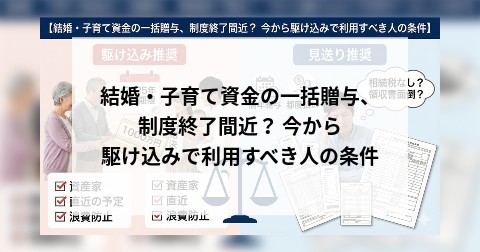家族信託はどこに相談するべき?依頼先の選び方や費用について解説
老後の認知症対策や相続対策として、「家族信託」を利用する方が増えています。
家族信託を扱う専門家には、弁護士、司法書士、行政書士、税理士などがいますが、どの専門家に依頼するのが適切なのでしょうか。
本記事では、家族信託の依頼先や費用等について詳しく解説します。
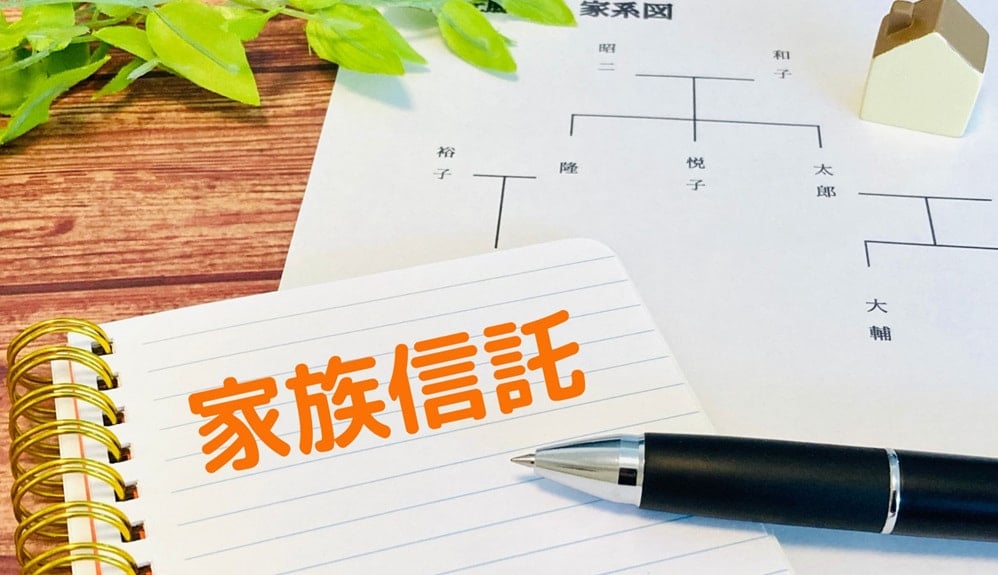
|
■この記事を要約すると ・家族信託の依頼先は一般的には司法書士に依頼することが多いが、安心感や費用・節税対策等に重点を置きたい場合などは弁護士や税理士などに相談する場合もある ・家族信託を専門家に依頼する場合の費用の相場はあるが、実際にかかる費用は専門家や依頼する業務の範囲によってばらつきがある ・家族信託を専門家に相談する内容としては家族信託の仕組みと自身の状況を共有し、契約の内容について意見をすりあわせるのが一般 |
家族信託とは家族に財産の管理や処分を委任する契約のことで、老後や認知症などの対策として注目を集めています。
家族信託をするには契約書の作成や不動産の登記などの手続きが必要で、知識のない方には難しいため、法律や税務の専門家に依頼するのが一般的です。
家族信託の手続きを依頼できる専門家は下記のとおりです。
家族信託の依頼先
・弁護士
・司法書士
・税理士
・行政書士
・信託銀行、不動産会社
弁護士|依頼内容に制限がない分費用が高い
弁護士は法律に関する依頼内容に制限を受けないため、多岐に渡る業務を行えるメリットがあります。
また、家族信託で絶対に必要となる信託契約は契約行為であるため、法律の専門家である弁護士に作成を依頼するのが安心です。
しかし、実際には家族信託専門の弁護士は少ないのが現状です。また、家族信託には登記手続きが必要になりますが、登記手続きに精通している弁護士は少ないのが現状です。
また、司法書士や行政書士などほかの法律の専門家に比べて、依頼料が高額になりやすい点も注意が必要です。
司法書士|家族信託の依頼先としては一般的
家族信託の手続きを依頼する専門家として、もっとも一般的といえるのは司法書士です。
司法書士の主な業務内容は登記や相続であり、家族信託の内容と一致する部分が多くあります。
家族信託の専門家といえるでしょう。
ただし、司法書士の場合は弁護士とは異なり、法律上の紛争解決の交渉はできません。また、司法書士は税務の専門家ではないため、相続税などの節税に関するアドバイスをもらうのは難しいです。
税理士|法律の専門家ではないため依頼できる範囲が狭い
税金や会計の専門家である税理士も、家族信託の依頼先としてメジャーな存在です。家族信託の対応ができる税理士もいますが、書類の作成や登記手続きなどに対応できる専門家ではありません。
相続対策についてのアドバイスを求めたい場合には税理士に相談するのが良いですが、家族信託では書類の作成や登記手続きなどを行う必要がありますので、法律の専門家である弁護士か司法書士と税理士を併用するのが良いでしょう。
行政書士|幅広い業務を依頼できるが登記の代理権はない
行政書士は官公庁に提出する書類や権利・義務を証明する書類など、多種多様な書類を作成する専門家です。
しかし、行政書士は提出書類の作成はできますが、登記の代理権がありません。
弁護士や司法書士より依頼料が比較的リーズナブルな点がありますが、登記の問題は司法書士などの専門家に相談し、登記手続きを代理してもらうことが望ましいでしょう。
信託銀行・不動産会社|弁護士や司法書士と連携している企業もある
信託銀行や不動産会社などで家族信託の手続きをしているところもあります。
たとえば不動産会社は不動産登記の業務を通じて、日常的に司法書士と連絡を取っているため、司法書士を紹介してもらえる可能性があります。
また信託銀行や不動産会社は、法律事務所よりは身近で相談しやすいと感じる方もいと思いますが、仲介料がかかってしまうため、専門家に直接依頼する方が費用が安く済む可能性が高いです。
家族信託を専門家に依頼する場合の費用相場一覧
| 専門家 | 主な業務範囲 | 費用相場 |
| 弁護士 | 信託契約書の作成 不動産登記 信託監督人 |
60万円~ |
| 司法書士 | 信託契約書の作成 不動産登記 信託監督人 |
40万円~ |
| 税理士 |
信託監督人 相続対策 |
40万円~ |
| 行政書士 | 信託契約書の作成 信託監督人 |
40万円~ |
| 信託銀行・不動産会社 |
信託契約書の作成 ※信託契約書の作成と登記手続きについては専門家に依頼する必要があります |
5万円~40万円 |
費用の内訳
費用の内訳例は下記のとおりです。
|
・コンサルティング報酬 |
依頼することが多ければ、その分費用も多くなります。とくに不動産登記は登記報酬と登録免許税がかかり、これだけで数十万円程度の費用になるでしょう。
家族信託の相談内容ごとのおすすめの相談先
弁護士|相続紛争が予想される場合
家族信託は特定の家族に財産の管理・処分を委託するため、選ばれなかった家族が不満を持つ可能性があります。
家族や親族関係が悪かったり関係性が希薄だったりするなど、家族信託についてトラブルになる可能性がある場合には、弁護士に依頼するといいでしょう。
司法書士|信託財産に不動産がある場合
信託財産にアパートやマンションなどの不動産が含まれている場合、司法書士に相談するとよいでしょう。
司法書士は不動産登記を代行する業務が認められており、登記についてもっとも知識・経験のある士業といえます。
弁護士でも不動産登記は資格によって認められていますが、司法書士の方が経験豊富な方が多いので安心できるでしょう。
税理士|相続税対策としての信託活用の場合
家族信託では、相続税などの税金も重要な要素となります。税金について疑問や不安がある場合、税のプロフェッショナルである税理士に相談しましょう。
節税に関する適切なアドバイスがもらえて、間接的に節税効果が得られる可能性があります。
家族信託を専門家に依頼してから開始するまでの流れ
家族信託の流れ
- 専門家を探して問い合わせ
- 相談・委任契約の締結
- 信託契約についての打ち合わせ
- 信託契約書の作成・信託契約の締結
- 信託登記・信託口口座の開設
- 受託者による管理・運用開始
専門家を探して問い合わせ
まずは司法書士・弁護士・税理士など、どの専門家に依頼するかを決めましょう。家族信託を取り扱っている専門家の事務所や相談所で面談の予約を入れます。
中には初回無料で相談できる場合もあるので、実際に話を聞きに行って決めるのがおすすめです。
相談・委任契約の締結
家族信託について30~60分ほどの面談を受け、希望する内容を伝えます。直接訪問して面談するほか、リモート面談を受け付けている事務所もありますので、自宅の近くに専門家がいない場合、リモート面談を利用するのも良いでしょう。
相談後に依頼することが決めれば、委任契約書を締結します。
信託契約についての打ち合わせ
家族信託契約の具体的な内容について、依頼した弁護士や司法書士と打ち合わせを行います。
委託者・受託者・受益者・信託財産などは基本的に相談者側で決めます。
信託契約書の作成・信託契約の締結
希望する家族信託の内容を伝えたら、専門家に契約書を作成してもらいます。基本的には家族構成や財産の状況などに応じて、家族信託の内容を設定していきます。
選んだプランに沿って、専門家が信託契約書の内容を作成します。契約書について家族での合意が取れたら、公正役場に出向いて公正証書として作成します。
信託登記・信託口口座の開設
信託財産は、個人の財産と分けて管理することが義務付けられています。そのため、家族信託専用の口座を開設する必要があります。なお、どの金融機関でも信託口口座を開設できるわけではないので注意しましょう。
受託者による管理・運用開始
信託契約の締結や各種事務処理が完了すると、家族信託の運用のスタートです。受託者は家族信託契約の内容に従い、財産の管理・処分を適切に行います。
専門家に相談できる内容とは?
信託契約について
家族信託の契約書には、「趣旨」や「目的」「委託者・受託者・受益者」「信託財産の管理方法」「終了時期」などについて記載します。
自身の考えを伝えた上で、専門家の視点からメリットやデメリットについてアドバイスを受けて、記載事項を決めていくのが基本です。
「判断能力を喪失する可能性がある」というトラブルも予測しながら、最終的な内容を決めていきましょう。
遺留分について
家族信託をするにあたって「遺留分」についても相談できます。遺留分とは相続で使われる用語で、兄弟姉妹以外の法定相続人の最低限の取り分です。
受益者が死亡して、信託受益権が別の人に引き継がれる際には、遺留分侵害額請求の対象になる可能性があります。
あらかじめ遺留分を侵害しないような信託契約を専門家と考えておくことで、後に起こるトラブルを防止できるでしょう。
まとめ
本記事では家族信託をどこに頼むのが適切かをはじめ、専門家に依頼した場合の特徴と費用について解説しました。
家族信託は自分ですることもできますが、法律・税務・相続などに関する幅広い知識が求められるため、一般の方が自力で行うのはハードルが高いです。
家族信託の実績を見て、相談先を決めましょう。また、相談先の士業が信託監督人となる場合もあるため、相談相手が信頼できる人物かどうかを判断することも重要なポイントとなります。