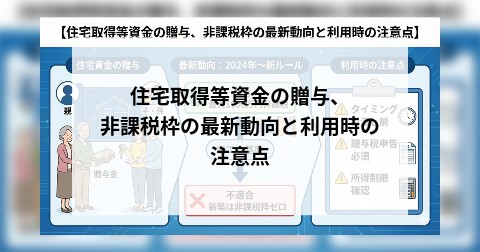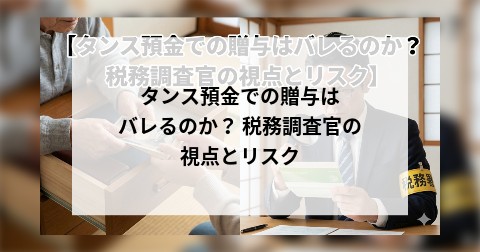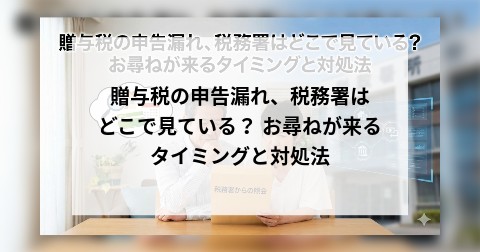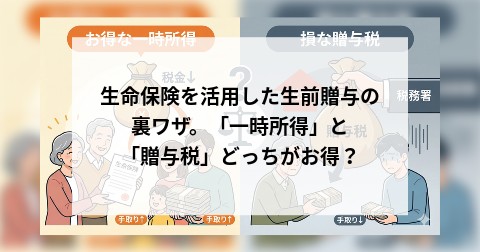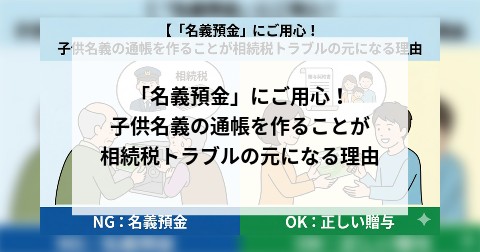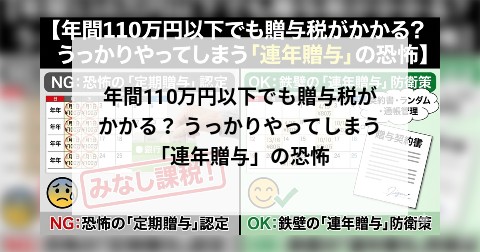贈与税とは何か?かからなくする方法は?非課税、配偶者控除
個人が財産を誰かに無償で渡す方法のことを「贈与」といいます。
贈与は親から子へ、祖父母から孫への資金援助や不動産譲渡などの場面に発生します。
このように贈与は自分の家族や大切な人に、自分の意思で自由に計画的に財産を渡すことができる渡し方です。
ところで誰かに無償で財産を渡すと「贈与税」という税金が課されます。ただし、贈与の仕組みを理解し、贈与に関する「非課税制度」を上手に活用することで、贈与税をかからなくしてくれます。
では、贈与税とは一体どんなものでしょうか。今回は、贈与税とは何か・贈与税をかからなくする7つの方法について徹底解説します。
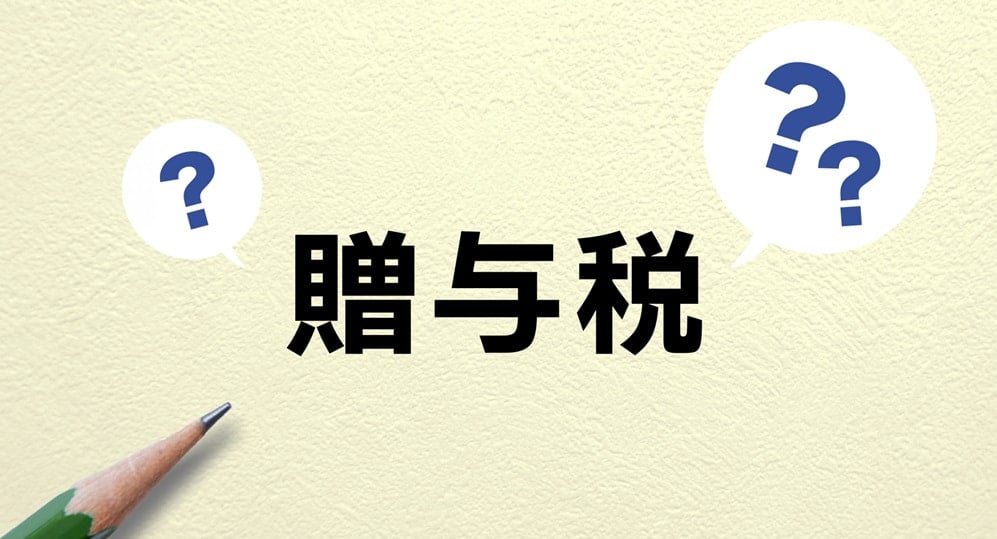
贈与税とは何か?
贈与税とは、誰かから無償で財産をもらった時に、もらった本人にかかる税金のことです。
この時、財産を渡す側のことを「贈与者(ぞうよしゃ)」、財産をもらう側のことを「受贈者(じゅぞうしゃ)」といいます。
贈与税は財産をもらう側の受贈者のみに課される税金です。
逆に財産を渡す側の贈与者はどれだけ財産を渡しても一切税金はかかりません。
贈与税の対象とは?
贈与税の対象は「個人のみ」です。贈与税は「個人から個人へ」の財産の移動の時にしか適用されません。
例をあげると、親から子へ、祖父母から孫へなどです。
ちなみに個人から法人への財産の移動があった場合には、もらった法人には「法人税」が、あげた側の個人も所得税や住民税の課税対象になります。
また逆に法人から個人への財産の移動があった場合には、もらった個人は「所得税」や「住民税」が、あげた側の法人は法人税の課税対象になります。
個人⇔法人への財産の移動は無償であっても、その財産を時価(有償)で渡したものとして考えます。そのため、取得費より時価が高ければ差額は利益とみなされ課税対象となります。
扶養義務者間の生活費・教育費の贈与は課税対象?
結論から言うと、配偶者や親子、兄弟姉妹など扶養義務者間で行った生活費・教育費の贈与には、贈与税がかかりません。具体的には以下の行為はすべて非課税になる可能性があります。
|
・子供への仕送り ・子供の教育費や学費 ・結婚式費用、出産費用、祝い金 |
一方で、受贈者が贈与財産で生活に不必要なものを購入した場合や高額すぎるものを購入した場合は、贈与税がかかる可能性がありますので注意しましょう。
現金の贈与の場合は税金はどうなる?
現金手渡しであっても、税務署から贈与事実を隠し通すことはほぼ不可能なので止めましょう。
税務署には強力な調査権限が与えられており、税務調査で必要と認められる場合、銀行口座をすべて調べることが可能です。通常、現金の贈与の場合、贈与の前に贈与者の口座から現金を引き出すことが考えらえます。
また、受贈者がその現金を口座に入金した場合にも銀行口座に記録が残ります。このようなことから現金手渡しでも課税対象となるので注意しましょう。
贈与税の課税対象期間と申告・納付期間
こちらでは「暦年課税制度」を利用した場合の贈与税の課税対象期間と申告・納付期間についてご紹介します。
①贈与税の課税対象期間
贈与が発生した年の1月1日から12月31日までの1年間が課税対象期間になります。
例をあげると、令和7年の5月7日に親から子へ200万円の贈与があった時です。
贈与が発生した時に、特に何も手続きをしなければ「暦年課税制度」が自動的に適用されます。
②贈与税の申告・納付期間
贈与が発生した翌年の2月1日から3月15日までが贈与税の申告と納付の期間になります。
例をあげると、令和7年の5月7日に親から子へ200万円の贈与があった場合、翌年の令和8年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告と納付をする必要があります。
贈与税の基礎控除額は110万円
贈与税の基礎控除とは、財産をもらった側が使える「非課税制度」のことです。贈与税は、贈与された財産の全額にそのまま課税されるわけではありません。
基礎控除として1人年間「110万円」を、贈与された財産の全額から無条件で差し引くことができます。
例をあげると、令和7年の5月7日に親から子へ200万円の贈与があった場合、200万円から基礎控除額「110万円」が差し引かれ、残額の「90万円」に対して贈与税が課せられます。
簡単にまとめると、次の通りです。
|
・贈与税は1年間の贈与全額の110万円を超えた額に対して課税される 1年間の合計贈与額 < 110万円 = 贈与税がかからない 1年間の合計贈与額 ≧ 110万円 = 贈与税がかかる |
※1人の受贈者が110万円を超えた場合には贈与税がかかりますが、仮に何人からもらっても合計110万円を超えなければ贈与税はかかりません。
贈与税をかからなくする7つの方法とは?
財産の贈与はもらった方にとっては嬉しいことです。ただし財産の贈与が行われると贈与税が課せられます。
できれば贈与税がかからなくしたり、安くすませたりしたいのは誰しも思うところだと思います。
こちらでは贈与税をかからなくする7つの方法について徹底解説します。
①暦年課税制度の基礎控除
暦年課税制度の基礎控除とは、1年間の贈与の合計が110万円以下なら贈与税がかからない制度のことです。
暦年とは1月1日から12月31日までの1年間という意味のことです。
財産をもらった1人に対し、1年ごとに基礎控除「110万円」が控除されます。
贈与税の申告をすると、自動的に「暦年課税制度」が適用され、基礎控除が差し引かれる仕組みです。
例をあげると、令和7年の5月7日父から子へ100万円の贈与があり、同年の6月7日母から子へ100万円の贈与があった場合、子は令和7年に合計200万円の贈与を受けたことになります。すると、贈与合計200万円から基礎控除の「110万円」を差し引かれ、残額の90万円に贈与税が課されます。
基礎控除は毎年リセットされるので、毎年使うことが可能です。
ただし、相続発生前7年間の間に受けた贈与については、相続財産に加算して(持ち戻し)相続税の計算をしなければなりませんので注意してください。もし、贈与を受けた際に払った贈与税がある場合は、相続税から相殺することができます。
②相続時精算課税制度の活用
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母、祖父母(直系尊属)から18歳以上の子や孫に贈与を行う際、贈与者ごとの贈与額が合計2,500万円まで贈与税を一旦保留するという制度です。合計贈与額が2,500万円を超えると、超えた分に一律20%課税されます。
課税を保留しているだけなので、贈与者が死亡した際(相続発生時)に相続税として精算します。もし、既に贈与額が2,500万円を超えていて贈与税を払っている場合は、相続税の計算時に相殺できます。
相続時精算課税制度の1つ目のメリットは、相続時に加算する価額が贈与時の価額であることです。
たとえば、贈与時に300万円だった有価証券が、相続発生時に500万円となっていたとしても課税価額は300万円のままです。つまり、不動産など将来的に価値が上がると予想される財産を相続時精算課税制度を利用して生前贈与しておけば、相続税の減額ができるのです。
2つ目のメリットは、2024年から2,500万円とは別枠で毎年110万円の基礎控除額が設けられたことです。しかも、相続前7年間の持ち戻し制度はありませんので毎年110万円以下継続贈与を行えば無税で資産の移転が可能です。
相続時精算課税制度を利用する場合は、税務署へ「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要ですが、110万円の基礎控除額が設けられたことで、暦年贈与より有利な制度となりました。ただし、一度この届出を行うと暦年贈与へ戻ることはできません。
③夫婦間贈与の配偶者控除
夫婦間贈与の配偶者控除とは、婚姻期間20年以上の夫婦間でマイホーム(居住用不動産)または、マイホームの購入資金の贈与に対して一定額まで贈与税がかからないというものです。
通称「おしどり贈与」といいます。
「最大2,000万円の配偶者控除」「110万円の基礎控除」の合計2,110万円の控除を受けることができます。この控除は同じ配偶者間においては一生に一度しか受けられません。また、この適用を受けるためには必ず申告が必要です。
④住宅取得等資金の非課税制度
住宅取得等資金の非課税制度とは、子や孫が住むための家の購入、増改資金に贈与税がかからない制度のことです。
適用要件は両親や祖父母から子や孫への贈与であり、贈与を受ける子や孫の年齢が18歳以上で合計所得金額が2,000万円以下(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合1,000万円以下)であることです。
省エネ住宅なら1,000万円まで、一般住宅なら500万円までの控除が受けられます。
適用期限は令和8年12月31日です。
⑤教育資金の非課税制度
教育資金の非課税制度とは、祖父母が孫の教育資金を一括贈与する場合に贈与税がかからない制度のことです。贈与を受ける人の年齢が30歳未満で合計所得が1,000万円以下であることが条件です。
1,500万円まで非課税で贈与が可能です。適用期限は令和8年3月31日です。
⑥結婚や子育て資金の非課税制度
結婚や子育ての非課税制度とは、両親や祖父母が子や孫の結婚・子育て資金を一括で贈与する制度のことです。
贈与を受ける人の年齢は18歳以上50歳未満であり、合計所得額は1,000万円以下であることが条件です。
1,000万円(うち結婚関係300万円)までの贈与が非課税です。
適用期限は令和9年3月31日です。
⑦贈与税の障害者控除
障害者に対する非課税制度とは、子や孫が障害者の場合に一定額まで贈与税がかからない制度のことです。
親族が委託者となり、信託銀行等と信託契約を結び、贈与を受ける人(障害のある方)を受益者に指定します。受益者は信託契約に定められた方法で、信託銀行から定期的に金銭を受け取ります。
贈与人が亡くなった後も信託銀行等が財産を管理しているので継続的に障害のある方へ贈与資金を渡すことができる制度です。特別障害者は6,000万円まで、特別障害者以外の方は最大3,000万円までの控除を受けられます。
まとめ
今回は、贈与税とは何か・贈与税をかからなくする7つの方法について解説しました。
贈与税を上手に回避するには「贈与税の7つの非課税制度」の活用を検討してみましょう。
利用しやすいのは暦年贈与ですが、相続前7年間分の贈与額を相続財産に加算しなければならないことに注意が必要です。その点、110万円の基礎控除を活用した贈与なら届出という手間はありますが、相続時精算課税制度のほうが持ち戻しの必要がないため利便性は高いかもしれません。
住宅資金贈与、結婚子育て資金贈与、教育資金贈与の非課税措置は適用期限があります。今後、延長される可能性もありますが、利用の際には最新の情報を得るようにしてください
贈与税の負担を軽減しつつ、計画的に財産を渡したい場合には、ぜひ今回ご紹介した7つの方法を活用してみることをおすすめします。
それにより大切な人に賢く財産を届けることができることでしょう。