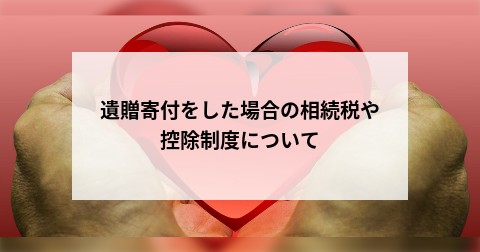新しい社会貢献「遺贈寄付」とは? 遺贈寄付を考えるときに覚えておきたい注意点まとめ
慈善団体やNPO団体に遺産を譲る行為は遺贈寄付と呼ばれ、近年新しい社会貢献の一つとして注目が集まっています。
今回はそんな遺贈寄付について、特に気をつけたい点に絞ってお話をしていきたいと思います。

「遺贈寄付」とは
遺贈寄付の話をする前に、まず遺贈について確認をしておきましょう。
遺贈とは、遺言によって民法で決められた相続人以外の人や団体に遺産の一部または全部を無償で譲る行為をいいます。
その中でも、慈善団体やNPO団体など社会貢献につながる活動に遺産を譲る行為が遺贈寄付です。
遺産を譲ると聞くと、相続と何が違うのかと思われる方も多いと思いますので、両者を比較してみましょう。
相続は、民法で定められた相続人(法定相続人)のみが遺産を引き継ぎます。
一方で、遺贈寄付は自らの意志で選んだ団体への寄付となるため、両者の性格は大きく異なります。
遺贈寄付の種類
遺贈寄付には大きく分けて「特定遺贈」と「包括遺贈」という2つの種類があります。
特定遺贈
特定遺贈とは、遺贈する財産を具体的に明示して行う方法です。
たとえば、「現金100万円を○○団体へ」や「自宅を××団体へ」というように、具体的な財産を遺贈の対象とするやり方です。
当然ですが、受け取る団体側から見れば、亡くなられた方(被相続人)が指定した以外の遺産は受け取る権利はありません。
また、仮に被相続人にマイナスの資産(負債)があった場合でも、受け取る団体はそれを考慮する必要がなく、指定された財産だけを受け取ればよい(負債を引き継ぐことがない)というメリットがあります。
包括遺贈
包括遺贈とは、被相続人の財産を包括的に遺贈する方法です。
包括的とはどういう意味でしょう。
たとえば、「全財産をAさんへ」や「B団体とC団体で全財産を1/2ずつ」のように、具体的な財産を指定せず、割合のみを示す方法です。
この場合、受け取る側は現金・不動産など具体的に財産が指定されていないため、すべての財産の評価額を算出したうえで指定された割合を受け取ることになります。
また、ここで言う「財産」には現金などのプラスの財産以外に、負債などマイナスの財産も含まれることが大きなポイントになります。
つまり、先ほどの「全財産をAさんへ」という例では、もし被相続人に負債があった場合、その負債も一緒にAさんが引き継ぐことになるのです。
この点から発生する注意点については後ほど詳しくお話します。
遺贈寄付のメリット
遺贈方法について理解が深まったところで、次に遺贈寄付のメリットについてみていきましょう。
遺贈寄付の最大のメリットは、なんといっても財産の行く先を自分の意思で決められる点です。
相続では、先に述べたように基本的には法律で定められた相続人にしか財産を遺せないという制約があります。
しかし、遺贈寄付では自分が遺産を譲りたい先を自由に決められます。
自分の想いを自由に未来の社会へ託せるので、遺贈寄付は最後の社会貢献とも呼ばれています。
遺贈寄付のデメリット
寄付のデメリットとして、寄付団体と相続人との間でトラブルが発生するリスクが挙げられます。
遺贈寄付は、被相続人にとってはご自身の想いを自由に団体へ託せる一方で、相続人から見ると引き継ぐ財産が少なくなってしまうことでもあります。
そのため、相続人から十分な理解を得られないリスクをはらんでいると言えます
特に、遺留分といって特定の相続人には法律で認められた割合で遺産を受け取る権利があり、遺留分を侵害した内容ではトラブルへ発展する可能性があることは覚えておきたいところです。
この点は後ほど詳しく解説します。
遺言作成時の注意点
デメリットでも見たように、遺贈寄付には注意すべき点がいくつかあります。
ここでは遺言作成時に注意しておくべき点をまとめて解説します。
作成にはルールがある
遺言を残すことは民法で規定された法律行為に該当します。そのため、遺言が効果を持つために厳格なルールが定められています(民法第960条)。
ルールに則って書かれていない遺言は無効となり、最初からなかったものとして相続が行われてしまいます。
せっかくの想いがかなえられない事態を避けるためには、作成の際に相続や遺言寄付の知識と経験を持った信頼できる士業(弁護士や司法書士など)への相談がとても大切になってきます。
寄付先団体はすべての遺贈が受け取れるとは限らない
ルールに従って作成された遺言であっても、寄付先の団体が受け取れない場合というのもあります。
「どうしてそんなことが?」と不思議に思われる方が多いでしょうが、それは団体それぞれの事情が要因です。
たとえば、団体によっては不動産の遺贈寄付を受け付けていないところもあります。
その主な理由は、不動産を受け取った後に現金化できないリスクを団体が抱えることになるからです。
都心の一等地とは違い、地方の土地や田んぼ、畑などは処分できずに困っているという話はよく聞きますよね。
こうした処分性が低い不動産が遺贈の対象だった場合で、もし買い手が見つからなければ、受け取った団体は未来永劫保有をし、固定資産税や維持費用などをずっと負担し続けることになります。
規模が大きく財務的な体力がある団体であれば大きな問題ではないでしょうが、地域に根差した草の根活動をする団体などでは負担が大きくなり、もしかすると本来の活動自体にも支障が出るかもしれません。
そのため、多くの団体が不動産寄付の受入には慎重になるのです。また、同じように包括遺贈を受け付けていない団体も多くあります。
包括遺贈のリスクとして、寄付を受けた団体が負債を引き継ぐ可能性がある点は先に述べた通りです。
寄付を受け取った後に負債が判明し、逆に団体が負債を抱えてしまうリスクがゼロとは言えない以上、慎重にならざるを得ないという事情も理解できますね。
このように、遺贈寄付を行う場合には団体の受入状況についても把握しておくことが重要です。
活動内容や理念に共感を持って寄付先を決められる方が多いと思いますが、事前に遺贈寄付をしたい旨を団体側にも伝えて、自分の遺産がちゃんと届くのかを確認しておきましょう。
寄付先団体と事前にコミュニケーションを取っておけば、スムーズに遺言通りの寄付が実現できますし、何より団体側にとっても大きな喜びになることは間違いないでしょう。
相続人には一定の財産を受け取る権利がある
最後の注意点としては遺留分です。
デメリットの部分でも触れましたが、特定の相続人には一定の割合で財産を相続する権利があります。
なお、特定の相続人とは配偶者や子ども(条件付きで孫)、または父母を指し、兄弟姉妹に遺留分は認められていません。
たとえば、遺言が財産のほぼすべてを遺贈寄付するという内容だった場合、遺贈寄付後に残る遺産が相続人の遺留分を下回ることが考えられます。この状態を遺留分侵害と呼びます。
遺留分侵害が起きると、相続人は寄付先団体に対して侵害された金額分の返還を求めることができます(遺留分侵害額請求)。
この請求は必須ではなく、相続人が侵害された遺留分を取り戻したいと考えたときに請求ができるとされています。
逆に言えば、相続人が納得してくれれば遺留分侵害が起きている状態でも寄付先団体は遺贈寄付された全額を受け取ることは可能です。
遺留分侵害額請求は法律上の相続人の権利で、一般的には家庭裁判所での手続きを経て、寄付先団体が相続人に対して侵害額を現金で支払うという流れをたどります。
このように遺留分侵害が起きると、寄付先団体も相続人にも相応の負担が発生する可能性があります。
こうした点においても遺贈寄付では作成時に法律などの専門的知識が不可欠で、確実に想いを実現するには、経験豊富な士業への相談と、相続人・寄付先団体との丁寧なコミュニケーションが必要と言えるでしょう。
人生最後の社会貢献で失敗しないために
遺贈寄付は自らの想いを込めて未来に夢を託せる魅力的な制度です。
また人生の集大成としての最後の社会貢献とも言われています。
そんな遺贈寄付にとって、確実に想いが実現できるようにしっかりとした準備がとても重要ということが、ここまでお読みくださった方ならご理解いただけたのではないでしょうか。
遺言を残すと聞くと、自分のこれまでの人生を振り返り、自分一人で決着をつけるものと思われている方が多いですが、信頼できるパートナーを見つけることが遺贈寄付で失敗しないために最も重要なのではないでしょうか。
まだ遺贈寄付をしようと決めていない方でも、少しでも興味があるのであればまずは相談してみてはいかがでしょうか。
この記事の監修者
寺林 智栄(てらばやし ともえ)
2007年弁護士登録。2013年頃より法律記事のライティングを始める。相続問題に関する記事を多数執筆している。弁護士としても相続はじめ家事事件の受任多数。