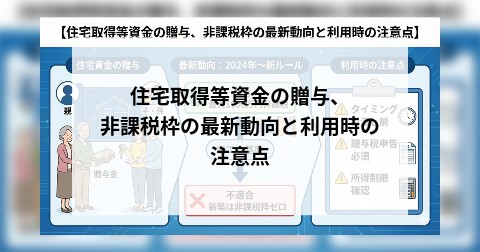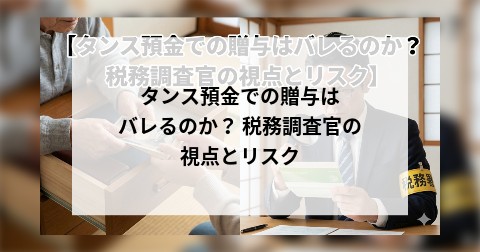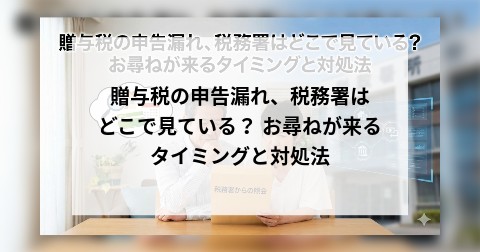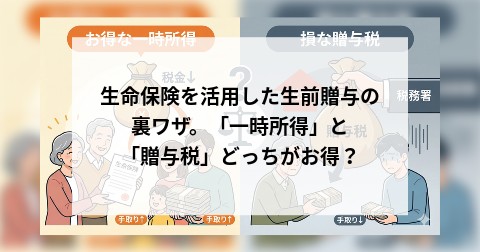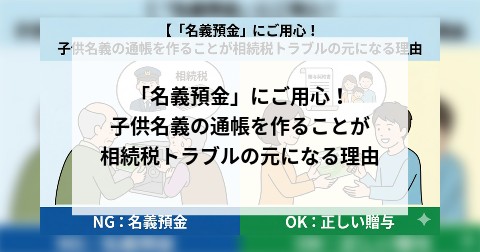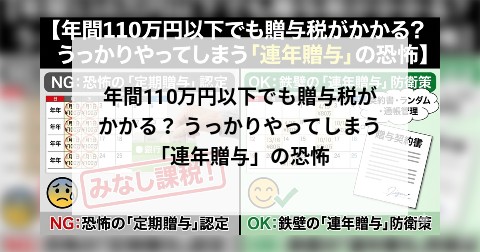遺贈寄付をした場合の相続税や控除制度について
財産を自身が亡くなられた後に寄付することを遺贈寄付といいます。
遺贈寄付をした際に相続税に与える影響や、税金の控除制度、非課税になる場合について解説します。
また、遺贈寄付をする際の注意点についても併せて解説いたします。

遺贈寄付の種類
遺贈寄付は「遺言による寄付」と「相続財産による寄付」の2種類をいうことがあり、課税関係がそれぞれ異なります。
2つの寄付について、課税関係の違いについて解説します。
遺言による寄付
遺言による寄付の場合、寄付したい財産や寄付先を遺言書に明記することで、寄付の手続きが行われます。
遺言による寄付のメリットとして、生前に財産の移動なしで、自分の意思で寄付する財産や寄付先を決められる点があります。
寄付先がNPO団体などの法人の場合、その寄付が相続税を不当に減少させるために行われた行為とされない限り、相続税はかかりません。
一方で、寄付先が個人や、法人格を持っていない団体の場合、相続税がかかります。ただし、その団体などが公益的な事業を行っている場合は相続税がかからない場合があります。
また、遺言による寄付では、遺産全体について割合を指定して遺贈する「包括遺贈」と、具体的な財産を個別に指定して遺贈する「特定遺贈」の2種類があります。
資産だけでなく負債も残して亡くなった場合、包括遺贈では負債も遺贈する財産に含まれてしまうため、注意が必要です。
このことから包括遺贈を受け付けていない団体もあるため、寄付したい特定の団体がある場合、寄付先へ確認するようにしましょう。
相続財産による寄付
相続財産による寄付では、相続人がいったん財産を取得して寄付を行うため、本来は相続人に相続税が課せられます。
ただし、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に国、地方公共団体、特定の公益法人に寄付した場合は、その財産については相続税がかかりません。
特定の公益法人とは、独立行政法人、一定の学校法人、公益社団・財団法人、社会福祉法人、認定NPO法人などです。
一般社団・財団法人、認定を受けていないNPO法人、宗教法人などは対象外です。
この非課税措置を受ける場合、相続人は相続税申告書にこの適用を受ける旨を記載し、所定の書類を申告書に添付する必要があります。
相続財産を相続人が寄付すると、寄付先が国や地方公共団体、特定の公益法人などの場合、相続人の所得税の確定申告において寄付金控除を受けることができ、税制上のメリットがあります。
所得税の寄付金控除は、寄付先により所得控除と税額控除のどちらか有利な方を選べますが、寄付金控除を受けるためにはその事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。
税額控除の場合、政党等寄付金、認定NPO法人等寄付金、公益社団法人等寄付金によって計算方法が異なり、控除される割合も異なります。
寄付先がどの団体に当てはまるかを確認するようにしましょう。
所得控除は所得から一定の額を控除し、その後に税率を乗じて税額を算定します。
一方で、税額控除の場合、算定された税額から直接控除します。
税額から直接控除する分、税額控除の方が有利になると思われがちですが、
必ずしも税額控除の方が有利になるわけではないため、厳密にどちらが有利かを知りたい場合は両方の方法で計算して比較をする必要があります。
遺贈寄付による控除
遺言寄付による場合、税金計算において一定の控除が受けられます。
各控除の概要及び、計算方法などについて解説します。
準確定申告における控除
準確定申告とは、亡くなった方の所得税申告です。
年の途中で亡くなった方に関し、相続人はその年の1月1日から死亡した日までの所得について税額を計算し、申告が必要な場合は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告及び納税します。
現金以外の財産を相続した相続人は、この所得税と相続税を納めるためのお金を別途用意する必要があるため、準確定申告による税金が多いと相続人が用意する必要がある現金も多くなり、負担が増します。
遺言書により国や地方公共団体、特定の公益法人などに対し寄付を行った場合、準確定申告において寄付金控除が受けられます。
ただし、遺言書に遺贈の旨を記載していたとしても、遺贈先の団体がその財産を取得したくない場合、遺贈の放棄により断ることができます。
遺贈が放棄された場合、対象となる財産は未分割財産となり、相続人がその財産を相続し、相続税の課税対象になります。
準確定申告における寄付金控除も受けられなくなるため、事前に遺贈したい先に相談し、財産を受け入れてもらえるか確認することで、こうした事態が起こる可能性を下げられます。
相続財産の寄付における控除
相続税は遺産総額から基礎控除額を引いた額に対して課税されます。
基礎控除額の計算式は下記になります。
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
遺贈寄付をした場合、基礎控除額に加え、寄付をした金額分を控除できます。
例えば遺産総額が2億円、相続人が妻と子供1人、遺贈寄付を3,000万円したと仮定して、遺贈寄付をしない場合とした場合で比較してみます。
遺贈寄付をしない場合
遺産総額:2億円
基礎控除額:3,000万円+600万円×2=4,200万円
課税遺産総額2億円-4,200万円=1億5,800万円
課税対象額:妻1億5,800万円÷2=7,900万円、子供1億5,800万円÷2=7,900万円
相続税額:妻7,900万円×30%-700万円=1,670万円(配偶者の税額軽減により0円)、子供7,900万円×30%-700万円=1,670万円
相続税の合計額:0円+1,670万円=1,670万円
遺贈寄付をした場合
遺産総額:2億円
基礎控除額:3,000万円+600万円×2=4,200万円
遺贈寄付:3,000万円
課税遺産総額2億円-4,200万円-3,000万円=1億2,800万円
課税対象額:妻1億2,800万円÷2=6,400万円、子供1億2,800万円÷2=6,400万円
相続税額:妻6,400万円×30%-700万円=1,220万円(配偶者の税額軽減により0円)、子供6,400万円×30%-700万円=1,220万円
相続税の合計額:0円+1,220万円=1,220万円
このように、遺贈寄付をすることで寄付金に対する相続税相当額が減ることになります。
遺贈寄付の注意点
遺贈寄付をする際には、受け取る側の都合や、遺贈寄付を受け入れてもらえる団体かを考慮する必要があります。
遺贈を放棄されてしまうと遺贈寄付自体ができなくなるため、生前に相手側に確認を取るようにしましょう。
その他、遺贈寄付をする際の注意点を解説します。
相続税が課されない寄付先
遺贈寄付をした財産は、相続税が課税される財産から除かれ、相続税が課されません。
ただし、遺贈寄付をする際に相続税が課されない寄付先かを確認する必要があります。
原則として、国や地方公共団体、法人に対しては相続税が課されません。
ただし、遺言によって行った「持分の定めのない法人」への寄付が、相続税を不当に減少させるために行われた行為とみなされる場合は相続税が課されます。
持分の定めのない法人とは、一般社団・財団法人、社会福祉法人、持分の定めのない医療法人、学校法人、宗教法人、NPO法人などです。
また、個人や、PTAや町内会などの人格を持っていない任意団体への寄付の場合は相続税がかかります。
ただし、その場合でも公益的な事業を行っている団体の場合は相続税がかかりません。
不動産等を寄付する場合の含み益
法人に不動産等を寄付する場合に、その財産が値上がりしており含み益が生じていると、含み益分に対して譲渡所得として、譲渡した方に所得税が課税されます。
この制度を「みなし譲渡」といいます。
例えば1億円で取得した土地が値上がりして時価1億5,000万円になっており、その土地をNPO法人に寄付したとすると、時価と取得価格の差額5,000万円に対して所得税がかかり、準確定申告において納める税金が増加します。
そのため、特に取得してから長い年月が経過している土地などを遺贈寄付しようと考える場合は、時価を確認する必要があります。
まとめ
遺贈寄付には、あらかじめ遺言で対象財産や寄付先を指定しておく方法と、相続した財産を相続人が寄付する方法の2種類があり、遺贈寄付を行うと税制上のメリットがあります。
ただし、相続税がかからない寄付対象は原則として国や地方公共団体、特定の公益法人であること、相続税を不当に減少させるために行われた行為とみなされる場合は相続税が課されることがあります。
寄付という本来の目的がスムーズにできるよう、課税関係や財産の受け入れの可否などを、あらかじめ寄付先に確認することが大事になってきます。
この記事の監修者
濵川 誠司(濵川誠司税理士事務所)
資格:税理士
出身地:愛知県
経歴:税理士法人、コンサルティング会社での税務担当業務(相続税、贈与税、事業承継、法人・個人事業主の事業サポート)
得意分野:相続税
趣味:ドライブ