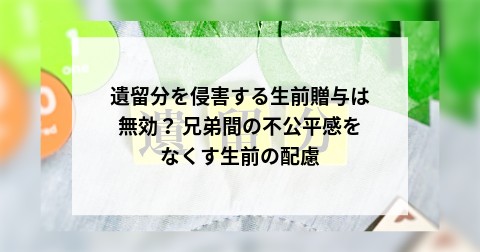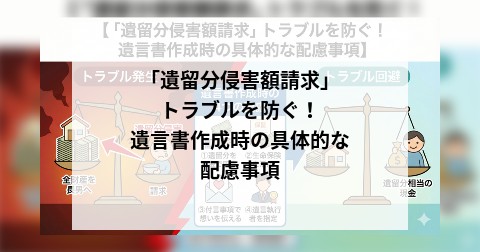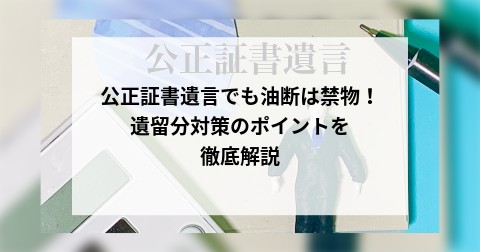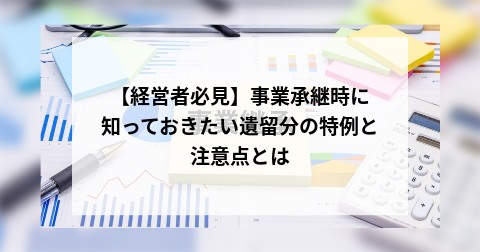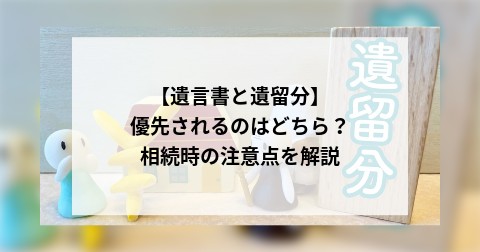相続の遺留分とは何か?家族間のトラブルを避ける方法とは?
相続に関するトラブルは、家族間で深刻な対立を引き起こすことがあります。その中でも「遺留分」は、相続人が最低限の財産を受け取る権利として保障する制度で、重要な役割を持っていますが、これがトラブルの原因となることが少なくありません。
本記事では、遺留分の基本的な考え方や計算方法、遺留分を巡るトラブルの防ぎ方について詳しく解説します。円満な相続を実現するための具体的な対策についても紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
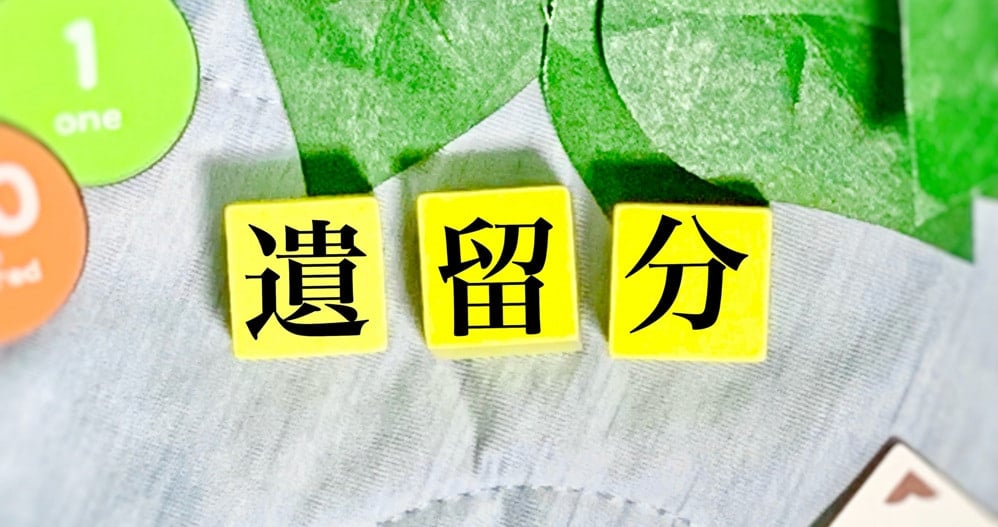
遺留分とは?基本的な考え方
相続において「遺留分」とは、一定の相続人が最低限受け取る権利を持つ財産の割合を指します。これは、相続人の生活保障や財産の公平な分配を目的として民法で定められている制度です。
被相続人(亡くなった人)は遺言によって自由に財産を配分することは可能ですが、特定の相続人に全財産を譲るなどした場合、他の法定相続人がまったく財産を受け取れなくなる可能性があります。
このような事態を防ぐために、一定の相続人には最低限の取り分が確保される仕組みとして「遺留分」が設けられています。
遺留分が発生するケース
遺留分が問題になるケースとして、以下のような状況が挙げられます。
・被相続人が遺言書で全財産を特定の相続人に与えると指定した場合
・相続財産が特定の相続人へ偏った配分になっている場合
・生前贈与が行われ、残された相続人の取り分が極端に少なくなった場合
これらのケースでは、遺留分を主張することで最低限の財産を確保できます。
遺留分の計算方法と割合
遺留分は、配偶者・直系尊属(父母・祖父母)・直系卑属(子・孫)に認められる権利です。遺留分の割合は、相続人の関係によって以下のように定められています。
直系尊属(父母など)が相続人の場合:遺産全体の1/3
上記以外(配偶者・子など)が相続人の場合:遺産全体の1/2
なお、兄弟姉妹、甥姪に遺留分はありません。
複数の相続人がいる場合、全体の遺留分割合に各相続人の法定相続分を乗じて個別の遺留分を算出します。遺産が3,000万円の場合の具体例でみていきましょう。
【具体例】遺産3,000万円の場合
①配偶者と子供2人が相続人
遺留分の合計:3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
配偶者の遺留分:1,500万円× 1/2 = 750万円
各子供の遺留分:1,500万円 ×1/2×1/2 = 375万円(子供2人で合計750万円)
②配偶者のみが相続人
遺留分の合計:3,000万円×1/2=1,500円
配偶者の遺留分:1,500万円
③両親が相続人
遺留分の合計:3,000万円×1/3=1,000万円
両親の遺留分:1,000万円
④配偶者と兄弟姉妹が相続人
遺留分の合計:3,000万円×1/2=1,500万円
配偶者の遺留分:1,500万円
兄弟姉妹の遺留分:権利なし
このように、遺留分は最低限の取り分を確保する仕組みとして機能します。
遺留分侵害額請求の手続き
遺留分侵害額請求は、2019年の民法改正によって導入された制度です。改正前は遺留分減殺請求と呼ばれており、「侵害された財産を取り戻す権利」という位置づけでしたが、、改正により遺留分の請求方法が遺産そのものではなく、金銭的請求に変更されました。このことにより柔軟な解決が可能になりました。
遺留分が侵害された場合、適切な手続きを進めることで正当な権利が守られます。
遺留分を請求するためには、被相続人の遺産を正確に把握することが大切です。まずは遺留分を侵害している相手と話し合いで解決できないか検討してみましょう。話し合いで解決できない場合は、調停となり、調停でも合意できない場合は訴訟という流れになります。
以下に、遺留分侵害額請求の全体の流れを整理します。
1.遺留分侵害額請求の準備
遺留分はいつでも請求できるわけではなく期限があります。
遺留分の請求期限は、「相続または遺留分を侵害されていることを知った日から1年間」かつ「相続開始の時から10年間」です。
•必要書類の準備
・遺留分侵害額請求書(正式な請求をするための書類)
・被相続人の出生時から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本(相続人であることの証明)
・被相続人の子どもで死亡している人がいる場合は、その人の出生時から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・遺言書の写し
・財産目録(被相続人の財産に関する証明)
2.相手方へ遺留分侵害額請求の通知
遺留分を侵害した相手方)に対し、内容証明郵便を利用して正式な通知を送ります。
•通知の目的:
・交渉の開始
・証拠として残す
•通知の内容:
・遺留分の計算根拠
・返還を求める財産の金額
3.交渉と話し合い
相手方と直接話し合い、遺留分の支払いについて合意を目指します。
•示談交渉:双方で合意に至ることを目指す。
•弁護士の介入:交渉が難航する場合は、弁護士を通じて交渉する。
4.家庭裁判所への調停申立て
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てます。
•調停の流れ
1.申立書を家庭裁判所に提出
2.調停委員を介して双方の意見を調整
3.合意が成立すれば、調停調書が作成される
5.裁判での解決
調停が不成立の場合、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。
・遺留分の計算根拠を明確にする
・被相続人の生前贈与や遺産配分を証明する
・財産の分割方法について具体的な主張をする
このような流れを踏むことで、遺留分の侵害に適切に対処することが可能です。
遺留分に関する判例と実際の事例
近年の判例では、遺留分侵害額請求に関するものが多く見られます。これは、2019年の民法改正により、遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求に変更されたためです。裁判所では、遺留分の計算方法、生前贈与の評価、金銭による支払い方法などが争点となっています。
裁判所で争われた遺留分に関する判例を紹介します。
遺留分に関する判例と実際の事例
事例1:遺言による不公平な財産分配
被相続人が遺言で全財産を長男に相続させると指定。しかし、他の相続人である次男と長女が遺留分を請求。長男は当初、遺言の有効性を主張して支払いを拒否しましたが、調停を経て最終的に次男と長女に遺産の一部が分配されました。このケースでは、家庭裁判所での調停が有効に機能し、円満な解決につながりました。
事例2:生前贈与が影響した相続トラブル
被相続人が生前に次男へ不動産を贈与していたため、遺産分割の際に長男と次男の間で争いが発生。長男が遺留分の侵害を主張し、調停の結果、生前贈与分を考慮したうえで遺留分の計算が行われ、長男に金銭補償がなされました。この事例では、被相続人の生前の財産移転が相続に大きな影響を与えることが示されています。
生前対策としての遺産管理
遺留分について巡るトラブルを未然に防ぐためには、生前からの適切な財産管理が重要です。以下の方法を活用することで、相続争いが避けられます。
1.生前贈与の活用
生前に一定の財産を贈与することで、相続時のトラブルを軽減できます。
メリット:贈与税の特例を活用できる。
デメリット:遺留分計算の対象となるため、事前に対策が必要。
2.家族信託の導入
家族信託を利用することで、相続時のスムーズな遺産分割が可能になります。
メリット:相続発生後の遺産管理が容易になる。
デメリット:設計が複雑なため、専門家の助言が必要。
3.生命保険の活用
受取人を指定することで、遺産分割とは別に資産を移転できます。
メリット:生命保険金は遺産分割協議の対象外となり、確実に指定した相続人に渡せる。
デメリット:保険金額が非課税枠を超えれば相続税の対象になる。
遺留分トラブルを防ぐための法律相談の活用
遺留分トラブルを未然に防ぐためには、早めに専門家へ相談することが重要です。
1.無料相談窓口の活用
・法テラス:所得条件を満たせば無料で法律相談が可能。
・自治体の法律相談:各自治体が定期的に行う無料相談会を活用。
2.専門家(弁護士・司法書士・税理士)の活用
・弁護士:調停・訴訟を見据えた対応が可能。
・司法書士:書類作成や登記のサポートが得られる。
・税理士:相続税対策のアドバイスを受けられる。
遺言書の種類と注意点
遺留分について巡るトラブルを防ぐために、有効な遺言書を作成することが重要です。遺言書には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、ここでは公正証書遺言と自筆証書遺言について説明します。
1.公正証書遺言
2名以上の証人立ち合いの下、公証人が遺言書を作成します。原本は公証役場で保管し、正本は遺言者が保管します。
・メリット:無効になることがなく、遺言書を紛失することもない。。
・デメリット:費用がかかる、証人2名の立会いが必要。
2.自筆証書遺言
遺言者が自筆で作成します。証人は必要ありません。保管場所は自宅など遺言者が決めた場所、または法務局に保管することもできます。
・メリット:いつでも遺言書が作成できる。費用はかからない。
・デメリット:無効になるリスクがある。
3.無効にならないための注意点
・自筆証書遺言は法律上次の要件を満たさなければ無効とされますので注意してください。
1.遺言者本人が自筆で全文を書く。ただし、財産目録はPCで作成可
2.作成日、氏名を正確に自筆で書く。
3.押印
遺産分割協議におけるケース
1.対立が深刻化したケース
家族間で意見が対立し、協議が進まなかったケース。話し合いが決裂し、最終的に裁判で決着することになった。
2.スムーズに解決したケース
事前に専門家を交えた協議する。また、公正証書遺言を活用することで、相続人全員が納得のいく形で遺産分割が行われた。
遺留分を活用して相続トラブルを未然に防ぐ方法
遺留分を正しく理解し、適切な対策を講じることは、円満な相続を実現するために重要です。生前からの準備や、相続発生後の適切な対応によって、遺留分に関するトラブルを防ぐことが可能です。家族間の話し合いや専門家の助言を活用しながら、相続手続きを進めることが望まれます。
※本記事では、2019年の民法改正後の遺留分侵害額請求について解説しています。改正前の遺留分減殺請求とは制度が異なる点にご注意ください。
この記事の監修者
山﨑 裕佳子
ファイナンシャルプランナー
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者、証券外務員保有。
通関士として通関業務、メーカーにて海外営業事務、銀行にてテラーなどを経験し、FPの道へ。
2022年「FP事務所MIRAI」設立。「家計の見直しでMIRAIを変える」をモットーに、家計相談、金融記事執筆、書籍監修など、幅広く活動している。