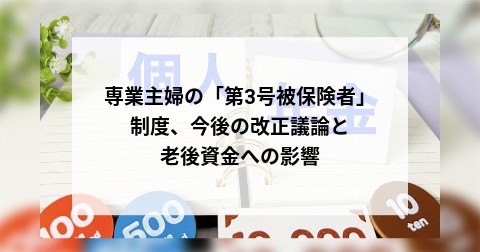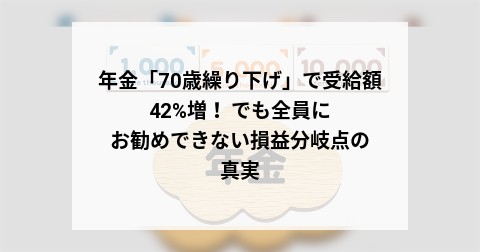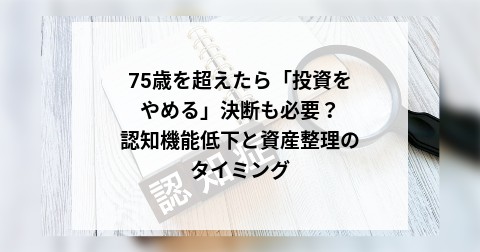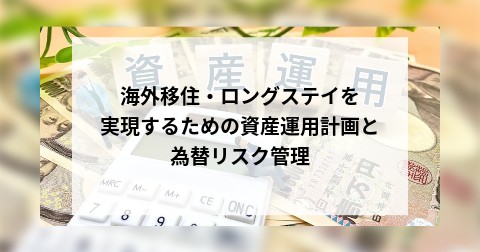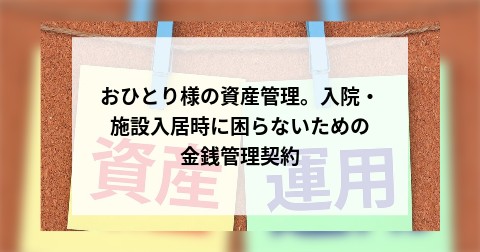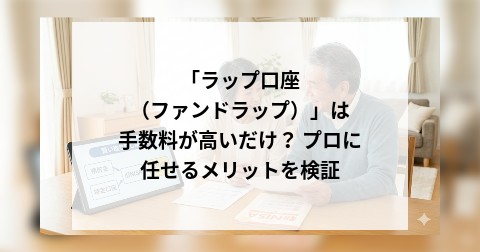【お金の寿命」を延ばすために】70歳から見直すべき「固定費」と「保険」
はじめにー平均寿命より大切な「お金の寿命」
人生100年時代、長寿化は喜ばしいことですが、その一方で「お金が尽きるリスク」、すなわち「お金の寿命」が平均寿命よりも短くなることへの不安が高まっています。
特に70歳を迎える頃は、収入が現役時代と比べて大きく減少し、貯蓄を取り崩して生活するフェーズに入ります。この時期に支出構造を最適化することが、「お金の寿命」を延ばすための最重要課題となります。
この記事では、老後の家計を圧迫しやすい「固定費」と「保険」に焦点を当て、70歳からでも実践できる具体的な見直しポイントを解説します。

家計の出血を止める!見直すべき「固定費」3つの柱
生活費の中でも、毎月決まって出ていく「固定費」は、一度削減すれば永続的な効果があります。チリも積もれば大きな差となる固定費の3つの柱を見直しましょう。
柱① 住居費:持ち家でも賃貸でも見直しを
| 項目 | 見直しポイント |
| 住宅ローン | 完済しているか確認。残債がある場合は、繰り上げ返済や借り換えで利息負担を軽減できないか検討する。ただし、手元の現金を減らしすぎないよう注意が必要。 |
| 固定資産税・都市計画税 | 節税の余地は少ないが、特例が適用されているか確認。また、自治体の減免制度などを確認する。 |
| 賃貸住宅の家賃 | 家賃の安い物件への住み替えを検討する。サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)なども選択肢に入れる。 |
柱② 通信費:スマホ・インターネット料金
シニア世代の通信費は、無駄が多い傾向にあります。
【契約プランの見直し】
大容量データプラン(使い放題など)は本当に必要か確認し、データ使用量が少ない場合は、格安SIMや低容量プランへの変更を強く推奨します。
【不要なオプションの解約】
留守番電話サービスや保証サービスなど、利用していないオプションがあれば解約します。
【固定電話の利用頻度】
携帯電話がメインになっているなら、固定電話の契約自体の見直しを検討します。
柱③ サブスクリプション・会費:使っていないサービスは即解約
新聞の購読、スポーツジムの会費、動画配信サービス(Netflix, Amazon Primeなど)、クレジットカードの年会費など、毎月引き落とされているサービスを全てリストアップします。
利用頻度の低いサービス
年に数回しか利用しない、あるいは全く利用していないサービスは、思い切って解約します。
家族割の確認
家族で同じサービスを利用している場合、重複契約や家族割の適用漏れがないか確認します。
リスクとバランス!70歳からの「保険」見直し術
保険は「万が一」に備えるものですが、70歳になると、現役時代と比べて「守るべきもの(子どもの教育費など)」や「残すべきもの(高額な死亡保障)」の必要性が変化します。
① 死亡保険:過度な保障は不要かも
必要額の再計算
持ち家の有無や配偶者の年金、貯蓄額を考慮し、葬儀費用と配偶者の生活費、遺産の清算費用など、本当に必要な死亡保障額を再計算します。
定期保険の見直し
期間満了が近い定期保険は、保険料が高騰する終身保険に切り替えるのではなく、「解約」または「保障額を最小限に減額」することを検討します。
② 医療保険・がん保険:高額療養費制度を前提に考える
日本の医療制度には、医療費の自己負担額に上限を設ける「高額療養費制度」があります。この制度があるため、過剰な入院給付金や手術給付金は不要になるケースが多いです。
入院日額の見直し
貯蓄で十分まかなえる場合は、入院日額を減額します。
自己負担額の明確化
医療費の自己負担額は月々の上限があるため、差額ベッド代や食事代など、高額療養費制度の対象外となる費用に備える設計に絞るのが賢明です。
保険期間の確認
終身型であれば問題ありませんが、一定期間で終了する定期型の医療保険は、更新時の保険料が急激に高くなるため注意が必要です。
③ 介護保険:公的介護保険で足りない部分に絞る
40歳以上の国民は公的介護保険に加入しています。民間介護保険は、公的サービスで不足する部分(自己負担額や在宅サービスの拡充など)を補う目的で検討します。
公的サービスとの重複回避
公的介護サービスの内容を理解した上で、足りない部分に絞った保険(一時金型など)を検討します。
見直しの「処方箋」:まずは現状把握から
お金の寿命を延ばすための第一歩は、「現状を知る」ことです。
【70歳からの家計見直し 3つの処方箋】
- 「現状把握」:過去1年間の通帳やクレジットカード明細、保険証券をすべて集め、収入と支出、資産の正確な状況を把握する。
- 「家族会議」:配偶者や子と一緒に、老後の生活方針や、もしものときの介護費用について話し合い、必要な保障額の共通認識を持つ。
- 「専門家への相談」:保険や年金、相続対策など、トータルで相談できるファイナンシャル・プランナー(FP)に相談し、客観的な意見を取り入れる。
まとめ:支出をコントロールして、老後の自由を確保する
70歳からの家計見直しは、単なる節約ではなく、老後の「自由」と「選択肢」を確保するための前向きな作業です。固定費と保険を見直すことで、将来への不安を減らし、人生の後半戦を心豊かに過ごすための土台を築きましょう。