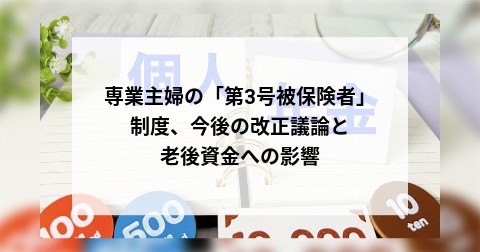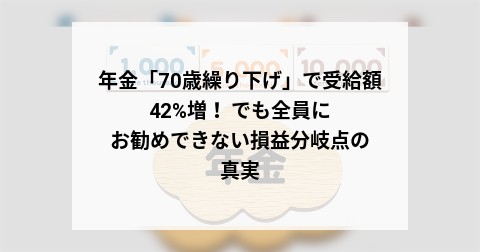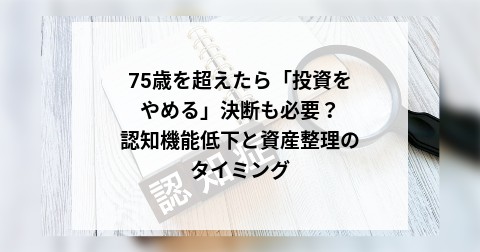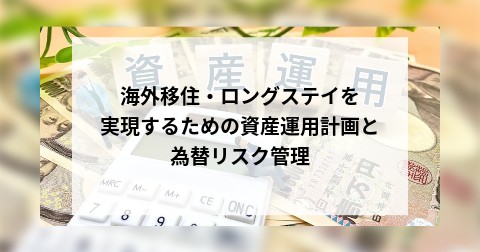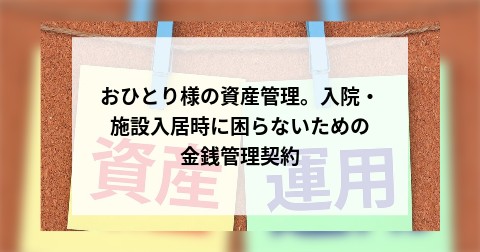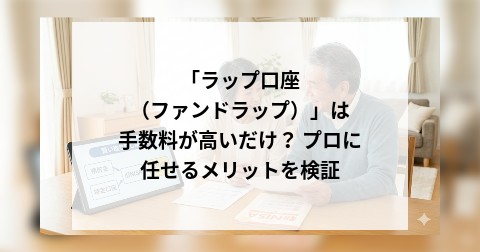相続対策でシニア世代が新NISAを利用する人急増!メリットや投資商品の選び方を解説
近年、2024年からスタートした新NISA制度は、現役世代だけでなく、シニア世代の間でも活用する人が急増しています。特に、相続税対策の一環として新NISAを利用するケースが増えており、そのメリットや手続き方法について関心が高まっています。
この記事では、新NISAがなぜシニア世代の相続対策に有効なのか、そのメリットや活用方法、投資商品についてわかりやすく解説します。

新NISAとは?
そもそもNISA(少額投資非課税制度)とは、株式や投資信託で得た利益が非課税になる、少額からの投資を支援する制度です。そして2024年1月からは、新NISA(新しいNISA)としてさらに使い勝手がよくなり資産形成を後押ししてくれる制度になりました。
これまでのNISAとの違いは?
| 旧NISA | 新NISA | |||
| 名称 | つみたてNISA | NISA | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
| 年間の投資上限枠 | 40万円 | 120万円 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有限度額(総枠) | 800万円 | 600万円 | 合計1,800万円 (成長投資枠は1,200万円まで)売却した場合、枠の再利用が可能 |
|
| 勘定の併用 | 不可 | 可 | ||
| 購入方法 | つみたて | 一括/つみたて | つみたて | 一括/つみたて |
| 対象商品 | 積立・分散投資に適した一定の投資信託 | 制限なし | 積立・分散投資に適した一定の投資信託 | 投資信託・上場株式・ETF・REIT |
| 制度期間 | 2018年~2023年 | 2014年~2023年 | 無期限 | |
| 非課税期間 | 20年 | 5年 | 無期限 | |
上記のように、これまでのNISAと新NISAには多くの変更点があります。
その中でも変わった点は次の3つです。
- 非課税保有期間の無期限化
- 年間投資上限額の拡大
- 生涯非課税限度額の拡大
なぜ新NISAがシニア世代の相続対策に有効なのか?
新NISA制度は、投資で得た利益(運用益や配当金)が非課税になることが最大のメリットです。シニア世代が新NISAを利用して資産運用を行う場合、主に以下の点で相続対策に役立ちます。
非課税運用による効率的な資産増加
新NISAは、非課税で運用できる上限額が1,800万円と大幅に拡大されました。シニア世代がまとまった資金を新NISAで運用することで、非課税で資産を増やし、老後の生活資金を充実させることができます。この増加分は、課税口座で運用した場合に比べて手取り額が大きくなるため、結果的に相続財産の総額を圧縮する効果も期待できます。
生前贈与と組み合わせた資産の移転
新NISAは、18歳以上であれば誰でも利用できます。このため、シニア世代が子どもや孫に資金を贈与し、その資金で子どもや孫が新NISA口座を開設して運用を始めるという方法が考えられます。年間110万円の贈与税の基礎控除と組み合わせることで、贈与税を支払わずに効率的な資産移転が可能となります。
シニア世代に適した投資商品の選び方
こちらでは新NISAで投資できる商品、シニア世代に合った投資商品の選び方を説明します。
新NISAで投資できる商品
投資できる商品は大きく分けて「投資信託」「国内株式」「外国株式」の3つがあります。
投資信託:つみたて投資枠・成長投資枠
- 株式型:株式に分散投資
- 債券型:安定的な利回りを期待できる
- バランス型:株式・債券へバランス良く投資
- コモディティ型:金・原油等の商品市況に投資
国内株式:成長投資枠
- 国内株式:配当や株主優待を重視する利用者におすすめ
- J-REIT:少額で不動産投資
- 国内ETF(上場投資信託):日経平均株価・東証株価指数(TOPIX)等の動きに連動する運用成果を目指す
海外株式:成長投資枠
- 外国株式:世界の有名企業に投資
- 海外ETF:国際分散投資
シニア世代に合った投資商品の選び方
シニア世代の投資は、ハイリスクではあるが短期に大きな利益を得る運用より、資産を減らさず、資産の寿命を延ばす運用が求められます。
当然、退職金があるからと一括購入をするのは避け、資金を分けて購入しましょう。
投資する商品は、値動きの激しい株式やREIT(不動産投資)ではなく、国内・海外の債券が最適です。
株式に魅力を感じる場合でも、投資先を全部株式にするのではなく「株式〇%、債券〇%」というように分散投資を心がけ、リスクの軽減を図ります。
まとめ
新NISAは、単なる資産形成の手段にとどまらず、シニア世代の相続対策としても非常に有効な制度です。非課税枠を活用して資産を増やし、将来の相続税の負担を軽減するだけでなく、家族への資産承継を円滑に進める手助けにもなります。
ただし、投資にはリスクが伴います。ご自身の年齢、資産状況、リスク許容度を考慮し、専門家とも相談しながら、最適な投資プランを立てることが重要です。これを機に、新NISAを上手に活用して、ご家族の未来を守る準備を始めてみてはいかがでしょうか。
【PR】
お金に対して漠然と不安を抱えているのであれば「資産運用」を検討してみてはどうでしょう?
新NISAや投資に関する相談なら投資信託相談プラザのセミナーに参加してみては?
| 投資信託相談プラザの無料セミナーご参加はこちらから |
| 店舗またはオンラインでの個別相談はこちらから |