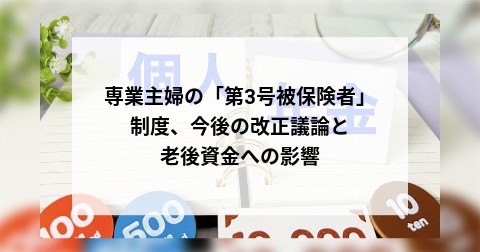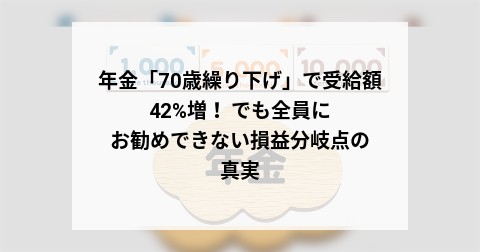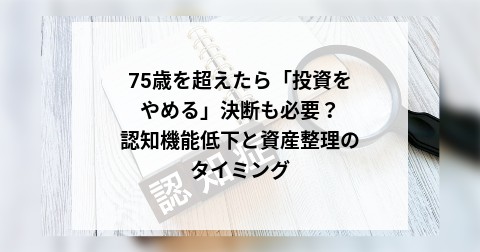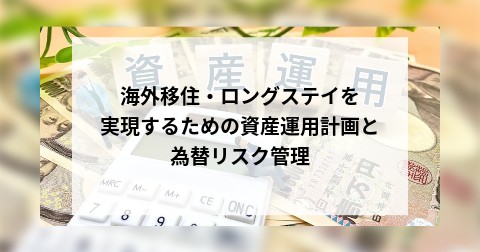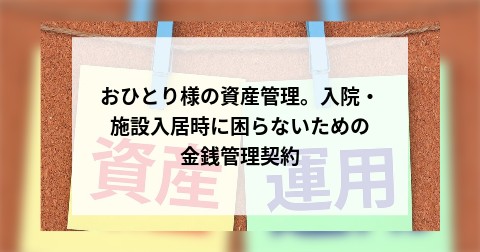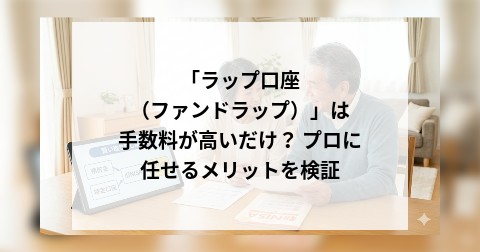知らないと損!老後の医療費・介護費に備える「高額療養費制度」と貯蓄の考え方
はじめに
人生100年時代を迎え、老後の生活において医療費や介護費の備えは避けて通れない課題です。特に病気や怪我で長期入院や治療が必要になった場合、「医療費が家計を圧迫してしまうのではないか」という不安を感じる方も多いでしょう。
しかし、日本には、医療費の負担を軽減するための強力な制度「高額療養費制度」があります。この制度を正しく理解し、公的制度でカバーしきれない部分を計画的に貯蓄で備えることが、安心して老後を送るための鍵となります。

知らないと損!医療費の自己負担を抑える「高額療養費制度」
高額療養費制度とは?
高額療養費制度とは、ひと月(1日から末日まで)にかかった医療費の自己負担額が、年齢や所得に応じて定められた上限額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。
「窓口で3割負担」といっても、例えば100万円の治療費がかかれば30万円の自己負担になりますが、この制度があることで、実際に支払う額は大幅に軽減されます。
制度の仕組み:自己負担限度額
自己負担限度額は、70歳未満と70歳以上で区分が異なり、さらに現役並みの所得があるかどうかなどで細かく分類されます。
【70歳以上(一般的な所得の場合)の自己負担限度額の目安】
| 適用区分 | 外来(個人ごと)の上限額 | 世帯ごと(入院を含む)の上限額 |
| 一般 (年収約156万円~約370万円) | 18,000円 | 57,600円 |
※「一般」区分の場合、外来の月額負担は最大18,000円です。入院など世帯全体の負担がある場合でも、最大57,600円(多数回該当を除く)で済みます。
さらに負担が軽くなる「多数回該当」
過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した月があった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下げられます。これを「多数回該当」といい、長期にわたる治療が必要な方にとって、大きな経済的メリットとなります。
医療費と介護費を合算できる「高額介護合算療養費制度」
医療費だけでなく、介護保険サービスを利用している場合、医療と介護の両方の自己負担額が高額になることがあります。
「高額介護合算療養費制度」は、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、世帯の年間限度額を超えた場合に、その超えた分が支給される制度です。
老後においては、入院後のリハビリで介護サービスを利用するなど、医療と介護が密接に関わるため、この合算制度も必ず覚えておきましょう。
公的制度でカバーできない費用と貯蓄の考え方
高額療養費制度があるとはいえ、すべての費用がカバーされるわけではありません。以下の「制度の対象外となる費用」と、それに対する貯蓄の考え方を知っておくことが重要です。
制度の対象外となる主な費用
| 費用項目 | 概要 | 備えの考え方 |
| 差額ベッド代 | 個室や少人数部屋を利用した場合の費用。全額自己負担。 | 入院日数を想定し、1日あたり5,000円~1万円で試算。 |
| 先進医療費 | 厚生労働大臣が定める高度な医療技術にかかる費用。技術料は全額自己負担。 | 民間の医療保険の「先進医療特約」で備えるのが効率的。 |
| 食費・居住費 | 入院時の食事代や、介護施設での居住費。 | 高額療養費制度の対象外。老後資金の一部として備蓄。 |
| 通院・介護の交通費 | 病院や施設への移動にかかる費用。 | 年間の雑費として予算計上。 |
貯蓄の目標額設定と資金準備
高額療養費制度により、短期的な入院や治療の「ピーク時の出費」は抑えられますが、上記のような対象外費用や、長期的な介護施設の入居費用(月額平均約20万円)は公的制度ではカバーできません。
シニアの医療・介護費用の貯蓄目標額の考え方は以下の通りです。
-
「制度対象外の医療費」の備え(100万円〜200万円)
-
差額ベッド代や、一時的な自己負担限度額の支払いに充てるための資金として、いつでも引き出せる流動性の高い貯蓄(預貯金)で確保する。
-
-
「介護・生活費」の備え(必要に応じて)
-
介護施設に入居する可能性や、在宅介護が長引く可能性に備え、老後資金全体とは別に確保する。これは退職金や資産運用の取り崩し計画に組み込む。
-
高額療養費制度を理解した上で、足りない部分を預貯金や民間の保険で補う計画的な備えが、老後の不安を解消する最善策と言えるでしょう。
【PR】
老後の医療費・介護費に不安を抱えているのであれば「資産運用」を検討してみてはどうでしょう?
お金の不安を相談するなら投資信託相談プラザのセミナーに参加してみては?
| 店舗またはオンラインでの個別相談はこちらから |