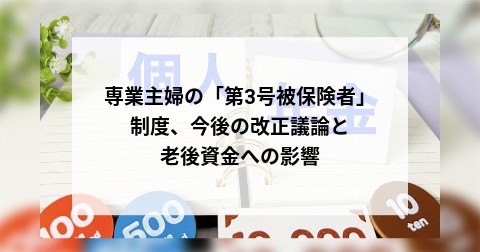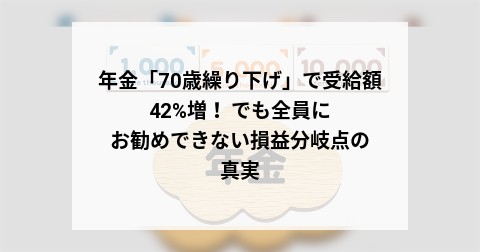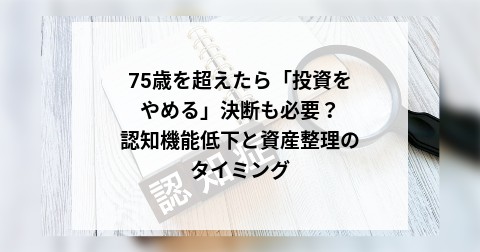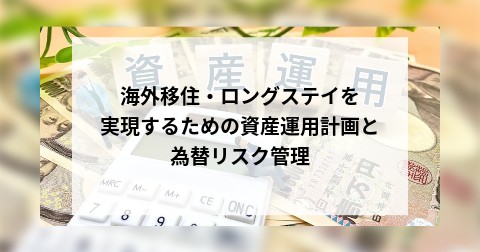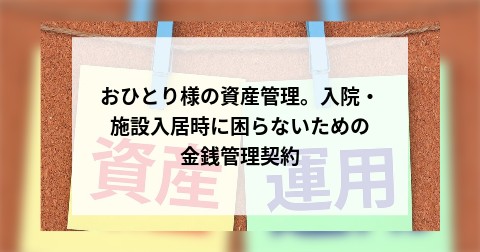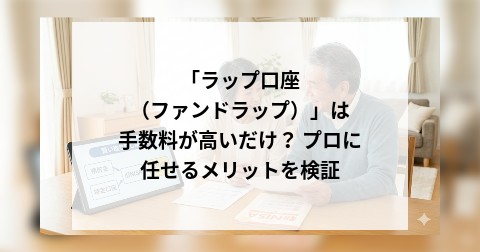相続対策は「生前贈与」だけじゃない!シニアが今からできる家族信託の基礎知識
はじめに【なぜ今、「生前贈与」以外の対策が必要なのか】
「相続対策」と聞いて、まず「生前贈与」を思い浮かべる方は多いでしょう。確かに生前贈与は、計画的な財産移転や相続税対策として有効な手段です。
しかし、生前贈与はあくまで財産を渡すための対策であり、シニア世代が直面する大きなリスクである「認知症」に対しては十分に対応できません。
もし、財産を持つ方(親御さん)が認知症になってしまうと、銀行口座が凍結され、介護費用や生活費のために財産を使うことができなくなってしまいます。
このような「財産凍結リスク」や、何世代にもわたる確実な財産承継のニーズから、今、「家族信託」という新しい対策が注目を集めています。本記事では、生前贈与ではカバーしきれない部分を補い、円満な相続を実現する家族信託の基礎を解説します。

家族信託とは?その基本的な仕組み
家族信託とは、自分の大切な財産を、信頼できる家族(主に子ども)に託し、特定の目的(例えば、自分の生活費や介護費用、将来の相続など)に沿って管理・運用・処分してもらうための仕組みです。法的な正式名称は「民事信託」と言います。
家族信託には、主に以下の3者の登場人物がいます。
| 登場人物 | 役割 |
| 委託者 | 自分の財産を託す人(財産の所有者。主に親御さん) |
| 受託者 | 財産を託され、管理・運用する人(主に信頼できるお子さん) |
| 受益者 | 信託された財産から利益を受け取る人(多くの場合、当初は委託者本人) |
仕組みのイメージ
- 委託者(親)と受託者(子)が信託契約を結びます。
- 親の財産(不動産や預金など)の名義は子に移りますが、財産の所有権は信託されたままです。
- 財産から生じる利益(家賃収入や利息など)は受益者である親に戻ってきます。
- 子は親のために、信託契約書に定められた通りに財産を管理・運用する義務を負います。
生前贈与や遺言にはない!家族信託の強力なメリット
家族信託が、他の相続対策と一線を画す、シニアにとって特に重要なメリットは以下の3点です。
メリット① 認知症による「財産凍結」を未然に防げる
家族信託契約を元気なうちに結んでおけば、たとえ委託者が将来認知症になっても、受託者(家族)がスムーズに財産を管理・運用できます。これにより、銀行口座の凍結による生活費の引き出し不能や、不動産の売却不能といった事態を避けることができます。
メリット② 柔軟で長期的な財産管理・運用が可能
信託契約の中で、「この不動産は私が生きている間は賃貸で運用し、私の死後、孫の教育資金に充てるために売却すること」といった、財産の使い道や管理方法を細かく指定できます。これは、法定後見制度では認められない、非常に柔軟な財産管理方法です。
メリット③ 二次相続以降の承継先まで指定できる
一般的な遺言書は、「誰に(一次相続)何を渡すか」しか決められません。しかし、家族信託では、「私の死後、妻に財産を渡し(一次相続)、妻の死後、残った財産を特定の孫に渡す(二次相続)」といった、二次相続以降の承継先(後継ぎ遺贈型受益権)まで、あらかじめ設定しておくことが可能です。
家族信託を始める際の注意点とステップ
家族信託は非常に有用ですが、導入にあたっては以下の点に注意が必要です。
【注意点】
-
受託者の負担と責任 財産を預かる受託者には、信託財産の管理や税務申告など、大きな責任が伴います。受託者となる家族が、その役割を理解し、担えるのか事前に十分話し合う必要があります。
-
税務上の専門知識が必要 家族信託は、税法上の取り扱いが複雑になることがあります。節税効果は限定的ですが、信託契約の内容によって課税関係が変わるため、税理士など専門家の助言が不可欠です。
-
契約書の作成が専門的 信託契約書は、法律上、税務上問題がないよう慎重に作成する必要があります。司法書士や弁護士など、家族信託に詳しい専門家への相談が必須です。
【シニアが今からできるステップ】
- 家族会議の開催:まずは家族全員で、現在の財産状況や将来に対する考え、信託の仕組みについてオープンに話し合います。
- 専門家への相談:家族信託の経験豊富な司法書士や弁護士に相談し、自分たちの希望に合った契約内容(信託スキーム)を設計してもらいます。
- 信託契約書の作成・締結:専門家のサポートのもと、公正証書などで信託契約書を作成し、家族間で契約を締結します。
- 財産の名義変更:不動産や預金などの財産の名義を受託者へと変更する手続きを行います。
まとめ
家族信託は、単に「誰に財産を渡すか」という相続の決め方だけでなく、「もしもの時」に財産が家族のために確実に活用される未来を築くための、シニア世代にとって最高の「安心」対策です。
生前贈与と家族信託は、どちらか一方を選ぶのではなく、目的に応じて使い分ける、あるいは組み合わせて使うことが理想的です。特に、認知症リスクや複数世代にわたる資産承継を検討されている方は、ぜひこの機会に家族信託の専門家にご相談ください。