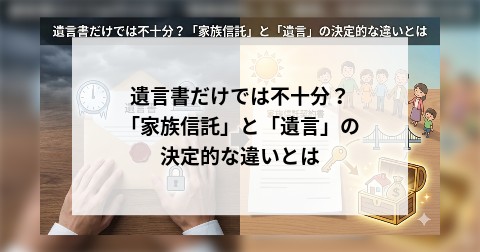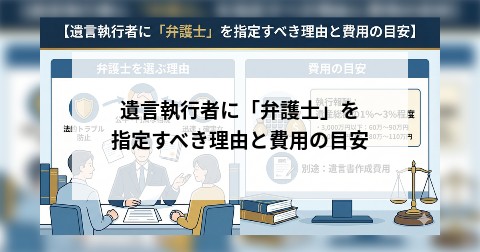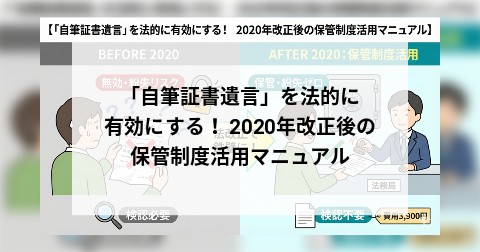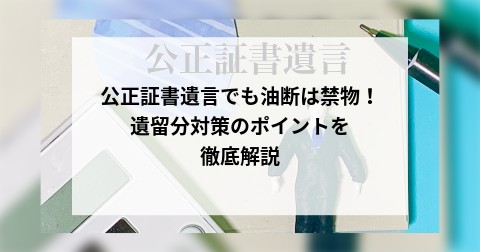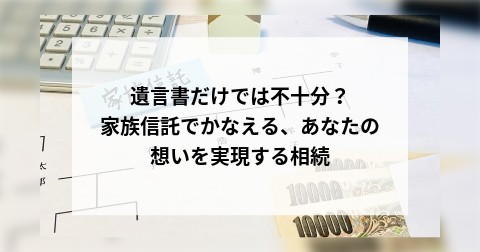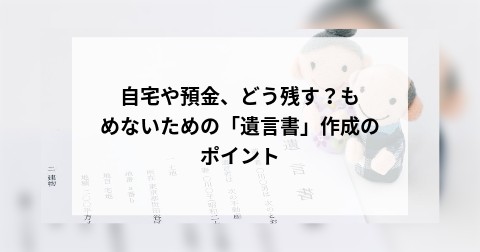【遺言書と遺留分】優先されるのはどちら?相続時の注意点を解説
相続が発生した際、亡くなった被相続人の意思を示す遺言書と、法律で保障された相続人の権利である遺留分をめぐり、衝突することがあります。「一体どちらが優先されるのだろう?」と疑問に思う方も少なくないでしょう。
そこで本記事では、遺言書と遺留分の関係性について詳しく解説し、相続発生時の注意点や、トラブルを避けるための対策について詳しく解説します。

遺言書と遺留分の違いとは?
遺言書とは、ご自身の財産の分け方や相続人などを指定するために残す法的な文書です。生前に作る必要があり、遺言書がある場合は原則としてその内容に従って相続財産の分配が行われます。
遺言書を作成することで、特定の相続人に多くの財産を相続させたり、相続人以外の人や団体にも遺贈したりすることが可能です。
遺言書の主な種類
遺言書にはさまざまな種類がありますが主に作成される種類は以下の3つです。
①自筆証書遺言
遺言者本人が全文を自筆し、日付と氏名を署名、押印した遺言書です。費用もかからないため簡単に作成できますが、法的な要件を満たしていないケースも多く、家庭裁判所での検認の手続きも必要です。(※)
②公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。公証人が内容を確認するため、自筆証書遺言よりも法的な不備が起きにくく検認の手続きも不要です。ただし、費用が発生し、証人2名の立ち会いも必要です。
③秘密証書遺言
上記の①と②に比べると、作成数は非常に少ない形式の遺言書です。 遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、公証人と証人2名にその存在を証明してもらう遺言書。内容は秘密にできますが、法的な要件を満たしているかどうか家庭裁判所での検認手続きは必要とされています。
(※)自筆証書遺言の検認について
自筆証書遺言には2020年7月10日から始まった保管制度があります。自筆証書遺言の原本を法務局で保管してもらう「自筆証書遺言書保管制度」と呼ばれるものです。この制度を利用している場合、相続開始後の検認手続きは不要です。
遺留分とは
遺留分とは、民法で規定されている「法定相続人(兄弟姉妹以外)に保障された最低限の遺産の取り分」のことを意味します。法定相続分ではありませんのでご注意ください。
被相続人の生前の贈与や遺言によって、特定の相続人に多くの財産が渡ってしまい、他の相続人がまったく財産を受け取れないといった不公平な事態を防ぐために設けられています。
遺留分の割合は、法定相続人の構成によって異なります。(兄弟姉妹は除いています)
| 相続人の構成 | 配偶者の遺留分 | その他の相続人の遺留分 |
| 配偶者と子(直系卑属) | 4分の1 | 4分の1 |
| 配偶者と親(直系尊属) | 3分の1(6分の2) | 6分の1 |
| 配偶者のみ | 2分の | なし |
| 子(直系卑属)のみ | なし | 2分の1 |
| 親のみ(直系尊属)のみ | なし | 3分の1 |
遺言書と遺留分の違いとは
遺言書と遺留分は、いずれも相続にまつわる用語ですが、以下のように異なっています。
| ・遺言書は、ご自身の財産の分け方や相続人などを指定するために生前に残す法的な文書 ・遺留分は、民法で規定されている「法定相続人(兄弟姉妹以外)に保障された最低限の遺産の取り分」 |
つまり、遺言書で特定の相続人に財産を集中させる内容を記載すると、その他の相続人の遺留分を「侵害」してしまうおそれがあるのです。この問題点については、次の章で説明します。
遺言書と遺留分|優先されるのはどちら?
大切な家族が亡くなり、遺言書を開いてみたら特定の相続人に財産が集中しており、その他の相続人が遺留分さえもらえない内容の遺言書だった場合、遺言書の内容と遺留分のどちらが優先されるでしょうか。
遺留分が優先される
遺留分は民法で保障されている「最低限度」取得できる遺産の割合であるため、遺留分権利者の請求により、遺言書の記載内容よりも、遺留分が優先されます。
しかし、遺言書の内容が遺留分を侵害していても、遺言書の内容が違法であり、無効となるものではありません。もしも、遺留分が侵害されていても遺留分の権利者である相続人が請求しなかったら、遺言書の内容どおりに分割が進められます。
遺留分が侵害されたら請求が必要
もしも遺留分の権利者が遺言書によってご自身が本来貰えるはずの遺留分さえもらえないとわかったら、遺留分侵害額請求を行うことができます。(※)
ただし、遺留分侵害額を請求する場合は、以下の時効を念頭に置いたうえで手続きを進める必要があります。
①遺留分の侵害を知った日から1年以内(時効)民法1048条
②相続開始から10年(除斥期間)
時効については、被相続人の死去とご自身が遺留分の権利を持つ相続人である知った日から1年以内を意味します。一般的には①に該当することが多いため、遺言書の内容に不服がある場合は早急に請求しましょう。
一方で、被相続人の死去や自身が相続人であるなどを全く把握していないケースでも、相続開始から10年の除斥期間を過ぎると遺留分の請求権は消滅します。
(※)2019年6月30日以前の相続については、遺留分減殺請求と呼びます。
遺留分侵害額請求の方法
遺留分が侵害されていた場合、侵害している人に対して、侵害された金額に相当する金銭の支払いを求めることができます。この「遺留分侵害額請求」の方法は以下の流れで行います。
遺留分侵害額請求の流れ
- 遺言書の確認と相続財産の調査
遺言書の内容を確認し、相続財産の全体像を把握します。 - 遺留分侵害額の算定
法定相続人の構成や相続財産の額に基づいて、自身の遺留分を計算します。 - 遺留分侵害額の算定
次に遺留分がどれだけ侵害されているかを計算します。 - 遺留分侵害額請求の意思表示
遺贈などで遺留分を侵害した人に対して、遺留分侵害額を請求する意思を伝えます。内容証明郵便を利用することが一般的です。 - 協議・交渉など
当事者間で遺留分侵害額の支払いについて協議・交渉を行います。協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停が不成立の場合は訴訟を提起します。
相続時の注意点|遺留分の調停・訴訟は長期化しやすい
遺留分侵害額請求は、相続人間で感情的な対立に発展することも多く、解決には時間を要するケースも少なくありません。
また、日本においては遺留分に関する紛争を訴訟で争う前に、調停を経る「調停前置主義」が採用されているため、調停~訴訟まで含めると時間がかかりやすくなります。
こうした長期化を避け、円満な相続を目指すためには遺留分に考慮がある遺言書の作成も検討する必要があります。
トラブルを招きにくい遺言書を作ろう
遺言書類の内容は遺留分だけではなく、その他についても配慮を尽くしておかないと、遺された相続人の間で激しいバトルに発展するおそれがあります。遺言書の効力を争うケースに発展するおそれもあるため、トラブルを招かない遺言書作りが大切です。そこで、この章ではトラブルを招きにくい遺言書について紹介します。
遺言書作りのポイント
遺言書を作成する際は、遺留分を考慮した内容にすることが望ましいです。特定の相続人に多くの財産を相続させたい場合は、その理由を具体的に遺言書内の「付言事項」へ記載したり、他の相続人への配慮を示す言葉を入れたりすることも有効です。
たとえば、事業継承などを理由に特定の相続人へ財産を集中させる場合は、その旨を伝えるようにしましょう。
生前から家族間のコミュニケーションを大切に
生前から相続について家族間で話し合い、それぞれの意向を理解しておくことが、相続発生後の紛争予防につながります。遺言書について激しく争っていると、相続税申告や相続登記などの手続きが遅れてしまうおそれがあります。
家族が相続後も円満に過ごしていくためにも、生前から家族間のコミュニケーションを行い相続について気軽に話し合うことが大切です。
まとめ
遺言書は故人の大切な意思表示ですが、遺留分が優先されます。遺留分は法定相続人の最低限の財産の取得分を保障するものだからです。相続人の生活を守るためのしくみと言えるでしょう。