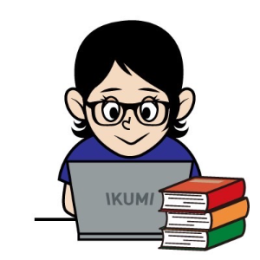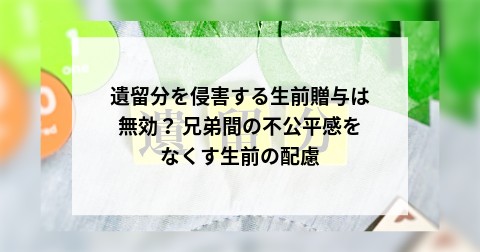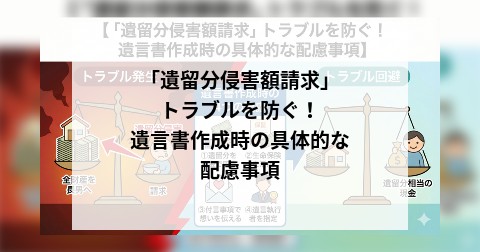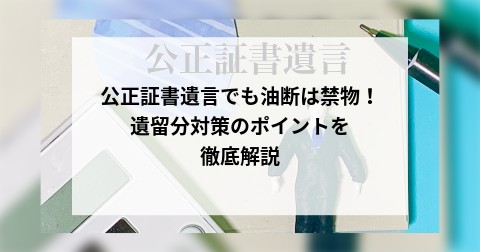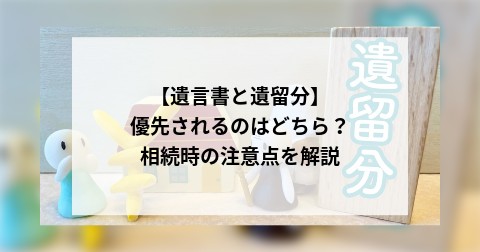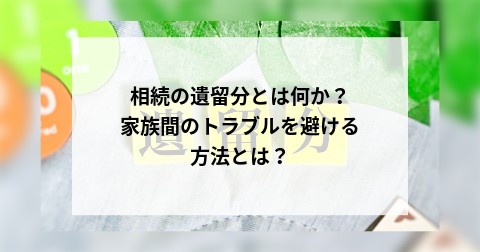【経営者必見】事業承継時に知っておきたい遺留分の特例と注意点とは
事業を経営されている方にとって、次の後継者に遺産を集中させる方法は気になるところでしょう。特に特定の相続人に遺産を集中させる場合は、他の相続人の遺留分を侵害してしまうおそれがあるため、十分な対策を講じておくことが大切です。
そこで、本記事では経営者向けに相続時の事業承継における遺留分について、民法上の特例や注意点を詳しく解説します。事業承継時には遺留分トラブルを回避できる特例がありますので、ぜひご一読ください。

事業承継前に押さえておきたい遺留分とは
遺産分は相続に直面してから知る方も多いですが、事業承継を迎える際には事前に知っておきたいものです。そこで、この章では遺留分の概要を中心に詳しく解説します。
遺留分の概要|法定相続分との違いとは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている、最低限保障された遺産に対する権利のことです。(民法1042条以下)
法定相続分と混同されることが多いですが、2つは考え方が大きく異なります。
・法定相続分ー各相続人に認められる相続分の割合
・遺留分ー兄弟姉妹以外の各相続人に保障された遺産の最低限度取得できる権利
法定相続分は遺産取得の目安になりますが、法的拘束力はありません。一方の遺留分は民法上で最低限度保障されている権利です。もしも遺留分が減ってしまうような遺言書が残されていた場合、侵害された相続人は、侵害している相続人にお金を請求できます。これを「遺留分侵害額請求権」と呼びます。
遺留分の割合とは
遺留分の割合については、以下のように定められています。
•直系尊属(父母、祖父母など)のみが相続人の場合:被相続人の財産の3分の1
•上記以外の場合(配偶者、子が相続人になる場合):被相続人の財産の2分の1
たとえば、相続人が被相続人の配偶者と子2名の計3名だった場合、遺留分は2分の1のため各相続人が取得する遺留分は4分の1です。
■計算例 被相続人の財産1億円、相続人は配偶者と子2名の計3名
・配偶者の遺留分は1億円×1/4で2,500万円
・子2名の遺留分も1億円×1/4で2,500万円のため、子1名の遺留分は1,250万
事業承継時に発生する遺留分トラブルとは
遺留分は事業承継時に問題となることがあります。その理由には、後継ぎとなる相続人に被相続人の遺産が集中し過ぎることが挙げられます。
被相続人が持つ自社株式や事業用不動産といった、事業の継続に欠かせない資産は、後継者に相続させたいものです。しかし、相続人が複数いる場合、特定の相続人に遺産を集中させると、その他の相続人の遺留分を侵害してしまうおそれがあります。
遺留分の侵害について、支払うように請求を受けると、代償金を用意するために大切な事業資産を売却せざるを得ない可能性があり、事業の継続に暗い影を落とす可能性があるのです。
遺留分を侵害するとどうなる?
遺留分を侵害すると、侵害を受けた相続人は「遺留分侵害額請求権」を行使してくる可能性があります。相続人間で話し合いを重ねて解決できるケースもありますが、話し合いがまとまらない場合は調停や訴訟に発展するおそれがあり、遺産分割ができない状態が長期化するケースもあります。
事業用財産も含む相続は相続税が発生することも多いですが、遺産分割が進まない場合は相続税の未分割申告を行う必要があります。一部の控除や特例が利用できなくなる(※)ほか、相続税の物納ができない等のデメリットが生じます。
(※)未分割で申告する際には「申告期限後3年以内の分割見込み書」を添付して提出することで、適用できます。
遺留分放棄は強制できない
遺留分は生前に家庭裁判所へ申立てすることにより、放棄が可能です。事業承継に備えて遺留分を放棄してもらうことも検討できますが、自身以外の推定相続人に遺留分の放棄を強制することはできません。
参考URL 裁判所 遺留分放棄の許可
経営者必見!遺留分に関する民法の特例とは
遺留分を詳しく理解せずに相続時に事業承継を進めることは、事業にとって大きなリスクとなります。そこで知っておきたいのが「遺留分に関する民法の特例」です。
日本国内の大多数は「中小企業」であり、親族間承継が非常に多くなっています。そこで、中小企業の事業承継を支援するため、「遺留分に関する民法の特例」が施行されています。
この章では本制度の概要と、適用要件などを詳しく解説します。
本特例の概要
本特例は、会社や個人事業を事業承継する際に経営者の推定相続人の合意の上で「除外合意」もしくは「固定合意」によって遺留分対策を進めることができます。
①除外合意
会社:自社株式の価額を、遺留分を算定するための財産の価額から除外する
個人事業主:事業用資産の価額を、遺留分を算定するための価額から除外する
②固定合意
会社:自社株式の価額について、遺留分を算定するための財産の価額に算入する時の価額を合意時の時価で固定する
個人事業主:適用なし
自社株式のある企業の場合、除外合意なら遺留分から自社株式を除けます。固定合意なら低い株価の時に合意しておけば、株式の価額がすでに固定されているため、遺留分の請求を受けた相続人は遺留分の計算がスムーズになります。
適用する要件
本特例を適用するためには、一定の要件を満たしている必要があります。要件は会社と個人事業主によって異なっています。
①会社の場合
・中小企業であること
・合意時点で3年以上継続して事業を行っている非上場企業であること
・後継者は合意の時点で経営者交代が済んでおり、先代経営者から贈与などで株式を取得し、会社の議決権の過半数を保有していること
②個人事業主の場合
・合意時点において3年以上帰属している個人事業主であること
・合意時点で経営者交代が済んでおり、先代経営者から贈与などで事業用資産を取得していること
適用までの流れ
- 自社株式や事業用資産を後継者へ生前贈与する
- 後継者と推定相続人全員が合意し、合意書を作る
- 経済産業省大臣の確認
- 家庭裁判所の許可 (遺留分の算定に係る合意の許可)
本特例は経済産業省と家庭裁判所の2つの行政機関の許可が必要です。通常の遺留分放棄よりも手続きが複雑であるため注意しましょう。詳しくは以下をご確認ください。
参考 中小企業庁 事業承継と民法<遺留分>- 中小企業庁
適用できないケースに注意
本特例を利用するためには、生前贈与や推定相続人全員の合意などの手続きをクリアする必要があります。たとえば、生前贈与の段階から家族内に反発がある場合は本特例の手続きは難航してしまうため注意が必要です。
相続時の事業承継における3つのポイント
対策も検討する必要があります。ここでは、事業承継のある相続時に重要な3つのポイントをご紹介します。
事業承継税制
事業承継税制は、自社株式や事業用資産にかかる相続税・贈与税の納税を猶予し、最終的には免除できるという制度です。遺留分に関する民法の特例とは異なる制度ですが、両者を併用することで、税負担と遺留分問題の両方を解決し、事業の安定的な承継を図ることができます。高齢の経営者からの事業承継時などに活用されることが多い制度です。
参考URL 国税庁 事業承継税制特集
経営者保証に関するガイドライン
事業承継の際に、現経営者の経営者保証が問題となるケースは少なくありません。経営者保証に関するガイドラインは、全国銀行協会と日本商工会議所が策定したガイドラインであり、「事業承継特別保証制度」も用意されています。
この制度は一定の要件を満たすと、経営者保証不要で融資が受けられるもので、事業承継時の経営者保証解除に活用できます。
生命保険の活用
事業承継には生命保険への加入で備えを作ることもおすすめです。
遺留分侵害額請求への備えや相続税の納税資金確保にも役立ちます。生命保険から支払われる死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があることも魅力的です。死亡保険金を会社の運転資金や事業継続のための資金として活用することもできます。
まとめ
本記事では、相続時の事業承継における遺留分について、民法上の特例や注意点を詳しく解説しました。事業承継時には遺留分トラブルに備えた特例がありますが、適用要件を満たす必要があるためご注意ください。
事業承継は複雑な手続きや資金移動が多く、税理士に相談しながら進めることがおすすめです。生前から専門家と家族が揃って準備を進めることで、円滑な事業承継が実現しやすくなります。