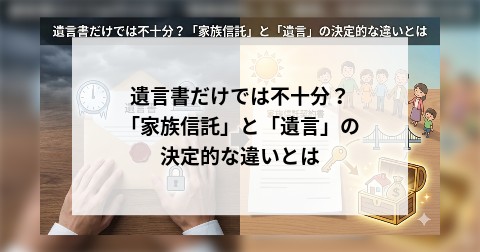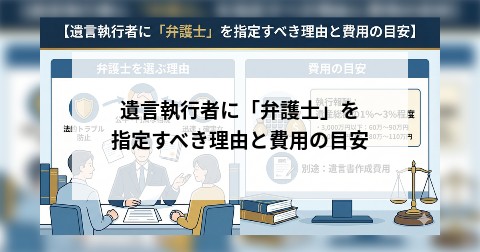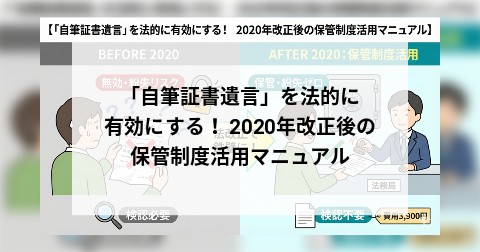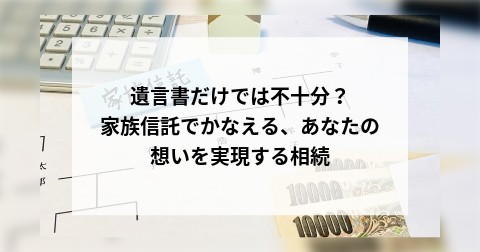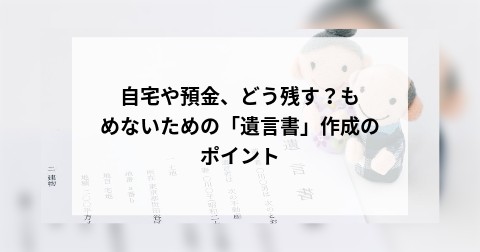公正証書遺言でも油断は禁物!遺留分対策のポイントを徹底解説
「公正証書遺言さえ作っておけば、遺産をすべて思い通りにできる」
そう考えている方は少なくありません。
しかし、公正証書遺言であっても、「遺留分」という制度を無視することはできません。この遺留分を考慮せずに遺言を作成してしまうと、遺された家族間で大きなトラブルに発展する可能性があります。
ここでは、公正証書遺言を作成する際にも知っておくべき遺留分対策のポイントと、後悔しないための具体的な方法を解説します。
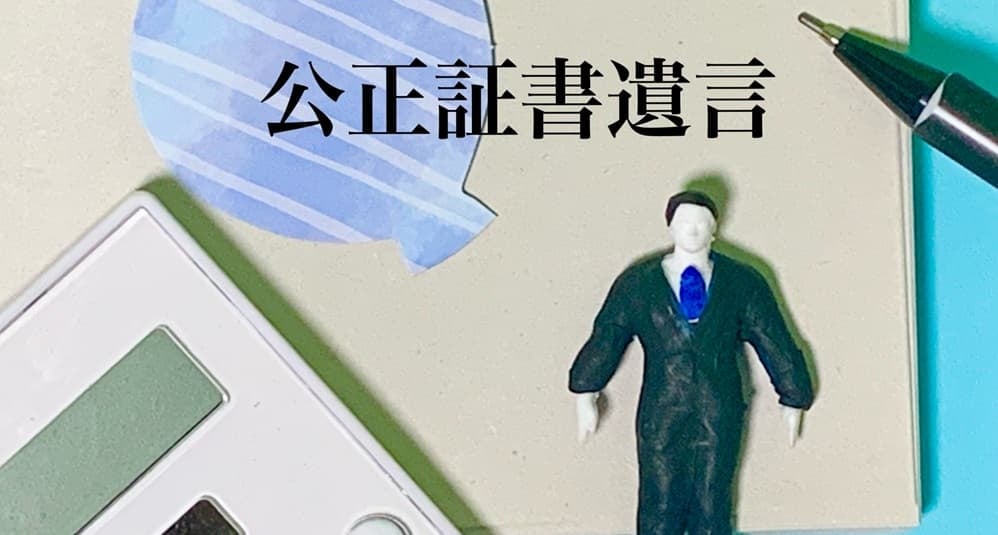
そもそも「遺留分」とは?
遺留分とは、被相続人が持っていた財産のうち、一定の法定相続人に保証された最低限の取り分のことです。
被相続人には、生前に財産処分や遺言を行う自由があります。自分の財産のうち、どの財産を誰に与えるかを自分の意思で決められるという原則がありますが、この原則を貫いてしまうと、配偶者や子といった遺族の生活が保障できないなどの問題も生じます。
このような問題が起こるのを防ぐため、民法では、遺留分という制度を設け、被相続人の処分の自由を一定程度制限しています。被相続人による生前の贈与や遺贈により自己の遺留分を侵害された遺留分権利者は、贈与や遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。これを、「遺留分侵害額請求」といいます。
公正証書遺言でも「遺留分」トラブルが起こる理由
相続人には、遺言書の内容に関わらず、遺留分を受け取る権利があります。
自筆証書遺言に限らず、公正証書遺言がある場合にも、事情は変わりません。
公正証書遺言によって遺留分を侵害された相続人は、遺産を多く取得した者に対して、遺留分侵害額請求を行うことができます。
公正証書遺言によって遺留分が侵害されるケースとしては、以下のような事例があります。
- 公正証書遺言において、長男だけにすべての遺産を相続させる旨が記載されていた場合
- 公正証書遺言において、被相続人と仲が悪かった子どもの相続分がゼロと指定されていた場合
- 配偶者や子どもがいるにもかかわらず、公正証書遺言において、遺産の大半を愛人に相続させる旨が記載されていた場合
遺留分トラブルを未然に防ぐための対策
遺言書を作成する
- 明確な遺言書を作成することで、相続の内容を具体的に指示できます
- 公正証書遺言にすると信頼性が高まり、無効とされるリスクを減らせます
- 遺留分を考慮した分配内容にすることで、後のトラブルを回避できます
遺留分に配慮した財産分配を検討する
- 遺留分を侵害しない形で、財産を分ける計画を立てます。
- 特定の相続人に多くの財産を与えたい場合は、その理由を遺言書に明記し、他の相続人に配慮した金銭や財産の分け方を提示します
家族で話し合いを行う
- 生前に家族間で相続に関する意思や希望を共有することで、認識のズレや不満を減らします。
- 被相続人の意思を直接伝えることで、相続人が納得しやすくなります。
生命保険を活用する
- 生命保険金は「受取人固有の財産」とみなされ、遺産分割協議の対象外になります
- 特定の相続人に生命保険金を指定しておくことで、遺留分を侵害しない形で財産の配分を補完できます
生前贈与を活用する
- 被相続人の生前に財産を分け与えることで、相続時の財産を減らしトラブルを回避します。
- ただし、生前贈与の一部は「特別受益」として相続財産に含まれることがあるため、遺留分を考慮した計画が必要です
専門家への相談
遺留分対策には専門的な知識が必要です。弁護士や税理士などの専門家に相談し、状況に合わせた最適な相続計画を立てることが、トラブルを未然に防ぐ上で非常に効果的です。
まとめ
遺言書を作成する際に遺留分を考慮することは、相続トラブルを防ぎ、被相続人の希望を最大限実現するために重要です。遺留分を侵害しない内容を工夫し、適切に遺言書を作成することで、相続人間の対立を未然に防ぐことができます。