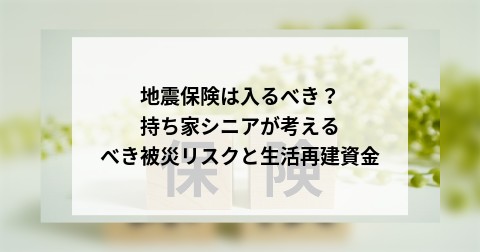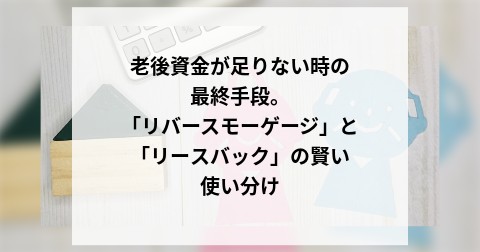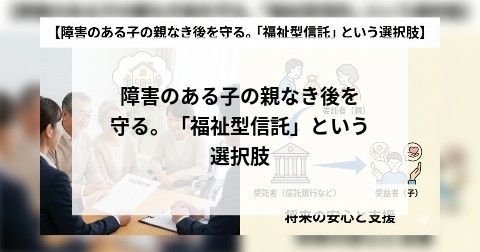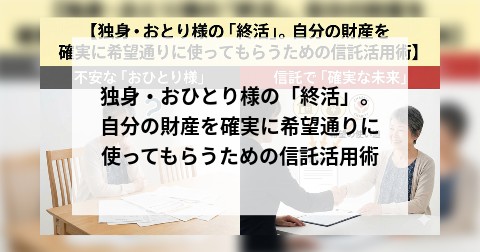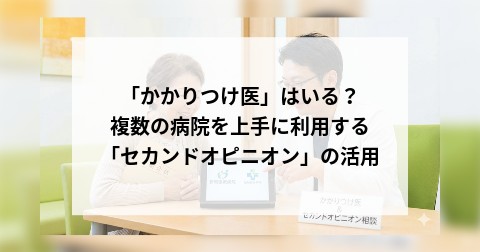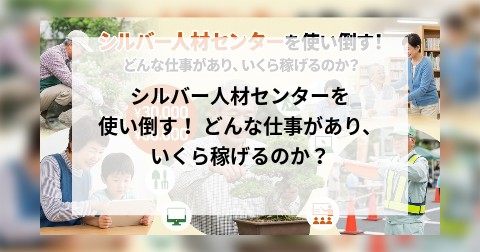子どもに負担をかけない!シニアのための「エンディングノート」活用術
「子どもに迷惑をかけたくない」「自分の人生の最期を自分らしく迎えたい」と考えるシニア世代が増えています。そんな思いを形にするための有効なツールが「エンディングノート」です。
エンディングノートは、もしもの時に備え、家族が困らないように自分の意思や情報をまとめておくノートです。この記事では、エンディングノートがなぜ必要なのか、そして子どもに負担をかけないための具体的な活用方法を解説します。
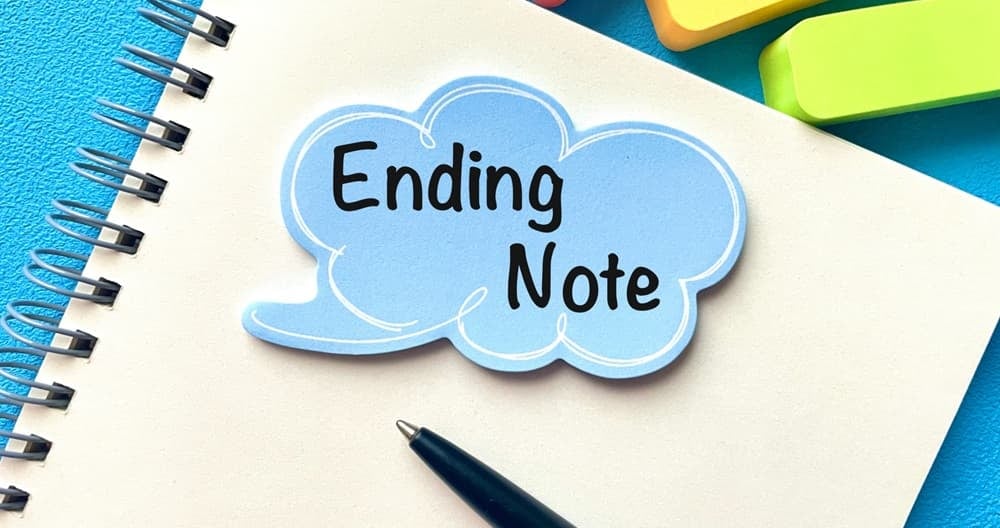
エンディングノートの目的は「情報共有」
エンディングノートは、法的な効力を持つ遺言書とは異なり、形式に決まりはありません。自分の死後のことだけでなく、これまでの人生や現在の状況を記録するための、いわば「自分史」です。
エンディングノートの一番の目的は、家族が困らないように情報や希望を共有することです。事前に情報を整理しておくことで、万が一のときに、家族が戸惑うことなく、スムーズに手続きを進めることができます。
エンディングノートが子どもを救う理由
家族の死は、ただでさえ悲しくつらいものです。その上、さまざまな手続きや手配に追われ、精神的・肉体的な負担はさらに大きくなります。
-
財産の所在が不明:どの銀行に口座があるのか、保険証券はどこにあるのか、子どもが把握していなければ、財産の整理に時間がかかってしまいます。
-
希望がわからない:どのような葬儀を望んでいるのか、お墓はどうしたいのか、子どもが故人の意思を知らなければ、判断に迷い、後悔する可能性があります。
-
人間関係がわからない:誰に訃報を伝えるべきか、大切な友人や知人の連絡先が分からなければ、関係を断絶してしまうことにもなりかねません。
エンディングノートは、これらの問題を解決し、子どもがスムーズに手続きを進められるようにする、親からの最後のメッセージです。
エンディングノート書くべき項目
エンディングノートに何を書けばいいのか悩む人もいますが、書くことを限定する必要はありません。つまり、人それぞれ自分自身が家族に伝えておきたいことを自由に書けばよいのです。しかし、家族にとっては「これを書いておいてくれたら助かる」ということはあります。
もしものときの連絡先
知人や友人、かかりつけ医等、一緒に暮らしていない家族でも、もしものときに連絡できるように、その人の名前や関係性、電話番号や住所等を書いておきます。
所有財産
こちらは、書くとなると面倒に感じる人も多いでしょう。そのため、書くというよりは関連する書類をこのノートとともに保管しておくことが大切です。以下に、一例を挙げておきます。
- 固定資産税通知書
- 通帳の表紙をめくった次のページのコピー
- 生命保険の証券
- 証券会社の残高証明書
1年に一度送られてくるものについては、毎年新しいものと差し替えておくとよいでしょう。
デジタルデータのIDとパスワードなど
こちらは、最近問題になりつつあるデジタル遺産についてです。IDとパスワードが分からければ、死後の手続きができないと問題になっています。
そのため、SNS関連やサブスクリプションの契約、インターネットバンクやインターネット証券に関するものなど、家族が困らないように書き残しておきましょう。
介護や延命治療、葬式や墓のことなど
介護状態になったときや延命治療を望むか望まないかという自分自身の命に関することは、家族に口頭でも伝えられます。しかしいざとなると、家族も「そう言っていたはずだけど……」と不安になります。本人の自筆で書き残してあれば、家族は家族自身が決めたのではなく本人が望んでいたのだ、と決定しやすくなります。
葬式や墓のことについても、同様のことがいえるので、家族に苦しい選択をさせないように書き残しておきましょう。
エンディングノート活用のためのアドバイス
-
市販のノートを活用する: 本屋さんにはさまざまな種類のエンディングノートが売られています。項目がすでに書かれているので、それに沿って埋めていくだけで簡単に始められます。
-
一度にすべて書こうとしない: 一度にすべてを完成させようとすると、途中で挫折してしまいがちです。少しずつ、気が向いたときに書き足していく感覚で取り組みましょう。
-
保管場所を共有する: エンディングノートを書いたことを家族に伝え、どこに保管しているのかを共有しておくことが大切です。
-
定期的に見直す: 住所や契約内容など、状況が変わることもあります。年に一度など、定期的に見直して情報を更新しましょう。
まとめ
エンディングノートは、自分自身の人生を振り返り、これからの生き方を考えるためのツールでもあります。そして、何よりも残された家族への思いやりを形にするものです。ぜひ、あなたのペースで始めてみてはいかがでしょうか。