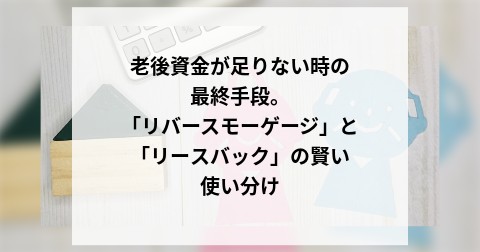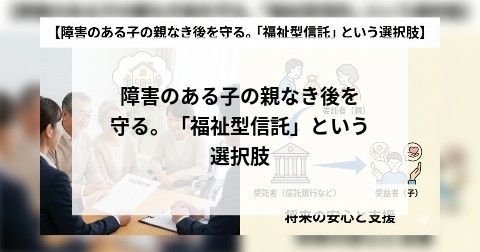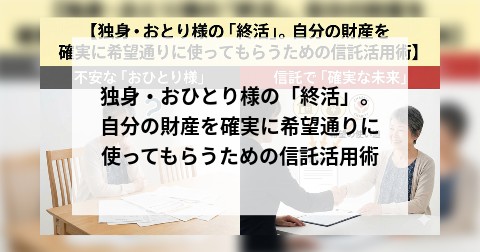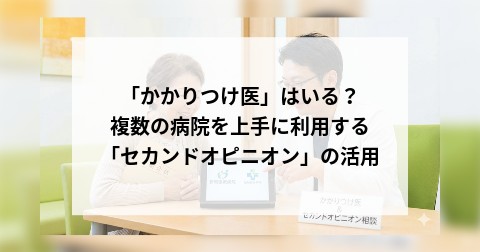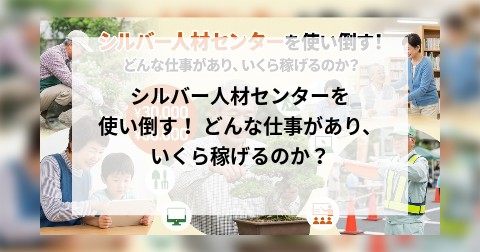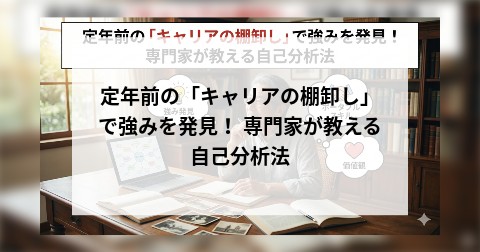「セカンドライフの充実度が劇的に変わる!定年後だからこそ始める “賢い移住” のススメ」
定年後の移住は、セカンドライフの充実度を劇的に変える大きなチャンスです。仕事の制約から解放され、本当に望んでいた暮らしを実現するための「賢い移住」について、ポイントを解説します。

定年とは、会社員生活のゴールであり、また新たな生活のスタートでもあります。人生100年時代と言われる今、定年後の移住は、より自分らしい生活を送るための大きなステップとなり得ます。
定年後の「移住スタイル」を見つける
定年後の移住には、一つの形だけではありません。ご自身のライフスタイルや理想に合わせて、最適な形を選びましょう。
| スタイル | 特徴 | メリット | デメリット・注意点 |
| 完全移住 | それまで住んでいた住居を手放し、新しい土地に生活の拠点を完全に移す。 | 心機一転、理想の土地で生活できる。地方では住居費や生活費が安くなる可能性がある。 | 医療機関やお店が少なく生活に不便を感じる場合がある。慣れるまでストレスを感じる可能性。 |
| 二拠点生活 | 今までの住居も維持しつつ、新たに住みたい場所に住居を持ち、2つの場所を行き来する。 | 従来の生活の利便性を保ちながら、新しい生活の楽しみも得られる。 | 2つの住居の維持費や移動の交通費がかかる。住んでいない間の防犯対策が必要。 |
| 地方移住 | 都会から地方へ移り住む。完全移住や二拠点生活の形で実現される。 | 自然豊かな地域で健康的な暮らしを送れる。 | 車がないと不便な地域もある。移住先のコミュニティや生活習慣になじめない可能性。 |
| 海外移住 | 日本より物価が安い国で、ゆとりのある生活を目指す。 | 生活コストを抑えられる可能性がある。長年の夢を叶えることができる。 | 言葉や文化の違い、病気や介護が必要になった際のハードルが高い。国内移住以上にしっかりとした準備が必要。 |
失敗しない!移住先を決める3つのポイント
定年後の移住先は、イメージだけで決めず、時間をかけて多角的に検討することが大切です。
①移住後の生活で「何を大切にしたいか」を明確にする
「自然の中でのゆとりある生活」「趣味の充実」「故郷に帰りたい」など、ご自身の希望をまず洗い出しましょう。その希望に沿った地域をピックアップします。
②日常生活の「利便性」をチェックする
高齢になると、車の運転ができなくなる可能性も考慮し、以下の点を検討しましょう。
-
買い物や通院などの日常生活に不便はないか
-
公共交通機関が利用できるか
-
シニアに対する医療や介護・福祉制度が整っているか
③事前調査を徹底する
候補地を見つけたら、すぐに引っ越すのではなく、必ずお試しで短期間住んでみることをおすすめします。できれば、四季を通じた気候を経験しておくと、移住後のギャップを減らせます。
成功に導くための3つの「賢い準備」
充実したセカンドライフのための移住を成功させるには、事前の準備が鍵となります。
ポイント1:資金計画を立てる
移住には引っ越し費用や新居の購入費用がかかります。また、地方移住で生活費が安くなるのが一般的ですが、寒冷地では光熱費がかさむ、車が必須など、地域特有の出費も考慮が必要です。
最も重要なのは、移住後の病気や介護のリスクに対する資金をしっかり備えておくことです。不安のないように、綿密な資金計画を立てましょう。
ポイント2:家族に相談する
移住は、ご自身だけでなく家族の生活にも関わる大きな決断です。特に配偶者とは、これからどのような生活を送りたいのかをじっくり話し合い、両者が納得した上で進めることが大切です。子どもに対しても、移住先での生活スタイルや将来の見通しを共有しておきましょう。
ポイント3:現在住んでいる家をどうするか決めておく
完全移住の場合、今の家を手放す(売却・賃貸に出す)という選択肢が考えられます。老後の生活を考えると、家は保有しているだけでコストと手間がかかるため、できるだけ生活をコンパクトにしておくことがおすすめです。売却して新生活の資金に充てることも賢い選択肢の一つです。
また、自治体によっては、移住希望者に対して移住支援制度やお試し移住、空き家紹介などの支援を行っている場合があります。移住先を探す際には、こうした支援制度があるかも確認し、積極的に利用しましょう。
まとめ
定年後の移住は、仕事や子どもの教育環境などに縛られず、「自分が本当に送りたかった生活」に踏み出す絶好のチャンスです。しっかりと情報収集を行い、家族と話し合いながら、自分に合った最適な移住先を見つけ、充実したセカンドライフを送りましょう。
【関連記事】趣味と健康を両立!定年後に輝くための「理想の移住先」選び方と失敗しないステップ
【関連記事】不安解消!支援制度をフル活用し、安心して移住を実現する「シニア向け地域」5選
【PR】移住の資金準備のための資産運用を今から始めてみては?
| 【PR】まとまった資金の個別相談は投資信託相談プラザへ |