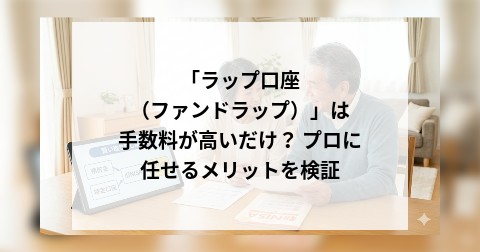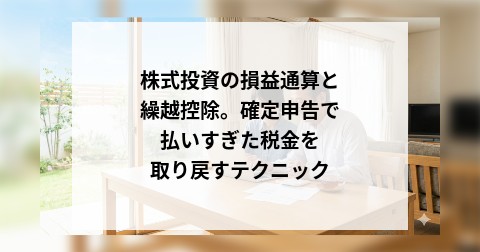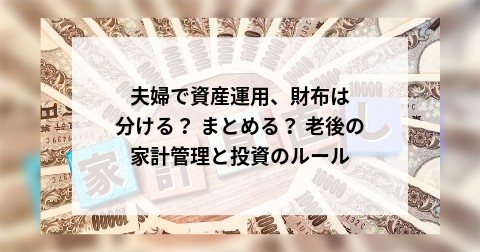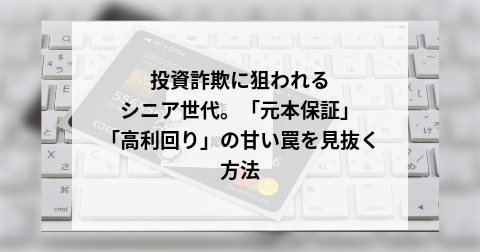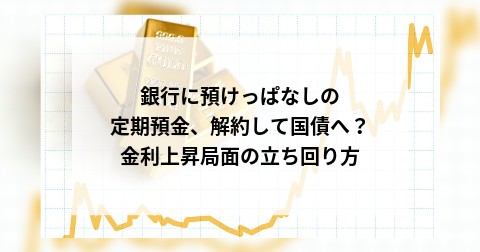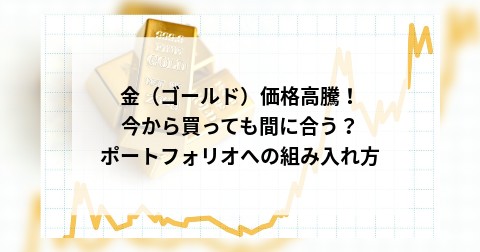投資信託の「出口戦略」:老後生活で資産を賢く取り崩すための5つのルール
長年にわたり積み立ててきた投資信託。いざ老後を迎え、その資産を「取り崩す」フェーズに入ると、資産形成期とは異なる戦略、すなわち「出口戦略」が必要になります。
ただ漠然と売却していては、「資産寿命」が尽きてしまうリスクがあります。ここでは、賢く、計画的に資産を取り崩し、老後生活を豊かにするための5つの重要なルールを紹介します。

ルール1:資産を「使い道」で3つのブロックに分ける
資産形成期は一つの目標に向かって積み立てますが、取り崩し期では資産を性質や使い道によって3つのブロックに分けることで、安心して生活できます。
| ブロック | 目的・必要時期 | 運用方法 |
| 短期資金 | 1~3年以内に必要となる生活費、旅行などの資金 | 預貯金、MRFなど、元本割れリスクのない安全な資産 |
| 中期資金 | 3年~10年後に必要となる資金、イベント資金 | 低リスクの債券型投信やバランスファンド、個人向け国債 |
| 長期資金 | 10年後以降の生活費、インフレ対策を兼ねた資金 | 株式中心の投資信託など、運用益を狙ったリスク資産 |
この短期資金(生活防衛資金)を確保しておくことで、相場が急落しても、慌てて長期資産を売却する必要がなくなり、資産寿命を延ばすことができます。
ルール2:「運用しながら取り崩す」を基本とする
老後の期間は20年〜30年と長く、この間に物価が上昇する(インフレ)リスクや、資産が目減りするリスクに備える必要があります。
そのため、すべての資産を現金化するのではなく、長期資金は運用を継続しながら取り崩すことが賢明です。
4%ルールを参考に、目標取り崩し率を決める
欧米の資産運用で知られる「4%ルール」は、資産全体を年率4%(インフレ調整後)で取り崩した場合、高い確率で30年間資産が尽きないという考え方です。
このルールはあくまで目安ですが、老後の取り崩し額を決める際の一つの基準として参考にし、「年間の取り崩し率」を決定しましょう。公的年金で賄えない不足分を、この取り崩しで補うという考え方です。
ルール3:「定額」と「定率」の取り崩しを使い分ける
資産の取り崩し方には、主に「定額取り崩し」と「定率取り崩し」があり、老後の時期に応じて使い分けることが推奨されます。
| 取り崩し方法 | 概要 | 特徴と適した時期 |
| 定額取り崩し | 毎月(毎年)決まった金額を取り崩す | 年金と生活費の差額が明確な老後後半に有効。資産が減りやすい。 |
| 定率取り崩し | 資産残高に対して一定の割合を取り崩す | 資産残高の減少に伴い取り崩し額も減るため、資産寿命が延びる。老後前半に有効。 |
組み合わせ戦略の例
-
老後前半(65歳〜75歳頃):資産を減らしすぎないよう、残高に応じて取り崩し額が変わる「定率取り崩し」を主体とする。
-
老後後半(75歳以降):公的年金などで収入が安定し、毎月の不足額が明確になったら、シンプルで分かりやすい「定額取り崩し」に切り替える。
ルール4:暴落時には「取り崩しを一時中断」する
資産形成期に「ドルコスト平均法」が有効であったように、取り崩し期においても市場の状況に左右されない冷静な判断が必要です。
株価が大きく下落した「暴落時」に投資信託を売却すると、元本が大きく毀損し、回復が難しくなります。
この時に役立つのが「ルール1:短期資金のブロック」です。短期資金を取り崩すことで、暴落時の運用資産の売却を避け、回復を待つことができるようになります。短期資金は最低でも2〜3年分の生活費を確保しておきましょう。
ルール5:非課税口座(NISA・iDeCo)からの優先的な取り崩しを検討する
税制優遇制度を活用して資産形成を行った場合、取り崩し時にもそのメリットを最大限に活かすことが重要です。
| 口座 | 特徴 | 取り崩しの優先度 |
| iDeCo(イデコ) | 全額非課税で受け取れるが、一時金か年金かの選択が必要。所得税・住民税の課税対象になる場合がある。 | 受給時の税負担を考慮し、他の年金や所得とのバランスを見て計画的に。 |
| NISA(ニーサ) | 運用益は全額非課税。いつでも自由に売却可能。 | 一般NISAやつみたてNISAで得た非課税の利益をまず取り崩すことを検討する。 |
| 特定/一般口座 | 売却益に約20%の税金がかかる。 | NISA・iDeCoの後に取り崩し、課税される利益の額を抑える。 |
非課税の恩恵を最大限に享受するため、原則としてNISAで運用した資産から優先的に取り崩し、課税口座の資産は最後まで残す、という順序を検討しましょう。
まとめ-賢い出口戦略で「資産寿命」を延ばす
投資信託の出口戦略は、資産を「いつ・いくら・どこから」取り崩すかという綿密な計画がすべてです。
5つのルールを参考に、ご自身の年金額や生活費を考慮したシミュレーションを行い、「資産寿命」と「人生の寿命」を一致させることを目指しましょう。定期的に資産状況を見直し、必要に応じて取り崩し計画を修正する柔軟性も大切です。