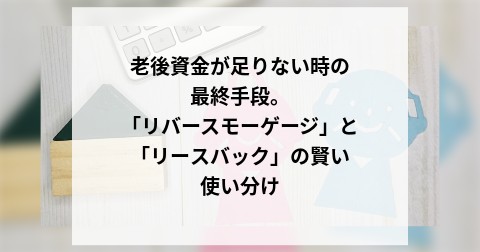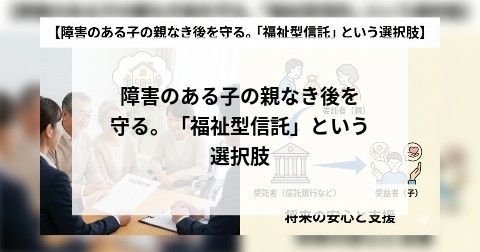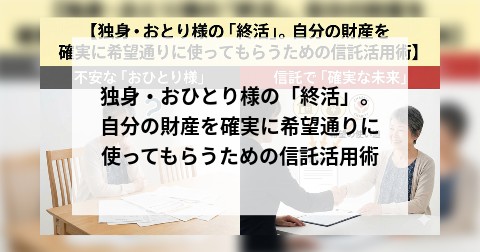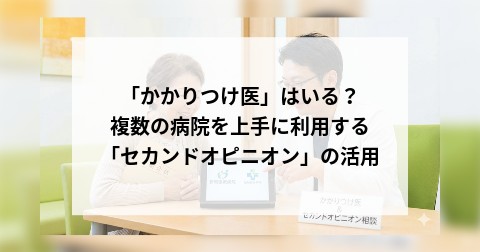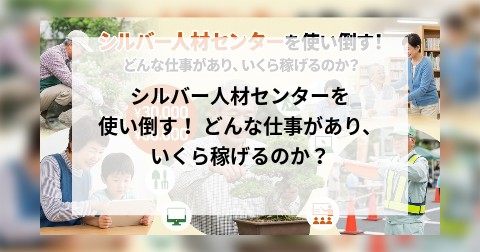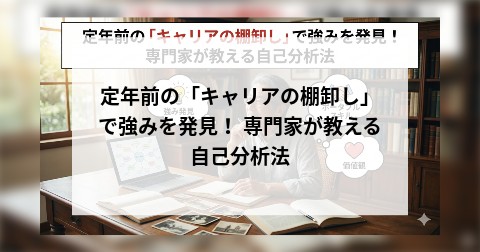遺品整理、生前整理で揉めないための家族と協力する上手な進め方
親の死後、あるいはご自身の老後を考えた時に、頭を悩ませるのが「遺品整理」や「生前整理」です。
「親が大事にしていたものを勝手に捨てられない」「何から手をつけていいかわからない」「兄弟姉妹で意見が合わない」といった理由から、なかなか作業が進まず、家族間のトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。
今回は、遺品整理や生前整理をスムーズに進め、家族が協力して取り組むための上手な進め方をご紹介します。
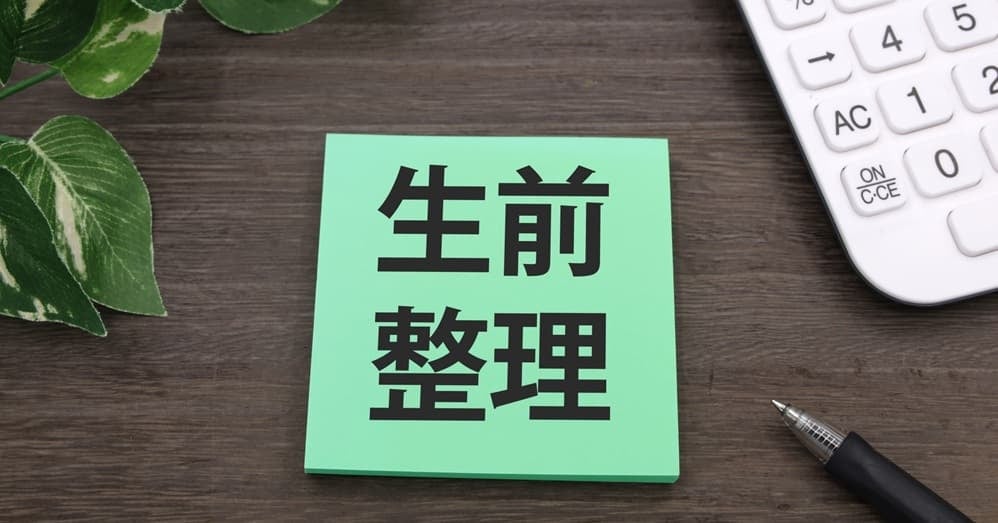
整理を始める前に「話し合いの場」を設ける
遺品整理や生前整理は、個人的な感情や思い出が深く関わるものです。まずは、家族全員が顔を合わせ、率直に話し合う場を設けましょう。
-
誰が主導するのかを決める:中心となって動く人を決めることで、作業が円滑に進みます。全員で分担するのか、特定の人が中心となって進め、他の家族がサポートするのかなど、役割分担を明確にしましょう。
-
整理の目的を共有する:「故人の思い出を大切に引き継ぐ」「住まいを次の世代へ引き継ぐ」「親の老後の生活を快適にする」など、何のために整理を行うのか、全員で目的を共有することで、方向性がぶれにくくなります。
-
「いるもの」「いらないもの」の基準を決める:思い出の品や、価値があるかどうかわからないものについて、どのような基準で処分するか、あるいは残すかを話し合っておきます。後から「これは捨てないでほしかった」といったトラブルを防ぐことができます。
遺品整理・生前整理で揉めがちなポイント
なぜ遺品整理や生前整理は揉めることが多いのでしょうか?主な原因は以下の3つです。
-
物の価値観の違い: 「これは貴重な骨董品だ」と考える人もいれば、「ただの古いガラクタだ」と思う人もいます。物の価値観は人それぞれであり、それが対立の原因になります。
-
思い出の品の扱い: 親が大切にしていた物、家族の思い出が詰まった物など、捨てていいかどうかの判断が難しくなります。
-
作業の負担: 誰が、いつ、どのくらいの時間をかけて作業するのか、役割分担が不明確だと、特定の家族に負担が集中し、不満が溜まりやすくなります。
遺品整理と生前整理の違い
遺品整理とは、故人が生前に使っていた家具や衣類、日用品、書類などの家財を整理・処分する行為を指します。
それに対しして、生前整理とは、自分自身が元気なうちに、身の回りのものや財産、情報を整理しておく行為です。
以下が比較したものになりますので参考にしてください。
| 遺品整理 | 生前整理 | |
| 目的 | 故人が亡くなった後に行う家財整理 | 元気なうちに自分で進める身辺整理・終活 |
| タイミング | 死後数日~相続発生後 | 介護・相続・看取りの備えとして今から始められる |
| 関わる人 | 遺族・相続人中心 | 本人・家族・福祉関係者・専門家も |
遺品整理の進め方
①遺言書・相続人の確認
遺品整理に取りかかる前に、まず確認すべきなのが遺言書の有無と相続人の範囲です。故人がどのような意思を残していたかによって、物の取り扱いや分配の方法が変わってくるため、この確認作業は、整理の前提となる大切なステップです。
公正証書遺言であれば、公証役場に照会することで内容を確認できますし、自筆証書遺言であっても、家庭裁判所の「検認」を受けたうえで法的な効力が認められます。遺言書が見つかった場合は、勝手に開封せず、必ず法的手続きを踏むことが必要です。
②財産/形見の仕分け
遺言書や相続人が確認できたあとは、遺品の中身を分類・仕分けする作業に入ります。
この段階では、家財や私物を「財産として扱うもの」「形見として残すもの」「処分するもの」に分けていくことが求められます。通帳や有価証券、不動産に関する書類などは相続財産としての取り扱いが必要となるため、不用意に処分したり移動させたりしないよう注意が必要です。また、預かりものやレンタル品など、故人の所有物ではないものが混じっているケースもあるため、確認は慎重に行う必要があります。
一方で、写真、手紙、日記、趣味の道具などは、形見分けの対象になることが多く、ご遺族それぞれが想いを寄せる中で、どのように扱うかを話し合う場面も生まれます。
③家財の処分・供養(必要に応じ業者活用)
仕分けが終わると、次に考えるのは不要となった家財や遺品の処分方法です。家具や寝具、家電製品などの大型品は、自治体のルールに沿って処分する必要があり、作業量によっては家族だけで対応するのが難しい場合も少なくありません。また、仏壇や人形、遺影、手紙など、処分にためらいを感じる品に対しては、廃棄ではなく「供養」という選択肢もあります。
生前整理の進め方
家財・不用品の整理(断捨離)
生前整理の第一歩は、身の回りの物を見直すことから始まります。長年使っていない家具や衣類、増えすぎた生活雑貨など、少しずつ手放していくことで、空間にも心にも余裕が生まれます。「いる」「いらない」の判断を繰り返す中で、自分が何を大切にしているのかが、少しずつ見えてくることもあります。ひとつずつ、今の自分にとって必要かどうかを確かめていくことが、生前整理のはじまりです。
財産・契約関係の棚卸し
家の中が整ってきたら、次はお金や契約の整理に目を向けます。通帳、保険証券、不動産の書類、年金手帳など、重要な書類をまとめておくだけでも、いざという時の負担は大きく減ります。また、見落としがちなものとして、携帯電話やサブスクリプションなど、日常の契約を見直すことも忘れてはいけません。不要な出費を抑えるだけでなく、死後の手続きがスムーズになるメリットもあります。
エンディングノートや遺言書の作成
生前整理の仕上げとして、自分の意思を文字で残すという選択があります。エンディングノートには、家族へのメッセージや希望、医療・葬儀・財産のことなど、“もしも”に備えた情報を記しておくことができます。法的効力はありませんが、気持ちを伝える手段として多くの人に活用されています。一方で、相続に関わる内容については、正式な遺言書を残すことでトラブルの回避にもつながります。
[PR]タンスの肥やしになっている着物や貴金属、実は意外な高値がつくかもしれません。生前整理として、一度プロに査定してもらい、老後の楽しみに使うお小遣いに変えませんか?
まとめ
遺品整理や生前整理は、故人や親の人生を振り返る大切な時間でもあります。この機会を「家族の絆を深めるための時間」と捉え、お互いを尊重し、協力し合うことで、きっと良い形で終えることができるはずです。