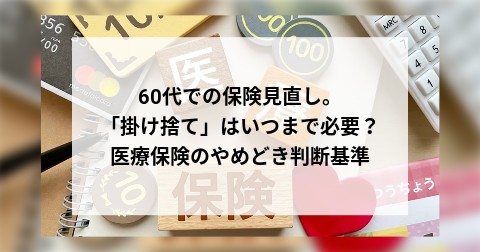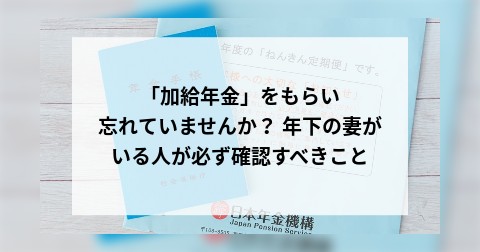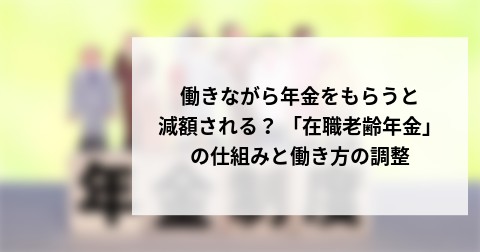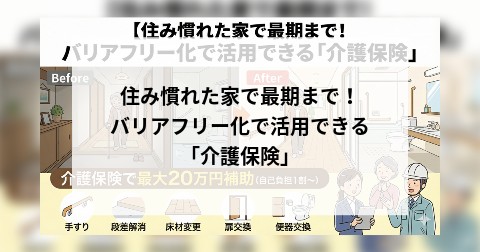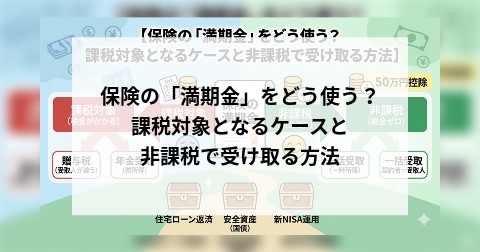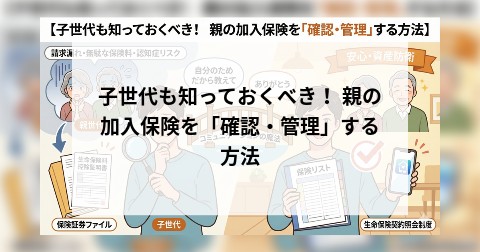介護保険って何?申請からサービス利用まで、知っておくべきことの全て
介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みです。しかし、「何歳から利用できるの?」「どうやって申請するの?」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、介護保険の基本的な仕組みから、申請方法、そしてサービス利用までの流れをわかりやすく解説します。

介護保険の基本をおさらい
介護保険とは、介護や支援が必要な方(要介護者・要支援者)に、介護や介護予防でかかる費用の一部を給付する制度です。
介護保険制度を利用すると、65歳以上の要介護状態または要支援状態になった方が訪問介護や訪問看護といった介護サービスを利用した場合、サービスにかかった費用の一部を保障してもらえます。
介護保険の仕組み
介護保険制度は、以下の3者から構成されています。
● 被保険者
● 保険者
● 介護サービス事業者
被保険者とは、介護保険料を支払っている方のことです。特定の要件を満たした際は、1~3割の自己負担割合で介護サービスを受けられます。
保険者とは、公的介護保険制度を運営している市町村・特別区(東京23区)のことです。
介護サービス事業者とは、実際に介護サービスを提供している人や団体を指します。
介護保険のサービスを利用できる人
介護保険のサービスを利用できる人(被保険者)は、次の通りです。
・第1号被保険者:65歳以上の人
・第2号被保険者;40歳以上64歳以下で医療保険に加入している人
40歳以上の人、すなわち被保険者は、保険料(介護保険料)を支払う義務があります。保険料を支払うことで、介護が必要になったときに、市区町村に申請し、手続きを経ることで、介護保険の保険料・税金による補助を受け、利用料の1割から3割を自己負担するだけで、サービスを利用することができるのです(サービスの種類によっては、別に費用がかかる場合があります)。
介護保険の申請方法
申請者
要介護認定の申請は、基本的には本人から行うものですが、家族のほか、特別養護老人ホーム・老人保健施設などの介護保険施設や、居宅介護支援事業者(介護サービス計画作成事業者)が代行して行うこともできます。
原則として、認定は申請の日から30日以内に行われます。
申請に必要な書類
要介護認定に必要な書類は次のとおりです。
| 被保険者の区分 | 申請に必要な書類 |
| 第1号被保険者 | 申請書、被保険者証 |
| 第2号被保険者 | 申請書、被保険者証(被保険者証が交付されてない方は、医療保険被保険者証) |
※ 申請の方法は各市町村の介護保険担当窓口にご相談ください。
要介護認定の手続き
申請を受けた市町村は、ご本人の状態を確認するため、調査員による訪問調査を行うとともに、申請書で指定された主治医に対して意見書の提出を依頼します。
訪問調査の結果と主治医意見書を基にコンピュータによる一次判定を行った後、市町村等が設置する介護認定審査会で審査を行い、要介護度が決定されます。
要介護認定の基本設計
要介護認定は、原則として、要介護認定等基準時間と呼ばれる「介護の手間」の総量の判断によって審査判定が行われます。
病状の重篤さや認知症の進行状況などの本人の「状態像」ではなく、介護者の「介護の手間」の多少で審査判定されます。
介護サービスの利用法
要介護認定されると、介護保険で以下のようなサービスが受けられます。
(1)居宅介護支援
ケアプランの作成、家族の相談対応など
(2)自宅に住む人のためのサービス(居宅サービス)
<訪問型サービス>
・訪問介護①生活援助(掃除や洗濯、買い物や調理など)
・訪問介護②身体介護(入浴や排せつのお世話)
・訪問看護(医師の指示のもと、看護師が健康チェックや、療養上の世話など)
・訪問入浴介護(自宅に浴槽を持ち込み入浴介助を受ける)
・訪問リハビリテーション(リハビリの専門家に訪問してもらい、自宅でリハビリを受ける)
・居宅療養管理指導(医師、歯科医師、薬剤師、栄養士などに訪問してもらい、療養上の管理・指導を受ける)
<通所型サービス>
・デイサービス(食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するためのリハビリやレク、「おいしく、楽しく、安全に食べる」ための、口腔清掃や口唇・舌の機能訓練などを日帰りで行う)
・デイケア(施設や病院などで、日常生活の自立のために理学療法士、作業療法士などがリハビリを行う)
・認知症対応型通所介護(認知症と診断された高齢者が利用するデイサービス)
<短期滞在型サービス>
・ショートステイ(施設などに短期間宿泊して、食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するためのリハビリの支援など。家族の介護負担軽減や施設入居準備などに利用できる)
(3)施設に入居するサービス(施設サービス)
・特別養護老人ホーム(特養)
・介護老人保健施設(老健)
・介護医療院
(4)福祉用具に関するサービス
・介護ベッド、車イスなどのレンタル
・入浴・排せつ関係の福祉用具の購入費の助成(年間10万円が上限で、その1~3割を自己負担することで購入できる)
(5)住宅改修
・手すり、バリアフリー、和式トイレを洋式にといった工事費用に補助金が支給される。最大20万円まで。利用者はその1割~3割を負担。
まとめ
介護保険サービスの利用料は、原則として費用の1割を自己負担します。ただし、所得に応じて自己負担が2割または3割になる場合があります。また、食費や居住費、日常生活費などは、別途自己負担となります。
介護保険は、高齢者だけでなく、その家族の負担も軽減してくれる重要な制度です。ご自身やご家族のために、ぜひ活用を検討してみてください。