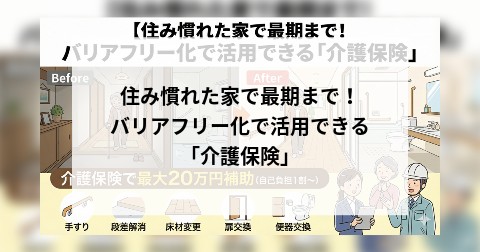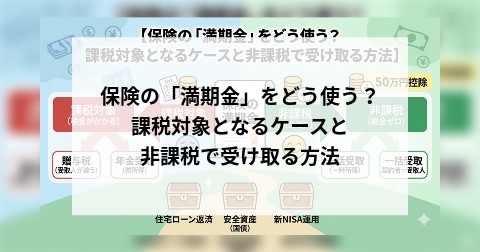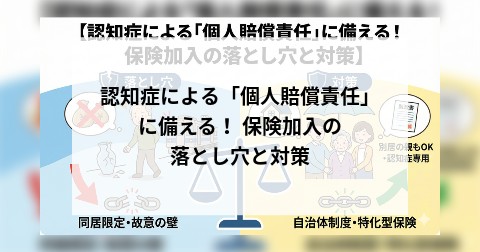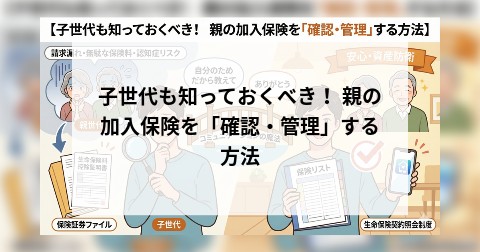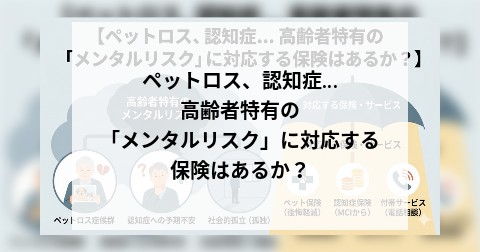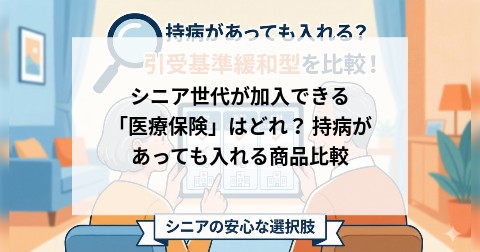「定年貧乏」にならないための老後資金を長持ちさせる節約と賢い出費
長寿化が進む現代において、定年後の生活は「人生の第二ステージ」とも言えます。しかし、公的年金だけでは生活費が不足すると言われており、「定年貧乏」への不安を抱えるシニア世代は少なくありません。
この記事では、定年後も安心して暮らすために、老後資金を長持ちさせるための「賢い節約術」と「価値ある出費」について解説します。

定年後に見直すべき「賢い節約術」
定年後、現役時代と同じ感覚でお金を使っていると、あっという間に貯蓄が底をついてしまう可能性があります。まずは、以下の支出を徹底的に見直しましょう。
固定費の見直し
収支と使途不明金を把握し、預貯金の目標額を決めたら、次は家計を見直していきましょう。まずは固定費の見直しです。固定費は毎月ほぼ定額の支出のため、少し見直すだけでも大きな節約効果を得られます。
固定費の分け方には特に決まりはありませんが、次の細目に分けることが一般的です。
- 住居費
- 水道光熱費
- 通信費
- 保険料
- 自動車関連費
住居費
賃貸住宅に暮らしている場合、家賃が低い住宅に引っ越すことで住宅費を抑えられます。家賃が高いと感じるときは、引っ越しも検討してみましょう。
住宅ローンの返済が家計を圧迫しているときは、借り換えも検討してみましょう。金利が低い住宅ローンに借り換えることで、利息を減らせることがあります。
ただし、借り換える際には手数料がかかるため、返済期間や借入残高があまり残っていないときは利息軽減効果がほとんどない可能性があります。借り換えによりどの程度利息を軽減できるのか、手数料も含めてシミュレーションしてみてください。
水道光熱費
水道や電気、ガスなどの水道光熱費は使用量によって金額が変わりますが、固定費として分類されることが一般的です。季節によって異なるため、1年間の記録をつけておおよその目安を把握しておきましょう。
通信費
インターネット通信費や携帯電話料金も見直してみましょう。オプションが必要かどうか、プランが適切か確認します。
保険料
健康保険や年金保険といった公的保険以外にも、民間の保険に加入している方も多いのではないでしょうか。例えば、生命保険や火災保険、損害保険などに加入している方もいるでしょう。
必要な保険は、ライフステージやライフプランによっても変わります。加入した時点では必要と思われた保険も、現在の状況には合っていないかもしれません。無駄な出費を抑えるためにも、定期的に保険を見直すことが大切です。
自動車関連
車を所有している場合は、駐車場代や自動車保険料、自動車税などが必要になります。自動車にかかる費用以上に活用できているか、一度見直してみるとよいでしょう。
例えば、通勤や通学、普段のショッピングといった日常生活に利用していない場合は、車の必要性は低いと考えられます。休日のお出かけにのみ車を使っているなら、レンタカーやカーシェアリングを利用してみてはいかがでしょうか。
資産の活用
「貯める」だけでなく、資産運用で「増やす」ことも検討する
預貯金で貯めるだけでなく、運用で資産を増やすことにも取組んでみましょう。
老後資金準備には、以下のような金融商品や制度が向いています。
- NISA(ニーサ。少額投資非課税制度)
- iDeCo(イデコ。個人型確定拠出年金)
- 貯蓄型保険
- 付加年金(国民年金加入者の場合)
- 国民年金基金(国民年金加入者の場合)
投資信託や株式投資、ETF、REIT等への投資は、運用益が非課税となるNISAを利用すると運用効率が高まりやすくなります。投資信託への投資にはiDeCoを使うこともできます。
ただし、価格が変動するタイプの投資商品は、元本割れするリスクもあることに注意が必要です。
変額保険や個人年金保険といった、貯蓄型保険も資産運用の手段のひとつです。
保険を活用すれば、貯蓄をしながら万一のときの保障が得られるので、老後資金準備やお子さまの教育資金準備としても役立てることができます。
ただし、変額保険は死亡・高度障害保険金には最低保証があるものの、満期保険金・解約払戻金には最低保証額がなく、特別勘定の運用実績によって増減するので注意が必要です。
また、変額保険も個人年金保険も、解約のタイミングによっては払込保険料総額を下回る可能性があるので、併せて注意が必要です。
働ける間は仕事を続ける
60代以降の就労は、老後資金をふやす効果的な方法です。現在は高年齢者雇用安定法により、希望者に対して65歳までの雇用確保が企業に義務付けられ、さらに70歳までの就業機会の確保も努力義務となっています。60歳以降も働きやすい環境が整いつつあるため、引き続き厚生年金に加入して保険料を納め続ければ、将来受け取れる年金額も増加します。
年金の繰り下げ受給
まとめ
老後資金は夫婦二人で約3,000万円が目安ですが、現状の資産と年金収入をもとに不足分を割り出し、計画的に準備を進める必要があります。その際、資産運用でお金の寿命を延ばすように心がけましょう。また、老後資金として必要なお金を目的別に考えると現在の貯蓄と必要な資金の不足が具体的になり、計画的な貯蓄がしやすくなります。