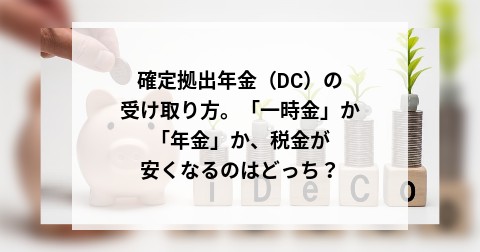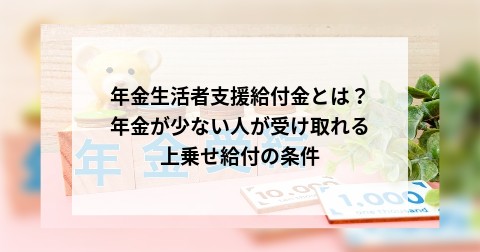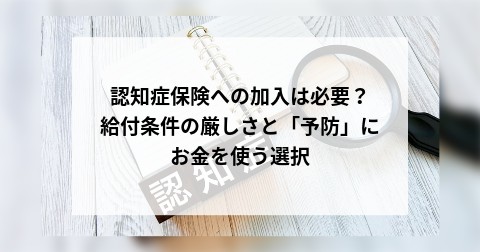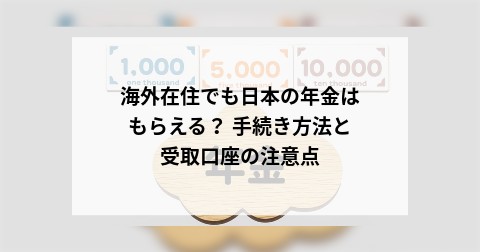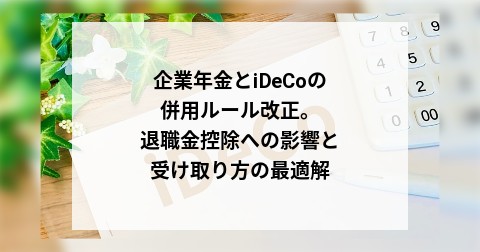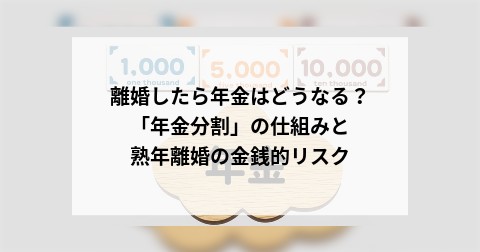預金を生命保険に変えるだけ!今日からできる相続税対策と「非課税枠」
「相続税対策」と聞くと、「複雑で難しそう」「資産家がやるもの」というイメージを持つ方も多いかもしれません。
しかし、実は今日からすぐに始められる、シンプルで効果的な相続税対策があります。それが、預貯金を生命保険に変えるという方法です。
ここでは、生命保険がなぜ相続税対策に有効なのか、その仕組みと、知っておきたい「非課税枠」について解説します。
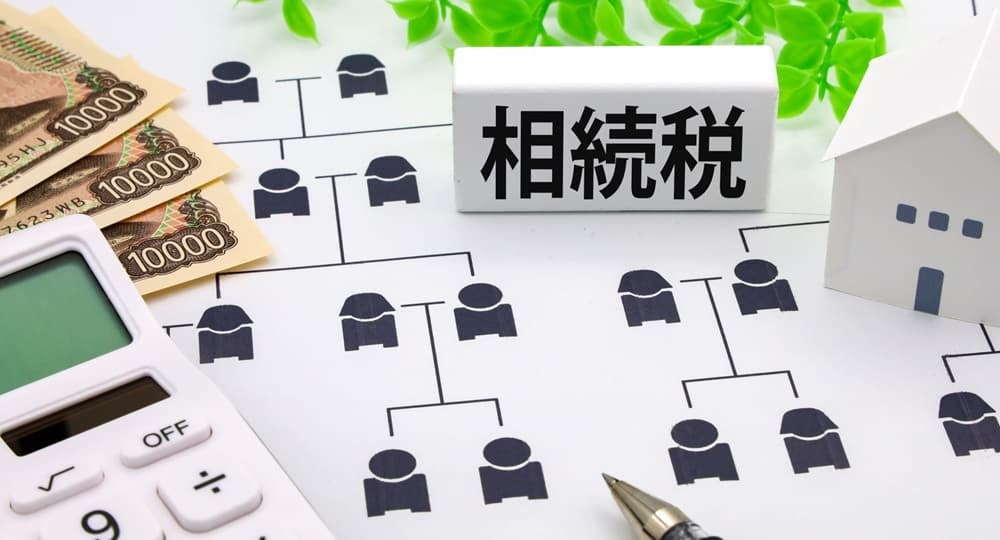
なぜ生命保険が相続税対策になるのか?
生命保険の契約において、所定の要件を満たした場合に保険金受取人が受け取れる死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
これは、死亡保険金は故人が所有していた財産ではないものの、死亡を原因として支払われるお金のため、相続財産とみなされるのです。
一方で、一定の要件を満たす必要はありますが、生命保険の死亡保険金には「非課税枠」があります。この非課税枠が、相続対策としてよく活用されています。
生命保険における死亡保険金の非課税枠と非課税限度額とは
生命保険の死亡保険金には非課税枠があると説明しましたが、この非課税枠に基づいて、非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算できます。そのため、法定相続人の数によって、非課税限度額が増減します。
一方で、相続税には基礎控除があり、「基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出される金額までは、相続税がかかりません。
死亡保険金の非課税枠は、この相続税の基礎控除とは別に適用されるため、非課税枠を利用することで相続税の負担をより軽減できます。そのため、相続対策として生命保険を活用するとよいのです。
生命保険の死亡保険金は、残された家族の生活を保障するという大切な役割があります。
そのため、相続人が受け取った死亡保険金については、一定金額まで相続税がかかりません。
具体的には、全ての相続人が受け取った死亡保険金の合計額のうち「500万円×法定相続人の人数」で計算される非課税限度額を超える部分に相続税がかかります。
例えば、法定相続人が3人である場合、非課税限度額は500万円×3人=1,500万円です。
ただし、相続人が法的な親子関係を結んだ「養子」である場合、生命保険金の非課税限度額の計算時にカウントできる人数は、以下のとおり制限されます。
- 被相続人に実子がいる場合 :1人まで
- 被相続人に実子がいない場合 :2人まで
一方で、相続人のなかに相続を放棄した人がいても、相続税の計算上は放棄がなかったものとして非課税限度額は計算されます。
生命保険で相続対策をするメリット
生命保険を活用することで相続税の負担を軽減できることを説明してきましたが、ここからは具体的なメリットを見ていきましょう。
|
生命保険に加入していない場合は、預金などの保有資産すべてが相続財産とみなされ、相続税がかかります。
一方で、預金の一部を使って生命保険(一時払い終身保険)に加入した場合は、相続財産の総額が減少し、相続税の課税対象額も抑えられます。
さらに、死亡保険金の非課税枠を活用することで、非課税限度額までは相続税がかからず、結果として相続税の負担を軽減できます。
生命保険を活用した相続対策
生命保険の保険金が「相続財産に含まれず、受取人固有の財産になる」という特徴を活かして、相続対策に用いられるケースは少なくありません。
ここでは、生命保険を活用した相続対策について具体的に解説します。
納税資金として活用する
相続税の納税期限は、被相続人が亡くなってから10カ月以内です。また、相続税は原則として一括で納付しなければなりません。
仮に相続財産のほとんどが不動産である場合、期限までに不動産を売却して換金しなければ、納税資金を準備できない可能性があります。
不動産の買い手が見つからなかった場合、相続人自身の財産からの納税が必要になるかもしれません。
そこで、保険金の受取人が相続人である生命保険に加入していれば、支払われた死亡保険金を納税資金として活用できます。
生前贈与として活用する
生前贈与は、生きているうちに財産を配偶者や子ども、孫など特定の人へ贈与することです。
贈与された金額が年間で110万円以内である場合、贈与税はかかりません。
そこで、子どもや孫に110万円以内の財産を贈与し、生命保険の保険料を支払ってもらう方法があります。
例えば、子どもが保険料の負担者かつ受取人、被保険者が父親である生命保険に加入するとしましょう。
保険料は、父親から贈与された財産をもとに支払います。
父親が亡くなったとき子どもが受け取る死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となり、相続財産には含まれません。
子どもに贈与された財産の額が110万円以下であれば、贈与税は非課税です。
また、死亡保険金額と払込保険料総額の差が50万円以内であれば、所得税もかかりません。
代償分割する際の相続分として活用する
代償分割とは、相続人のうちの1人または数人が遺産を現物で取得します。
その現物を取得した人が、他の相続人に対し債務を負担する(代償金、その他の財産を支払う)遺産の分割方法です。
代償分割は、現物の分割が困難な場合に利用されます。
例えば、遺産が4,000万円の自宅と1,000万円の現金であり、相続人が配偶者と長男、長女の3人であったとしましょう。
配偶者が4,000万円の自宅を相続すると、長男と長女はそれぞれ500万円ずつの現金しか相続できなくなってしまいます。
そこで、配偶者が自宅を相続する代わりに、長男と長女に対して一定額の代償金を支払って精算するのが代償分割です。
代償分割をするためには、不動産や車などの現物を相続する人が代償金を支払うための財産を持っていなければなりません。代償金を支払う可能性がある相続人を受取人にして生命保険に加入することで、死亡保険金を代償金の支払いに充てられます。
特定の相続人に財産を遺す
亡くなった人が残した財産は、遺言がない場合は相続人同士で遺産分割協議をして引き継ぎ方を決めます。そのため、亡くなった人の意思に沿って財産が相続されるとは限りません。
そこで、生命保険に加入して、特定の相続人に財産を渡す方法があります。生命保険の保険金は受取人固有の財産であり、遺産分割協議の対象にならないためです。
例えば、献身的に介護をしてくれた長女に1,500万円の現金を遺すとしましょう。その場合、以下のような契約内容の一時払い終身保険への加入が有効です。
終身保険とは、途中で解約をしない限り死亡または高度障害の保障が一生涯にわたって続く生命保険です。
- 契約者かつ被保険者:自分自身
- 保険金の受取人:長女
- 加入時に支払う保険料:1,500万円
- 死亡保険金:1,500万円
上記のような契約内容の一時払い終身保険に加入すると、自分自身が亡くなったとき受取人である長女に1,500万円の現金を渡すことができます。
まとめ
「預金を生命保険に変える」という簡単な方法で、相続税を賢く減らし、スムーズな相続を実現することができます。今日からできる相続税対策として、まずは非課税枠を計算し、ご自身の状況に合った生命保険を検討してみてはいかがでしょうか。未来の「安心」のために、今できることから始めてみましょう。