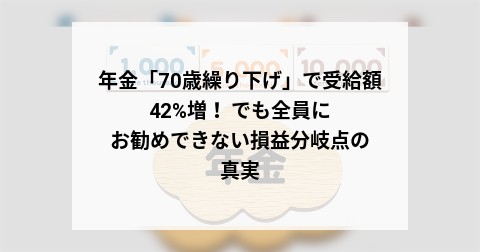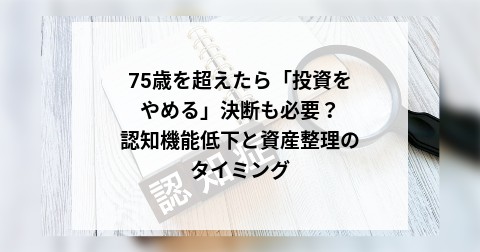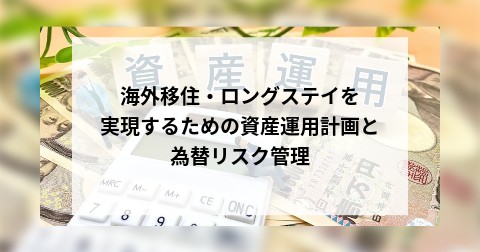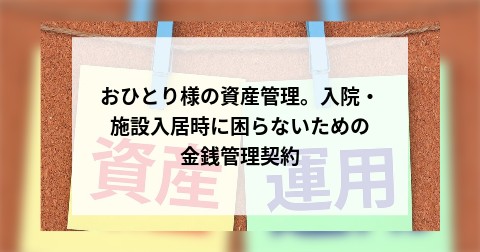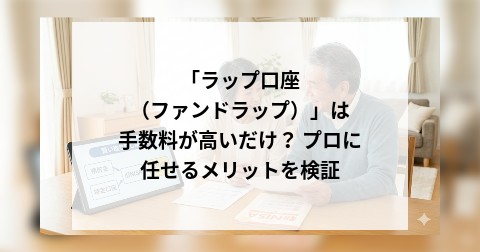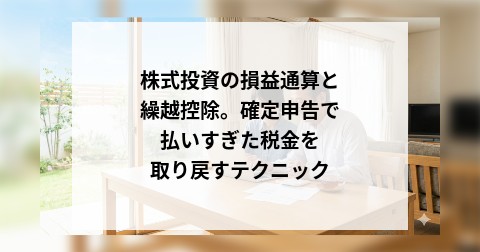【シニア向け】iDeCoと新NISA、活用しないともったいない!賢い節税投資ガイド
「将来のために資産形成を始めたいけれど、何から手をつければいいか分からない」 「銀行に預けているだけではお金が増えないのは分かっているけれど、損をするのが怖い」
そう考えているシニアの方は多いのではないでしょうか。そんな方々にぜひ活用してほしいのが、「iDeCo」と「新NISA」です。これらは、国が私たちの資産形成を支援するために設けた、非常にメリットの大きい制度です。
「難しそう」と感じるかもしれませんが、仕組みを理解すれば誰でも手軽に始めることができます。この記事を読んで、賢くお得に資産を増やす一歩を踏み出しましょう。

iDeCoと新NISAの違いは?
新NISAとiDeCoの概要を表にまとめました。まずは各制度の特徴と違いを確認しておきましょう。
| 新NISA | iDeCo | |
| 利用できる人 | 18歳以上 | 20歳以上65歳未満 |
| 投資上限額 |
つみたて型:年120万円 |
年14.4万円~81.6万円 |
| 投資できる商品 | つみたて枠:国が厳選した投信・ETF 成長投資枠:株,ETF,REIT,投信 |
投信、定期預金、保険 |
| 投資方法 | 積立・一括どちらも可能 | 積立のみ |
| 非課税期間 | 無期限 | 資産を受け取るまで (受取開始は60~75歳の間で選択) |
| 税制 | 運用非課税 |
全額所得控除 受け取りが終了するまで運用益非課税 受け取り時に税控除あり |
| 資産の引き出し | いつでも引き出せる | 60歳まで払い戻せない |
|
口座開設手数料 |
無料 | 口座開設:2,829円 口座管理:年2,052円~7,000円程度 |
| 最低拠出額 | 制限なし | 月5,000円から |
【新NISAの特徴】
新NISAとは、NISAの抜本的拡充・恒久化を図るために、それまでのNISA(以降、旧NISA)に代わり、2024年1月から導入された制度です。
|
旧NISAに比べ、非課税保有期間の無期限化や年間投資枠の拡大など、新NISAには安定的な資産形成を達成しやすいような変更が加えられています。
【iDeCoの特徴】
iDeCoに加入するためには、iDeCoを取り扱っている金融機関で加入手続きをする必要があります。公的年金と異なり、自分自身で金融機関を選び、掛金を運用しなくてはいけません。
|
新NISAとiDeCoはどっちがいい?メリット・デメリットを知っておこう
新NISAとiDeCoは全く異なる制度で、それぞれにメリットとデメリットがあります。
|
【新NISAのメリット】
【新NISAのデメリット】
|
新NISA最大のメリットは、運用益が非課税であることです。また、口座を開設するのに年齢制限がない点もiDeCoにはない特徴です。ただし、ほかの課税口座と損益通算や繰越控除ができない点がデメリットになります。
|
【iDeCoのメリット】
【iDeCoのデメリット】
|
iDeCoは税制優遇が受けられるのが大きなメリットでしょう。「原則60歳まで引き出せない」ことはメリットでもデメリットでもあります。自由に引き出せないことは、急な出費に対応できないということでもあるためです。ただし、掛金額の変更が年1回であることを踏まえても、新NISAよりも流動性が低い分、長期での資産形成には向いている制度といえそうです。
新NISAには保有できる上限額があり、iDeCoには運用と加入に年齢制限の上限があることを考えると、資産形成の目的にもよりますが、少額ずつ、片方だけではなく、併用するのが好ましいでしょう。
【目的別】iDeCoと新NISAを選ぶならどっち?
老後資金に備えるならiDeCo
これから老後資金を備えるのが目的であれば、iDeCoが適切な選択肢でしょう。原則、60歳まで運用資産を引き出せないからこそ、複利効果を活かした長期的な運用が可能です。
参考までに総務省が公表しているアンケート調査「家計調査報告」などを参考に算出した老後に必要な資金を紹介します。
|
【夫婦(高齢夫婦無職世帯)の老後資金】(※) 【独身(高齢単身無職世帯)】(※) ※65~95歳の「老後」30年間を暮らすために必要と考えられる、年金収入以外の資金を試算。持ち家で住宅ローンの返済が完了後の場合 |
老後資金を目的にiDeCoを始める場合は、上記を参考に目標額を設定してみましょう。
節税効果を狙うならiDeCo
資金づくりをしながら節税もしたい人には、前述のように、「積立時」「運用時」「受取時」の3つのタイミングで税制優遇を受けられるiDeCoがおすすめです。ただし、住民ローン減税やふるさと納税をしていると、積立時の節税効果が減じる可能性がある点に注意しましょう。
まとめ
iDeCoと新NISAを始める場合は、自分に合った方法を選ぶことが大切です。ある程度の収入がある人や、個人事業主の人は所得控除があるiDeCoのメリットが大きくなります。資金を自由に引き出したい人や、株や投資信託などさまざまな商品で運用したい人はNISAがおすすめです。
iDeCoとNISAのメリットデメリットをよく理解して、無理のない金額で運用を始めるようにしましょう。