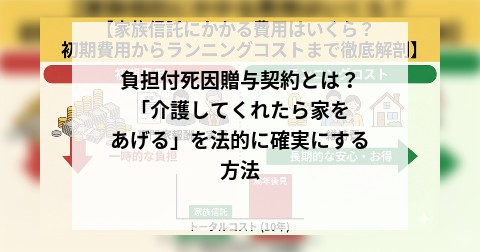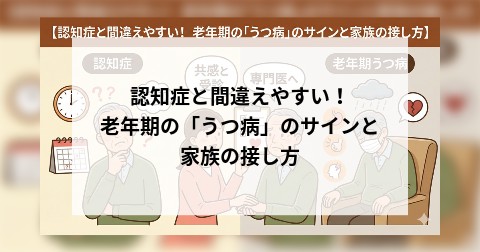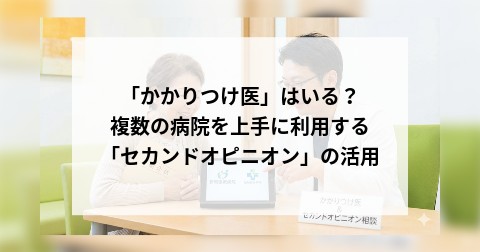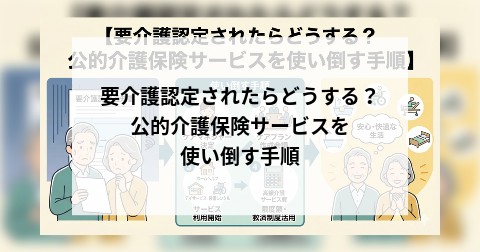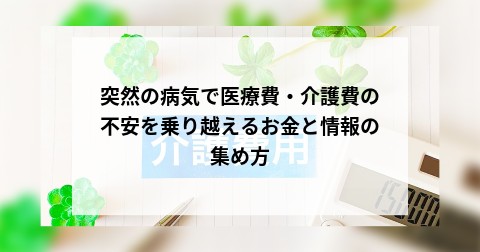介護が始まる前に備える!知っておきたい準備と心構え
親の健康状態について話し合うことは、介護を考える上で欠かせません。
実際に介護が始まってから慌てないためには、早めの準備がとても大切です。とはいえ、「何を準備すればいいのか分からない」「何から手をつければいいの?」と悩む方も多いはず。
そこでこの記事では、親の介護に備えるために知っておくべき、介護が始まるきっかけ、お金の備え方、使える制度やサービスの情報などを解説します。
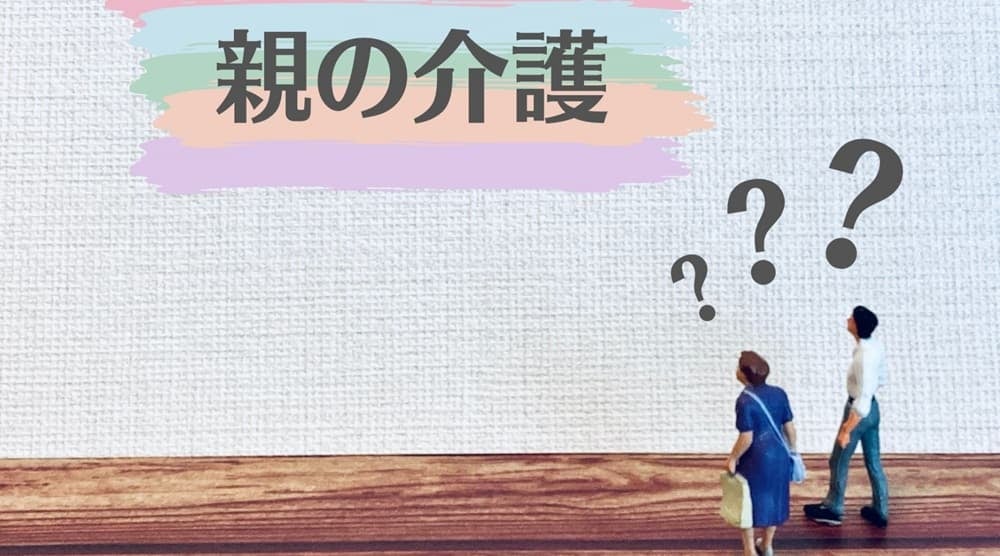
「まだ元気だから」は要注意。介護は突然始まるもの
「親はまだ元気だから、介護のことはまだ先の話」と考えていませんか?しかし、介護はいつ、どんなきっかけで始まるか分かりません。転倒による骨折、脳梗塞による後遺症、認知症の進行など、ささいなことがきっかけで、昨日まで元気だった親に、急に介護が必要になることは珍しくありません。
介護が始まってから慌てて準備を始めると、金銭的な負担や精神的なストレスが大きくなり、共倒れしてしまうリスクも高まります。そうならないためにも、親が元気なうちから、介護に向けた準備を始めることが大切です。
介護の準備として最初にすべきこと
介護に備える第一歩は、親や家族との話し合いです。親や家族の希望や役割分担、情報の整理など、今からできる準備を具体的にご紹介します。
親の希望を確認する
介護を始める前に、まずは親自身の意思を確認しておくことがとても大切です。例えば、「自宅で過ごしたい」「延命治療は望まない」といった希望は、事前に知っておくことで、家族全体の方針が立てやすくなります。
「どんな老後を送りたいか」を聞いてみましょう。
家族間の役割分担を話し合う
介護は一人で抱え込むと心身ともに大きな負担になります。兄弟姉妹がいる場合は、介護の分担や金銭的な支援について明確に話し合っておくことが重要です。
一人っ子の場合でも、親戚や近隣との関係を見直し、協力をお願いできる体制を整える準備が必要です。
連絡先や医療情報を整理する
親のかかりつけ医、服用している薬、加入している保険、年金の情報など、緊急時に必要な情報は一覧にしておくと安心です。ノートやスマートフォンにまとめておくと、いざという時に慌てずに済みます。
話し合いの始め方に工夫をする
介護の話題は切り出しづらいものですが、「最近調子はどう?」「どんな暮らしをしたいと思ってる?」といった日常の会話から自然に入り込むと、スムーズに進みます。
無理に重い話をするのではなく、徐々に親の気持ちを聞き出していくのがポイントです。
介護にかかるお金を備える
介護にかかる費用は決して小さくありません。平均的な費用、支援制度、事前の準備について見ていきましょう。
平均的な介護費用とは?
平均的な介護費用は、介護の仕方(在宅か施設か)、要介護度、利用するサービスの内容などによって大きく異なります。
在宅介護では月5〜15万円程度、施設に入所すると月20〜30万円以上かかることもあります。
特に施設介護では、入居一時金や月額利用料が大きな負担になるため、あらかじめ費用感を知っておくことが重要です。
在宅介護の費用
- 初期費用: 自宅を改修する場合、平均70万円前後かかることがあります。
- 月額費用: 月々の平均は、およそ5万円~15万円という調査結果があります。内訳は、介護保険サービスの自己負担額と、おむつ代や食費、日用品代などです。
- 特徴: 介護保険サービスをどれだけ利用するか、住宅改修が必要か、家族がどの程度サポートするかによって、費用は大きく変動します。
施設介護の費用
- 初期費用(入居一時金): 公的な施設(特別養護老人ホームなど)は入居一時金が不要な場合が多いですが、民間の有料老人ホームなどでは、数十万円から数千万円かかることもあります。
- 月額費用: 月額費用は、施設のタイプや立地、居室の種類によって大きく異なります。
- 公的施設(特別養護老人ホームなど): 月額5~15万円程度が目安です。
- 民間施設(有料老人ホームなど): 月額15~30万円以上かかることもあります。
- 特徴: 施設費用には、居住費、食費、管理費、介護サービス費用などが含まれます。高額な施設ほど、手厚いサービスや充実した設備が期待できます。
親の資金と家族の負担のバランス
「親の介護費用は誰が負担すべき?」と悩む方も多いでしょう。原則としては、親の年金や貯蓄を使うのが一般的です。ただし、すべてを親の資金でまかなえるとは限らないため、家族で分担方法を話し合い、将来のトラブルを防ぎましょう。
公的支援制度の活用
高額介護サービス費制度は、一定額を超えた自己負担分を払い戻してくれる制度です。他にも、介護保険による訪問介護やデイサービスの費用補助があります。これらを上手に利用すれば、家計への負担を軽減することができます。
事前にすべきお金の準備
いざというときに困らないために、親の保険の有無や貯金口座の場所、介護保険の給付内容を事前に確認しておきましょう。民間の介護保険に加入している場合も、保障内容や請求手続きを把握しておくと安心です。
介護保険制度と使えるサービスを理解しよう
介護保険制度を正しく理解することで、介護の負担を大きく軽減できます。申請方法や利用可能なサービスについて見ていきましょう。
介護保険制度とは?
介護保険制度は、40歳以上の人が加入し、介護が必要になった際に1〜3割の自己負担で介護サービスを利用できる仕組みです。要介護や要支援と認定された人に対し、必要なサービスが提供されます。
申請から認定までの流れ
まず、市区町村の介護保険課に要介護認定の申請を行います。その後、訪問調査と医師の意見書に基づいて審査が行われ、要支援1〜2または要介護1〜5の区分で認定されます。この認定によって利用できるサービスが決まります。
利用できるサービスの種類
介護保険で利用できる主なサービスには、訪問介護、デイサービス、ショートステイなどがあります。たとえば、日常生活の一部を支援する訪問介護や、日中だけ施設で過ごすデイサービスなど、状況に応じた柔軟な利用が可能です。
地域包括支援センターの活用
制度について不安がある方や申請手続きに迷う方は、地域包括支援センターに相談するのが安心です。介護に関する総合的な相談窓口として、情報提供や手続きのサポートをしてくれます。
住まいと介護環境をどう整える?
自宅介護と施設介護、それぞれに必要な住まいの環境整備と考慮すべき点を紹介します。将来の暮らし方を考える参考にしてください。
自宅介護と施設介護の違い
親の介護をどこで行うかは大きな判断になります。自宅介護は慣れ親しんだ環境で過ごせるメリットがある一方で、介護者の負担も大きくなります。対して施設介護はプロの支援を受けられる安心感がある反面、費用や入所条件に注意が必要です。
住まいのバリアフリー化と補助制度
親が住み慣れた自宅での生活を続ける場合、介護しやすいように家を整える必要があります。介護が始まってから慌てて改修するのではなく、親が元気なうちから少しずつ準備を進めておくのが理想です。
転倒を防ぐための工夫
高齢者の事故で最も多いのが転倒です。転倒を防ぐために、以下のような対策を検討しましょう。
・手すりの設置: 階段や浴室、トイレ、玄関など、段差のある場所や立ち座りの動作が多い場所に手すりを設置します。
・段差の解消: 部屋の間の敷居や玄関の段差をなくし、つまずきにくい環境に整えます。
・滑りにくい床材: 浴室やトイレの床を滑りにくい素材に変えるだけでも、転倒のリスクを減らせます。
施設介護という選択肢
在宅での介護が難しい場合や、親がより専門的なケアを望む場合は、介護施設への入居も選択肢の一つです。
施設のタイプと選び方
介護施設には様々な種類があります。それぞれの特徴を理解し、親の状況や希望に合った施設を選ぶことが大切です。
・特別養護老人ホーム: 重度の介護が必要な方が入居できる公的な施設です。費用は比較的安価ですが、入居待ちが長いことがあります。
・介護老人保健施設: 病院から退院した後のリハビリを中心とした施設です。在宅復帰を目指すための短期的な入所が目的となります。
・有料老人ホーム: 比較的自由度が高く、多様なサービスを受けられる民間の施設です。費用は高めですが、手厚いサービスやレクリエーションが充実している場合があります。
まとめ
親の介護に備えるには、「元気なうちにできること」を一つずつ進めておくことが大切です。準備しておけば、いざという時に慌てず、親の希望を尊重した介護ができるようになります。
この記事で紹介した「話し合い」「お金の準備」「制度の理解」「住まいの選択」「相談先の把握」は、すべて今からでも始められることばかりです。
介護は突然やってくるもの。だからこそ、今のうちにできる備えが、将来の安心につながります。「まだ早いかな」と思っていても、今日できる一歩を踏み出すことが、あなたとご家族を支える大きな力になりますよ。