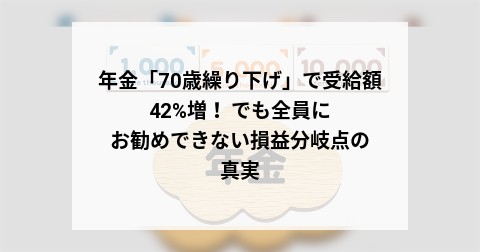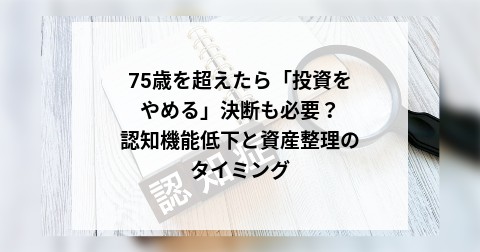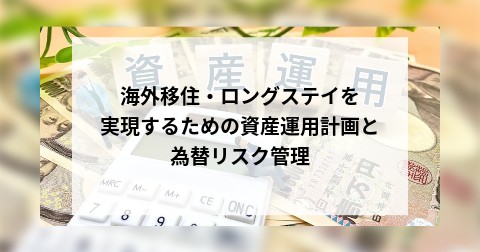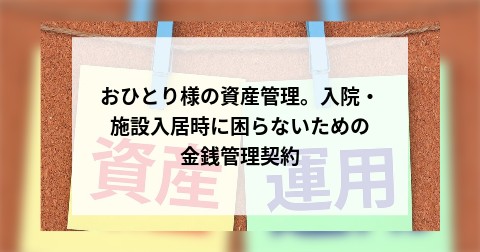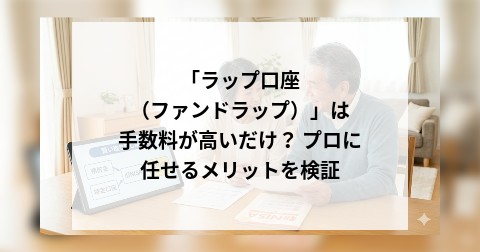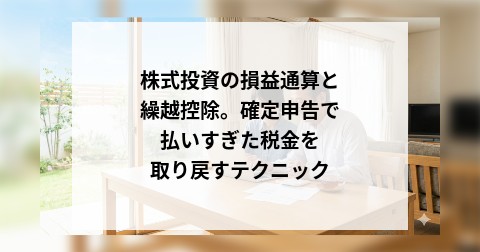「長生きリスク」に備える!シニア世代が今すぐ見直すべきポートフォリオ
人生100年時代と言われる今、多くの人が直面するのが「長生きリスク」です。これは、想定以上に長生きすることで、老後の資金が尽きてしまうリスクを指します。
「退職金や年金で十分だろう」と考えていたポートフォリオでは、このリスクに対応できない可能性があります。
この記事では、シニア世代が安心して長生きするためのポートフォリオ見直しポイントを解説します。

長生きリスクに対応するポートフォリオとは?
長生きリスクに対応するポートフォリオとは、老後の生活資金が不足するリスク、つまり長生きすることによってお金が尽きてしまうリスクに備えるための資産運用ポートフォリオのことです。具体的には、リスクを抑えつつ、老後の生活資金を安定的に確保できるような資産配分を目指します。
具体的には、以下のような特徴を持つポートフォリオを目指しましょう。
-
安定性を重視しつつ、インフレに負けないリターンを目指す
-
定期的な収入(インカムゲイン)を確保する
-
急な支出に備えるための現金を確保しておく
ポートフォリオ見直しの3つのポイント
ポイント1:資産の「守り」と「攻め」のバランスを見直す
退職後は、積極的にリスクを取って資産を増やすフェーズから、資産を守りながら運用するフェーズへと移行します。しかし、すべてを預貯金にしてしまうと、物価上昇(インフレ)によって資産の実質的な価値が目減りしてしまいます。
- 守りの資産【収益資産】
元本が減るリスクが低い、安定性を重視した資産(個人向け国債や定期預金など) - 攻めの資産【安全資産】
価格変動リスクはあるものの、大きなリターンが期待できる資産(株式や投資信託など)
安全性ばかりを追求すると、インフレによって資産価値が実質的に目減りしてしまう。一方で、リターンだけを追い求めると、元本割れのリスクが高まることになる。
一般的に、シニア世代のポートフォリオでは「守りの資産」と「攻めの資産」の比率を7:3、もしくは6:4程度にすることが理想だ。
例えば、資産の6〜7割を個人向け国債や定期預金で安全に守り、残りの3〜4割を高配当株式や投資信託(バランス型・インデックス型)に振り分けるとよい。
このバランスを意識することで、資産をしっかりと守りながら、安定的なリターンを目指すことができるでしょう。
ポイント2:定期的な収入(インカムゲイン)を確保する
年金収入だけでは生活費が不足する可能性に備え、ポートフォリオから定期的な収入を得る仕組みを作ることが重要です。
投資信託・ETF|分散投資が可能でプロに資産運用を任せる
| メリット | ・プロの運用で安心 ・分散投資でリスクも比較的低い ・新NISAは税制優遇がある |
| デメリット | ・元本割れすることもある ・銘柄が非常に多く初心者には選びづらい(新NISAは限定されている) |
| リスクとリターンの目安 | 低~高(新NISAは低) |
| 向いている人 | プロに任せてほったらかしで資産形成をしたい人 |
投資信託とは、複数の投資家から集めたお金を資産運用のプロである専門家(ファンドマネージャー)が運用して利益を得る金融商品を指します。
複数の投資先を組み合わせるため比較的リスクが低く、投資信託の商品(ファンド)によっては大きなリターン(分配金)が得られるものもあります。
J-REIT|複数の投資家から資金を集め不動産を運用
| メリット | ・配当金が株式と比較して高い傾向がある ・不動産銘柄のためインフレに強い ・現物ではないため不動産によくあるリスクがない ・流動性が現物不動産と比較すると高い |
| デメリット | ・不動産特有の災害リスクなどがある ・配当控除が受けられない ・投資法人の倒産リスクがある |
| リスクとリターンの目安 | 中~高 |
| 向いている人 | いつか不動産投資をしたいが難しいため、不動産投資の勉強を兼ねて投資しつつ、資金を貯めたい人 |
RIETは、不特定多数の投資家から集めた資金で、オフィスビルや商業施設などの不動産を購入・運用し、その不動産から得られる家賃収入などを投資家に分配する仕組みです。
投資家から資金を集めてプロが運用するのは投資信託と同じですが、REITの特徴は不動産経営によって賃料収入等を得る運用方法ということです。
またその制度上、基本的に「利益の90%超を分配すれば法人税が課税されない」というルールになっています。
出した利益はほぼ投資家への配当金になるため、他の投資方法と比較して利回りが高くなる傾向があります。
不動産を扱っていることからインフレにある程度強く、他の金融資産が目減りした場合でもあまり価値が下がらないため、リスク分散のためにポートフォリオに組み込まれることがあります。
個人年金保険
将来受け取る年金を保険で準備できる商品です。保険料を支払い、60歳もしくは65歳など、契約時に決めた年金支払開始の年齢になったら年金が支払われます。
個人年金保険には「確定年金」「有期年金」「終身年金」の3つの種類があります。確定年金は決められた期間だけ年金が受け取れる仕組みになっています。
有期年金も決められた期間、年金を受け取れますが、年金支払期間中に被保険者が死亡した場合には、その後の年金は支払われません。その場合、確定年金では、遺族が代わりに受け取れる点が異なります。
終身年金は、被保険者が生きている間は一生涯年金を受け取ることができます。
いずれも年金支払期間前の保険料を支払っている間に万一被保険者が死亡した場合には、払込保険料総額の相当額が死亡給付金という形で死亡給付金受取人に支払われます。
ポイント3:急な支出に備える現金を確保する
医療費や介護費用など、予期せぬ大きな支出に備えて、すぐに引き出せる現金を一定額確保しておくことが不可欠です。
-
生活防衛資金:生活費の3ヶ月〜6ヶ月分を目安に、いつでも引き出せる普通預金などに置いておきましょう。
-
緊急予備資金:病気や介護など、大きな支出に備えるための資金です。これはすぐに使う予定のないお金なので、流動性の高いMMF(マネー・マーケット・ファンド)などで運用するのも一つの手です。
まとめ
長生きリスクに備えるポートフォリオは、一人ひとりのライフプランや資産状況によって異なります。
「自分のポートフォリオはこれで大丈夫だろうか?」と少しでも不安に感じたら、資産運用の専門家(ファイナンシャル・プランナーなど)に相談することも検討してみましょう。プロの視点を取り入れることで、より安心できる未来設計が可能になります。