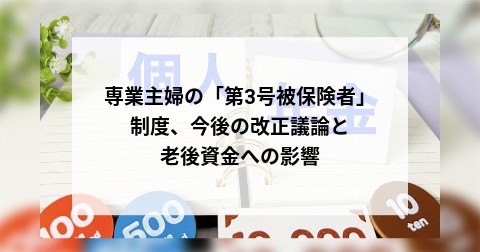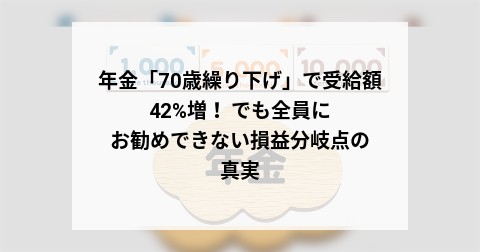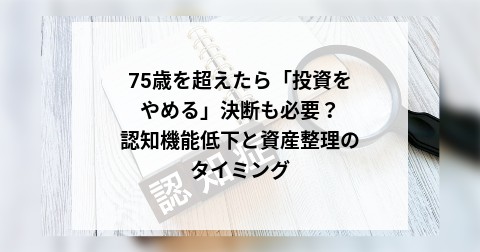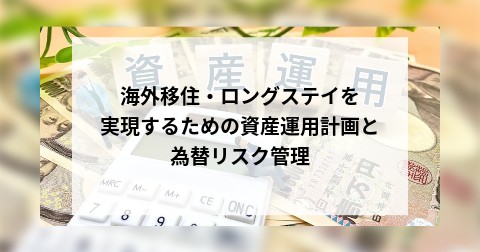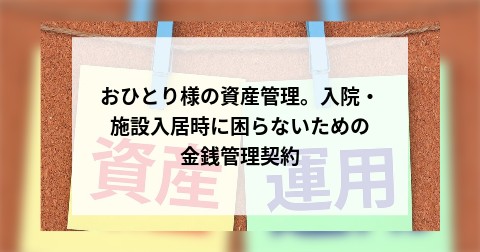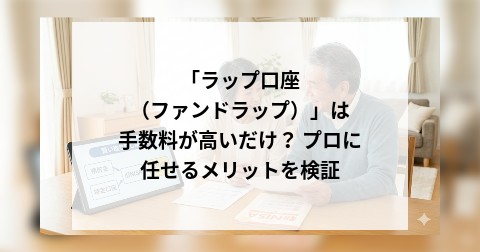インフレに負けない資産防衛!シニアが選ぶべき「国内外インデックス投資信託」
「老後の備えは預貯金で十分」と考えているなら、それは大きなリスクかもしれません。近年、日本は物価が継続的に上昇するインフレ時代に入りつつあります。
銀行に預けているお金は安全に思えますが、インフレが年率2%進むと、100万円の現金の価値は10年後には実質的に約82万円に目減りしてしまいます。つまり、お金の「量」が変わらなくても、「購買力」が下がってしまうのです。
シニア世代の資産防衛の鍵は、インフレに負けない資産を持つことです。そこで最も堅実で有効な手段が、国内外のインデックス投資信託の活用です。
この記事では、老後資金をインフレから守り抜くための、インデックス投資信託の選び方と活用法を解説します。

1. なぜシニア層こそインデックス投資信託なのか?
インデックス投資信託は、日経平均株価やS&P500といった特定の**「指数(インデックス)」**と連動した動きを目指す商品です。
① インフレに強い「実質的なリターン」
インフレはモノやサービスの価格が上がることですが、同時に企業の売上や利益、そして株価も上昇しやすい傾向があります。
インデックス投資信託を通じて世界の成長企業に分散投資することで、物価の上昇(インフレ)に合わせた資産の成長が期待でき、現金の目減りを防ぐことができます。
② 手間いらずの「ほったらかし運用」
老後の時間を複雑な投資の勉強に使う必要はありません。インデックスファンドは指数通りに運用されるため、個別の企業の業績を分析したり、頻繁に売買したりする手間が一切かかりません。一度設定してしまえば、あとは基本的に「ほったらかし」でOKです。
③ 資産を減らさないための「低コスト」
インデックスファンドは、プロが個別に銘柄を選ぶアクティブファンドに比べて、運用コスト(信託報酬)が非常に低いのが特徴です。このコストの差は、運用期間が長くなるほど大きな差となって現れます。コストを抑えることが、老後資金を減らさないための最重要ポイントです。
2. インフレ対策で選ぶべき「2つのベストセラー」
インフレ対策と資産防衛を目的とするシニア世代には、以下の2つのタイプのインデックス投資信託がおすすめです。
全世界株式インデックスファンド
最もリスク分散効果が高いのが、日本を含む世界中の先進国・新興国の株式市場全体にまとめて投資できるファンドです。
-
メリット: 世界経済の成長を丸ごと享受できます。どこかの国や地域で景気が悪化しても、他の地域でカバーできるため、リスクが分散され、極端な暴落に強くなります。
-
代表的な指数: MSCI ACWI(オールカントリー・ワールドインデックス)やFTSE Global All Capなど。
先進国(日本除く)株式インデックスファンド
日本の将来的な成長力に不安を感じる方は、経済成長が安定しているアメリカやヨーロッパなどの先進国市場に絞って投資するファンドも有効です。
-
メリット: 特に世界の時価総額の多くを占めるアメリカ市場の成長を享受しやすい一方、日本国内の景気低迷の影響を受けにくい体制が作れます。
-
代表的な指数: MSCI Kokusai(コクサイ)インデックスなど。
3. 資産防衛を成功させる活用のステップ
インデックス投資信託の効果を最大限に引き出し、老後資金を確実に守るための具体的なステップです。
ステップ① まずは新NISAの「非課税枠」を優先する
投資の利益が非課税になる新NISAの成長投資枠や、つみたて投資枠を最優先で活用しましょう。非課税でインフレ対策ができれば、老後資金の目減りを最大限に防げます。
ステップ② 余裕資金を「定期的に」積み立てる
一度に大きな金額を投資するのではなく、年金や生活費の残りを毎月少額でも積立に回しましょう。
-
価格が高い時は少なく、安い時は多く買うことになる「ドルコスト平均法」の効果で、高値掴みのリスクを抑え、より安定した運用結果に繋がります。
ステップ③ 暴落時も「売らずに耐える」
インデックス投資は、長期で持ち続けることでその効果を発揮します。世界的な経済危機や株価の暴落が起きたときこそ、売却せずに耐えることが重要です。
-
シニア世代の投資は、現役世代の「攻めの投資」とは異なり、「時間をかけて静かに資産を守り育てる」防衛戦です。短期的な変動に惑わされず、どっしりと構えましょう。
まとめ
インフレは預貯金の実質価値を静かに蝕んでいきます。国内外のインデックス投資信託は、手間とコストを最小限に抑え、あなたの老後資金を力強くインフレから守ってくれる、最適な防衛策の一つです。早速、新NISAでの活用を検討してみてはいかがでしょうか。