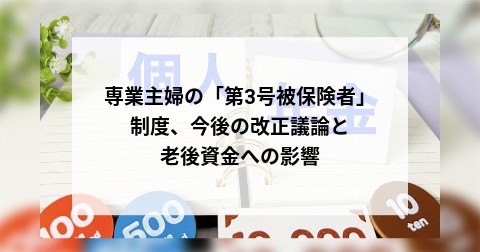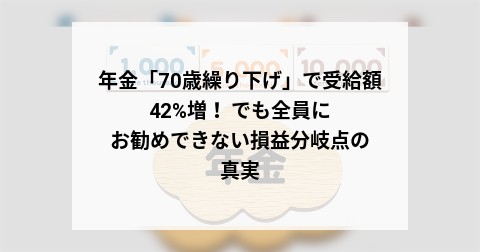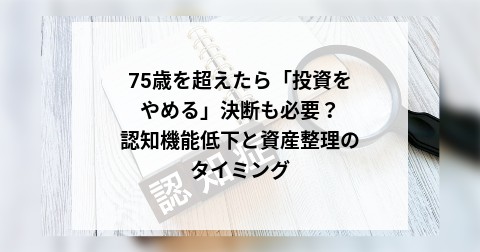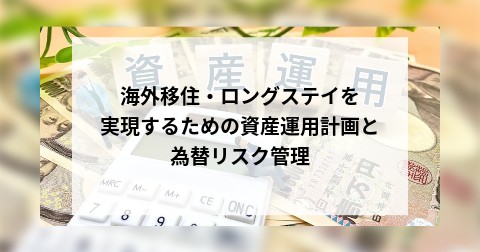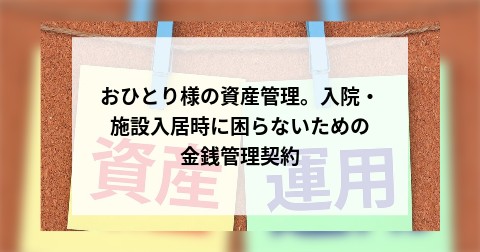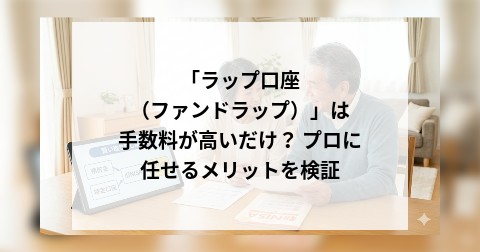年金受給額を最大化する!「繰り下げ受給」のメリット・デメリットと判断基準
老後に困窮しないためには、公的年金がいつからもらえるのかを把握して、それに応じた人生設計を行うことが非常に大切です。
少しでも年金額を増やしたいと、年金の繰下げ受給を検討する人が増えています。一方、「いつから受給開始すると損をしない?」と疑問を感じる人もいるでしょう。
この記事では、一般的な年金の受給年齢を紹介し、受給開始年齢を繰り上げたり、繰り下げたりした場合のメリットとデメリットなどについて解説します。

はじめに
老後の生活設計において、公的年金の受給開始時期は非常に重要な選択です。特に「繰り下げ受給」は、将来の年金額を大きく増やせる可能性がある一方で、注意すべきデメリットもあります。
「繰り下げ受給」とは?
年金は原則として65歳から受給できますが、66歳以降75歳までの間で希望する時期に繰り下げて受け取り始めることを「繰り下げ受給」といいます。
【増額率】
受給を1ヶ月遅らせるごとに年金額が0.7%増額されます。
【最大増額率】
75歳まで繰り下げた場合、最大で84%(0.7% × 12ヶ月 × 10年)の増額となります(2022年4月以降に70歳に達する方などが対象)。
繰り下げ受給のメリット
最大のメリットは、生涯にわたって受け取れる年金額が増加することです。
| メリット | 詳細 |
| 年金額の大幅な増加 | 繰り下げた期間に応じて年金額が恒久的に増額されるため、特に長生きした場合に生涯の受給総額が大きく増えます。 |
| 老後の経済的な安心 | 毎月の年金収入が増えることで、よりゆとりのある老後生活を送れる可能性が高まります。 |
| 老齢基礎年金と老齢厚生年金の別々の選択 | 老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰り下げ時期を個別に選択できるため、柔軟な受給計画を立てられます。 |
繰り下げ受給のデメリット・注意点
メリットが大きい一方で、以下のデメリットには十分な注意が必要です。
| デメリット・注意点 | 詳細 |
| 早期死亡リスク | 繰り下げ期間中に亡くなった場合、65歳から受け取り始めた場合に比べて年金の受給総額が少なくなり、損をする可能性があります。 |
| 税金・社会保険料の負担増 | 年金額が増えることで、所得税や住民税、国民健康保険料(または後期高齢者医療制度の保険料)などの負担が増加する可能性があります。 |
| 加給年金・振替加算の受給権 | 繰り下げ待機期間中(65歳から繰り下げ受給開始までの間)は、加給年金や振替加算(要件を満たす場合)が受け取れません。加給年金を受け取る人がいる場合は、特に注意が必要です。 |
| 在職老齢年金との調整 | 65歳以降も厚生年金に加入して働く場合、「在職老齢年金」の仕組みにより、年金の一部または全額が支給停止になる可能性があります。この支給停止分には増額率が適用されない点も留意が必要です。 |
繰り下げ受給の判断基準
繰り下げ受給が「得」になるか「損」になるかは、個々の状況と寿命に大きく左右されます。以下の要素を総合的に考慮して判断しましょう。
健康状態と寿命
【長寿に自信がある人】
繰り下げ受給のメリットを最大限に享受できる可能性が高いです。
【健康に不安がある人】
早期死亡リスクを考慮し、65歳からの受給や短期間の繰り下げを検討した方が安心かもしれません。
【損益分岐点】
70歳まで繰り下げた場合の損益分岐点(65歳受給の総額を上回る年齢)は、約81歳11ヶ月が目安とされています。この年齢を超えて長生きするかどうかが一つの判断基準です。
65歳以降の収入・貯蓄
【十分な収入や貯蓄がある人】
繰り下げ期間中の生活費に困らないため、繰り下げ受給を検討しやすいです。65歳以降も働いている場合は特に向いています。
【年金がないと生活が厳しい人】
繰り下げ受給は難しく、65歳から受給を開始するのが現実的です。
配偶者の状況(加給年金・振替加算)
【加給年金や振替加算の受給権がある夫婦】
繰り下げ待機期間中はこれらの年金が受け取れないため、その期間の合計額と、繰り下げによって増える年金額の差を比較検討することが重要です。
年金以外の資産状況と老後資金計画
老後資金全体(貯蓄、退職金、企業年金、iDeCo、NISAなど)のバランスを考慮し、年金に頼る度合いを判断します。
まとめ
繰り下げ受給は、老後の経済的な安定性を高める強力な手段ですが、人生における最善の選択は人それぞれです。ご自身の健康状態、経済状況、ライフプランを入念に検討し、必要であればファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談して、最適な受給開始時期を決定しましょう。
【PR】
高配当株やREITの活用の他、お金に対して漠然と不安を抱えているのであれば「資産運用」を検討してみてはどうでしょう?お金の不安を相談するなら投資信託相談プラザのセミナーに参加してみては?
| 店舗またはオンラインでの個別相談はこちらから |