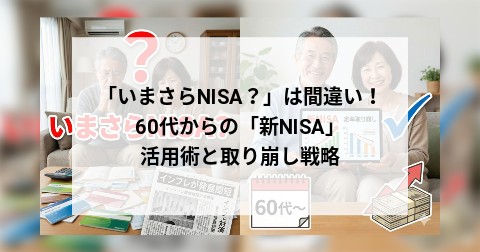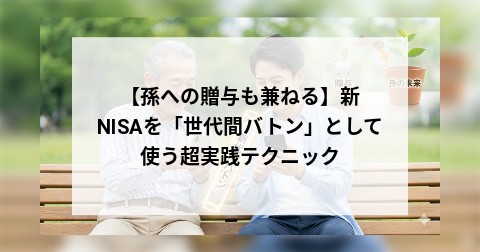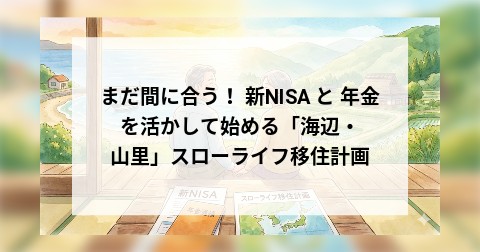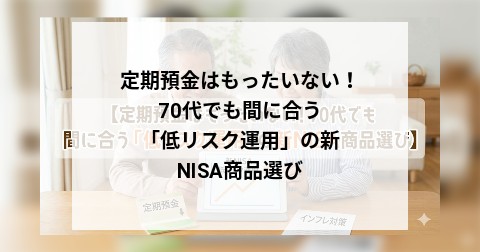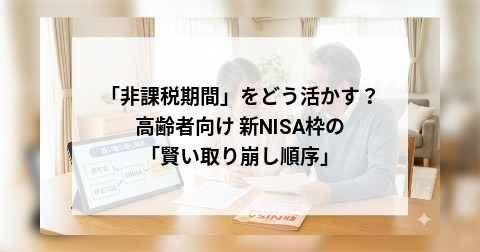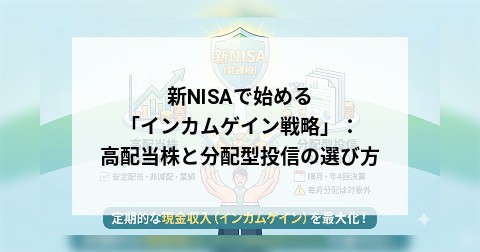将来の不安を解消!老後資金を見据えた長期的な資産計画の立て方
「老後2,000万円問題」をはじめ、年金や健康に対する不安から、「このままで大丈夫だろうか?」と漠然とした不安を抱えているシニア・ミドルシニア世代の方は少なくありません。
しかし、その不安の多くは「老後資金の全体像が見えないこと」から生じます。この不安を解消し、安心して老後を迎えるためには、長期的な資産計画を具体的に「見える化」することが最も重要です。
この記事では、老後生活の質(QOL)を維持・向上させるために、今すぐ取り組むべき資産計画の立て方と、その実行のステップを解説します。

ステップ1:現状と将来の必要資金を「見える化」する
不安の最大の原因は、将来のお金に対する「不確実性」です。まずは現状の家計と、将来発生するイベントに必要な資金を明確にすることから始めましょう。
(1) ライフイベント表の作成
今後の人生で起こりうる大きな出来事(ライフイベント)をリストアップし、かかる費用と時期を予測します。
- 結婚・出産:子育て、教育にかかる費用
- 住宅購入・リフォーム:頭金やローンの残債、修繕費
- 退職・セカンドライフ:退職年齢、年金受給開始時期
- 介護・医療:長期的な介護費用や病気になった場合の費用
特に老後資金については、「ねんきん定期便」などで将来の公的年金の見込額を確認し、退職後の毎月の生活費(現役時代の7〜8割が目安)との差額を把握することが重要です。
(2) キャッシュフロー表の作成
現在の収入と支出をベースに、(1)でリストアップしたイベントの費用や年金額を時系列で当てはめ、将来の貯蓄残高の推移を一覧にします。
これにより、「何歳のときに」「いくらお金が足りなくなりそうか」が明確になり、漠然とした不安が「具体的な目標(不足額)」へと変わります。もし貯蓄残高が途中でマイナスになりそうなら、計画を見直す必要があると分かります。
ステップ2:資産形成の「3本柱」で目標達成を目指す
キャッシュフロー表で目標額と期間が明確になったら、その不足分を補うための具体的な行動に移ります。資産形成の基本は、以下の「3本柱」をバランス良く実行することです。
1. 収入を増やす
昇進・転職による給与アップ、資格取得、副業・兼業など、収入源を増やす方法を考えます。特に定年後を見据え、長く働き続ける計画を立てることも、老後資金の不安を解消する強力な手段となります。
2. 支出を減らす
家計簿などで現状の支出を把握し、固定費の削減を徹底します。
- 保険の見直し:必要以上の保障になっていないか
- 通信費の見直し:格安SIMへの切り替えなど
- 住宅費:ローンの繰り上げ返済や住み替えの検討
小さな支出の積み重ねでも、長期的に見れば大きな差になります。
3. 資産を運用して増やす(投資)
長期的な資産形成において、貯蓄(預貯金)だけでは物価上昇(インフレ)に負けてしまうリスクがあります。そこで活用したいのが、長期・積立・分散を原則とした資産運用です。
非課税制度の活用:NISA(つみたて投資枠・成長投資枠)やiDeCo(個人型確定拠出年金)など、国の優遇制度を最大限に利用しましょう。これらは運用益が非課税になるため、効率的に資産を増やせます。
再投資型の選択:前回の記事でも触れた通り、長期運用では分配金を再投資するタイプを選び、複利効果を最大限に活かしましょう。
ステップ3:計画を定期的に見直し「柔軟性」を持たせる
ライフプランは、一度作ったら終わりではありません。人生には予期せぬ出来事や、心境の変化が必ず起こります。
計画は年に一度見直す
家族構成の変化、収入の増減、住宅ローンの完済、子供の進学先の決定など、大きな変化があった際には計画を修正しましょう。少なくとも年に一度はキャッシュフロー表を確認し、資産形成の進捗状況をチェックすることが重要です。
リスクの管理と資産配分の調整
長期的な運用では、市場の変動により資産が増減します。老後に近づくにつれて、大きなリスクを取ることが難しくなるため、年齢や運用期間に合わせて徐々にリスクを抑えた(値動きの小さい)資産配分へと見直していく柔軟性も必要です。
まとめ:計画が将来の安心を生む
老後資金の不安は、漠然としているうちは非常に大きく感じられます。しかし、「見える化」することで具体的な課題が明確になり、「行動」することでその課題を克服する道筋が見えてきます。
今日から計画を立て、一歩踏み出すことが、将来の安心と豊かなセカンドライフへと繋がるのです。
【PR】
年金以外でもお金に対して漠然と不安を抱えているのであれば「資産運用」を検討してみてはどうでしょう?
お金の不安を相談するなら投資信託相談プラザのセミナーに参加してみては?
| 投資信託相談プラザの無料セミナーご参加はこちらから |
| 店舗またはオンラインでの個別相談はこちらから |