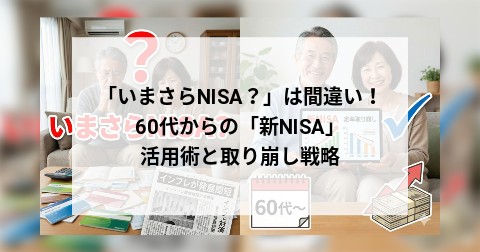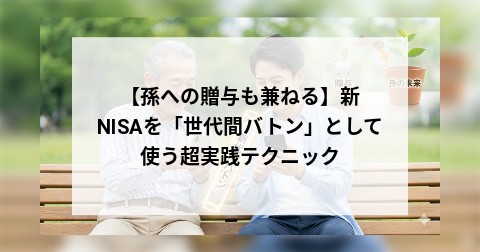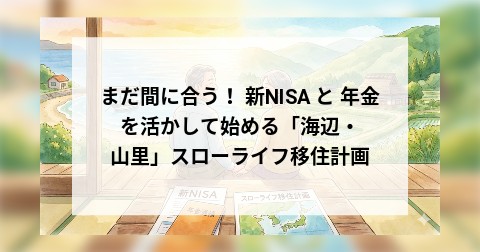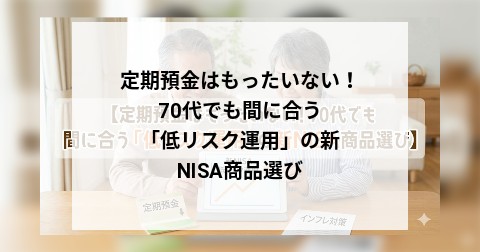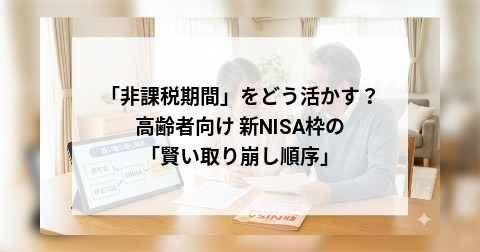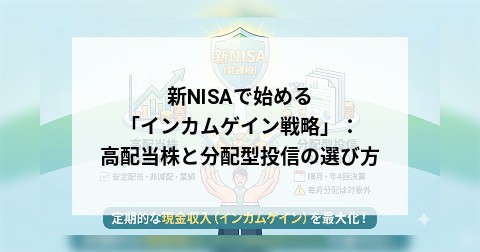シニア世代の資産状況別!投資信託で「守り」と「増やし」を両立するバランスポートフォリオ
シニア世代にとっての資産運用は、現役世代とは目的が異なります。大切なのは「積極的な増殖」よりも、「築き上げた資産をいかに守りながら、物価上昇に負けない程度に増やしていくか」というバランスです。
特に、老後の生活資金を取り崩し始める時期を前にして、投資信託をどのように組み合わせるべきか悩む方も多いでしょう。
この記事では、シニア世代を資産状況と運用目的に応じて3つのタイプに分け、それぞれのゴールに合わせた「守り」と「増やし」を両立させる具体的なバランスポートフォリオを提案します。

シニア世代の資産運用における大原則
シニア世代の投資信託運用では、以下の3つのポイントを念頭に置くことが重要です。
- 「時間分散」よりも「資産分散」の徹底: 運用期間が短くなるため、特定資産への集中投資はリスク大。国内・海外、株式・債券など、分散投資を徹底します。
- インフレ対策を忘れない: 現金や預金だけでは物価上昇(インフレ)に対応できません。緩やかでも成長が期待できる資産(株式など)を組み入れる必要があります。
- 出口戦略(取り崩し方)を意識する: 運用と同時に、いつ、いくら取り崩すかを計画に組み込みます。
【タイプ別】「守り」と「増やし」を両立するポートフォリオ
シニア世代の資産状況を「守備型」「バランス型」「成長追求型」の3つに分類し、投資信託の具体的な配分を提案します。
タイプA:守備型(資産残高がやや不安・保守的な運用希望)
-
運用目的: 資産の大きな目減りを防ぎ、取り崩し期間中の安心感を最優先にする。
-
特徴: 既に年金や生活資金の確保はできているものの、投資経験が浅く、元本割れに対する耐性が低い方。
| 資産の種類 | 投資信託の具体例 | 割合 | 役割(目的) |
| 国内債券 | 国内債券インデックスファンド | 40% | 資産の防衛。値動きが小さく、下落相場でのクッション材になる |
| 外国債券 | 先進国債券インデックスファンド | 20% | 分散効果。為替リスクはあるが、国内債券と異なる動きでリスクを低減 |
| 国内株式 | 日経平均 or TOPIX連動型ファンド | 20% | インフレ対策。最低限の成長性と配当利回りを期待する |
| 外国株式 | 全世界株式(除く日本)ファンド | 20% | 緩やかな成長。世界経済の成長を取り込み、物価上昇に対応する |
<運用のポイント> 「債券60%・株式40%」と、守りを固めた配分です。市場が大きく下落しても、資産全体の下落幅を抑えることを重視します。
タイプB:バランス型(年金・資産残高に余裕あり・標準的な運用希望)
-
運用目的: 生活に必要なお金を残しつつ、将来の予期せぬ出費や子供・孫への資産承継を見据え、資産の目減りを防ぎながら適度な成長を目指す。
-
特徴: 資産規模が老後20年以上の生活費を賄えるレベルで、ある程度のリスク許容度がある方。
| 資産の種類 | 投資信託の具体例 | 割合 | 役割(目的) |
| 国内債券 | 国内債券インデックスファンド | 20% | ベースとなる安心感。資産の土台として安定性を確保 |
| 外国債券 | 先進国債券インデックスファンド | 20% | 国際分散。海外の金利動向を取り込み、安定性を高める |
| 国内株式 | 日経平均 or TOPIX連動型ファンド | 30% | 中程度の成長。国内経済の回復、企業成長によるリターンを追求 |
| 外国株式 | 全世界株式(除く日本)ファンド | 30% | 資産の牽引役。世界経済のダイナミズムを非課税枠で最大限享受 |
<運用のポイント> 「債券40%・株式60%」と、株式の比率を高めることで、インフレ耐性と長期的な資産成長を期待します。新NISAの成長投資枠はこの株式部分に優先的に充てましょう。
タイプC:成長追求型(十分な資産残高・積極的な運用希望)
-
運用目的: 余裕資金が多く、退職金などを活用して将来的に大幅な資産承継や大きな目標達成を目指す。多少のリスクを許容し、高いリターンを求める。
-
特徴: 潤沢な資産があり、万が一のリスクを取っても生活に影響がない。既に投資経験が豊富で、株式相場の変動を許容できる方。
| 資産の種類 | 投資信託の具体例 | 割合 | 役割(目的) |
| 国内債券 | 国内債券インデックスファンド | 10% | 最低限のリスクヘッジ。相場急変時などに備える |
| 外国債券 | 先進国債券インデックスファンド | 30% | 国内での高リターン追求。個別株に近いリターンを目指す |
| 国内株式 | 日経平均 or TOPIX連動型ファンド | 50% | 資産の最大化。米国の強力な成長力や世界全体の成長力を活用 |
| 外国株式 | 全世界株式(除く日本)ファンド | 10% | 新たな分散先。株式・債券と異なる値動きで、分散効果を狙う |
<運用のポイント> 「株式・REIT90%・債券10%」と、資産の大部分を成長性の高い資産に投じます。高いリターンが期待できますが、短期的な値動きの幅も大きくなります。
【重要】投資のプロが実践する「資産の引き出し方」
シニア世代が投資信託を取り崩す際に、資産を長持ちさせる「出口戦略」を意識しましょう。
1. 守りの資産(債券)から引き出す
-
株式が下落している時期に、成長中の株式を売却するのは損失を確定させることになります。
-
下落相場のときは、値動きの安定している債券ファンドや現金から優先的に生活費を引き出しましょう
2. リバランスを定期的に行う
-
資産が増えると、自動的に「株式」の割合が増え、リスクが高まります。
-
毎年一度、決めた割合(例:債券40%・株式60%)に戻すリバランスを行いましょう。増えすぎた株式を売って債券を買い、リスクを一定に保つことが「守り」につながります。
3. 「新NISA」を最後の砦にする
-
新NISA口座の資産は非課税であるため、最も効率よく利益を得られる口座です。
-
生活費の引き出しは、「特定口座などの課税口座」の資産から優先的に行い、新NISA口座の資産はできるだけ長く運用を続ける(=非課税期間を最大限に活用する)ことをおすすめします。
あなたの資産状況はどのタイプに当てはまりましたか?まずは今の資産配分を見直すことから、安心できる老後資金運用を始めましょう。
【PR】
年金以外でもお金に対して漠然と不安を抱えているのであれば「資産運用」を検討してみてはどうでしょう?
お金の不安を相談するなら投資信託相談プラザのセミナーに参加してみては?
| 投資信託相談プラザの無料セミナーご参加はこちらから |
| 店舗またはオンラインでの個別相談はこちらから |