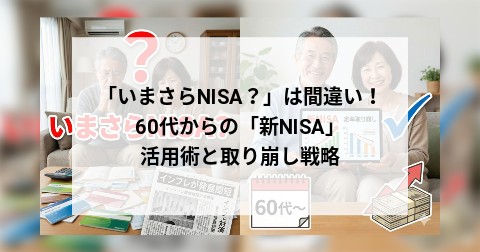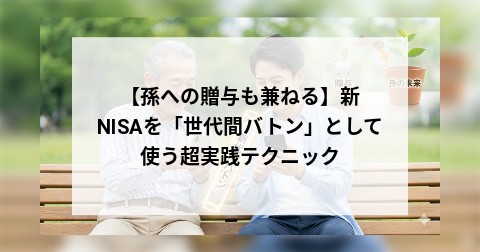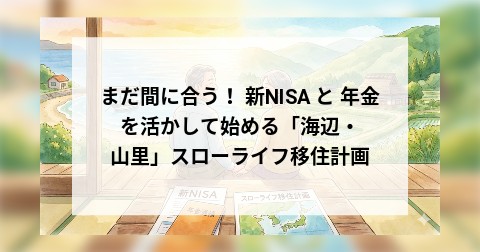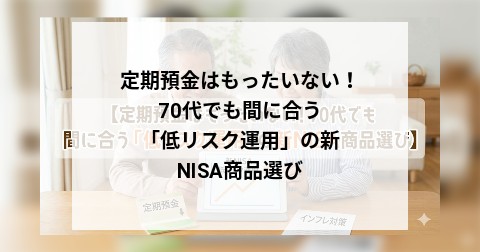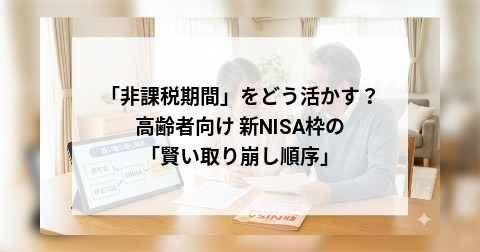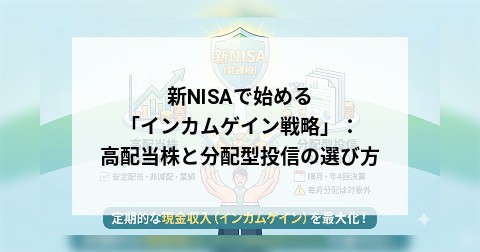投資初心者でも安心!シニアが押さえるべき「投資信託」のコストとリスク基礎知識
「老後資金を預貯金だけで持っていて大丈夫だろうか?」
長引く低金利や物価高騰を背景に、シニア世代でも資産運用に関心を持つ方が増えています。投資信託は、少額からプロに運用を任せられるため、投資初心者にとって有効な手段です。
しかし、投資には必ずコストとリスクが伴います。特にシニア世代は「資産を大きく増やす」ことよりも「資産寿命を延ばす(守りながら増やす)」ことが重要です。
ここでは、投資信託を始める前に必ず押さえておきたい「コスト」と「リスク」の基礎知識を解説します。

1. 投資信託の「3つのコスト」を知る
投資信託にかかるコストは、運用成果を左右する重要な要素です。主なコストは以下の3種類があり、これらはすべて実質的に投資家の負担となります。
(1) 購入時手数料(販売手数料)
- いつかかる?:投資信託を購入する際
- 費用の特徴:販売会社(証券会社や銀行)に支払う手数料です。
- チェックポイント
最近は「ノーロード(手数料無料)」の投資信託が増えています。特に長期の積立・分散投資に適した商品は、ノーロードであることが一般的です。
手数料が有料の場合、1〜3%程度が目安ですが、手数料が高いほど運用効率は悪くなります。
(2) 信託報酬(運用管理費用)
・いつかかる?:投資信託を保有している間、毎日
・費用の特徴:運用会社や販売会社などに支払う、投資信託の管理・運用にかかる費用です。日々投資信託の資産から差し引かれます。
・チェックポイント:年率で示され、保有している限り継続的にかかります。このコストは長期運用になるほど影響が大きくなります。
インデックス型(市場平均を目指す)の投資信託は、年率0.1%〜0.5%程度と比較的低コストです。
アクティブ型(市場平均を上回る利益を目指す)は、人件費などがかかるため、年率1.0%以上になることもあります。
(3) 信託財産留保額
- いつかかる?:投資信託を解約(換金)する際
- 費用の特徴:投資信託を途中解約する投資家が、売買にかかる費用を負担することで、継続して保有する投資家との公平性を保つための費用です。
- チェックポイント:かからないファンドも多くあります。徴収される場合でも、解約時の基準価額に対して0.1%〜0.5%程度が一般的です。
特に長期で運用する老後資金であれば、信託報酬が低い「インデックス型」を選ぶことで、コストの負担を抑え、効率的な資産形成を目指しましょう。
2. 投資信託の「主なリスク」と対策
投資信託には元本保証がなく、損失を被る可能性があるため、リスクを理解することが重要です。
(1) 価格変動リスク(市場リスク)
投資信託の組み入れ資産(株式、債券など)の価格が変動することで、基準価額が上下するリスクです。
対策の基本は「分散」:特定の国や資産に集中せず、国内外の株式や債券などに「分散投資」することで、一つの値下がりが全体の損失に与える影響を軽減できます。
(2) 為替変動リスク
外貨建ての資産(外国株や外国債券など)に投資している場合、為替レートの変動によって基準価額が変動するリスクです
例:1ドル=100円のときに買った外国資産が、円高(1ドル=90円)になると、資産の円換算価値は目減りします。
対策:円建て資産と外貨建て資産の比率を調整したり、「為替ヘッジあり」のファンドを選ぶという選択肢もあります(ただし、ヘッジコストがかかります)。
(3) 信用リスク
投資対象となっている国や企業(債券の発行体など)の経営・財務状況が悪化し、利払いや元本の償還ができなくなる(債務不履行)リスクです。
対策:信用力の高い先進国の国債や、分散された優良企業の株式などに投資する投資信託を選ぶことで、リスクを軽減できます。
【シニアが特に注意すべきリスク管理】
シニア世代の投資は、守り」を重視することが鉄則です。
- 目的を明確にする
老後の生活費として取り崩す時期が近い資産は、リスクを抑えた債券中心の運用にするなど、目的と期間に応じて資産配分を調整しましょう。 - 詐欺に注意する
「必ず儲かる」「元本保証」といった甘い誘い文句で、未公開株や高利回りな商品を持ちかける詐欺が増えています。人から勧められた投資話は、必ず金融庁などの公的情報を確認し、自分で判断することが重要です - 余裕資金で運用する
当面の生活費や、数年以内に使う予定のあるお金には手をつけず、長期的に使わない「余裕資金」でのみ運用を行いましょう。
まとめ
投資信託は、コストを抑え、リスクを理解した上で「長期・積立・分散」を実践すれば、シニア世代の資産寿命を延ばす強力なツールになります。
「よく分からないから手を出さない」のではなく、正しい基礎知識を身につけ、ご自身の資産計画に合わせた賢明な選択をすることが、老後の不安解消への第一歩です。
【PR】
年金以外でもお金に対して漠然と不安を抱えているのであれば「資産運用」を検討してみてはどうでしょう?
お金の不安を相談するなら投資信託相談プラザのセミナーに参加してみては?
| 投資信託相談プラザの無料セミナーご参加はこちらから |
| 店舗またはオンラインでの個別相談はこちらから |