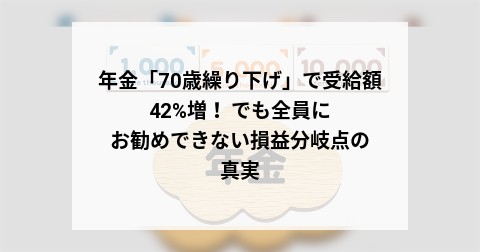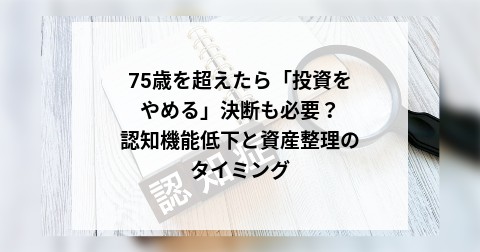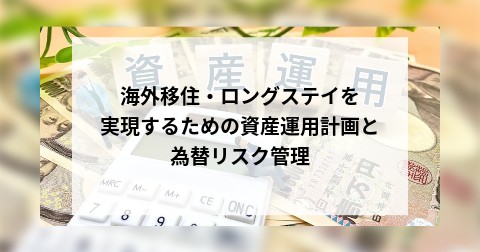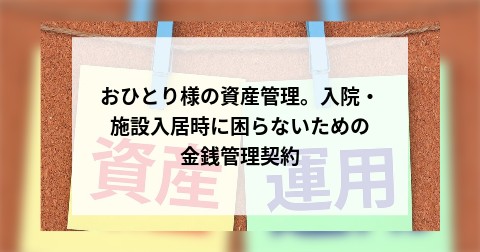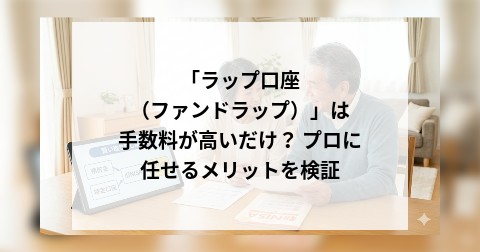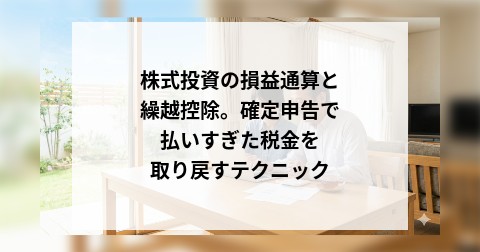【知識ゼロでも安心】定年後に始める「失敗しない」投資のポイント
定年後の人生をより豊かにするために、「投資」に興味をお持ちの方も多いのではないでしょうか?「でも、投資なんて全くの初心者だし、損をするのは怖い…」と感じている方もいるでしょう。
たしかに投資にはリスクが伴いますが、正しい知識とステップを踏めば、定年後からでも安心して資産形成を始めることができます。
本記事では定年後の投資を始める上での心構えと、失敗しないための基本原則をお伝えします。
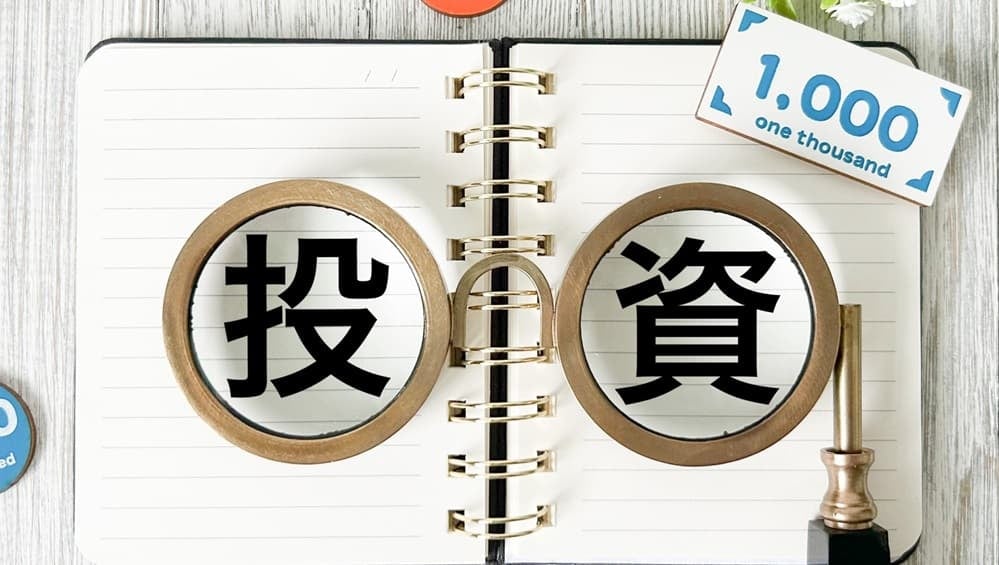
なぜ資産運用が必要なのか
公的年金だけでは足りない?老後資金の実情
老後の生活を支える主な収入源となる公的年金ですが、多くの場合、現役時代の収入と比べると受け取る額は少なくなります。 また、少子高齢化が進む中で、将来的に年金の支給額や受け取りを開始できる年齢が変わる可能性も指摘されています。
公益財団法人生命保険文化センターの調査(令和4年度「生活保障に関する調査」)によると、夫婦2人が老後生活を送る上で最低限必要と考える日常生活費は、月額平均で約23万円。 さらに、旅行や趣味など、ゆとりある生活を送るためには月額平均で約38万円が必要と考えられています。
現在の公的年金だけで、これらの費用をすべて賄うのは、簡単なことではないかもしれません。 資産運用は、こうした不足分を補うための一つの有効な手段となり得ます。
インフレリスクから資産を守る必要性
インフレとは、モノやサービスの価格(物価)が継続的に上がることです。 近年、食品やエネルギー価格の上昇など、物価上昇のニュースを耳にする機会が増えています。
もし今後もインフレ傾向が続けば、現在銀行などに預けているお金の価値は、実質的に目減りしてしまうことになります。 例えば、物価が毎年2%ずつ上がると仮定すると、今の100万円は、約10年後には約82万円、約20年後には約67万円分の価値しか持たなくなってしまう計算になります(これはあくまで計算上の目安です)。
預貯金は元本が保証されている安心感がありますが、現在の低金利状況では、インフレによってお金の価値が減っていくスピードに追いつけない可能性があります。
投資を始める前に知っておくべきこと
現状を把握する
投資を始める前に、まず大切なのはご自身の現状を把握することです。家計の収支、現在の貯蓄額、そして定年後の生活費や使いたいお金について具体的に考えてみましょう。
-
家計の棚卸し: 毎月の収入と支出を把握し、無理なく投資に回せる金額を明確にします。
-
貯蓄額の確認: 今ある貯蓄を把握し、生活防衛資金(何かあったときのためにすぐに使えるお金)を確保できているか確認します。一般的に、生活費の3ヶ月~6ヶ月分が目安と言われています。
-
ライフプランと目標設定: 「いつまでに、いくら増やしたいのか」「何のためにそのお金を使いたいのか」を具体的に設定しましょう。「孫の教育資金に」「旅行資金に」「万が一の備えに」など、明確な目標があることで、モチベーションを維持しやすくなります。
このステップは、投資の羅針盤となる「お金の地図」を描く作業です。ここをしっかり固めることで、漠然とした不安が具体的な目標へと変わり、投資への第一歩を踏み出しやすくなります。
65歳からの資産運用で押さえるべき3つのポイント
①「増やす」よりも「守る」意識を強く持つ
現役世代の資産運用は、資産を積極的に増やしていくことを目標としますが、65歳からの資産運用は、「現在の資産をいかに目減りさせずに長持ちさせるか」、つまり「守りの運用」が基本となります。
-
ハイリスク商品への過度な投資は避ける: FXや仮想通貨、個別株への集中投資など、価格変動の激しい商品は、短期間で大きな利益を狙える反面、資産を大きく失うリスクがあります。一度失った資産を取り戻すための時間や収入源が限られるため、生活の基盤となる老後資金には適していません。
-
生活防衛資金を確保する: 病気や介護など、予期せぬ大きな支出に備え、すぐに引き出せる預貯金を確保しておくことが重要です。一般的に、生活費の6ヶ月~1年分程度が目安とされます。
-
詐欺に注意する: 高齢者を狙った「必ず儲かる」「元本保証で高利回り」といった甘い誘い文句の投資詐欺が増加傾向にあります。人任せにせず、自分で判断し、不審な話には絶対に乗らないようにしましょう。
②「長期・分散・積立」の原則を継続する
現役時代から資産運用を行っていた方も、これから始める方も、「長期・分散・積立」の基本原則は変わりません。ただし、65歳からはその目的や配分を調整していく視点が必要になります。
-
長期的な視点を持つ: たとえ65歳からでも、人生100年時代と言われる現代において、運用期間はまだ十分にあります。短期的な値動きに一喜一憂せず、数年~数十年といった長い目で資産を育てていく意識を持ちましょう。
-
分散投資を徹底する: 投資先を複数の資産(国内外の株式、債券など)や地域に分散することで、リスクを軽減します。例えば、株式の割合を減らし、比較的安定した債券の割合を増やすなど、リスク許容度に応じたポートフォリオの見直しを検討しましょう。
-
積立投資の継続または調整: 毎月一定額をコツコツと積み立てていくことで、高値掴みのリスクを抑える「ドルコスト平均法」の効果が期待できます。収入状況に合わせて積立額を調整したり、年金収入の中から無理のない範囲で継続したりすることも有効です。
③元本割れリスクを理解しておく
資産運用は、必ずしも投資した額(元本)が増えるとは限らず、投資した額(元本)を下回ってしまう「元本割れ」のリスクがあります。
特に、株式や投資信託といった価格が変動する金融商品は、経済や市場の状況によって価値が上がったり下がったりします。
「絶対に損はしたくない」という気持ちは誰でもありますが、残念ながらリスクを完全にゼロにすることはできません。
「これくらいのマイナスであれば、許容範囲だ」というラインをあらかじめ自分の中で決めておくこと、そして、「なぜ自分はリスクを取って運用するのか(インフレ対策のため、ゆとり資金作りのため、など)」という目的を明確にしておくことが、市場が変動した際にも冷静な判断を保つ助けになります。
リスクについて正しく理解し、ご自身が納得した上で運用を始めることが何よりも大切です。
65歳からでも始めやすい資産運用方法
65歳から資産運用を始める場合、現役世代とは異なり、「資産を大きく増やす」ことよりも「資産を守りながら、無理なく長く運用していく」ことに重点を置くのが賢明です。
ここでは、65歳からでも始めやすい、比較的リスクを抑えた資産運用方法をいくつかご紹介します。
新NISA(少額投資非課税制度)の活用
2024年から新しくなったNISAは、非課税で投資できる枠が大幅に拡充され、生涯にわたって非課税で運用できる非常に魅力的な制度です。年齢制限もないため、65歳からでも活用できます。
つみたて投資枠の活用
-
特徴: 毎月一定額を自動で積み立てる仕組みで、時間分散の効果(ドルコスト平均法)により、高値掴みのリスクを抑えられます。
-
メリット: 長期的な視点でコツコツと資産形成を目指すのに適しており、投資初心者でも始めやすいです。非課税投資枠が年間120万円と大きいのも魅力です。
-
おすすめの商品: 国内外の株式や債券に分散投資する「バランス型投資信託」や、特定の指数に連動する「インデックス型投資信託」など、低コストで分散効果の高いものがおすすめです。複数の資産に分散されているため、リスクが比較的抑えられています。
成長投資枠の活用
-
特徴: 個別株や投資信託を自分で選んで購入できる枠です。
-
メリット: 成長が期待できる企業に投資したり、高配当の銘柄を選んだりすることも可能です。ただし、個別株はリスクが高い場合もあるため、慎重な選定が必要です。
-
おすすめの商品: つみたて投資枠と同様に、インデックス型投資信託やバランス型投資信託を検討するのが良いでしょう。もし個別株に興味がある場合でも、まずは少額から始め、十分に企業を調べてから投資することをおすすめします。
個人向け国債
個人向け国債は、日本国政府が個人向けに発行している債券です。 国がお金を借りる代わりに、利子を支払う仕組みになっています。
-
特徴: 国が元本と利子の支払いを保証しているため、非常に安全性が高い金融商品です。元本割れのリスクがほとんどなく、購入から1年経過すればいつでも中途換金が可能です。
-
メリット: 定期的な利子収入が得られ、比較的安定した運用が可能です。「増やす」というよりも「守る」ことに重点を置きたい方、特に退職金などのまとまった資金を安全に運用したい方におすすめです。
-
注意点: 金利は低い傾向にあります。
債券型投資信託・バランス型投資信託
投資信託の中でも、債券を中心に運用するタイプや、株式と債券などを組み合わせて運用するタイプは、比較的リスクが低いとされています。
債券型投資信託
-
特徴: 国内外の債券に投資する投資信託です。債券は一般的に株式よりも価格変動が小さく、安定した収益が期待できます。
-
メリット: 専門家が分散投資してくれるため、個別の債券を選ぶ手間がかかりません。比較的安定した利回りを目指したい場合に適しています。
バランス型投資信託
-
特徴: 株式、債券、不動産投信(REIT)など、複数の資産に分散して投資する投資信託です。リスクとリターンのバランスを調整して運用されています。
-
メリット: 複数の資産に自動で分散投資してくれるため、投資初心者でも手軽に分散投資が実践できます。商品によっては、アセットアロケーション(資産配分)を自動で調整してくれるものもあります。
まとめ
65歳から始める上での重要な心構え
-
「増やす」よりも「守る」を優先する: 現役時代のようにリスクを取って大きなリターンを狙うのではなく、資産の目減りを防ぎ、安定した運用を目指しましょう。
-
長期的な視点を持つ: 65歳からでも運用期間は十分にあります。短期的な値動きに一喜一憂せず、落ち着いて運用を続けることが大切です。
-
分散投資を心がける: 一つの商品に集中せず、複数の商品や資産に分散して投資することで、リスクを軽減できます。
-
無理のない範囲で始める: まずは少額から始め、徐々に慣れていくことが大切です。生活資金を削ってまで投資に回すのは避けましょう。
-
わからないことは専門家に相談する: 銀行や証券会社の窓口、またはファイナンシャルプランナーなどの専門家は、個別の状況に合わせたアドバイスを提供してくれます。
これらの方法を参考に、ご自身のライフプランやリスク許容度に合わせて、無理なく安全な資産運用を始めてみてください。