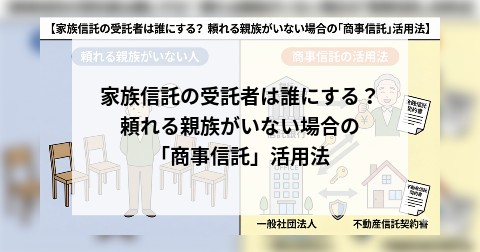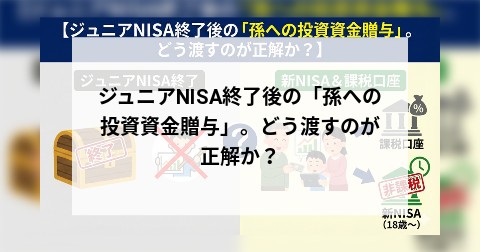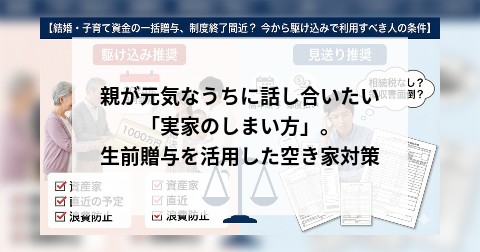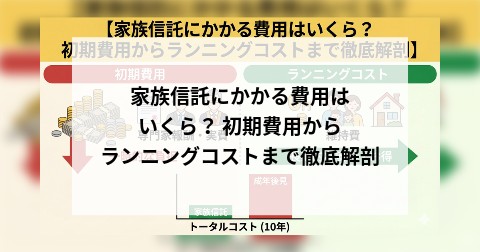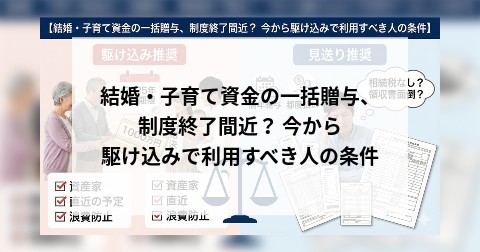中小企業の事業承継に!家族信託で後継者と会社の未来を守る
多くの中小企業にとって、事業承継は避けて通れない重要な課題です。特に、後継者へのバトンタッチは、会社の将来を左右する一大イベント。しかし、「後継者にスムーズに会社を任せたいけれど、経営権の承継や相続で揉めないか心配…」「認知症になったら会社はどうなるんだろう?」といった不安を抱える経営者の方も少なくありません。
そんな中小企業の事業承継の悩みを解決する有効な手段として、近年注目されているのが家族信託です。家族信託を活用することで、後継者へのスムーズな事業承継を実現し、万が一の事態にも備えながら、会社の未来を確実に守ることができます。この記事では、家族信託が中小企業の事業承継において、どのようなメリットをもたらし、どのように活用できるのかを具体的に解説していきます。

事業承継における中小企業の課題
中小企業庁の調査によると、多くの企業が後継者不在の問題に直面しており、経営者の高齢化も進んでいます。M&Aなどの選択肢もありますが、長年築き上げてきた会社を家族に引き継ぎたいと考える経営者も多いでしょう。しかし、家族への事業承継には、以下のような特有の課題が潜んでいます。
-
経営権の分散・混乱: 株式が複数の相続人に分散してしまうと、経営の意思決定がスムーズに行えなくなる可能性があります。
-
後継者以外の相続人との軋轢: 後継者以外の兄弟姉妹が株式を相続した場合、会社の経営に関与しようとしたり、高値での買い取りを要求したりするなど、トラブルに発展するケースも少なくありません。
-
経営者の認知症・病気への備え: 経営者が認知症などで判断能力を失うと、会社の重要な意思決定ができなくなり、経営が停滞するリスクがあります。
-
相続時の多額の納税: 株式や事業用資産は相続財産となり、多額の相続税が発生する可能性があります。
これらの課題を解決し、円滑な事業承継を実現するために、家族信託が有効な手段となり得るのです。
家族信託とは?事業承継における基本を理解する
家族信託とは、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産を託し、その財産を特定の人(受益者)のために管理・運用してもらう制度です。事業承継の文脈では、主に以下のように活用されます。
-
委託者: 経営者本人(会社の株式や事業用資産を託す人)
-
受託者: 後継者(託された財産を管理・運用する人)
-
受益者: 経営者本人、または後継者、その家族など(財産から利益を受け取る人)
家族信託を設定する際には、財産の管理・運用方法や、誰にどのような利益を与えるかなどを定めた信託契約を締結します。この信託契約によって、経営者の意思を反映した形で、会社の株式や事業用資産を後継者に引き継ぐことが可能になります。
家族信託による事業承継のメリット
家族信託を事業承継に活用することで、以下のような多岐にわたるメリットを享受できます。
現経営者が経営に関わり続けられる
株式移転による事業承継の場合、事業承継により会社を経営する権利は後継者に移転し、現経営者は経営から退くことになります。
一方で、家族信託による事業承継の場合、指図権者という受託者に信託財産の管理や処分等の指図ができる権利を持つ者を定めることができます。
現経営者を委託者兼指図権者とすることで、現経営者は後継者に対して議決権の行使についての指図ができるようになり、引き続き会社の経営に関わり続けることができます。
後継者が多額の自己資金を必要としない
家族信託による事業承継であれば、株式の売買を伴わないため、後継者が会社の価値に応じた自己資金を準備する必要がありません。
また、現経営者を株式の委託者兼受益者、後継者を受託者とする場合、株式の形式的な所有権は後継者に移転しますが、会社から利益を受ける権利は現経営者のままとなります。
家族信託による事業承継であれば、後継者に多額の自己資金を必要とせずに、経営権を引き継ぐことが可能となります。
次世代以降の後継者を決めることができる
家族信託による事業承継の場合、後継者がなくなった場合の次世代の後継者についても、予め委託者が決めておくことができます。
株式移転によって事業を承継した場合は、その後継者が死亡した際に株式が相続されることになり、後継者の夫・妻やその兄弟など、思いもよらない人が事業を承継することになる可能性があります。また、後継者が株式を第三者に譲渡してしまう可能性も考えられます。
家族信託による事業承継であれば、「現経営者の直系血族に、受益権を代々承継させる。」などと信託内容に含めておくことで、次世代以降の後継者を指定しておくことも可能になります。
家族信託による事業承継の注意点
現経営者の死亡時には相続税が発生する
家族信託を利用した事業承継では、現経営者を第一受益者、後継者を第二受益者として、現経営者の死亡により次の受益者を後継者とするスキームが一般的です。
この場合には、現経営者の相続時において、後継者が取得する株式の受益権が相続税の課税対象になります。
そのため、後継者は現経営者の相続が発生するまでの間に、相続税の支払いに備える必要があります。
後継者を変更できるようにしておく
家族信託の場合、10年を超えるような長期的な契約期間が想定されます。
その期間中に後継者が適格であるかどうかを見定めることができますので、万が一不適格であることがわかったときに備えておくことが大事です。
そこで、契約書には“現経営者の意思に基づいて信託契約が解除できる”とする条項を設けておくべきです。
遺留分に配慮する
遺産の大半が株式である場合、これを特定の人物に与えてしまうことが「遺留分の侵害」と評価されてしまう可能性があります。
亡くなった方の配偶者や子、親などには民法で遺留分の請求権が認められています。
これは遺産の一定割合を確保するための権利です。遺産のうちごくわずかの財産しか受け取れなかった相続人は、遺留分の請求をすることで最低限の取り分を確保することができると法定されているのです。
自社株式を信託財産として後継者に渡すことが遺留分の侵害になるかどうか、これは様々な事情を考慮して考えなければ判断できません。トラブルを避けるためにも、事前に弁護士に相談して評価をしてもらうようにしましょう。
まとめ
中小企業にとって、事業承継は会社の存続をかけた重大な局面です。後継者へのスムーズな移行、経営権の安定、そして経営者の万が一の事態への備えは、会社の未来を左右します。
家族信託は、これらの課題を解決し、経営者の想いを実現するための強力なツールとなり得ます。あなたの会社と家族の未来を盤石なものにするために、この機会に家族信託の導入を検討してみてはいかがでしょうか。専門家と協力し、最適な形で事業承継を進めることで、会社は新たな時代へと力強く歩みを進めることができるでしょう。