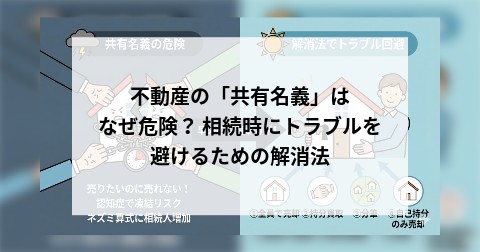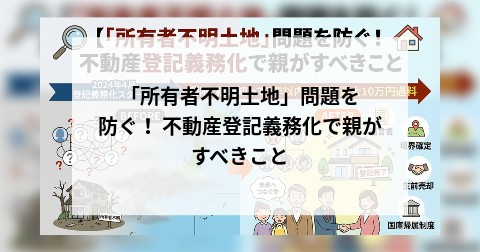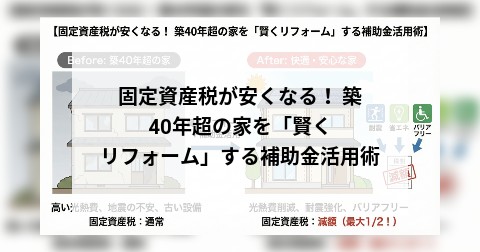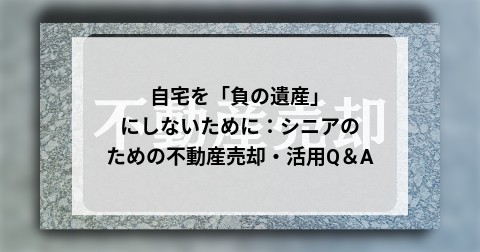共有名義でトラブルになりやすい不動産相続の賢い対処法
家や土地などの不動産を複数人で相続するとき、とりあえず相続人全員の共有名義にするケースがあります。しかし、共有名義での不動産相続はトラブルになることが多いため注意が必要です。
本記事では、共有名義で不動産を相続する際にどのようなトラブルが発生しやすいのか、またトラブルを回避する方法などをご紹介します。

共有名義での不動産相続とは?
共有名義とは、一つの不動産を複数の人が共同で所有することを指します。この形態は家族間の相続や共同購入などでよく見られます。
共有名義の最大の特徴は、各共有者が不動産全体に対して持分を有していることです。つまり、不動産の一部ではなく、全体に対して権利を持ちます。これにより、各共有者は不動産の使用や処分に対して一定の権限を持つことになります。
共有名義での相続でも相続登記が必要
共有名義で家などの不動産を相続した場合であっても、単独名義で相続した場合と同様に相続登記は必要です。
2024年4月から不動産を相続した場合の相続登記申請が義務化されたため、不動産を相続したら、相続登記申請を必ずしなければなりません。
相続登記申請は、被相続人(亡くなった人)と相続人(相続する人)について、戸籍謄本や住民票など、さまざまな書類を揃えて申請書と共に法務局に提出します。
自分で相続登記をすることも可能ですが、手続きが煩雑で提出書類を揃えるのが大変なので、司法書士に依頼することが多いです。
相続登記申請をして、名義人が亡くなった人から相続人に変更されると、共有名義人全員に登記識別情報通知書が発行されます。
共有名義の持分割合について
複数の相続人で不動産を相続する際に決めなければならないのが、誰がどのくらいの割合で不動産を所有するかという「持分割合」です。
遺言があれば遺言の内容に従って、遺言がなければ法定相続分(民法によって定められた各相続人の相続割合)に基づいて、それぞれの相続人の持分割合が決まります。
共有名義の基本を理解するために、具体的な例を見てみましょう。たとえば、兄弟姉妹3人が実家を共有名義で相続した場合、以下のように持分が分かれます。
| 共有者 | 持分割合 | 権利範囲 |
| 兄 | 1/3 | 不動産全体の1/3 |
| 姉 | 1/3 | 不動産全体の1/3 |
| 妹 | 1/3 | 不動産全体の1/3 |
法定相続分通りに分けない場合は、「誰に、どれくらい」持分割合を分けるのかを相続人同士で話し合い、話し合った内容を遺産分割協議書にまとめなければなりません。
共有名義で不動産を相続する問題点
共有名義で家を相続すると、以下のような問題が生じる恐れがあります。
- 遺産分割協議がまとまらない
- 共有者全員が同意しなければ売却や活用ができない
- 固定資産税や管理費などの負担で揉める
- 新たな相続によってさらに持分が複雑になる
遺産分割協議がまとまらない
相続する財産が、亡くなった方(被相続人)の自宅のみで、かつ相続人が複数いるような場合、家の持分割合を決める際に揉める可能性が高くなります。
遺言がない場合は、それぞれが受け取るのは基本的に法定相続分です。
法定相続分通りに分けない場合は、相続人同士で遺産分割協議をして決めることになりますが、寄与分や特別受益で揉めるケースも考えられます。
共有者全員が同意しなければ売却や活用ができない
スムーズに相続した不動産の持分割合が決まったとしても、共有者が多いと将来的に揉めることもあります。
なぜなら、共有名義の不動産は、共有者全員が同意しなければ売ったり活用したりできないからです。一人でも「売るのは反対」や「人に貸すのはイヤ」などと言いだせば、売却することも活用することもできません。
さらに、いざ売却するという話になっても、媒介契約書や売買契約書、売買代金の領収証などには共有名義人全ての記名と実印による押印が必要になるため、手続きに手間がかかるという問題もあります。
固定資産税や管理費などの負担で揉める
共有名義の家に相続人のうちの誰かが住むのであれば、その人が固定資産税や管理にかかる費用を支払うことになるケースが多いです。
しかし、空き家のままでとりあえず置いておくケースなどでは、誰が固定資産税や管理費などを負担するかが揉める原因となります。
持分割合に応じて負担するのが一般的ですが、支払いをしない共有名義人がいると、代表者やほかの名義人全員で負担しなければなりません。
新たな相続によってさらに持分が複雑になる
不動産を共有名義にしていた場合、名義人の一人が亡くなると、その持分が次の相続人に引き継がれることになります。
たとえば、亡くなった父の不動産を母と息子(妻と子どもがいる)の共有名義にしていたケースで、息子が亡くなってしまった場合、息子の持分を相続するのは息子の妻と子どもです。
このように共有者が死亡して相続人の世代交代が進むと、共有者の数が増え、不動産の権利関係がさらに複雑化することになってしまいます。
親しい仲であるうちは問題がありませんが、細分化していくと共有者がだれなのかわからなくなり、連絡もとれず、家をどうすることもできないという状態になりかねないのです。
不動産は共有持分(それぞれの人がその不動産について持っている所有権の割合のこと)のみ売却することも可能ですので、赤の他人と共有者になる可能性もあります。
共有名義での不動産相続を回避する対策
共有持分の「売却」
共有状態を解消する手段として、もっとも現実的かつ多く利用されているのが「売却」です。
売却には「共有者全員で不動産を売却する方法」「自分の持分だけを第三者に売却する方法」の2つがあります。
前者は市場価格での売却が見込める一方、全員の合意が前提となるため、1人でも反対すれば実現できません。一方、後者では自分の共有持分だけを手放すことができ、共有者との調整が困難な場合でも有効です。
通常の買い手は見つかりにくいですが、訳あり不動産に特化した専門業者であれば買取が可能なケースもあります。持分の処分によって精神的・金銭的な負担から解放される場合もあるため、状況に応じて柔軟に検討することが重要です。
代償分割
代償分割とは、相続人の誰か1人が不動産を取得して、他の相続人には代償金を支払うことによって清算する方法です。
次のようなケースでよく用いられます。
- 相続財産が亡くなった人の家のみ
- 相続人が複数いる
- 相続人のうちの一人が相続した家に住んでいる
具体例を用いて代償分割を解説します。
|
父親の遺産を相続する例
上記の例では、遺産を均等に分配することはできません。兄が不動産を取得する場合、兄の手出し金で弟へ「代償金1,000万円」を支払うことで代償分割が成立します。
|
代償分割なら、代償金で清算することで兄弟2人とも「2,000万円の価値」を相続できます。
換価分割
換価分割とは、相続した家を売却し、売却によって得られたお金を相続割合で分割するという方法で、次のようなケースで用いられることの多いです。
- 相続財産が亡くなった人の家のみ
- 家と現金などを含めた相続財産がうまく分割できない
- 相続人が複数いてだれも相続した家に住まない
もちろんこの場合も、自宅を相続人全員の共有とすることができます。しかし、分割できない家を「持分」で分けると、トラブルになる可能性が高いというのは前述の通りです。
不動産はだいたいの金額であれば、不動産会社に査定してもらうなどで、家の価格を知ることができますが、売却するまでは実際にいくらで売れたのかということは誰にもわかりません。
そう考えれば、代償分割よりも換価分割の方がより公平に分け合える方法だといえます。
相続時に換価分割する場合は、便宜上、相続人のうちの1人が代表者として売却活動することが一般的です。そうすることで、共有不動産にして売却するよりも、手間が少なくすみます。
土地を物理的に分ける「分筆」
「分筆」とは、1つの土地をいくつかの部分に区分する手続きを指し、共有持分が土地の状態である場合に選択可能です。
例えば、兄弟2人で土地を等分して共有している場合、それぞれが半分ずつの土地を独占する形で分筆すれば、それぞれの土地に対する権利が明確となり、共有に伴う問題(例:話し合いの必要性や相続問題など)が生じるリスクを軽減できます。
この手法は、全員が該当の土地を保持したい場面に適しています。重要な点として、分筆により土地を単独所有としても、贈与税は生じないことを確認しておきましょう。ただ、このプロセスは所得税の課税の観点から見ると、懸念材料となる場合があります。
共有持分の「放棄」
共有者が持つ持分を放棄する。あるいは他の共有者から放棄を依頼することで、共有名義の土地を単独所有にすることが可能です。
この方法は贈与とは異なり、持分の受け取る相手を明示しない点が特徴。しかし、税務的な取り扱いは贈与と似ており、放棄を受けた共有者に贈与税や不動産取得税が課される場面が考えられます。
持分を放棄する行為は、他の共有者の同意を必要としないものの、登記の際には共有者全員の協力が必要です。もし、協力が得られない場合には、裁判所を通じて登記を実行するという方法もあります。
共有者同士での「持分交換」
複数の土地において、同じ共有者間での共有状態が継続している場合、持分の交換を考慮することで共有の問題を解消できます。
例として、土地Aと土地Bが兄弟の間で共有されている状態を想定します。持分を交換することで、土地Aは兄の単独所有、土地Bは弟の単独所有と変更可能。
このような持分の交換には、所得税が発生する可能性があります。ただし、一定の要件を満たす場合、所得税法に基づき税の非課税措置が受けられます。
この方法は、資金の準備や取引の手間が少なく、かつ税金の面でもメリットがあるため、共有者双方にとって有益な選択となる可能性が高いでしょう。
まとめ
共有名義は相続や贈与などで生じやすい一方、時間の経過とともに関係者の数が増え、話し合いが難しくなる傾向があります。「今は問題ないから」と放置しておくと、いざ売却や活用を考えた際に大きな障壁となる可能性も否めません。
将来的なトラブルを未然に防ぐためにも、自分のケースに合った方法で早めに共有名義の解消を検討ましょう。