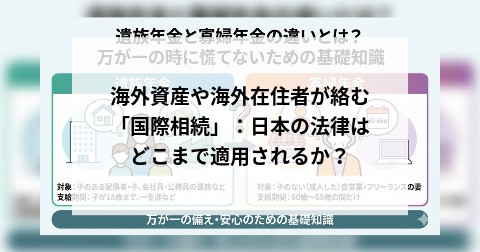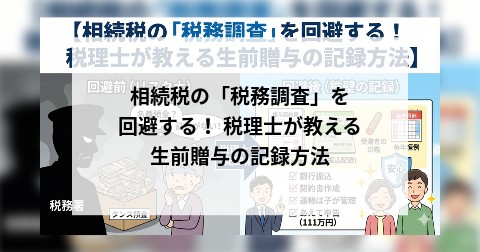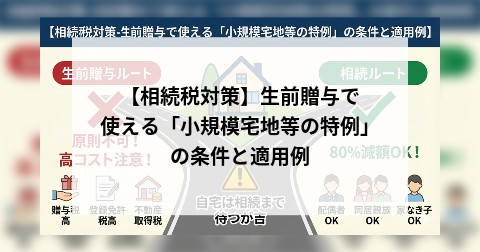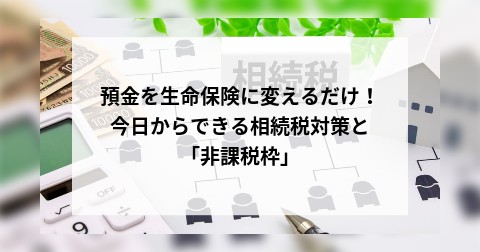【知らないと損】税金で後悔しない!シニアのための賢い相続税対策
相続が発生すると、遺産整理だけでなく、相続人自身の生活も大きく変わります。特に高齢者の場合、住まいや生活資金に関する不安が増大することもあります。
今回の記事ではシニア世代に知っておいてほしい相続税対策をご紹介します。

相続税対策とは?
相続税とは、亡くなった人の財産を相続するときに発生する税金のことです。亡くなった人が「被相続人」、遺産を受け取る人が「相続人」です。民法で相続する権利があると定められている人を「法定相続人」と呼びます。
税率は10%から55%ですが、遺産の金額が大きいほど高い税率が適用される仕組みです。実際に納める税額は相続財産の総額や相続人の数によって異なります。
相続税は一定の額までは控除されるため、財産の総額がその範囲内であれば税金の支払いは発生しません。これを基礎控除額といい、以下の計算式で求めることができます。
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税額を抑えるために、生前からなんらかの準備をしておくことが相続税対策です。なお、相続財産とは現金・預貯金、株などの有価証券、宝石、不動産、生命保険など、金銭として見積もることができるものすべてです。
シニア世代の相続税対策について
相続税対策は、シニア世代にとって重要な財産管理の一環です。適切な対策を行うことで、相続人への負担を軽減し、円滑な資産の移転を実現することが可能です。以下では、シニア世代の相続税対策を考える際のポイント、課題、および対策について詳しく解説します。
相続税対策の課題
基礎控除の理解
相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。この額を超える財産がある場合、相続税が課税されます。
不動産評価額の変動
不動産の評価額は、立地条件や周辺環境によって変動するため、相続税の計算に影響を与える可能性があります
生前贈与の注意点
生前贈与は、相続税対策として有効な手段ですが、贈与税の課税対象となるため、贈与税の基礎控除額や特例を考慮する必要があります。また、生前贈与は、贈与者の財産状況や健康状態、贈与後の生活状況なども考慮する必要があります。
遺言書の作成
遺言書は、相続人の間で紛争が起こることを防ぐために有効な手段ですが、遺言書の作成方法や内容によっては、無効となったり、トラブルの原因になる可能性があります。
相続税の対策例
生前贈与
生前贈与は、相続税の基礎控除額を活用し、相続財産を減らすことで、相続税の負担を軽減する効果があります。年間110万円までの贈与は非課税となるため、毎年この範囲内で贈与を行うことで、相続財産を計画的に減らすことができます。また、一定の年齢に達した人が、住宅取得資金や教育資金を贈与する場合、特例が適用される場合があります。
生命保険の活用
生命保険は、相続税の非課税枠を活用することで、相続税の負担を軽減することができます。法定相続人1人あたり500万円までの生命保険金は非課税となるため、この非課税枠を活用することで、相続財産を減らすことができます。
不動産の活用
不動産を所有している場合、賃貸アパートを建てることで、相続税評価額を下げることができます。また、不動産を売却して現金化することで、相続税の計算がしやすくなります。
お墓や仏壇の購入
お墓や仏壇の購入は、相続財産から除外されるため、相続税の節税対策として有効です。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、一定の条件を満たす宅地について、相続税の評価額を減額する制度です。この特例を活用することで、相続税の負担を軽減することができます。
まとめ
相続税対策の種類は多岐にわたるものの、あまり節税効果のない方法や対象者が限定される方法もあります。最適な相続税対策をお探しの方は、ここまで紹介した節税効果が高く、取り組みやすい方法を参考にしてみてください。中には複雑な計算を要する控除制度も存在しますので、不安な方は税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。