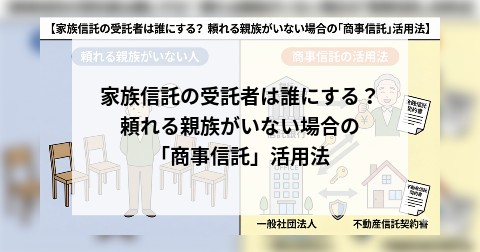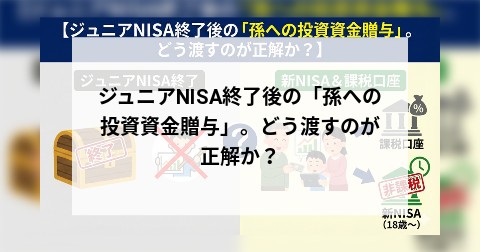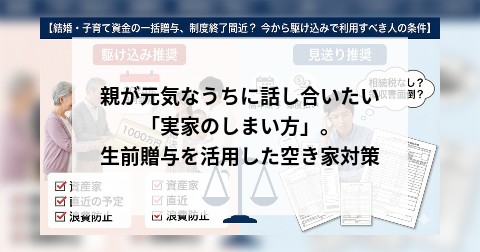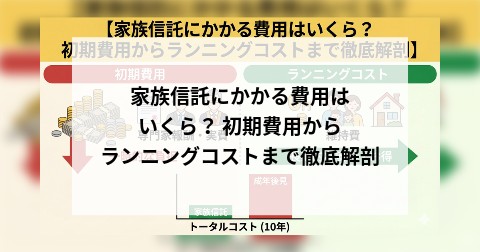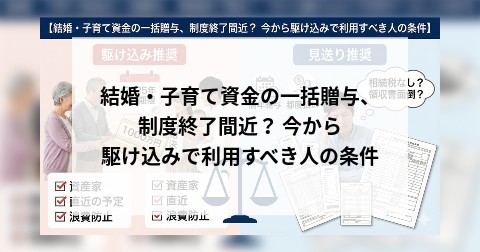相続税対策の切り札!「早めの生前贈与」で後悔しない資産承継を
「相続税は自分には関係ない」と考えていませんか?
しかし、税制改正によって相続税の基礎控除額が引き下げられたため、以前よりも多くの方が相続税の対象となる可能性が出てきました。
相続税は、故人が遺した財産を巡って、ご家族の間でトラブルになる原因の一つでもあります。
ここでは、相続税対策の「切り札」となる生前贈与について、そのメリットと後悔しないためのポイントをご紹介します。
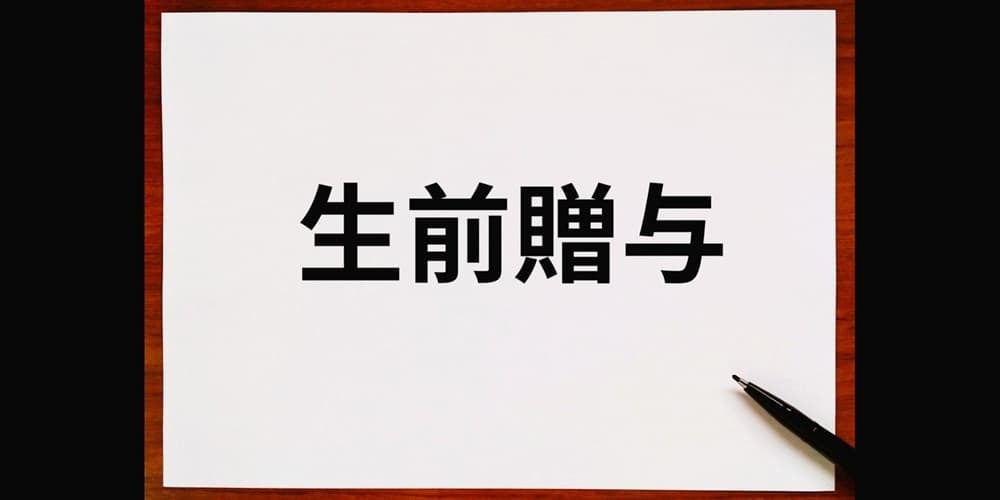
なぜ「生前贈与」が有効な相続税対策なのか?
生前贈与は、個人が自分の財産をほかの誰かに贈与することを言います。
贈与する側が「あげる」、受け取る側が「もらう」となるように双方の合意を得て成立します。
生前贈与は金額によっては受け取った側に贈与税が課税されますが、贈与税の特例や非課税制度を使えば節税可能です。
あらかじめ生前贈与して、相続税を目減りさせておくことによって、相続税額を下げる効果もあります。
生前贈与の方法
暦年課税の非課税枠
贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間で受け取った額を合計して計算します。
合計から基礎控除額110万円を差し引いて、残りの金額の税率をかけて計算する仕組みです。
税率は最低10%から最大55%まで所定の控除を差し引いて計算します。
贈与税は、基礎控除額の110万円までであれば、非課税で申告も不要です。
つまり、この非課税枠を利用すれば、毎年110万円以内で少しずつ贈与できます。
110万円ずつであっても、数年かければまとまった金額を贈与できます。
さらに、贈与する側は誰に対して何人でも贈与できるため、一度に子どもや孫のように複数に贈与すればまとまった金額を贈与可能です。
事前に相続財産を減らしたい時に有効な手段として使われています。
相続時精算課税制度
これは、60歳以上の贈与者が20歳以上の子または孫に対して、2500万円までの生前贈与をまとめて非課税にするが、贈与した人が亡くなったときは贈与した財産分も合わせて相続税を納税するという制度です。暦年課税が毎年110万円以下まで非課税にするなら、相続時精算課税制度は2500万円分の非課税の範囲をあらかじめとっておくイメージです。
たとえば、3000万円の資産を持つAさんが、相続時精算課税制度を利用して息子に2500万円贈与したとします。2500万円までは非課税なので、贈与税はゼロです。したがって、Aさんの資産は500万円になり、2500万円はそのまま息子の手元に移ることになります。しかし、Aさんが亡くなったとき、相続税は手元資金の500万円ではなく、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産の2500万円を足した3000万円に対して発生します。
また、相続時精算課税制度には届出の提出が必要であり、一度選択すると永久に継続されるといったデメリットもあります。さらに、暦年贈与と相続時精算課税制度は、どちらかしか利用できません。
特例や非課税制度」を活用した生前贈与
贈与税は特例や非課税制度を活用して対策可能です。
例えば、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」は、直系の父母、祖父母より20歳以上(2022年4月からは18歳以上)の子どもや孫が居住用の住宅取得資金などの援助を受ける場合に非課税の特例が受けられる制度です。
住宅の家屋の種類や受取人の条件もあるため、国税庁のホームページで利用できるかどうか確認してみましょう。
また、夫婦間で居住用の不動産などを贈与する場合にも、基礎控除額110万円とは別に最高で2,000万円まで控除可能です。
以前は、生前贈与した自宅も特別受益として遺産が分割されることがありました。
現在は法改正で相続から除外されるようになり、配偶者に確実に自宅を残したい場合に利用されています。
父母や祖父母などから30歳未満の人が教育資金に充てるお金を受け取った場合にも、最大で1,500万円の贈与税が非課税になります。
特例や非課税枠の制度は適用期間が決まっているものもあるので、必ず条件や期間を確認して利用してください。
生前贈与をする際の注意点
生前贈与は相続対策として有効な方法ですが、やり方を誤ると贈与が認められなかったり、予定外の税負担が生じたりする可能性があります。
特に、以下の4つの点に注意しましょう。
- 名義預金に注意する
- 贈与税の特例・制度の適用要件を確認する
- 遺留分侵害額請求に注意する
- 老後の資金計画にも注意する
名義預金に注意する
生前贈与をしたつもりでも、税務署の調査で「贈与とは認められない」と判断されることがあります。例えば、子どもや孫の名義で口座を作り、そこにお金を移しても、その通帳や印鑑を贈与者が管理していた場合は「名義預金」とみなされ、相続財産として相続税の対象になることがあります。
そのため、贈与した資金は、受け取った本人が自分で管理し、自由に使える状態にしておくことが重要です。その都度「贈与契約書」を作成することも有効です。
また、暦年課税で毎年少しずつ贈与する場合は、受贈者が日常的に使用している口座に振り込むと、通帳に記録が残り、贈与の証拠になります。さらに、信託銀行が提供する、暦年贈与をスムーズに行う信託商品を活用する方法もあります。
贈与税の特例・制度の適用要件を確認する
贈与税の特例や非課税制度を利用する際は、申告書の提出が制度適用の要件になっているケースもあるため注意が必要です。たとえ非課税になる場合でも、申告を忘れると適用されない可能性があります。
また、年間110万円を少し超える贈与を行い、贈与税の申告と納付をしておくことで、申告書の控えが贈与の証明資料として役立ちます。例えば年間200万円の贈与であれば、贈与税率10%により税額は9万円で済みます。手取り200万円を確保したい場合は、贈与税分を加えて210万円を贈与するという方法もあります。
遺留分侵害額請求に注意する
遺留分とは、法定相続人に法律で保障されている最低限の遺産取得分のことです。遺言や生前贈与によって特定の人に多くの財産を渡していた場合でも、他の相続人が遺留分を侵害されたと感じれば、「遺留分侵害額請求」に発展する可能性があります。
例えば、特に可愛がっていた孫に資産の大部分を贈与したような場合、他の相続人との間で不公平感が生じ、トラブルに発展することがあります。生前贈与は相続争いを避ける手段として有効ですが、財産の配分が偏ることでかえって争いを招くおそれもあるため、相続人全体のバランスを意識して慎重に判断することが重要です。
老後の資金計画にも注意する
生前贈与を行う際は、自身の将来の生活資金に支障が出ないようにすることも大切です。教育資金や結婚・子育て資金の支援として多額の贈与を行った結果、自分の生活費や医療・介護費が足りなくなると、かえって家族に負担をかけることになります。
近年は長寿化が進み、老後に必要な費用は想定よりも多くなる傾向にあります。そのため、生前贈与を検討する際は、長期的な生活設計を立てたうえで、余裕資金の範囲内で無理なく行うことが重要です。
まとめ
生前贈与は、税理士などの専門家と相談し、現在の税制や将来の家族の状況に合わせて計画的に進めることが大切です。贈与後の管理や税務署から贈与とみなされないための手続きをしっかりと行い、後から後悔することのない、納得のいく資産承継を実現しましょう。