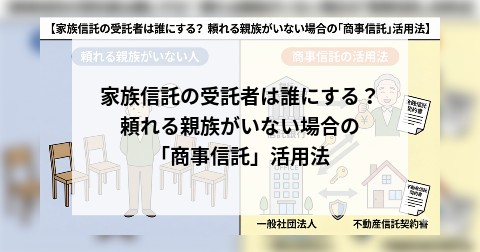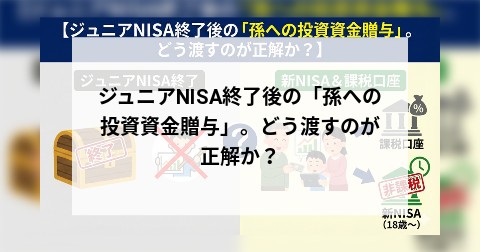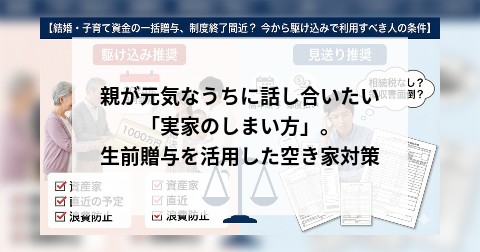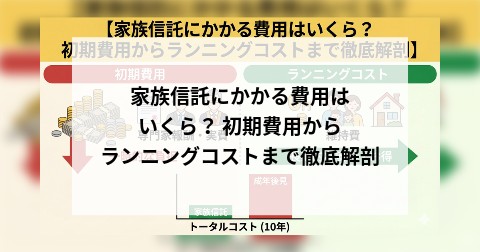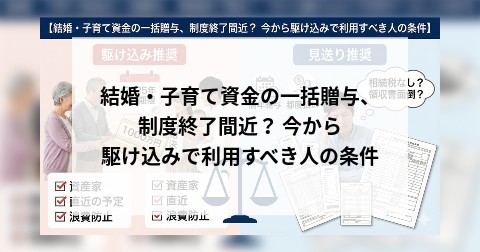家族信託は相続税対策にならない?「信託財産」にかかる税金の基礎知識
近年、生前対策として「家族信託」が注目を集めています。
家族信託とは、信頼できる家族に財産を託し、管理・運用・処分を任せる仕組みのことです。認知症などで財産管理ができなくなるリスクに備えられる、柔軟な財産承継ができる、といったメリットがあります。
しかし、家族信託は「相続税対策」になる、という誤解も少なくありません。
結論から言うと、家族信託自体に直接的な相続税対策の効果はありません。
ここでは、家族信託と税金の関係、そして「信託財産」にどのような税金がかかるのかをわかりやすく解説します。

家族信託と相続税の関係
家族信託とは、老後資金や相続財産になる資産の管理・運用を家族などの信頼できる人に任せる契約です。運用などによって利益が出た際には、受益者に指定した家族へ利益を渡すことになります。
家族信託が相続対策によく用いられるのは、自分が亡くなったあとの財産の承継先を決めておける機能があるためです。受益権を通じて死後も配偶者の老後資金を確保したり、信託終了時の指定によって相続財産の分配方法をあらかじめ決めておいたりできます。
上記のような契約を生前のうちに取り決め、信託契約書に記載することで、相続争いや相続者間のトラブルなどを防げます。財産運用による利点が大きく、認知症対策でも成年後見制度に対応できないケースに有効です。
家族信託で注意すべき税金
贈与税
信託設定時
一般的に、財産を無償で譲渡した場合には贈与税が課されますが、家族信託を用いる場合において、「委託者=受益者」であるとき、つまり財産を託した人本人が、信託財産から生じる利益を引き続き得るときは、贈与税がかかりません。
一方で、委託者以外の人が信託した財産の利益を得るときは、受益者に対して贈与税が課されます。
信託終了時
信託終了時に当初委託者が財産を取得する場合、つまり財産が元の持ち主に戻る場合は贈与税はかかりません。
また、信託終了時に、委託者でない受益者が財産を取得する場合、信託設定時点で贈与税の支払等がなされているため、贈与税の問題は起こりません。
受益者の死亡を原因とする信託の終了など、受益者以外の者が財産を取得する場合は、贈与税や相続税がかかる可能性があります。
不動産取得税
信託設定時
一般的には、不動産を取得した際に取得者に不動産取得税がかかることがありますが、信託ではあくまで財産の管理者を変更するだけであり、財産の確定的移転ではないため、不動産取得税はかかりません。
信託終了時
信託終了時に当初委託者が財産を取得する場合、つまり財産が元の持ち主に戻る場合は不動産取得税はかかりません。
また、信託終了時に、委託者兼受益者の相続人が財産を取得する場合、相続税の問題となりますので、基本的には不動産取得税の問題は起こりません。(一定の条件あり)
それ以外の方が財産を取得する場合には、不動産取得税がかかる可能性があります。
譲渡所得税
信託設定時
不動産を処分した場合に、利益が生じていれば譲渡所得税が課されることがあります。
信託を設定するときは、不動産を処分した訳ではないため、譲渡所得税はかかりません。
信託終了時
信託が終了し、受益者以外の者が財産を取得したときで、財産取得者が受益者に対価を支払った場合には、最終の受益者に対して譲渡所得税が課されます。
相続税
信託設定時
委託者が受託者と家族信託契約により財産を委託した場合、家族信託設定時点では当然ながら相続税はかかりません。
信託設定後契約中
家族信託契約後に受益者が死亡した場合、受益権が相続財産となり、相続税申告の対象財産となります。
家族信託は、相続財産から信託財産を隔離する機能もありますが、受益者死亡の場合で後継受益者を指定していない場合は、信託財産受益権は相続財産となります。
信託終了時
受益者が死亡した際に信託が終了する定めがあるときは、受益権は相続されず、信託財産の帰属権利者が財産(と受益権)を取得します。
帰属権利者の定めがないときは、委託者に財産が帰属し、委託者が死亡している場合は委託者の相続人が財産を相続します。
財産の帰属権利者が最終受益者でない第三者である場合は贈与税の問題になり、最終受益者の相続人である場合は相続税の問題になります。
家族信託は「相続対策」にならないのか?
あくまでも家族信託そのものに節税効果はありません。
家族信託では、財産の引き継ぎ方について柔軟に設計することが可能です。しかし、原則受益者には課税されるため節税対策にはつながらないと考えておきましょう。
家族信託のメリットは、認知症で財産を管理できなくなった場合に家族に任せられることや、生きているうちに財産の引き継ぎ先を指定できることにあります。
財産の引き継ぎ方次第ではなにも相続対策しなかったときと比べて節税できる可能性はあるものの、家族信託をすること自体には節税効果がないことを理解しておきましょう。
まとめ
家族信託によって発生する税金は、誰を受益者にするかによって大きく異なります。発生するタイミングや種類がさまざまなため、設計段階で明確にしておくことが重要です。
また、家族信託そのものには節税効果はありません。むしろ、相続で財産を引き継いだ方が軽減措置が受けられて、税金が抑えられるケースもあります。相続に向けて節税対策を考えているのであれば、家族信託以外の選択肢もたくさんあります。
家族信託契約によって発生する税金は設計内容によってさまざまなため、間違った認識でいると納税通知書が届いて驚くことになりかねません。家族信託契約を交わすべきかどうかもふくめ、早い段階で専門家の支援を受けましょう。