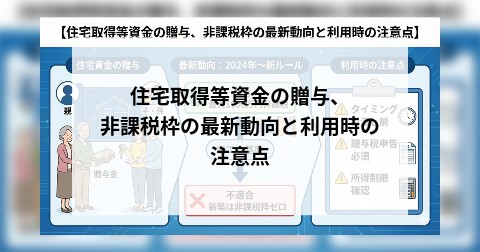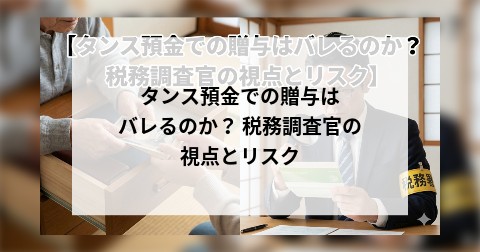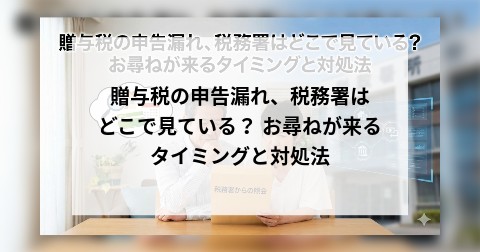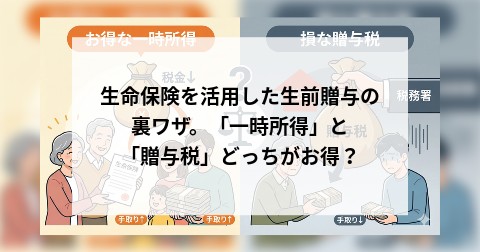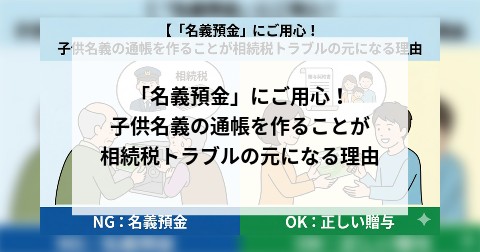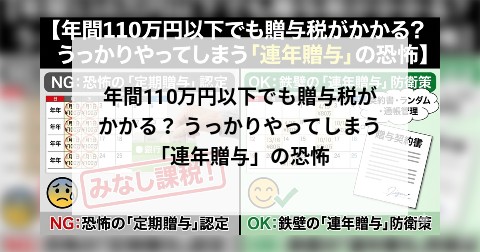夫婦でできる最強の相続対策!おしどり贈与で自宅を賢く引き継ぐ方法
「自宅は夫婦の共有財産だから、相続税はかからないだろう」
そう考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、自宅であっても、相続税の課税対象となります。
特に、自宅を夫婦のどちらかが単独で所有している場合、所有していない配偶者が亡くなった際に、自宅の相続を巡って思わぬ相続税が発生したり、遺産分割でトラブルになったりする可能性があります。
そこで有効なのが、「おしどり贈与」と呼ばれる特例です。これは、夫婦でできる最強の相続対策の一つといえます。
ここでは、おしどり贈与のメリットや活用方法、注意点について解説します。

おしどり贈与とは?その仕組みとメリット
おしどり贈与とは、贈与税の配偶者控除の通称です。婚姻期間が20年以上の夫婦間にしか使えない控除であることから、「おしどり」と呼ばれています。
おしどり贈与は、居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための金銭の贈与に対して2000万円まで控除できる特例です。暦年贈与の基礎控除である110万円と合わせて使うことができるため、贈与額2110万円まで非課税で贈与できます。
現在所有している財産を生前に減らすことで相続財産を減らし、結果的に相続税を下げられるため、おしどり贈与は相続税対策の1つとして広く知られています。
ただし、贈与された配偶者が先に亡くなると相続財産として扱われるため、生前に贈与した分にかかる贈与税と相続時にかかる相続税を二重で納税しなければなりません。そもそも節税効果でいうと、相続税の配偶者控除のほうが高いため、おしどり贈与をわざわざ行う必要がない場合もあります。
おしどり贈与を利用するための主な要件
おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)は夫婦だからといって、誰でも利用できるわけではありません。以下の3つの要件すべてに当てはまらなければ、2000万円の控除が使えないため注意しましょう
- 婚姻期間が20年以上であること
- 贈与された財産が居住用不動産、または居住用不動産取得のための資金であること
- 贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその不動産(土地・建物)に居住してその後も引き続き居住する見込みであること
婚姻期間が20年以上であること
婚姻関係が20年以上ある夫婦の間で行われる贈与であることが第1の要件です。
婚姻期間が19年10か月の場合、「19年」とみなされて要件に当てはまりません。
婚姻期間は通算でも認められ、途中離婚している期間があったとしても、同じ相手と再婚すれば婚姻期間を合算できます。たとえば、結婚して8年で離婚したあと、しばらくして12年婚姻期間が経過すれば合算して「婚姻関係20年以上」の要件を満たします。
ただし、婚姻届を出してない内縁関係や事実婚の2人には適用されません。法律上の夫婦と変わらない関係であっても、婚姻関係がなければおしどり贈与を使えないため注意しましょう。
贈与された財産が居住用不動産、または居住用不動産取得のための資金であること
贈与された財産が居住用不動産であるか、居住用不動産を取得するための資金であるかのどちらかでなければなりません。
ここでの居住用不動産とは、国内にある自宅を指します。つまり、生活の拠点とするための土地・あるいは家屋である必要があります。
また、自宅で個人事業を営んでいる店舗兼住宅も、住居用部分についてはおしどり贈与の対象です。たとえば、1階を飲食店、2階・3階を住居用として利用している建物を配偶者に贈与したとき、2階・3階の住居用部分だけがおしどり贈与を適用できます。
住居用部分の面積がおおむね90%以上である場合は、すべて居住用不動産として建物全体が控除の対象とみなされます。
贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその不動産(土地・建物)に居住してその後も引き続き居住する見込みであること
おしどり贈与には、居住要件もあります。「贈与された年の翌年3月15日までに贈与によって取得した不動産に住んでいて、そのあとも住み続ける見込みがある」必要があります。
この要件は、住むつもりのない不動産を贈与して相続税を引き下げるような、おしどり贈与の特例を利用した税金逃れを防ぐために設けられています。
ただし、実際には住み続けるつもりで贈与を受けたものの、数年後に手放すことになったというケースもあるでしょう。たとえば、健康状態や環境の変化によって介護施設に入居することとなり、息子夫婦に譲る場合や売却する場合が出てきても不自然ではありません。
この要件は、あくまでも贈与時点や贈与の翌年の3月15日時点における意向に対する要件です。おしどり贈与によって取得した不動産だからといって永久に住み続ける必要はないため安心しましょう。
おしどり贈与を適用するための手続き・添付書類
おしどり贈与の特例を使うためには、以下の3つの書類を添付して申告をする必要があります。
① 贈与を受けた日から11日目以降に作成された戸籍謄本もしくは抄本
② 贈与を受けた日から11日目以降に作成された戸籍の附票の写し
③ 贈与を受けた居住用不動産の登記事項証明書
贈与された財産が取得資金ではなく居住用不動産であった場合には上記3つに加え
④ その不動産を評価するための書類(固定資産評価明細書等)
を添付しましょう。
おしどり贈与のメリット
おしどり贈与の代表的なメリットは以下の4つです。
- 相続税対策に活用できる
- 生前贈与加算が不要
- 相続発生後も配偶者の住居を確保できる
- 自宅を売却したときの譲渡所得税を低くできる
おしどり贈与を活用すると相続財産を2,000万円分減らせるため、相続税の課税価格(相続税がかかる金額)も低くなります。
通常、相続開始前3年以内に行われた贈与の場合、贈与分の金額を相続財産に加算しなければなりませんが、おしどり贈与は相続財産への加算が不要です。居住用不動産の一部または全部が配偶者のものとなるため、自宅の所有権をめぐる相続トラブルに巻き込まれることがありません。相続発生後も配偶者の住居を確保できるので、主な相続財産が自宅のみの場合はおしどり贈与のメリットを活かせるでしょう。
おしどり贈与のデメリット
おしどり贈与には以下のデメリットがあるので、生前贈与の節税効果が低くなる可能性も想定されます。
- 不動産取得税が発生し、登録免許税の税率も高くなる
- 贈与された配偶者が先に亡くなるリスクがある
- 節税効果は相続税の配偶者控除の方が高い
不動産を贈与で取得すると、「固定資産税評価額×原則税率4%」の不動産取得税が課税されますが、相続で取得した場合は非課税です。登録免許税も「固定資産税評価額×税率」で計算しますが、贈与の場合は税率2%、相続は税率0.4%が適用されるので、贈与の方が税負担は重くなるでしょう。
まとめ
おしどり贈与は、最大で2,000万円までの贈与が非課税になるため、節税効果が大きな制度と思うかもしれません。しかし、このおしどり贈与を利用したからといって、必ず税負担を軽減できるとは限りません。
配偶者の場合は、相続税においても税額軽減という制度があり、こちらの方が非課税となる財産の額が大きくなります。また、相続と贈与では不動産取得税や登録免許税に違いがあります。
結婚して20年経過したからすぐに利用するのではなく、本当にメリットがあるのかよく考えてから利用するようにしましょう。