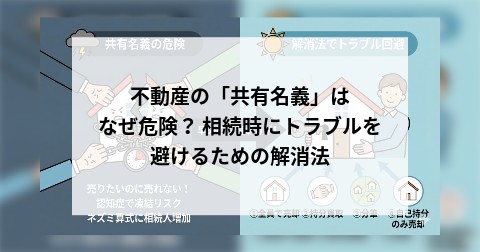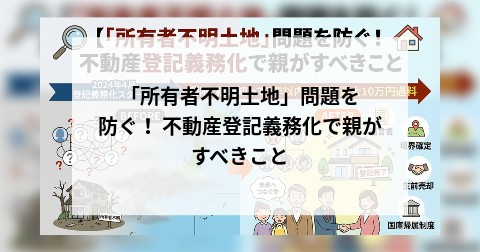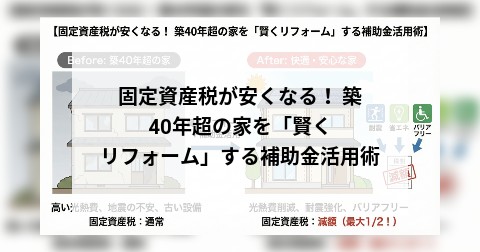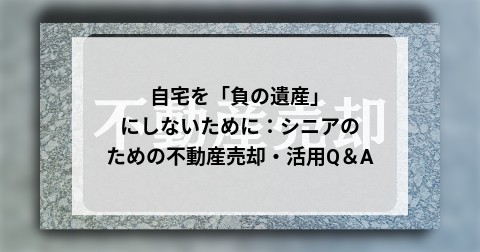家を相続するには?相続登記の方法や注意点
2024(令和6)年4月から相続登記の義務化がスタート。不動産の相続は手続きが複雑で、多くの方が「何から始めればいいのか」と悩んでいるのではないでしょうか。
この記事では、相続登記の方法や注意点を初心者の方にも分かりやすく解説します。将来のトラブルを防ぎ、円滑に相続手続きを進めるための参考にしてください。

家の相続登記とは? 名義変更の義務化
相続登記とは、当該不動産の所有者が亡くなったあと、その名義を相続人へと変更する法的な手続きのことです。
相続登記を行うことで、不動産の所有権が明確になり、相続人がその不動産を自由に売却したり利用したりすることができます。逆に相続登記を行わないと、将来的に不動産を処分する際に手続きが複雑化し、相続人間での紛争となる可能性があります。
相続登記を行わないことで社会問題になっていることから、相続登記の申請が義務付けられました。所有者の死亡を知った日から3年以内に手続きしないと、過料(10万円以下)が科せられます。
この制度は、義務化前の相続も対象です。義務化前で相続登記していない場合は、令和9年3月末まで登記しなければなりません。それでは、どのように相続登記をすればいいのでしょうか。
相続登記の方法:登記の流れと必要書類
相続登記の流れを、複数のステップに分け、それぞれに必要な書類とポイントについてまとめます。
ステップ1:戸籍収集と法定相続人の確定
相続登記の第一歩は、誰が法定相続人なのかを確定することです。被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本が必要です。
必要な書類
- 被相続人の生涯にわたる連続した戸籍謄本
- 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本(除籍謄本)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
ポイント
- 被被相続人の生涯にわたる戸籍謄本を漏れなく集めることが重要です。
- 本籍地に変更があった場合は、本籍地のあった市区町村役場で取得します。
- 戸籍謄本は発行から3ヶ月以内のものが必要です
ステップ2:遺産分割協議書の作成
法定相続人が複数いる場合は、相続人全員で不動産の分割方法を決める必要があります。遺言書がある場合は、その内容が優先されますが、ない場合は遺産分割協議を行います。
必要書類
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印の押印が必要)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
記載すべき内容
- 被相続人の氏名、死亡日
- 相続財産の詳細(不動産の所在地、地番、面積など)
- 各相続人の取得分
- 相続人全員の住所、氏名、実印の押印
- 作成年月日
ポイント
- 相続人全員の合意が必要
- 協議書は原本を作成し、登記申請時にも原本が必要
ステップ3:登記申請書の作成
不動産の登記申請に必要な書類を準備し、申請書を作成します。法務局のウェブサイトでひな形を入手できます。です。
必要な書類
- 登記申請書
- 登記原因証明情報(遺産分割協議書または遺言書)
- 固定資産税評価証明書(不動産の評価額を確認するため)
登記申請書の記載事項
- 申請人の氏名、住所(相続人)
- 不動産の表示(所在、地番、家屋番号など)
- 登記の目的(「所有権移転」と記載)
- 登記原因(「平成○○年○月○日相続」など)
- 課税価格
- 登録免許税額
ポイント
- 登記申請書の作成には正確な不動産情報が必要
- 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を事前に取得しておくと便利
- オンライン申請の場合、電子証明書が必要
ステップ4:法務局への申請と登録免許税の納付
必要書類をまとめて法務局に提出し、登録免許税を納付します
申請方法
- 窓口申請:管轄(対象不動産の所在地)の法務局に直接持参
- 郵送申請:書留郵便で送付
- オンライン申請:電子証明書を使用して申請
必要な費用
- 登録免許税:不動産の固定資産税評価額 × 0.4%
- 郵送の場合は返信用封筒と切手
ポイント
- 登録免許税は収入印紙で納付(法務局で購入可能)
- オンライン申請の場合は電子納付も可能
ステップ5:登記完了と書類受け取り
申請後、法務局での審査を経て登記が完了します。通常、数日~数週間程度で処理されます。
受け取り書類
- 登記完了証
- 登記事項証明書(希望する場合)
登記完了後の確認
- 登記情報は「登記情報提供サービス」や「登記事項証明書」で確認できます。
- 相続登記が完了したことを他の相続人にも共有しておくと良いでしょう。
ポイント
- 登記完了証は大切に保管しましょう。
- 登記完了後、固定資産税の納税通知書の宛名変更手続き(市区町村役場)も忘れずに行いましょう。
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
| 被相続人の戸籍謄本 | 市区町村役場 | 被相続人の生涯にわたるすべて |
| 被相続人の住民票除票 | 市区町村役場 | 最後の住所地にある役所 |
| 相続人の戸籍謄本 | 市区町村役場 | 相続人全員分 |
| 相続人の住民票 | 市区町村役場 | 相続人全員分 |
| 印鑑証明書 | 市区町村役場 | 相続人全員分(3ヶ月以内) |
| 遺産分割協議書 | 相続人が準備 | 相続人全員で作成 |
| 登記申請書 | 法務局 | 法務局提供ひな形 |
| 固定資産税評価証明書 | 市区町村役場 | 不動産評価額を確認するため |
※状況に応じて必要となる書類は異なります。
家を相続登記する際の注意点
相続登記を行う際には、いくつかの重要な注意点があります。これらを把握しておくことで、スムーズに手続きできます。
土地と建物の評価額
土地と建物の評価額の基準は以下のとおりです。
- 土地の評価額:「路線価方式」か「倍率方式」で評価し、土地形状や立地条件に応じて補正する。
- 建物の評価額:自用家屋は、固定資産税評価額を基準とし、貸家は借家権割合(30%)分を差し引く。
これらの評価額は登録免許税の基準となるため、早めに確認しておくことが大切です。
自分で相続登記を行う場合の費用と注意点
相続登記には以下のような費用が発生します。
- 登録免許税:たとえば、評価額1,000万円の場合、登録免許税は4万円
- 書類取得費用:戸籍謄本や住民票など必要書類の取得で数千円程度。
- 交通費:法務局や役所への移動費
自分で手続きする場合は費用をおさえられる反面、以下の点に注意が必要です。
手続きの複雑さ:法定相続人の確認、不動産情報の調査、分割割合の決定など多くのステップがあります。不備がある場合は修正を求められることもあり、時間と労力がかかります。
時間的制約:平日に法務局へ行く必要があるため、仕事や予定との調整が必要です。
スムーズに手続きをするためには、専門家(司法書士)への依頼を検討します。前述の費用に加え、司法書士への報酬が追加されますので、費用負担と時間・労力とのバランスを踏まえて判断するといいでしょう。
まとめ
相続登記は、不動産を適切に引き継ぐための重要な手続きです。2024年4月の義務化により、3年以内の申請が求められるようになりました。手続きは複雑ですが、この記事で紹介したステップに沿って進めることで、スムーズに相続登記を完了させることができます。
特に重要なのは、法定相続人の確定と必要書類の収集です。戸籍謄本の収集から登記申請書の準備と提出まで、丁寧に進めましょう。自分で行うことも可能ですが、複雑なケースや仕事で時間が取れない場合は、専門家に相談することをおすすめします。