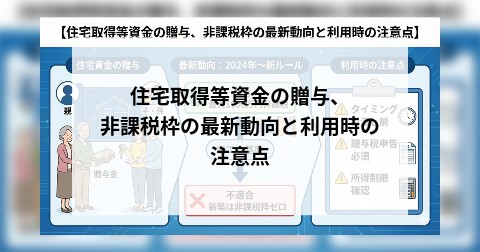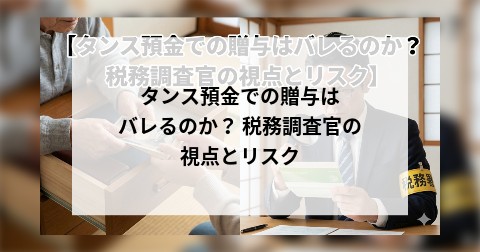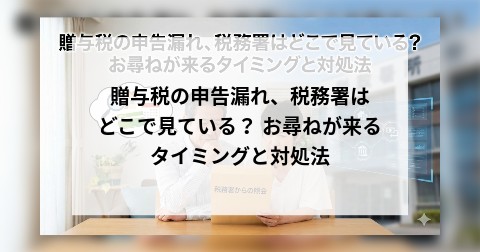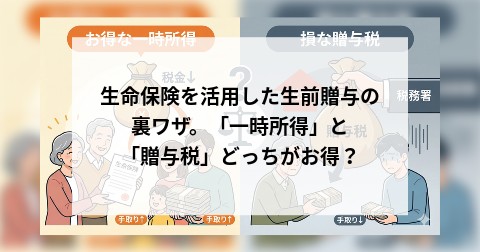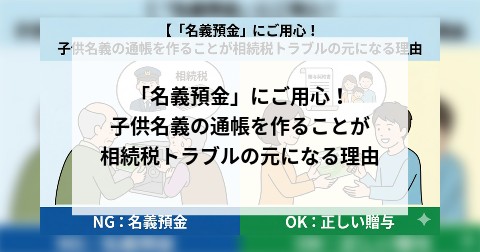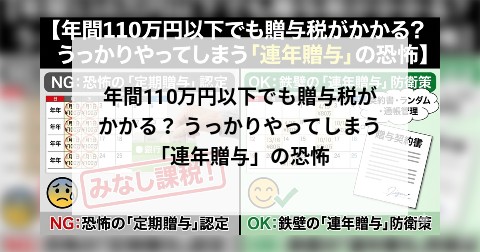相続まで見据える!家族に迷惑をかけない賢い資産の引き継ぎ方
大切な家族に、できるだけ迷惑をかけずに自分の資産を引き継ぎたい。そう考える方は多いのではないでしょうか。しかし、相続は「争族」という言葉があるように、時には家族間のトラブルを引き起こす原因にもなりかねません。
この記事では、相続をスムーズに進め、家族に安心を届けるための「賢い資産の引き継ぎ方」を、具体的な方法とともに解説します。

なぜ相続で「家族に迷惑をかける」のか?
相続がトラブルにつながる主な原因は、以下の3つに集約されます。
-
相続財産の把握不足:家族が故人の財産全体を把握していないため、遺産分割の話し合いが進まない、あるいは後から未申告の財産が見つかるといった問題が起こります。
-
遺産分割の不公平感:特定の相続人だけが多くの財産を受け取ったり、生前の贈与が考慮されなかったりすることで、不公平感が生まれ、トラブルに発展します。
-
相続手続きの煩雑さ:預貯金の解約、不動産の名義変更、相続税の申告など、相続手続きには多くの書類と手間がかかります。これらの手続きを家族だけで行うのは大きな負担となります。
これらの問題を解決するためには、生前から計画的に準備を進めることが不可欠です。
家族に迷惑をかけないためのポイント
財産目録を作成する
財産目録とは、不動産、預貯金、有価証券、負債など、相続財産の種類や内容をまとめたリストです。
財産目録を作成することで、相続財産の内容を明確にし、相続手続きをスムーズに進めることができます。
財産目録には、不動産の所在地や評価額、預貯金の口座番号や残高、有価証券の種類や銘柄、負債の金額や借入先などを記載します。
家族と話し合う
相続については、家族と事前に話し合い、それぞれの意見や希望を共有することが大切です。
相続に関する不安や疑問を解消し、家族が納得できる遺産分割協議を行うために、十分なコミュニケーションをとることが重要です。
相続に関する話し合いは、時には感情的になることもありますが、冷静に、お互いの意見を尊重し、理解し合うことが大切です。
遺言書を作成する
遺言書は、相続財産の分け方や、特定の相続人に財産を多く残したい場合など、相続に関する自身の意思を明確にするための重要なツールです。
遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。公正証書遺言は、公証人が関与するため、形式不備による無効のリスクが低く、原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
遺言書には、相続分や遺産分割方法の指定だけでなく、付言事項として、相続財産を分ける理由や、家族へのメッセージを書き添えることもできます。ただし、付言事項は長文にならないように注意が必要です。
必要書類を準備する
相続手続きには、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、遺言書、財産目録、不動産の登記簿謄本など、様々な書類が必要です。これらの書類を事前に準備しておくことで、相続手続きをスムーズに進めることができます。
必要書類は、相続の内容や状況によって異なるため、事前に専門家(弁護士、税理士、司法書士など)に確認すると良いでしょう。
生前贈与を検討する
生前に財産を贈与することで、相続税の負担を軽減したり、特定の相続人に財産を多く残すことができます。
生前贈与には、贈与税がかかるため、税金についても考慮する必要があります。
生前贈与は、相続税対策だけでなく、家族の将来の生活費や教育費を援助する目的で行うこともできます。
相続税の節税対策のためにできること
相続税を節税するには、相続税の概要や仕組みを理解しておく必要があります。まずは、相続税の基礎控除額や相続財産の種類、評価方法などについて確認していきましょう。
相続税の基礎控除額を知る
亡くなった人が所有していた財産を相続する際に、その遺産の合計額が基礎控除額を超えると相続税の課税対象となります。基礎控除額の計算式は、以下のとおりです。
●基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
夫が亡くなり、妻と子2人が相続人の場合、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」です。このケースでは、相続財産の合計額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。4,800万円を超える場合は、超える部分が課税対象となります。
相続財産を減らす
相続税を節税するには、相続財産を減らすことが有効です。生前のうちに財産を整理・処分しておけば相続財産が減るため、課税対象額を抑えられます。相続財産が基礎控除額の範囲に収まれば、相続税はかかりません。
相続財産の種類によっては、基礎控除額とは別に非課税枠が設けられています。この非課税枠を活用して、相続財産を減らすことも可能です。
相続財産の評価額を下げる
相続税の計算において、相続財産の価額の基準となるのが「相続税評価額」です。相続財産は、財産の種類によって評価方法が異なります。
たとえば、預貯金や投資信託などの金融商品は、相続発生時の時価で評価するのが原則です。一方、不動産は路線価や固定資産税評価額によって評価するため、通常は預貯金より評価額が下がります。
預貯金を他の資産に組み替えて相続税評価額が下がれば、相続税の節税が可能です。
相続税対策方法
生命保険に加入する
被相続人が亡くなって生命保険金を受け取る場合、その保険金は相続税の課税対象です。ただし、死亡保険金には基礎控除額とは別に「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
たとえば、妻と子2人が相続人の場合、死亡保険金が1,500万円(500万円×3人)までは相続税がかかりません。生命保険に加入することで、相続税の節税が期待できます。
死亡退職金の非課税枠を使う
被相続人が亡くなり、相続人が勤務先から受け取る死亡退職金は相続税の課税対象です。ただし、死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。受取金額が非課税枠の範囲内であれば、相続税はかかりません。
小規模企業の経営者や個人事業主が加入する「小規模企業共済」の共済金も、相続税法上の死亡退職金に含まれます。経営者や個人事業主は、小規模企業共済をうまく活用すれば相続税の節税が可能です。
養子縁組で基礎控除額を増やす
養子縁組とは、血縁関係のない人と法律上の親子関係をつくる公的な制度です。養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つがあります。
●普通養子縁組:実親との親子関係を存続したまま養親と親子関係を結ぶ
●特別養子縁組:実親との親子関係を解消して養親と親子関係を結ぶ
養子縁組をすれば、子ども(法定相続人)の数が増えます。その結果、基礎控除額や死亡保険金の非課税枠も増えるので、相続税の節税につながります。
ただし、法定相続人に含める養子の数には制限があるので要注意です。被相続人に実子がいる場合は「1人まで」、実子がいない場合は「2人まで」となります。
まとめ
賢い資産の引き継ぎ方には、事前の準備と計画が不可欠です。遺言書の作成、生前贈与、遺産分割協議の円滑化、そして専門家への相談などを活用し、スムーズな相続を実現しましょう。