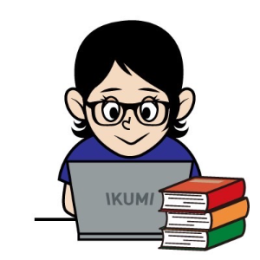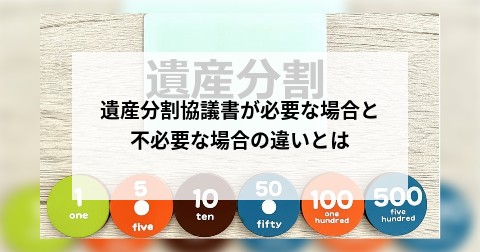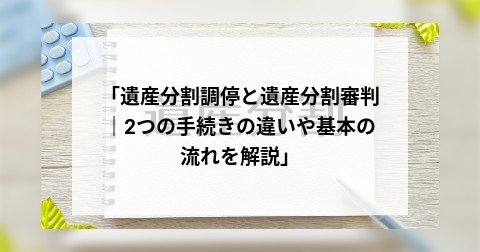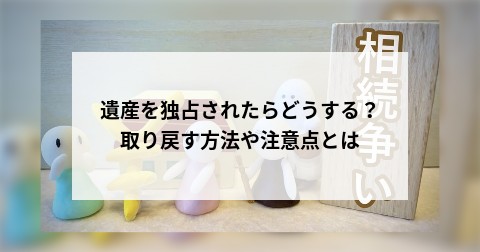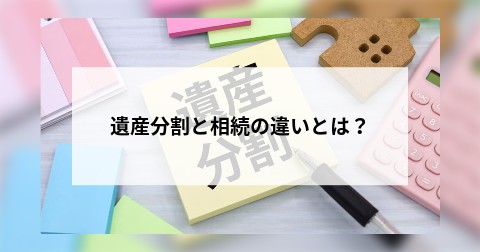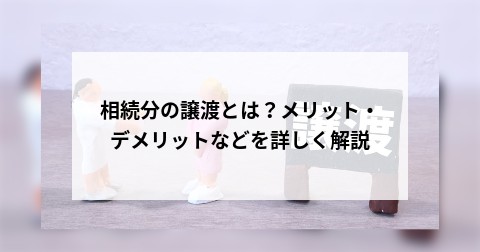遺産分割や相続の悩みを弁護士に相談すると費用はいくら?相場を解説
相続が開始されると、遺産分割や相続放棄などさまざまな悩みに直面することがあります。その際には、相続の相談先に「弁護士」を検討できますが、気になるのはやはり「費用」でしょう。
そこで、本記事では遺産分割などの相続の悩みを弁護士に相談する際の費用について、相場や費用がかかる理由を中心に詳しく解説します。費用に悩んだ場合の対処法も紹介しますので、ぜひご一読ください。

遺産分割の悩みを弁護士に相談する場合の費用相場とは
相続開始後は、被相続人が遺した「相続財産」を相続人で分けるために遺産分割協議を行います。(遺言書がある場合を除く)
遺産分割に臨むにあたっては、相続人調査や相続財産の特定だけではなく、親族間の話し合いをまとめる必要があります。感情的な対立が起きると、当事者だけで解決することが難しいケースも少なくありません。
トラブル時には弁護士に相談・依頼することで、法的な観点から冷静に事態を整理し、適切な解決へと導いてもらえる可能性があります。この章では遺産分割を弁護士に相談・依頼した際に発生する費用と、その理由を解説します。
法律相談料
法律相談料とは、弁護士に悩みや状況を説明し、アドバイスを受ける際に発生する費用です。正式に事件を依頼するかどうかにかかわらず、相談のみで発生します。
・相場 時間制で30分あたり5,000円〜1万円(税別)
遺産分割については初回相談を無料としている法律事務所も多く、費用が気になる場合は無料相談を活用することもおすすめです。
着手金
着手金とは、弁護士に事件の解決を正式に依頼した際に、交渉や書面の作成などに着手してもらうための費用です。結果の成功・不成功にかかわらず、原則として返還されない費用です。着手後以降、法律相談料は発生しません。
相場は事件の難易度や相続財産の金額(経済的利益)によっても大きく異なりますが、目安としては以下です。
相場
相続人調査や交渉全般 20万円〜50万円程度
調停・審判 30万円〜70万円程度
訴訟 30万円~
実費
実費とは、遺産分割の手続きを弁護士が進める上で発生する印紙代や切手代(郵券)などの費用です。事件が長期化したり、鑑定が発生すると高額になることがあります。
■主な実費の一例
印紙代 裁判所に申立て費用
郵便切手代 裁判所や相手方との書類のやり取りにかかる費用
謄本・証明書などの取得費用 戸籍謄本、不動産登記事項証明書などの取得費用
鑑定費用 不動産の評価などで鑑定が必要な場合の費用
・相場は数万~数十万程度
実費は着手金と同時に預り金として弁護士へ預けることが多く、事件終了後に精算されます。
報酬金
報酬金とは、遺産分割が解決した際に、弁護士へ報酬として支払う費用です。相場は「経済的利益」に応じて変動しているため、以下が相場となります。経済的利益とは問題解決時に依頼者側が得られた利益を意味します。
| 経済的利益の金額 | 報酬金の計算方法 |
| 300万以下 | 16% |
| 300万以上~3,000万以下 | 10%+18万円 |
| 3,000万以上~3億円以下 | 6%+138万円 |
| 3億円以上 | 4%+738万円 |
上記は以前日本弁護士連合会が定められていた「旧日本弁護士連合会弁護士報酬基準」を活用しているもので、全国の多くの弁護士が現在も目安として利用しています。詳しくは以下のPDFをご確認ください。経済的利益は普段耳慣れない用語であり、契約時に報酬トラブルにならないように目安を確認することが大切です。
参考 旧日本弁護士連合会 報酬基準
日当
日当とは、弁護士が遠方の裁判所や関係機関に出向く際に発生する出張費用です。
相場: 1日あたり5万円〜10万円程度
近くの裁判所や出張が不要な事案では日当は発生しません。交通費は実費の中に含めて請求する事務所もあります。(新幹線や特急の費用など)契約時に確認しましょう。
遺産分割以外で依頼する場合の弁護士費用相場とは
遺産分割だけではなく、相続放棄を検討したり、遺留分について争ったりするケースなどもあります。また、特定の相続人による遺産の使い込みが疑われたりするケースも少なくありません。
そこで、この章では遺産分割以外の相続関連トラブルを弁護士に依頼した場合の費用相場について解説します。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の借金などマイナスの財産が大きい場合に、相続の権利を一切放棄する手続きです。債権者とのやり取りが発生することも多く、弁護士に依頼することもあります。
・相場 5万円〜15万円程度
実費は別途数千円〜1万円程度(申述書添付書類の取得費用、郵券代など)で、報酬金は通常は発生しません。相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内という期限があるため、被相続人の債務を知ったらなるべく早期に弁護士へ相談しましょう。
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって、兄弟姉妹を除く法定相続人が最低限受け取れるはずの遺留分が侵害された場合に、その侵害額に相当する金銭を請求する手続きです。
内容証明郵便を使った交渉から始まることが一般的ですが、調停や訴訟に至るケースも多く費用は変動します。
・相場 内容証明郵便の依頼 3万円~5万円
調停や訴訟の場合は経済的利益を目安に着手金や報酬金を決めることが一般的です。遺留分の侵害額請求は時効(※)があるため、早期に弁護士へ相談するようにしましょう。
(※)遺留分が侵害されていることを知った時から1年、または相続開始から10年
使い込みが疑われる場合の訴訟
特定の相続人による被相続人の財産の使い込みが疑われる場合、その財産を取り戻すために訴訟を提起することがあります。主な方法として「不当利得返還請求」や「損害賠償請求」が考えられます。
これらの訴訟は、証拠の収集や裁判所への書面提出・出廷など専門的な知識が必要となるため弁護士へ依頼することが多いでしょう。
不当利得返還請求
不当利得返還請求は、理由なく不当に利益を得た人へ返還するように求める訴訟です。着手金は20万円~30万円、別途報酬については経済的利益を基本に算出することが一般的です。
不法行為に基づく損害賠償請求
損害賠償請求は、不法行為(使い込みなどの不正行為)によって生じた損害の賠償を求める訴訟です。着手金相場は20万円~40万円程度で報酬金は経済的利益を基本に算出します。なお、損害賠償請求の場合は相手方へ弁護士費用を請求できるため、負担が少なくなる可能性があります。
弁護士費用に困ったらどうする?
遺産分割やその他の相続問題で弁護士への依頼を考えていても、費用がネックとなる人も多いでしょう。そこで、費用に悩まれている人向けに、弁護士費用の対処法を2つご紹介します。
分割払ができる法律事務所へ依頼する
法律事務所によっては弁護士費用の分割払に対応しています。相談の際に確認し、契約を結ぶ前に、分割払の可否や条件(回数、支払い期間など)を確認しましょう。
法テラスを活用する
法テラス(日本司法支援センター)とは、国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所です。経済的に余裕がない方が法的支援を受けられるように、無料の法律相談や弁護士費用の立替制度(民事法律扶助制度)を用意しています。
ただし、利用については収入要件を確認しており、家族構成に応じた一定の収入基準と資産基準を下回っている必要があります。要件をクリアしている場合、弁護士費用を法テラスが一旦立て替えてくれるため、その後に月々5,000円〜1万円程度の分割で法テラスに返済します。
利用したい場合は最寄りの法テラスに依頼し、収入要件などを確認してもらうことがおすすめです。
まとめ
本記事では遺産分割をはじめとするトラブル時に、弁護士へ依頼する場合の費用相場や、費用に困った場合の対処法を解説しました。
相続はなるべく円満に終えることが望ましいですが、時に大きなトラブルに発展することも少なくありません。そんな時は、弁護士に依頼し迅速な解決を求めることも大切です。
費用相場はあくまでも目安ですが、高額の場合は分割払などの方法も検討できますので、まずは法律相談を通して弁護士を探してみましょう。