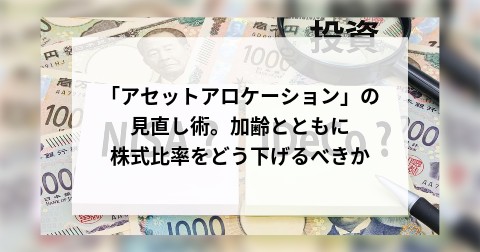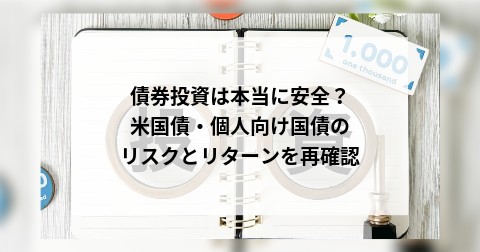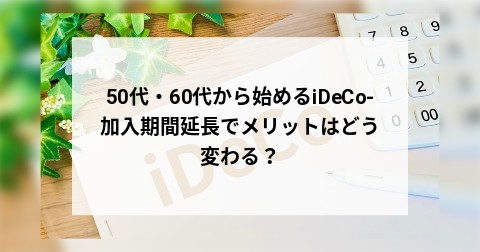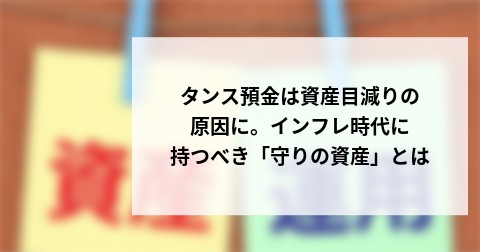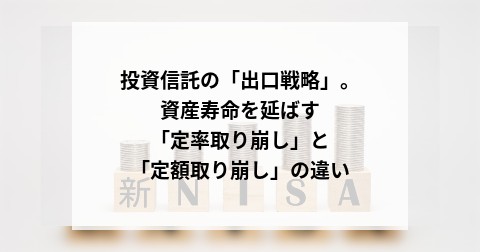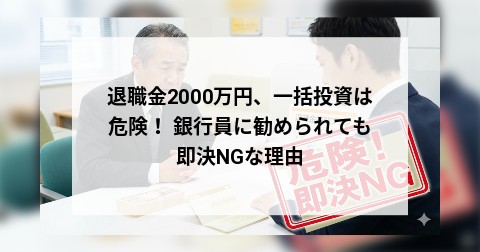「人生100年時代」のお金の不安を解消!老後資金を長持ちさせる運用戦略
人生100年時代と言われていますが、より充実して楽しむためには、生命寿命だけでなく、健康寿命と資産寿命をともに延ばすことが大切であるということでしょう。
今回は資産寿命に注目し、資産寿命を延ばす方法をご紹介していきます。
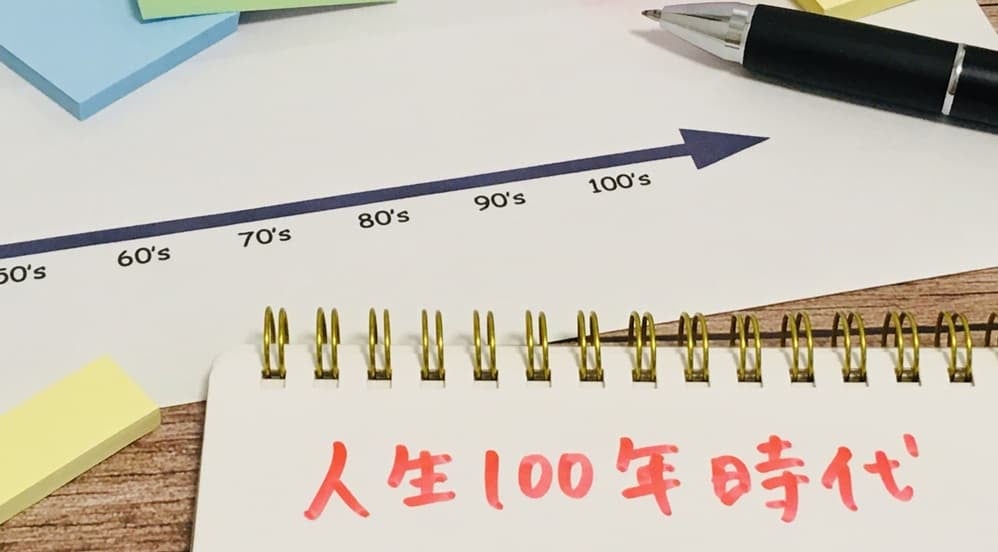
資産寿命とは?
資産寿命とは、老後の生活を送るにあたって現役時代に貯めた個人の資産や貯蓄などの資産がどの程度の期間にわたって持続するかという考え方です。
定年退職後の主な収入は年金になりますが、年金の額を毎月の支出額が上回る場合、赤字分は現役時代の貯蓄を取り崩さなければなりません。できるだけ早いうちから資産運用や正しい家計管理を行うことで資産を形成し、ご自身の寿命よりも資産寿命が先に来てしまう事態を回避することが大切です。
資産寿命の計算方法
資産寿命を計算する際は、
資産総額 ÷ 毎月(または毎年)の収支の不足額
などといった方法を用いるのが一般的です。
退職後の収入(公的年金や退職金の取り崩しなど)と支出額の差額を算出し、その不足分を資産から補填し続けた場合、あとどのくらいの期間で資産が尽きるのかを把握します。
たとえば、あなたが60歳で、現在の貯金が5000万円、毎月の生活費が25万円だとします。この場合、貯金を毎月25万円ずつ使っていくと、5000万円は200ヶ月、つまり約16年7ヶ月で使い果たされます。これが資産寿命です。
資産寿命を把握するためには
現在の資産状況を確認する
現在の資産状況を正確に把握することは、資産寿命を延ばす第一歩です。
銀行の預貯金、退職金、家や土地など、全部合わせてどれくらいあるのかをリストにしてみましょう。このリストを作ることで、これからの人生でどれくらいのお金が使えるのかがわかります。
難しいと感じる場合は、専門家に相談したり、資産管理ツールを使ってみると良いでしょう。
資産状況を一覧化し、日々の変化を計測できるようにすることで、正しく現状を把握することができます。
月々の出費を整理し、支出を正確に把握する
次に、毎月どれくらいお金を使っているのかをチェックしましょう。毎月の支出を把握することは、資産寿命を理解し、適切に管理するために必要不可欠です。
家賃や光熱費などの毎月決まった出費、食費や趣味に使うお金、これからの大きな出費(例:孫へのプレゼント、旅行など)をしっかり整理して数字で確認してみましょう。
支出のパターンを把握し整理することで、無駄な支出が削減できれば、資産寿命を延ばすことも可能です。これまで支出の分析をしてこなかった初心者の方でも、まずは家計簿アプリや紙に書いて整理してみることがおすすめです。
資産寿命の延ばし方
退職後は現役時代の貯蓄を取り崩しながら生活することになります。しかし、貯蓄を取り崩すだけでは減る一方となり、資産が予想より早く枯渇すると、生活費や医療費の賄えない状況に陥るなど、老後の生活資金に不安が生じかねません。
また、趣味やレジャー、旅行などの楽しみが制限され、老後の生活水準が低下する可能性があるでしょう。
こうした事態を回避するために、適切なライフプランニングと資産管理で資産寿命を伸ばすための行動を3つご紹介します。
家計を見直して支出を減らす
定年退職後を見据えて、今のうちに家計を見直すことが大切です。
無理なく支出を減らすには「固定費の見直し」が効果的
家計の支出は、「変動費」と「固定費」の2つに分けられます。
変動費は、金額が変わる支出のことです。家計では食費や医療費、交際費などが該当します。支出をコントロールしにくく、節約には我慢を伴います。
固定費は、毎月など定期的に決まった金額が発生する支出のことです。家計では保険料や住宅費、車両費、通信費などが該当します。一度見直せば節約効果が長く続くので、無理なく支出を減らすには固定費の見直しが効果的です。
例えば、保険は商品によって保険料が異なります。今より保険料が安い他の商品に入り直したり、不要な保険を解約したりすれば、必要な保障を確保しながら保険料の負担を減らせます。食費や交際費のように、我慢して節約する必要もありません。
複数の金融商品を組み合わせた資産運用で資産寿命を延ばす
資産を増加させ、資産寿命を延ばしたいと考える場合、何らかの金融商品を購入して資産運用するのが一般的です。金融商品による資産運用の際には、金融商品の価格が下落し資産が目減りしてしまうリスクと、価格が上昇したときに得られる利益のリターンのバランスが重要です。
ハイリスク・ハイリターンの金融商品は、価格変動が大きく、大きなリターンが期待できる一方で、値崩れによりマイナスになってしまう可能性も大いにあります。一方、ローリスク・ローリターンの金融商品は、利回りが小さく資産の増加幅は大きくありませんが、値崩れにより資産が目減りする可能性も低いという特徴があります。
単体でローリスク・ハイリターンという都合の良い金融商品は存在せず、リターンの大きさとリスクの大きさは比例します。
ただし、複数種類の金融商品を上手く組み合わせることで、資産の全体としてリターンを大きく、リスクを小さくすることが出来ます。
働く期間を延ばす
定年延長制度や再雇用制度を活用し、なるべく長く働く方が増えています。リタイアメントを少しでも遅らせることで、老後の生活費を確保するための収入を増やすことが可能です。
働く期間が長いほど社会保険制度からの恩恵を受けやすいです。例えば、年金制度などの社会保険からの受給額が増える可能性があります。
リタイア後にパートタイムの仕事を続けることなどでも、収入を補うことが可能です。退職後に少しでも働くことで生活にゆとりを持つことができるでしょう。
まとめ
期間が長いほど効果を得やすいとされる確定拠出年金などの資産形成には、現役時代から取り組んでおきましょう。
高齢になってからは、働く期間の延長を検討しつつ、資産形成と資産の取崩しのバランスを見極めることが大切です。
理想のセカンドライフは、過去の自分と未来の自分によって支えられるもの。それぞれのライフステージでできることを、今はじめてみませんか