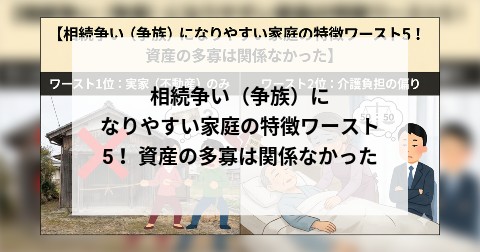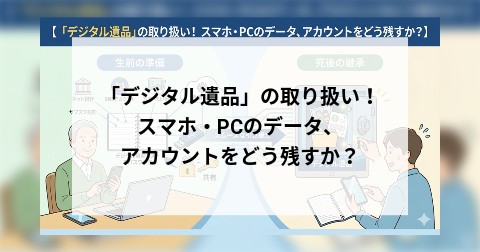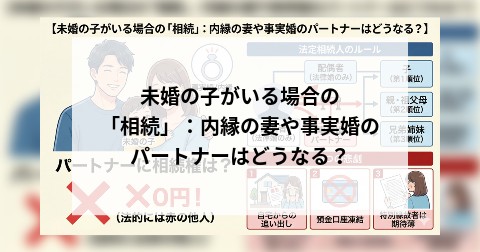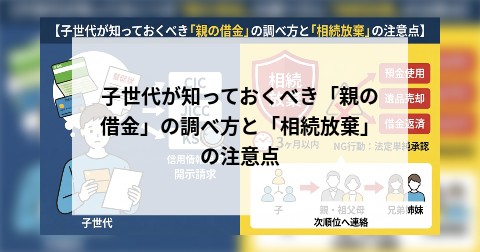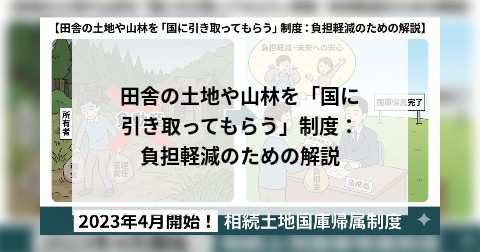実家の相続でやってはいけないことは?トラブルを避ける相続のポイント
実家の相続でやってはいけないことをご存知でしょうか。
間違った方法で実家を相続してしまうと、トラブルに発展したり無駄な費用を支払い続けたりしなければなりません。
そこで、本記事ではやってはいけない実家の相続とトラブルの回避方法について解説します。

実家の相続のときにやってはいけないこと
活用方法を決めずに実家を相続してしまうと、相続後も持て余してしまい固定資産税などの管理コストがかかり続けてしまいます。
実家の相続時にやってはいけないことは、主に下記の通りです。
兄弟姉妹などで共有名義として相続する
共有名義での相続は、一見すると管理の負担が分散されるように思えますが、大きなリスクが伴います。共有名義の不動産を売却や貸し出しする際には、他の共有者全員の同意が必要になるため、実家の活用について意見が食い違うとトラブルに発展する可能性があります。
また、修繕費用など管理費用の負担割合をめぐって争いが起きたり、売却時に共有者全員の許可が必要なため手続きが複雑になったりする問題も発生します。将来的な相続人間の関係悪化を防ぐためにも、共有名義での相続は避けることをおすすめします。
相続登記をしないまま放置する
相続登記とは、家や土地などの不動産を相続する際、亡くなった方から新しい所有者の方へと名義を変更する手続きです。
2024年4月1日以降、相続登記は法律により義務化されました。
相続したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければいけません。相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化される以前は、「名義は変えていないが実家は自分たちが管理している」というケースも多く見られました。
しかし、何代も前の名義(祖父母や曾祖父母)になっていると、登記の手続きが複雑になります。
そうしたケースでは、複数の戸籍を遡って調査したり、相続人をすべて洗い出したりする必要があるため、専門家(司法書士)に依頼することが一般的です。
相続した実家を放置する
実家を相続したときに名義変更手続きだけはすませたものの、その後、実家の土地や建物を手入れせず放置することはやめましょう。
空き家になった実家の管理状態が悪いと、特定空き家や管理不全空き家に指定されてしまう恐れがあるからです。
相続した実家が特定空き家や管理不全空き家に指定されてしまうと、実家の土地の固定資産税が最大6倍になってしまいます。
固定資産税には住宅用地の特例があり、住宅が建築されている土地の固定資産税は最大6分の1まで減額される仕組みだからです。
相続した実家を無計画に解体する
実家を解体する場合、建物の規模にもよりますが、およそ200万円前後の費用が必要です。さらに、建物を解体して更地にすると、住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税が最大で6倍に跳ね上がってしまいます。
例えば、土地の固定資産税評価額が1,000万円の場合、建物があれば年間約2.3万円の固定資産税ですが、更地になると年間約14万円に増加します。解体を検討する際は、この税負担の増加も考慮に入れる必要があります。
また、相続した実家の築年数が古い場合、建物を解体しても希望していた建物を再建築できない恐れがあります。
実家を建てたときの建築基準法と現在の建築基準法が異なる場合、実家解体後の再建築では、現在の建築基準法に従わなければならず建物の面積などの制限を受けてしまう可能性があります。
また、実家を解体した後に現在の建築基準法では再建築不可な土地であると判明すると、借り手や買い手が見つかりにくくなる可能性が高いのでご注意ください。
相続後すぐに売却する
相続税対策として「小規模宅地等の特例」という制度があります。これは、相続した土地の評価額を最大80%減額できる特例で、相続税を大幅に軽減できる可能性があります。
ただし、この特例を適用するには「相続開始時から相続税申告期限(相続発生を知った翌日から10カ月以内)まで相続した不動産を保有していること」という条件があります。相続後すぐに売却してしまうと特例が適用されず、多額の相続税を支払うことになるかもしれません。不動産の売却を考える場合は、税理士などの専門家に相談し、最適なタイミングを見極めることが重要です。
実家を相続したほうがいいのはどんなとき?
実家を相続する際にやってはいけないことを紹介してきましたが、実家を相続するのがプラスになる場合もあります。ここからは、実家を相続したほうがいいケースをご紹介します。
実家に住む予定がある
相続した実家の立地が良い場合や建物の状態が良い場合は、自分で住んでも良いでしょう。
特に、持ち家がない人が相続した実家に住めば家賃や住宅購入費用を浮かせられます。
ただし、相続した実家の状態によっては建物の大規模修繕が必要な場合もあるので、事前に建物の状態やリフォーム費用を確認しておきましょう。
実家の用途が決まっている
将来的に実家の土地や建物を有効活用する予定があれば、相続を検討する価値があります。例えば、賃貸経営や土地活用による収益化など、具体的な活用プランがある場合は、実家を相続することで資産としての価値を最大限に活かすことができます。
賃貸として他人に貸す
すでに自分も住宅を購入していて相続した実家に住む予定がない場合は、賃貸として他人に貸すのもおすすめです。
相続した実家を賃貸に出せば、定期的に家賃収入を受け取れます。
ただし、自分で住む場合と同様に他人に貸し出す場合も、実家の状態によっては大規模修繕が必要となるでしょう。
また、他人に賃貸として貸し出した場合、大家側の都合で退去してもらうことが難しくなるため、活用や売却の自由度が下がるのもデメリットといえます。
更地にして土地を他人に貸す
実家の状態が悪く賃貸として貸し出すことが難しいのであれば、建物を解体し更地を活用するのもおすすめです。
更地にした状態の方が借り手が見つかりやすくなることもあります。
ただし、実家が田舎にある場合や立地が悪い場合、更地にしたとしても需要が低く借り手が見つかりにくい可能性もあります。
本記事の1章で解説したように、更地にしてしまうと固定資産税の金額が最大6倍となるので、事前に借り手や活用方法を検討した上で実家の解体を行いましょう。
土地活用で利益を得る
実家の土地をアパートや駐車場として活用することで、より高い収益を得られる可能性があります。ただし、初期投資が必要で、収益が安定するまでに時間がかかる場合があります。
また、需要が少ない地域では期待通りの収益が得られないこともあるため、周辺環境や市場調査を十分に行ったうえで判断する必要があります。
自分が住む
相続した実家の立地が良い場合や建物の状態が良い場合は、自分で住んでも良いでしょう。
特に、持ち家がない人が相続した実家に住めば家賃や住宅購入費用を浮かせられます。
ただし、相続した実家の状態によっては建物の大規模修繕が必要な場合もあるので、事前に建物の状態やリフォーム費用を確認しておきましょう。
実家の相続トラブルを避けるポイント
生前贈与を検討する
生前贈与は、相続が発生する前に財産を子どもや家族に贈与することで相続財産を減らす方法です。古い実家の場合、評価額が基礎控除の範囲内に収まることもあり、相続税が課されないケースがあります。
ただし、生前贈与の場合は不動産取得税として実家の固定資産税評価額の1.5%が課せられる点に注意が必要です。相続税と生前贈与のメリット・デメリットを比較検討し、税理士などの専門家に相談しながら判断することをおすすめします。
遺言書を作成する
相続後の親族間の争いを避けるために、被相続人は生前に遺言書を作成しておくことをおすすめします。特に公正証書遺言は、公証人立ち会いのもと作成される正式な書類のため、相続時の争いを防ぐ効果があります。
遺言書があれば、遺産分割協議が不要になり、実家の相続人がスムーズに決定できます。また、配偶者の居住権を保護するなど、被相続人の意思を確実に反映させることができます。
相続放棄の検討
実家に住宅ローンなどの借入金が残っている場合や、維持費用が資産価値を上回る場合は、相続を放棄することも検討に値します。相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことになります。
ただし、相続放棄は相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。また、一度相続放棄すると取り消すことができないため、慎重に判断することが重要です。必要に応じて、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
実家を相続する際には、事前に活用方法や売却方法を検討しておくことが大切です。
相続した実家は使用していなくても固定資産税がかかり続けますし、管理の手間もかかるからです。
また、遺産分割方法に揉めてしまい共有名義で相続してしまうと、実家の活用や売却も難しくなるのでご注意ください。
実家の活用や売却方法には複数あるので、相続した実家の立地や状態、広さなどに応じてベストな活用、売却方法を見つけていくのが良いでしょう。