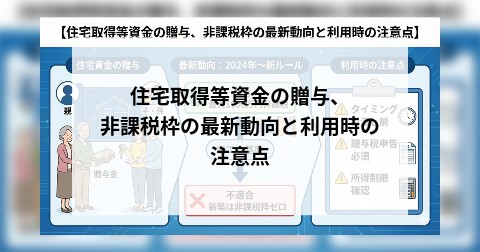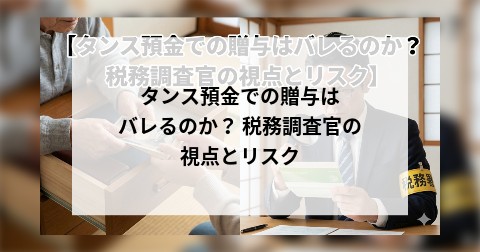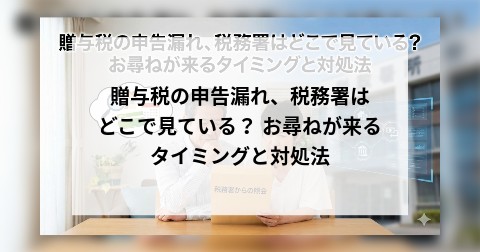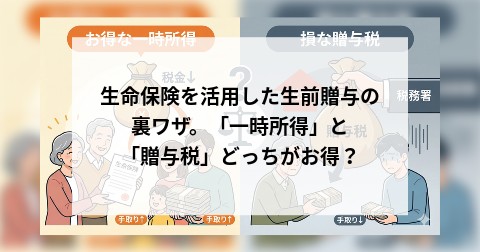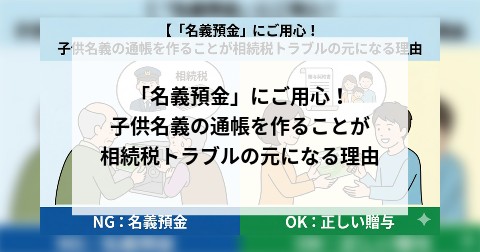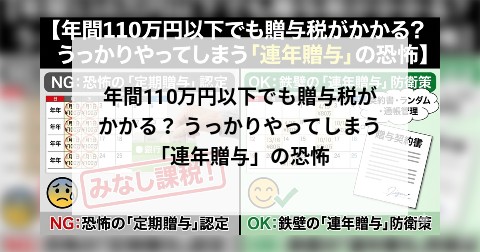不動産を相続したら相続税はいくらかかる?かかる場合とかからない場合はどんなケース?
身近な方が亡くなられ、その方の不動産を相続した場合、税金がいくらかかるのかは気になるポイントだと思われます。
そもそも相続税がかかるのかも含め、相続税の算定方法や不動産の評価方法、税負担を減らす方法についても解説します。
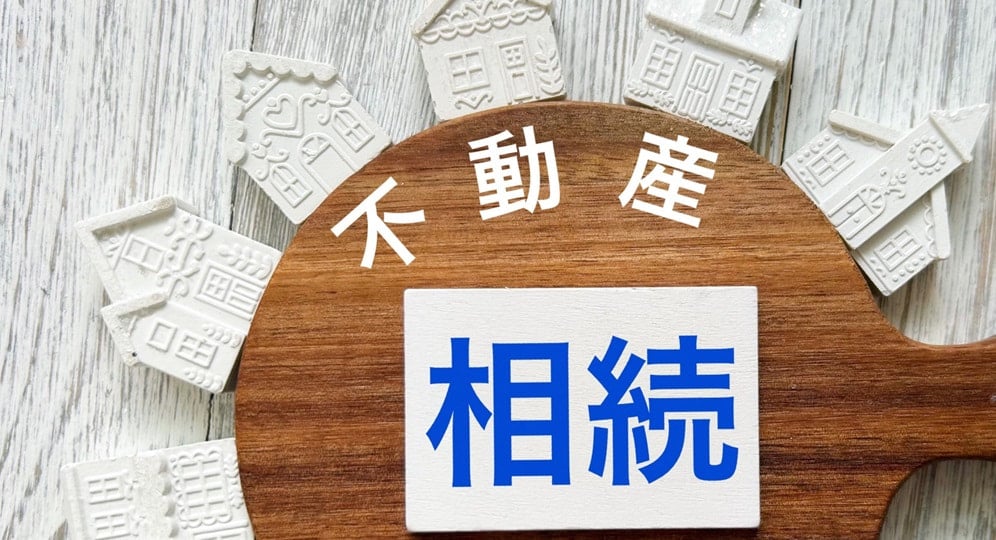
相続税がかからないケース
遺産を相続した場合、その遺産の相続税法上の評価額に対して税金が課せられます。
ただし、相続税には基礎控除があり、正味の遺産総額から基礎控除を差し引いた額が0以下であれば、相続税はかかりません。
基礎控除の額は下記の計算式で求めます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
また、基礎控除とは別に、配偶者は相続した財産が16,000万円と配偶者の法定相続分のどちらか多い金額までであれば相続税がかからない配偶者の税額軽減制度があります。
相続税の計算方法
相続税の計算はいくつかのステップに分かれて行います。
相続税の計算方法や、具体的な計算例を解説します。
不動産単体では相続税を算定できない
相続税の計算では、いったんすべての相続財産に対する相続税の総額を算出し、算出した相続税の総額を各人が実際に相続する財産の金額に応じて配分するといったプロセスになります。
そのため、不動産単体では相続税を算定できません。
また、相続税の総額を出してから、相続割合ごとに各人の税負担額を割り振るため、相続人の人数や遺産の相続割合によって税負担額は変わることになります。
正確に相続税額を知りたい場合は、債務も含めたすべての遺産を洗い出し、相続人がどの遺産を相続するかを確定させる必要があります。
相続税の計算方法
相続税の計算方法をステップごとに解説します。
ステップ①:法定相続人の確定
相続税の計算にあたり、法定相続人が誰で、何人いるかを把握します。
法定相続人は、亡くなった方から見た関係により順位が決まっています。
配偶者は必ず法定相続人
第1順位:子(または代襲相続人となった孫、ひ孫など)
第2順位:直系尊属(父母や祖父母など)
第3順位:兄弟姉妹(または代襲相続人となった甥姪)
配偶者は必ず相続人になる一方、第1順位の子がいるのに第2順位の父母が法定相続人になる、ということはありません。
子がいない場合は父母が法定相続人、父母もいない場合は兄弟姉妹が法定相続人というように、より順位の高い方と配偶者が法定相続人になります。
代襲相続とは、相続が発生した時点で相続権を持つ方が死亡している場合に、その人に子供がいればその子供が代わりに相続する制度です。
ステップ②:遺産総額を把握
相続税は、亡くなった方のすべての相続財産が対象になります。
亡くなった方に借金など債務がある場合はマイナスの相続財産としてプラスの
相続財産から差し引く形で計上します。
財産の評価額は、被相続人(亡くなった方)が死亡した日のものになります。
相続の際に、現金預金は金額が明確ですが、土地や不動産、骨とう品など、金額が明確でない遺産があるケースも多いです。
そういった財産は、まずは「財産評価基本通達」に則って評価額を算出する必要があります。
ステップ③:遺産総額から基礎控除を差し引く
遺産をすべて洗い出し、各遺産の評価額を算定したらその総額から基礎控除を差し引きます。
先ほども説明した通り、基礎控除の額は下記になります。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
仮に遺産総額が14,200万円、法定相続人が2人だとすると、課税遺産総額は下記になります。
課税遺産総額=14,200万円-(3,000万円+600万円×2人)=10,000万円
ステップ④:相続税の総額を計算
課税遺産総額を算出したら、定められた法定相続分にしたがって課税遺産総額に対する相続税の総額を計算します。
ここでの法定相続分は、実際に取得する財産の割合とは関係なく、あくまで法律上の相続割合で計算し、例えば配偶者と子なら1/2ずつ、配偶者と父母なら配偶者2/3で父母1/3といったように配分します。
続いて、法定相続分で財産を取得した場合の相続税を算出しますが、そのときに乗じる
相続税率は下記になります。
例えば課税遺産総額が10,000万円、法定相続人が配偶者と子供2人の場合、法定相続分は配偶者5,000万円、子供2,500万円ずつ配分されます。
税率表に基づいて計算すると、配偶者は5,000万円なので税率20%控除額200万円に該当し、子供はそれぞれ2,500万円なので税率15%控除額50万円に該当します。相続税の総額は配偶者の800万円(5,000万円×20%-200万円)と子供2人分650万円(2,500万円×15%-50万円×2人)の合計の1,450万円になります。
ステップ⑤::相続税の総額を実際の相続割合で按分
法定相続人それぞれに相続税を算出し、それを合算した相続税の総額を、実際の相続割合で按分します。
例えば、ステップ④と同じく配偶者と子供2人がおり、相続税の総額は1,450万円とします。
実際の相続では、長男が遺産の50%を相続し、配偶者が30%、次男が20%の割合で相続すると、長男は相続税1,450万円の50%で725万円、配偶者は30%で435万円、次男は290万円の税金が振り分けられます。
h4 ステップ⑥:各人に税額控除などを適用して納税額を確定
相続人ごとの相続税が決まったら、その後に税額控除を適用して納税額を確定させます。
配偶者に振り分けられた相続税については、この段階で配偶者の税額軽減制度が適用されることになります。
相続税の申告及び納付の期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内です。
相続税評価額の計算
不動産の相続税評価額を計算する方法について解説します。
計算方法は土地と建物で変わりますので、それぞれに分けて説明していきます。
土地の場合
土地の評価単位は土地の「地目」によって分けるため、土地を評価する際はまず地目を確認する必要があります。
地目は固定資産税の課税明細書や登記簿に記載されています。
地目を確認後、土地の評価に移りますが、土地の評価方法には「倍率方式」と「路線価方式」の2種類があります。
倍率方式
市街化が進んでいない農村部や山林などの地域では、路線価が設定されていない場合があります。
そうした地域の土地評価をする際は、倍率方式を使います。
倍率方式の場合、固定資産税評価額に、国税庁が定める評価倍率を乗じることで相続税評価額を求めます。
土地の相続税評価額=固定資産税評価額×評価倍率
固定資産税評価額は市区町村から「固定資産税評価証明書」を取り寄せるか、「固定資産税の課税明細書」に記載されています。
評価倍率は地域ごとに設定されており、国税庁のホームページの「評価倍率表」で確認できます。
路線価方式
路線価とは、毎年7月に国税庁が公開しているもので、不特定多数が通行する道路ごとに定められており、この路線価が定められている道路に面している場合は、路線価方式によって土地の評価を行います。
国税庁のホームページの「評価倍率表」に「路線」と記載されている場合は、路線価方式の評価を考えます。
路線価は国税庁のホームページから閲覧できる「路線価図」により確認でき、”150D”などと記載されています。
この場合、150Dの道路に面している土地は1㎡あたり150,000円を基礎に評価する、ということです。また、150DのDは路線価図の上部に記載されている借地権割合を示し、借地権割合は貸し借りをしている土地の評価で使うことになります。
路線価がわかったら、土地の図面などを用いて土地の縮尺や詳細、各種補正率を算定し、各種補正率と地積(土地の大きさ)を乗じて土地の価格を算定します。
土地の相続税評価額=路線価×各種補正率×地積
建物の場合
建物の相続税評価額は、その建物を被相続人が利用していた場合、現状の評価方法では固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。
ただし、タワーマンションなどの建物の評価については近年評価方法の改正があり注意が必要です。
貸家の場合は下記の計算式のより算定します。
相続税評価額=固定資産税評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)
このように、貸家であれば建物の相続税評価額を下げられます。
ただし、被相続人の死亡時に貸家が空室の場合はこの評価減はできないことがあるため注意してください。
借家権割合はほとんどの地域で30%ですが、評価をするときは変更の有無を確認するためにも国税庁ホームページでその年分の都道府県ごとの借家権割合を調べる必要があります。
賃貸割合は、建物の床面積に対して、貸している部分の床面積の割合になります。
例えば、固定資産税評価額10,000万円、借地権割合30%、床面積300㎡のうち120㎡を貸していたとすると、計算式は下記になります。
10,000万円×(1-0.3×120㎡÷300㎡)=8,800万円
不動産の相続税負担を減らす方法
建物の評価をする際に説明した通り、不動産を貸しだすことで、不動産の相続税評価額が下がるため税負担を減らせます。その他、税負担を減らす方法について解説します。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たした宅地等について、評価額を最大80%下げられる制度です。
土地は通常、評価額が多額になるため、それを最大80%下げられると相続税を大きく減らせます。
ただし、効果の大きい特例の分、そのメリットを受けるための要件が厳格に定められています。
例えば、被相続人が自宅として使っていた土地の場合、その宅地を相続または遺贈により取得した親族は、一定の要件を満たせば、その宅地のうち330㎡部分までの評価額を80%下げられます。
評価額5,000万円、面積500㎡の土地の場合、下記の計算により評価減部分を算定します。
(5,000万円×330㎡÷500㎡)×0.8=2,640万円
この場合の一定の要件とは、下記のいずれかです。
・配偶者
・同居親族
・別居親族のうち要件を満たす方
配偶者及び、被相続人の死亡時に一緒に住んでいた親族は特例を適用できます。
また、別居していた親族でも、下記の要件をすべて満たせば小規模宅地等の特例を適用できます。
・被相続人に配偶者や同居相続人がいないこと
・宅地等を相続した親族が相続開始前3年以内に、その親族やその親族の配偶者・3親等内の親族・同族会社等が所有する家屋(相続開始直前に被相続人が住んでいた家屋を除く)に住んだことがないこと
・相続時にその親族が住んでいる家屋を過去に所有していないこと
・申告期限まで引き続きその宅地等を所有していること
配偶者の税額軽減制度
配偶者は、16,000万円か配偶者の法定相続分までの財産に対する相続税負担を軽減できます。
したがって、財産の中でも評価額が大きくなりがちな不動産は、この制度を使える配偶者が相続する場合の方が、制度を使えない子供が相続する場合に比べて家族全体の相続税負担が減ることになります。
ただし、その配偶者が亡くなった後に、子供が二次相続する時には配偶者の税額軽減のような制度はないことから注意が必要です。
二次相続とは、例えば一次相続で父から母が相続した財産に、もともと母が持っていた固有財産を加えて、子供が母から相続する場合などをいいます。
そのため、一次・二次相続まで含めたトータルの相続税を考えると、一次相続で配偶者の税額軽減制度を使ったことでかえって税額が多くなってしまう場合もあるため、事前にシミュレーションをして一番税額が少なくなる方法を見つけるのがよいでしょう。
まとめ
不動産を相続した場合、他の相続財産も含めて、3,000万円と、600万円に法定相続人の数を乗じた額の合計よりも財産合計額が小さければ、相続税がかかりません。
なお、不動産単体では相続税額を確定できないため、亡くなった方が多額の財産を所有していた場合、財産の総額の算定と、誰が何を相続するのかを早めに決めましょう。
不動産、特に土地の相続税評価額を算定するのは専門的な能力が必要であり、算定を間違えると多額の追徴課税が発生するリスクがあるため、相続税の計算及び申告は税理士に依頼するのをおすすめします。