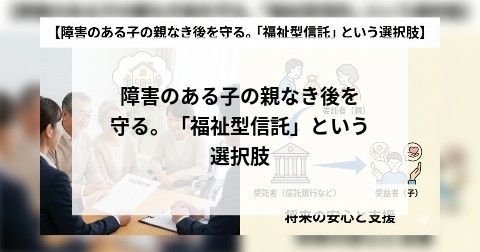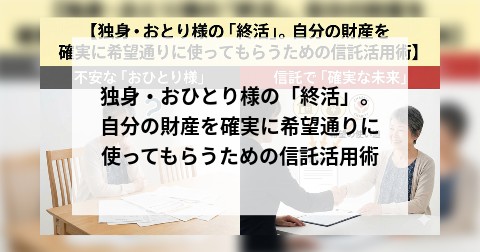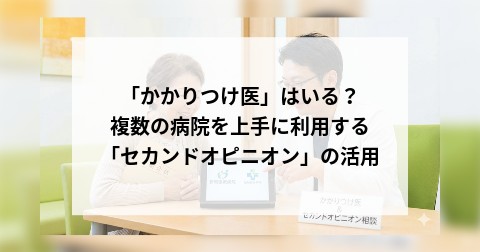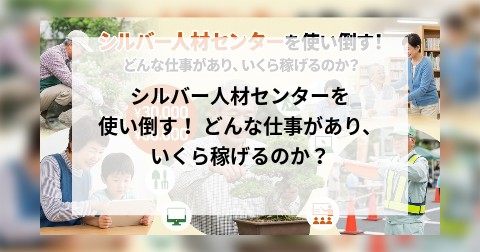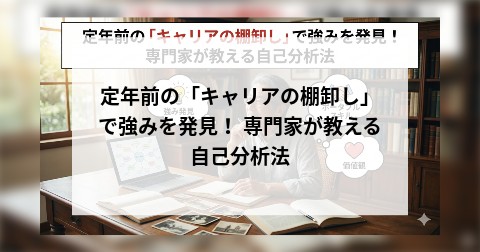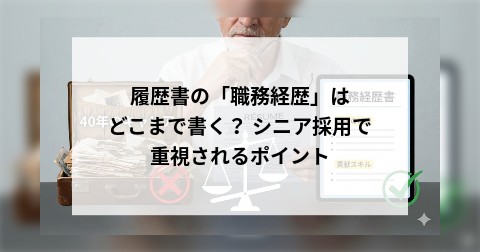【知らないと損】高額医療費から介護費用まで、シニア世代が活用すべき給付金や補助金
シニア世代には、多くの給付金や補助金が設けられていることをご存じですか?
日本には、一定の条件を満たせば高齢者が受け取れる給付金や助成金制度が数多く存在します。しかし、これらの多くは「申請主義」に基づいて運用されており、自動的に支給されるわけではありません。つまり、自分から申し出ない限り、もらえるお金がそのまま“受け取り損ね”になってしまうのです。
今回は、シニア層を対象とした生活に密着する給付金や補助金についてまとめていきます。

介護や生活全般に関する給付金や制度
年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金とは、公的年金などの収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。財源は消費税率引き上げ分が活用されており、消費税率が8%から10%に引上げとなった、2019年10月1日から施行されています。
給付額は「年金保険料を納付した期間」と「年金保険料を納めることが免除されていた期間」によって変動することを覚えておきましょう。
|
年金生活者支援給付金の対象者
|
補聴器購入を補助する制度
難聴の程度によって、国が性能を認めた補聴器の購入を補助する自治体主導の制度です。自治体によっては、65歳以上の高齢者が補聴器を購入する際に、費用の一部を負担してくれたり、現物支給したりすることもあります。
例えば、東京23区では中央区や豊島区、墨田区などで実施されています。要件なども各自治体によって異なりますので、気になる方はお住まいの自治体に確認してみましょう。
高額介護サービス費
公的介護保険を利用していて、自己負担1割の合計の額が同じ月に一定の上限を超えたときに、申請をすると払い戻される制度です。こちらは個人の所得や、世帯の所得に対して上限が設けられています。
また、高額介護サービス費の対象となるのは、介護保険適用の居宅介護サービスのみです。施設の居住費や食費、福祉用具のレンタルや住宅リフォーム費用などは含まれません。
特定入所者介護サービス費
特定入所者介護サービス費とは、介護施設の食費や居住費が一定額になるものです。規定はありますが、居住費や食費が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が返金されます。
この制度を使えば、負担を限りなく減らしながら介護を受けることができるでしょう。対象の施設は、介護老人福祉施設や介護医療院、短期入所生活介護など多岐に渡ることが特徴です。
ただし、サービスを利用するにあたっては、負担限度類認定を受けなくてはなりません。認知を受けるためには、市町村への申請手続きをする必要があります。
高額介護合算療養費制度
高額介護合算療養費制度とは、1年間の医療費と介護保険の自己負担額を合算した金額が以下の基準額を超えた場合に、超えた金額が返金される制度のことです。
なお、住民税非課税世帯かつ年金収入が80万円以下の世帯で、介護サービス利用者が複数いる場合の自己負担限度額は31万円になります。
介護が必要な状態の人はなにかしらの持病を抱えているケースがほとんどです。医療費と介護費用を合算できる高額介護合算療養費制度があれば、費用面の負担が軽減されるでしょう。
住宅リフォームに関する給付金や制度
高齢になると、自宅を住みやすいようにリフォームする人も多いでしょう。ここでは、住宅をバリアフリー仕様にリフォームする際に利用できる制度をご紹介します。
高齢者住宅改修費用助成制度
高齢者住宅改修費用助成制度は、住宅をバリアフリー仕様にリフォームする際に工事費用の原則9割が支給される補助金です。助成対象となる住宅改修は決められており、手すりの設置やトイレの取り替え、転落防止柵の設置といった高齢者向け住宅に改修する項目が並びます。
雇用に関する給付金や制度
高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付金とは、定年後(60歳以上65歳未満)に賃金が減額した人を対象とした給付金です。手続きは本人ではなく企業側が行う必要があります。
|
高年齢雇用継続基本給付金の対象者 ・定年後も今までと同じ会社で働いている |
高年齢再就職給付金
高年齢再就職給付金とは、雇用保険の基本手当の受給後、60歳以降に再就職した際に受け取れる給付金です。ただし、受給には以下のような要件があります。
|
高年齢再就職給付金の対象者 ・雇用保険の基本手当を受給した後、60歳以降に再就職した |
まとめ
シニア世代にとって知っておくべき給付金、そしてユニークな補助金制度についてまとめてきました。シニア世代を迎える前に給付金や補助金を知っておき、いざシニア世代になったときに活用することで、賢く生活を営むようにしましょう。
再就職手当
失業手当を受けていた人が再就職した場合に受け取れるお金です。該当者が60〜64歳の場合は、高年齢再就職給付金と再就職手当のどちらかを受け取るのかを選ぶ必要があり、両方は受け取れないので注意しておきましょう。
|
再就職手当の対象者 ・手続き後の7日間の待機期間後に就職した |