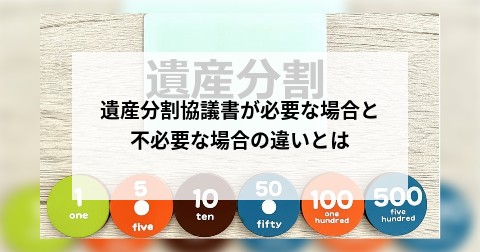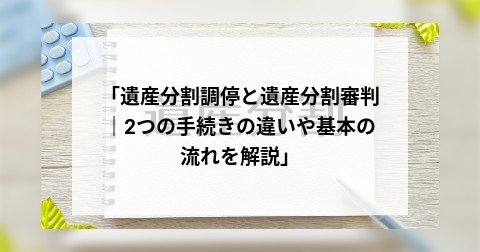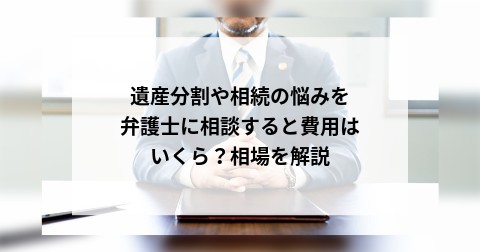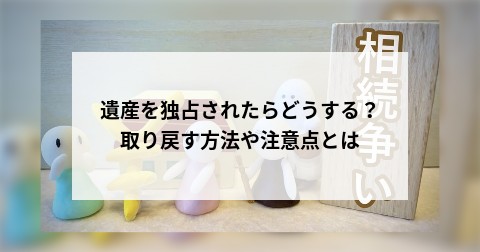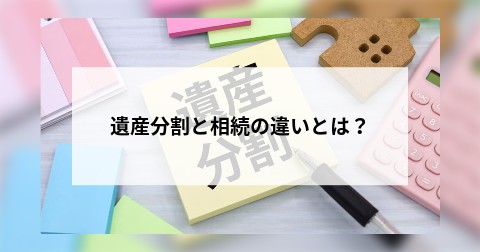相続分の譲渡とは?メリット・デメリットなどを詳しく解説
家族の死亡によって遺産相続が発生した場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、その協議内容に基づいて相続登記を行うのが一般的ですが、相続人の中に、遺産の取り分をめぐる争いは珍しくないため、相続から離脱したいと考える方もいるかもしれません。
そんな場合には遺産分割の方法がまとまる前に、ご自身の相続分を譲渡する「相続分の譲渡」という方法があります。
今回の記事では相続分の譲渡についてのメリット・デメリットを詳しく解説していきます。

相続分の譲渡とは
相続分の譲渡とは、自分の相続分を他の相続人に譲る、または第三者に譲ることです。
譲渡後には相続権がなくなるため、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。
仲の悪い家族がいるため相続に関わりたくない、または相続分を譲りたい人がいるときなど相続トラブルを避けるためには有効な手段といえます。譲渡の条件は有償でも無償でもかまいません。
相続分の譲渡と相続放棄の違い
相続分の譲渡と相続放棄はどちらも相続分の権利に関わる手続きですが、大きな違いがあります。
相続分の譲渡は相手(譲受人)を指定できますが、相続放棄は指定できないため、自分の相続分が誰に行き渡るか分からないという点です。
相続放棄すると、その人ははじめから相続人でなかったことになるので、負債も相続しません。相続分の譲渡の場合、譲渡した人にも負債の支払い義務が残ります。債権者から請求があれば譲受人は返済に応じなければなりません。
相続分の譲渡をするメリット・デメリット
相続分の譲渡を検討する場合、以下のようなメリット・デメリットがありますので双方を理解しておきましょう。
相続分の譲渡をするメリット
特定の人に譲渡できる
相続分の譲渡の最大のメリットと言えるのが、自分が渡したい人に相続分を譲渡することができるということです。
例えば父が亡くなり、母と自分、弟、妹が相続人になったとします。父亡き後の母の生活が心配ならば、自分の相続分を母に譲渡すれば母親の生活するための資金として役立ててもらうことができます。
遺産分割協議がスムーズに進みやすくなる
遺産分割協議の話し合いは相続人全員で話し合いをする必要があります。相続人の人数が多いほど意見がまとまりにくくなり、遺産を巡って対立するリスクも高まる可能性があります。
遺産の相続を希望していないのであれば、遺産分割協議をまとまりやすくするために、他の相続人に相続分を譲渡するのも1つの方法です。
対価を得ることもできる
相続分を有償で譲渡すると、遺産分割協議の終了を待たずに現金を得ることができます。
遺産であれば協議が終わらないと引き継ぐことはできませんし、遺産分割協議は長ければ成立までに1年や2年とかかる場合もあります。
相続手続きや相続トラブルを避けることができる
相続の手続きは想定以上に時間がかかることが多く、他の相続人とやりとりをして遺産分割協議が成立するまで何度も集まらなければいけません。また、遺産を巡って相続人同士が対立することも珍しくなく、相続問題で後々の関係性にも悪影響を及ぼしかねません。
また、戸籍などの書類の準備をするために各公的機関に出向く必要があるなど、時間も手間もかかります。
相続分を譲渡すると、これら一連の相続手続き・問題から離脱することができます。時間や労力を取られないだけでなく、他の相続人との良好な関係性も維持できるでしょう。
相続分の譲渡をするデメリット
債務の弁済を免れることができない
相続分をすべて譲渡したとしても、遺産に借金などの債務がある場合、債権者からの請求があればその弁済に応じなければなりません。相続分を他の相続人や第三者に譲渡したとしても、亡くなった人が残した債務の返済義務はなくなりません。
このようにマイナスの財産がある場合は、相続分の譲渡ではなく相続放棄を選択するのが一般的です
無償の場合、贈与の対象とされる場合がある
無償で相続分を譲渡した場合は贈与に該当するため、譲渡人が亡くなったときに特別受益の対象になる可能性があります。
相続分を譲った人が亡くなったとき、譲渡された相続分も考慮せずに遺産を分割しようとすると、譲ってもらえなかった相続人が不公平に感じ、特別受益を主張することがあります。
相続分を無償で譲渡する場合は、将来的に自分自身が亡くなったときに譲渡された人とされなかった人との間でトラブルが発生しないかをよく考えることが大切です。
税金がかかる場合がある
相続分を第三者に無償で譲渡した場合は税金が二重で発生する可能性があります。
共同相続人以外の第三者へ相続分を無償で譲渡すると、譲受人に「贈与税」が課税されます。一方、有償で譲渡した場合には、相続人に「譲渡所得税」が発生する可能性があります。
相続分の取り戻しが行われる可能性がある
相続分を法定相続人ではない第三者へ譲渡した場合、他の相続人はその第三者から相続分を取り戻すことが法律で認められています。ほかの共同相続人が取戻権を行使すると、相続分の譲受人となった第三者はこの請求を拒否できません。たただし、相続分の取戻権を行使できるのは「相続分が譲渡された時から1ヵ月以内」です。
相続分の譲渡がおすすめな場合
以下のような状況であれば、相続分の譲渡を検討しましょう。
- 遺産相続に関心が無く、手続きを避けたい場合
- 相続トラブルに巻き込まれたくない
- 特定の相続人に遺産を集中させたい
- 早期に相続権を現金化したい
- 遺産分割協議への参加が難しい・避けたい
上記などの状況には相続分の譲渡が有効な選択肢のひとつとなります。
相続分の譲渡と相続放棄はどちらを選んだ方がいい?
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない制度のことです。したがって、プラスの財産を引き継がないことはもちろん、借金などのマイナスの財産を引き継ぐこともありません。
続分の譲渡と相続放棄の主な違いは、以下のとおりです。
| 相続分の譲渡 | 相続放棄 | |
| 相続人としての地位 | 失わない | 失う |
| 相続権を引き継ぐ人の指定 | できる | できない |
| 相続分の一部のみの譲渡・放棄 | できる | できない |
| 債務の弁済義務 | 応じる義務がある | 応じる義務がない |
| 権利を行使できる期限 | 遺産分割協議が成立する前 | 相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内 |
| 家庭裁判所の手続き | 基本的に不要 | 必要 |
相続放棄を選ぶべき2つのケース
【相続放棄の方が向いているケース】
・プラスの遺産よりも大きな債務がある
・相続分を譲渡したい人が特にいない
相続放棄は債務の弁済に応じる必要がないので、遺産に債務が含まれ、これが取得できるプラスの遺産よりも大きな負担となる場合は譲渡よりも相続放棄を選ぶべきです。
また、相続分を譲渡したい人が特にいない場合は、相続放棄を選択することで他の相続人のトラブルを回避しやすくなりますので相続放棄をしたほうがいいでしょう。
相続分を譲渡する場合の相続の進め方
相続分を譲渡するときの大まかな流れは、以下のとおりです。
- 相続分譲渡の条件を決めて合意する
- 相続分譲渡証明書を作成する
- 相続分譲渡通知書を作成し、他の相続人に送る
相続分譲渡の条件を決めて合意する
まずは、譲渡人と譲受人が話し合いをし、相続分をどのように譲渡するのかを決めます。
「譲渡する相続分の割合」や「有償なのか無償なのか」を話し合い、譲渡人と譲受人の双方が合意したら、次のステップに進みます。
相続分譲渡証明書を作成する
相続分の譲渡内容が決まったあとは、合意した内容を書面に残すために相続分譲渡証明書を作成します。相続分譲渡証明書とは「相続分を譲渡したこと」を証明する書類のことです。
また、以下のようなケースでは相続分譲渡証明書が必ず必要になります。
・第三者である譲受人が金融機関から被相続人の預貯金を引き出す場合
・第三者である譲受人が不動産を相続して名義変更行う場合
・遺産分割調停中の場合
上記3つの場合、相続分譲渡証明書の書き方について提出先に確認すると良いでしょう。
それ以外の場合には相続分譲渡証明書の書き方に決まりはありませんが、譲渡人と譲受人の名前や住所、具体的な譲渡内容だけではなく、債務の取り扱いも必ず記載をしてください。
相続分譲渡通知書を作成し、他の相続人に送る
相続分譲渡証明書を作成したら次は「相続分譲渡通知書」を作成しましょう。「相続分譲渡通知書」とは、他の相続人に「相続分の譲渡が行われました」と伝えるための文書です。
この文書は必ず作成しなければいけないわけではありませんが、他の相続人に譲渡があったことを知らせないと混乱を招いてしまいます。
相続分の譲渡があった場合には遺産分割協議に参加する必要があり、仮に遺産分割協議に参加しなかった場合はその遺産分割協議は無効となってしまう可能性があります。
遺産分割協議に支障をきたさないようにするためにも、譲渡証明書とセットで作成することをおすすめします。
相続分譲渡通知書を送る場合は「内容証明郵便」を利用して、他の相続人全員に送付をしましょう。
まとめ
相続の事情は各家庭によって異なるため、顔を合わせるだけでもストレスになる相続人がいる一方、相続分を譲ってあげたくなる相続人がいるケースもあります。相続から離脱するだけであれば相続放棄で構いませんが、特定の人に相続分を譲りたいときは、ぜひ相続分の譲渡を検討してください。
相続分の譲渡など相続においてご不明点や心配事がある場合には、相続手続きの専門家に相談しましょう。