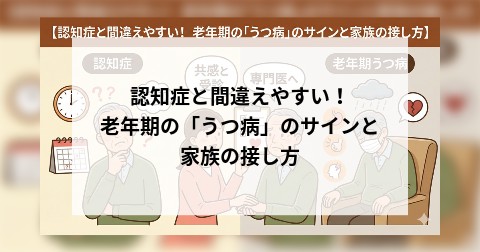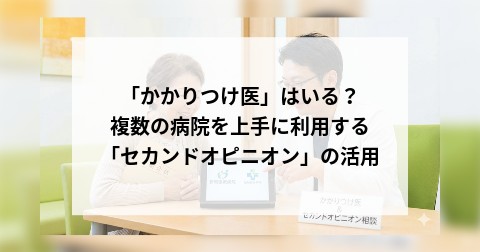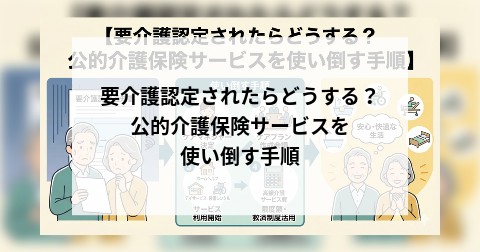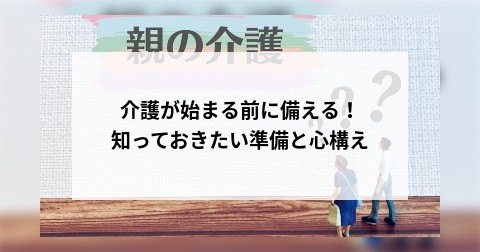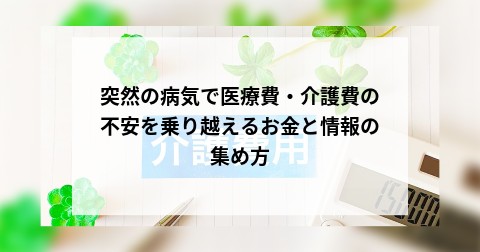離れて暮らす親の介護、どうする?遠距離介護の悩みと解決策
親の介護は、同じ家に住んでいても大変なことですが、離れて暮らしている場合はさらに難しさが増します。
今回は、遠距離介護の現状と課題、メリット・デメリットや遠距離介護を成功させるためのポイントについて詳しく解説します。
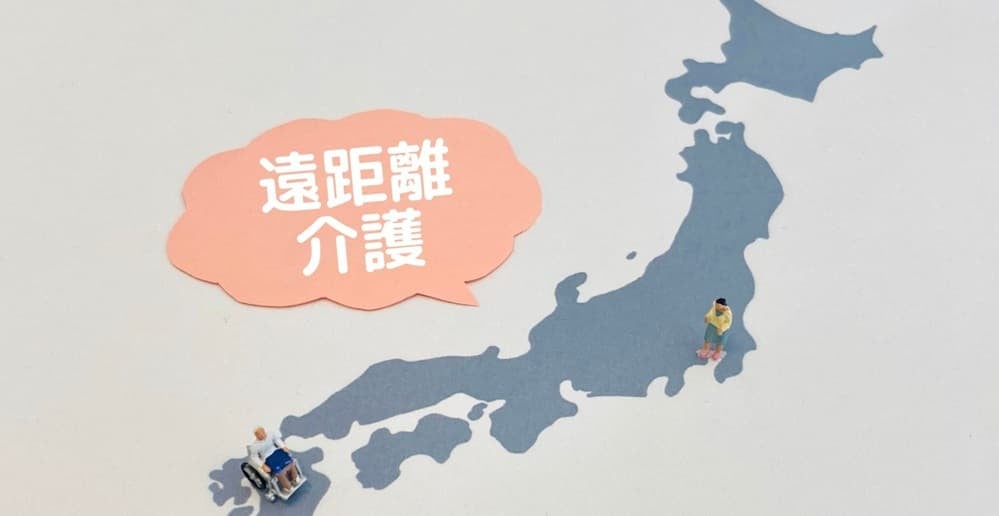
遠距離介護とは?
遠距離介護とは、主に親と離れて暮らす子が、加齢や病気などで日常的にサポートが必要になった親元に通って介護することを指します。
自宅で同居して介護をする在宅介護や、老人ホームなどに入所する施設介護のように、介護をする際に取りうる選択肢のひとつです。
交通費や移動時間などで介護者に大きな負担がかかるため、遠距離介護を行うことには多くの課題がつきまといます。
遠距離介護の現状
かつて老親の介護は子の務めと言われていた時代では、年老いた親の面倒を見るのは子どもとして当たり前の役割でした。
しかし現代では、高齢者の単独世帯・老夫婦世帯の増加、核家族化の進展により、親は地方に、子は都市部に住むといったライフスタイルが一般的になりました。
このようなことから、親が要介護状態になった場合でも、別々に暮らすスタイルを取り、仕事を続けながら親元へ通って介護する遠距離介護のニーズが高まってきたといえるでしょう。
遠距離介護の課題
遠距離介護は、介護が必要な家族や親族が離れた場所に居住している場合に行われる介護のことです。この介護方法には、多くの課題がつきものです。その1つは、介護者が介護が必要な家族や親族の状況を把握しにくいことです。また、介護が必要な家族や親族が孤独を感じやすいという問題もあります。さらに、介護者が介護に費やす時間や労力が多くなりすぎるという課題も挙げられます。
また、遠距離介護では、介護者が介護が必要な家族や親族の近くに住んでいないため、介護に必要な物品やサービスをすぐに調達することが難しいという問題もあります。さらに、遠距離介護では、介護者が介護が必要な家族や親族の近くに住んでいないため、介護にかかる費用が高額になるという課題もあります。
遠距離介護のメリット・デメリット
メリット
介護者の精神的、肉体的ストレスの軽減
まずひとつ目のメリットは、親と同居していない分、介護と切り離される時間ができ、物理的な距離を取れることで、常にそばにいて介護にかかわるよりもストレスが少なくて済むことです。
親のそばで常に介護をしている方のなかには、介護中にうつになってしまう方もいらっしゃいます。
その点、遠距離介護なら親と距離をおけるので、介護のことを客観的にみつめやすくなり、介護のことで悩んで追い詰められるというリスクを避けることができます。
転居の必要がない
自宅で老後を過ごしたい高齢者にとっては、遠距離介護で転居する必要がないことは大きなメリットです。
遠距離介護であれば、介護者が現在住んでいる地域を離れる必要がないので、介護に専念するために勤め先を退職する「介護離職」を回避できます。
親の介護に直面する人の多くは中年以降の世代で、年齢的にいったん仕事を辞めると、再就職は難しいことが多いようです。
介護をするために仕事を辞めるのは大きなリスクを伴うため、できるだけ転居は避けることをお勧めします。
介護保険サービスを利用しやすい
例えば親が認知症や脳血管疾患の後遺症によって要介護状態になった場合、特養への入居を検討する必要が出てくるかもしれません。
急きょ親の介護が必要になった場合、「現在、遠距離介護をしている」というケースに対しては、生活状況を考慮されて入居の優先順位が高めになる傾向があります。
老人ホームに入居できず待機している方が多いなか、少しでも早く入居できるというのは大きなメリットです。
デメリット
緊急時の対応が難しい
常に親の心身状態をチェックできる状況ではないので、急に容体が変化してもすぐに対応することができません。親とこまめに連絡をとることに加え、緊急時に対応できる体制づくりが必要になります。
まずはケアマネージャーと相談して見守りや安否確認を兼ねられるようなサービス利用を検討することが大事です。
また、近隣住民とコミュニケーションをとって、いざという時に協力してもらえる関係を作っておくことも重要です。
費用負担が大きくなる可能性大
遠距離介護をする場合、やはり「お金がかかる」というのは大きな難点です。
離れて暮らす距離が遠い場合、移動に飛行機や新幹線を使わなければならず、往復回数が増えると家計を大きく圧迫します。航空会社や鉄道会社が実施しているさまざまな割引制度を活用するなど、できるだけ交通費を抑える工夫が必要です。
また、交通費だけでなく、普段からかける電話などの通信費用も高額になる傾向にあります。
遠距離介護を成功させるためのポイント
遠距離介護が必要になった際に押さえておきたいポイントについて紹介します。
- 家族で役割分担を決める
- 周囲の人を頼る
- 介護休業制度について確認する
- 交通費は「介護割引」を利用する
- 高齢者向けサービスを活用する
- 老人ホームへの入居も検討する
家族で役割分担を決める
兄弟姉妹がいる場合は、介護をする上で誰がどのようなサポートをするのか、役割分担を決めておきましょう。それぞれの生活状況からできること、できないことを明確化し、誰か一人に負担が集中しないように協力する姿勢が大切です。
周囲の人を頼る
すぐに駆けつけることができない距離で介護をおこなう場合は、近隣の人や近くに住む友人の協力は必要不可欠です。
「日頃の見守りや声かけをおこなってもらえないか」「災害時には避難のサポートをしてもらえないか」など、遠くに住んでいるとなかなかできない不安なことをお願いしておくと安心です。
介護休業制度について確認する
現在、勤めている会社の介護休暇や介護休業制度について確認し、できるだけ活用しましょう。
現行の制度では、介護休暇は介護の対象となる家族が一人の場合は年間で5日まで、2人以上の場合は年間で10日までとなっています。一方の介護休業は介護の対象となる家族一人につき3回まで、通算93日まで休業できます。
なお、介護休業をする場合には条件を満たしていると介護休業給付金を受け取ることができる場合もあります。
交通費は「介護割引」を利用する
遠距離介護をおこなう上で一番問題になるのは、帰省のための交通費ではないでしょうか。
移動には身体負担が少なく、移動時間も短く済ませることのできる飛行機や新幹線を使いたいという人も多いでしょう。
そんなときに便利なのが交通各社の「介護割引」サービスです。条件によっては3〜4割引きになることもあります。詳しくは交通各社のホームページなどを確認しましょう。
高齢者向けサービスを利用する
近年では遠距離介護をおこなう人向けのサービスも展開されており、これらを活用し、介護負担を少なくすることも大切です。
自立した生活を継続するためには、本人ができることは自分でおこなってもらうことも大切です。その上で何か困っていることがあれば、サポートしてくれるサービスを活用するという方法も良いかもしれません。
具体的なサービスの例としては以下のようなものがあります。
- 自宅に食事を届けてくれる「配食サービス」
- 安否確認をしてくれる「見守りサービス」
- IoTを活用した「見守りサービス
- 買い物や掃除、食事作りなど必要な家事をしてくれる「家事代行」サービス
老人ホームへの入居も検討する
遠距離介護は何かあったときにすぐ駆けつけることができません。親の介護度が上がったり、認知症が悪化した場合は、自宅で生活を継続することが難しくなる場合もあるでしょう。
そのような場合は、老人ホームへの入居も検討しましょう。入居する際の費用はかかりますが、介護のプロに身の回りのことを任せることができて、安心して過ごすことができます。
なお、費用が比較的安い施設に関しては人気が高く、入居待ちになる可能性もあります。自宅での生活が難しいと感じた段階で早めにケアマネジャーに相談しましょう。
まとめ
遠距離介護のポイントやメリット・デメリットなどを説明しました。遠距離介護をする際には、常に近くにはいられないからこそ、しっかりとした事前準備と、親とのコミュニケーションが大切になってきます。
また、近隣の人や近くに住んでいる友人のサポートも必要不可欠です。こまめにコミュニケーションをとり、信頼関係を築くようにしましょう。
介護する人も介護される人も、それぞれが納得できる環境で生活していくために家族みんなで、介護の備えについて考えておくことをおすすめします。