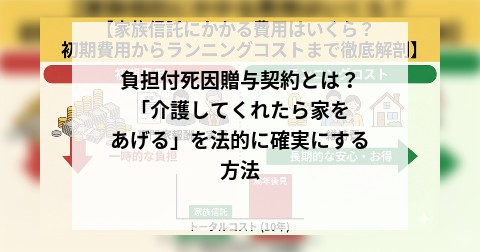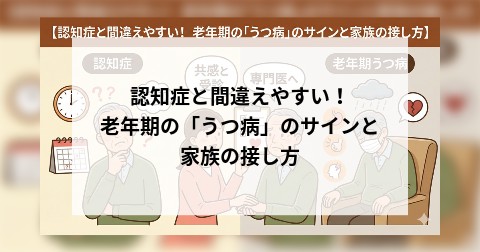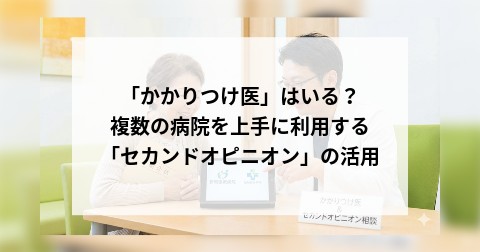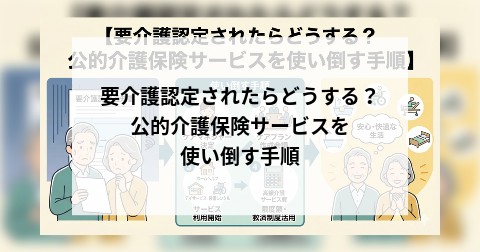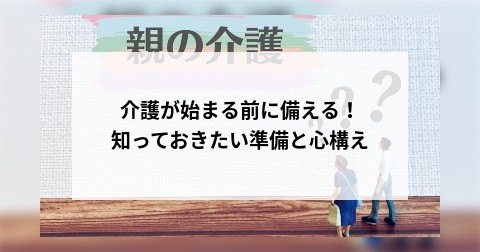突然の病気で医療費・介護費の不安を乗り越えるお金と情報の集め方
突然の病気、そのときのお金の不安を乗り越えるために
もし、自分や大切な家族が突然大きな病気にかかってしまったら…。治療費や介護費、働けなくなることへの不安など、お金の心配は尽きないものです。しかし、知っているかどうかで、その不安は大きく変わります。
この記事では、突然の病気で直面する医療費・介護費の負担を軽減するために、公的な制度や利用できるサービス、そして情報の集め方について分かりやすく解説します。

老後の医療費はどれくらいかかる?
老後の生活を考えるうえで、医療費の負担は避けて通れません。 加齢とともに医療機関を利用する機会が増えるため、あらかじめ必要な費用を把握しておくことが重要です。
厚生労働省のデータによると、2021年(令和3年)の日本人1人あたりの生涯医療費は2,815万円(男性:2,727万円 女性:2,901万円)とされています。
そのうち、年金受給が始まる65歳以上の医療費は1,604万円、つまり生涯医療費の57%が老後に集中していることになります。 特に70代後半から80代前半にかけて医療費がピークを迎える傾向があります。
老後の医療費は避けられない支出の一つであり、事前の資金計画や公的支援制度の活用を検討することが重要です。
65歳以上の医療費自己負担割合は?
65歳以上の医療費の自己負担割合は、所得に応じて異なります。 一般的な所得の方は 自己負担割合は1割 ですが、一定以上の所得がある場合は、負担割合が2割または3割となります。
介護にかかる費用はどのくらい?
(公財)生命保険文化センター「2021(令和3)年度生命保険に関する全国実態調査」によると、住宅を介護しやすく改造したり介護用のベッドを購入したりといった一時的な費用が平均740,000円、介護の月々の費用に平均83,000円が必要という結果になっています。介護期間が平均して5年1ヵ月なので、平均すると総額5,800,000円以上という計算になります。
親を介護施設に入れた場合の必要な費用
親を介護施設に入れると、介護費用は高くなる傾向にあります。
生命保険に関する全国実態調査(2021年度)によると、在宅介護でかかる平均の月額介護費用が4.8万円なのに対して、介護施設に入れた場合の月額介護費用は12.2万円です。
在宅介護では、月額15万円以上の費用をかけた事例は全体の5.8%にすぎません。
しかし、施設介護では、15万円以上の費用をかけた事例が30.7%を占めます。
介護費用を抑えたい方は、在宅介護が望ましいといえるでしょう。
医療費・介護費の負担を軽減するための制度やサービス・情報収集
医療費の不安を軽減する「高額療養費制度」
病気で入院したり手術を受けたりすると、医療費が高額になることがあります。そんなときに心強い味方となるのが高額療養費制度です。これは、1か月の医療費の自己負担額が一定の金額を超えた場合、超えた分が払い戻されるという公的な制度です。
自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。事前に「限度額適用認定証」を申請しておけば、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。もし、限度額適用認定証がない場合でも、後から申請すれば払い戻しを受けることができます。
この制度は、公的医療保険に加入していれば誰もが利用できます。詳しくは、ご自身が加入している健康保険組合や市区町村の窓口に問い合わせてみましょう。
医療費以外にかかるお金をカバーする制度
治療や入院には、医療費以外にもさまざまな費用がかかります。例えば、差額ベッド代や食事代、交通費、日用品代などです。これらの費用は高額療養費制度の対象外となるため、注意が必要です。
しかし、これらの費用をカバーするための公的な制度も存在します。
-
傷病手当金: 病気やケガで会社を休み、給与が支払われない場合に、生活を保障するために支給される手当です。健康保険の被保険者が対象となります。
-
障害年金: 病気やケガで日常生活や仕事に支障がある場合に、国から支給される年金です。初診日から1年6か月が経過していることなどの条件があります。
-
自立支援医療制度: 精神疾患や特定の難病、結核などで長期の通院治療が必要な場合に、医療費の自己負担額が軽減される制度です。
これらの制度は、それぞれ対象者や条件が異なります。まずは、ご自身が利用できる制度がないか確認することが大切です。
介護が必要になったときに備える
病気や高齢により介護が必要になった場合、介護保険制度を利用できます。介護保険は40歳以上の方が加入し、介護が必要になったときにサービスを受けられる制度です。
要介護認定を受けると、デイサービスや訪問介護など、さまざまな介護サービスを1~3割の自己負担で利用できます。介護保険料は毎月の給与や年金から天引きされているため、いざというときにスムーズに利用できるよう、仕組みを理解しておきましょう。
高額介護サービス費の活用
高額介護サービス費とは、1カ月の間に支払った介護費用の合計が「負担限度額」をオーバーした際に、オーバーした分の費用が払い戻される制度です。
所得に応じて負担限度額が異なり、令和3年8月からは以下のとおりに設定されています。
| 区分 | 負担の上限額(月額) |
|---|---|
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |
| 市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
| 世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |
| 世帯の全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方など | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 生活保護を受給している方など | 15,000円(世帯) |
高額医療・高額介護合算療養費制度
高額医療・高額介護合算療養費制度とは、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間で、医療保険と介護保険における自己負担が高額になる場合に、自己負担が軽減される仕組みのことです。
限度額は、医療保険の制度や収入などによって細かく設定されています
信頼できる情報収集のポイント
突然のことで何から手をつけていいかわからない、という方も多いでしょう。そんなときに役立つ、信頼できる情報源をご紹介します。
-
病院の医療相談室(地域連携室): 医療費や退院後の生活について、専門の相談員(ソーシャルワーカーなど)が相談に乗ってくれます。利用できる制度や手続きについて、具体的に教えてもらうことができます。
-
市区町村の窓口: 福祉担当の窓口では、利用できる公的な制度や地域の支援サービスについて相談できます。
-
加入している健康保険組合: 自分が加入している健康保険組合のウェブサイトや窓口では、高額療養費制度や傷病手当金などの詳細を確認できます。
-
信頼できる情報サイト: 厚生労働省や各自治体の公式サイト、社会福祉協議会のウェブサイトなど、公的な機関が発信する情報を参照しましょう。
まとめ
「病気はお金がかかる」というイメージから不安が大きくなることは当然です。しかし、多くの公的な制度が私たちの生活を支えるために用意されています。まずは、これらの制度の存在を知り、いざというときに備えておくことが何よりも大切です。
突然の病気に直面した際は、一人で抱え込まず、まずは病院の医療相談室や市区町村の窓口に相談してみましょう。専門家があなたの状況に合わせて、最適なサポートを一緒に探してくれます。