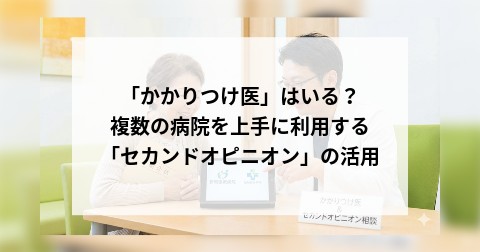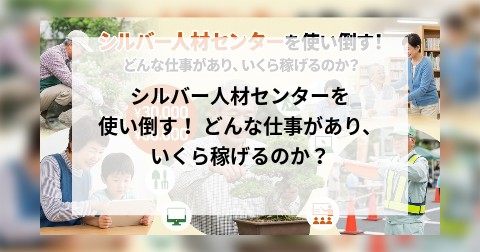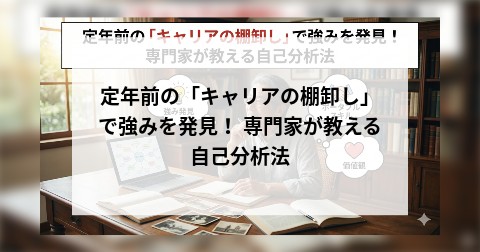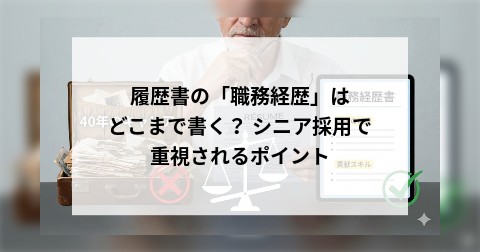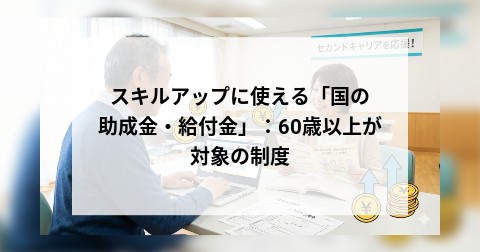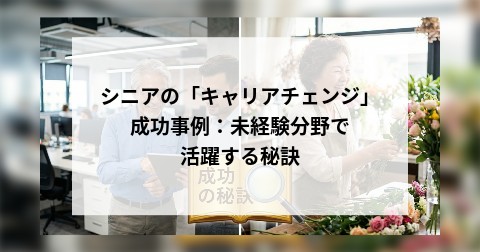【おひとりさまの相続】誰に、どう残す?後悔しないための終活と遺言のすすめ
独身で身寄りがない方にとって、「もしものとき」の準備はとても大切です。誰に相談すればよいのか分からない、あるいは相続問題や財産管理で苦労しそうと心配する方も多いようです。
老後のおひとりさまは、孤独死のようなさまざまなリスクを抱えることもあります。そのような状況に置かれ、老後や終活のことについてどうしたらよいか分からないという方もいるのではないでしょうか。
今回は、おひとりさまの方へ、終活の必要性や進める上での注意点についてご紹介します。

おひとりさまに終活が必要な理由
おひとりさまの場合、手助けしてくれる身内がいなかったり、いても遠方で思うように助けてもらえなかったりすることが多いでしょう。だからこそ終活を行って、いざというときのために備えておく必要があります。終活を行うことで不安を抑えられ、心の安定にもつながります。
また「おひとりさまは寂しい人生だ」と感じる方もいるかもしれません。しかし前向きに捉えれば、おひとりさまなら自己決定でき、将来も自分の思い通りに生きることができます。ポジティブに生きていくためにも、終活には意義があるといえるでしょう。
孤立死を防げる
身寄りがないおひとりの高齢者の方は、体調不良や生活習慣の乱れなどに気づきにくいため、孤立死の可能性が高まります。
終活の相談をしたり、定期的に連絡を取ったりする相手がいれば、日常生活や体調の異変にも気づいてもらいやすくなるでしょう。
定期的な訪問や監視カメラなどでの見守りサービスを提供している事業者もあるので、終活の一環として検討することをおすすめします。
生前の生活も安心して過ごせる
終活は、自分が亡くなった後のためだけに行うのではありません。残りの人生をより豊かに、より安心して過ごせるようにするためにも必要です。
例えば、認知症発症後の財産管理や亡き後の死後事務に関して、元気で健康なうちに信頼できる専門家などへ委任しておけば、不安も取り除かれるでしょう。
葬儀・お墓のことに関する希望を実現できる
おひとりの高齢者の方は、葬儀やお墓のことをはじめとした自身の亡き後に関する希望があったとしても、誰かに伝えていなければその内容は実現できない可能性があります。
完全に親族がおらず遺体の受取人がいない場合は、行政が主体となって火葬されます。
一方で、終活として遺言書で財産の相続人を指定したり、葬儀や納骨などについて第三者へ委任したりすると、本人の状況や希望を実現することが可能です。
死亡や認知症により周囲に迷惑をかける心配がなくなる
おひとりの高齢者の方が亡くなると、すぐに連絡の取れる親族がいない場合は、警察や自治体が戸籍をもとに親族を探します。
たとえ疎遠だったとしても、戸籍上で親族と確認されれば連絡が入り、遺体や遺骨の引き取りを求められます。
親族は、遺体や遺骨の引き取りを拒否することは可能ですが、法定相続人として財産を受け取るのであれば、遺品整理に関しても責任を求められるでしょう。
身元保証人問題を解決できる
おひとりの高齢者の方は、病院への入院時や、施設への入所時に身元保証人を用意できないおそれがあります。
病院や施設の多くは、リスク回避のために入院時や入所時に身元保証人を求めます。
通常であれば、家族や親族が身元保証人になりますが、おひとりの場合は頼れる人がいないケースもあるでしょう。
そこで、終活の一環として身元保証人をあらかじめ探しておくことで、いざ入院・入所するときに慌てる心配がなくなります。
おひとりさまの終活でやるべきこと
所有物など身辺の整理
すぐに始められるのが身辺の整理です。ひとり暮らしでも、長く暮らしていると物が増えてしまうのはよくあることです。いらない物を処分して、家の中を整理しましょう。
所有物を把握しながら整理することで、本当に必要な物はなにかがわかってくるというメリットもあります。また、片付かないことから起こるストレスも軽減できます。さらにいえば物につまずいてケガをするリスクも抑えられるでしょう。
エンディングノートを書く
近年、自分の意志を伝えるために、エンディングノートを書く方が増えています。エンディングノートは、自分の人生の記録や最期の希望を書き記すものです。そのなかに、自分の葬儀のことや死後のことについての希望を書くことで、周りの方にあなたの意志を伝えられます。
また、エンディングノートを書き残すことで、譲りたい遺品や大切な書類のことなども伝えられるため、家族や周りの方が財産整理をしやすくなるメリットがあります。
遺言書を作成する
相続させる財産がある場合は、遺言書を作成することが重要です。エンディングノートには法的拘束力がないため、相続については遺言書で意思を示す必要があります。正式な書式や形式に沿った遺言書を作成しておけば、自分の希望どおりの遺産相続ができるでしょう。
また、相続に関する希望を遺言という形で残すことで、遺産をめぐる争いを避けられます。遺言を残し、財産を誰にどれだけ相続したいのかを明確に示しておきましょう。
任意後見人制度を利用する
任意後見人制度は、判断能力が低下したときのために備えて締結できる制度です。締結をする場合は、判断能力があるうちに行う必要があります。信頼ができる人に相談をして、後見人になってもらいましょう。
任意後見人制度によって選んだ後見人は、判断能力が低下した場合や死後に財産管理や介護・医療などに関わる事務手続きを代行します。法廷後見人制度とは違い、自分が信頼のおける人物を後見人に指定できるのが特徴です。
葬儀・お墓の生前契約を行う
おひとりさまの場合、自分の葬儀の内容を生前に決めておくことをおすすめします。自分の葬儀のことを頼める人がいればよいですが、いない場合は、あとに残された方が困惑してしまう可能性があります。周りの方に迷惑をかけないためにも、自分の葬儀のことは自分で決めて、生前に契約しておくとよいでしょう。
遺言書でどこまで備えられる?できること・できないこと
おひとりさまにとって、遺言書は「自分の思いを残すための最も大切な手段」のひとつです。ここでは、遺言書によって何ができて、どこまでの備えが可能なのかを整理してみましょう。
できること(法的効力がある内容)
相続分の指定・遺贈の指示
法定相続人がいる場合は、民法第902条に基づき、法定相続分と異なる配分を指定することができます。相続人以外の方(友人やお世話になった人、団体など)へ遺産を渡す「遺贈」も可能です(民法第964条)。
特定の財産の帰属先指定
たとえば「○○市のマンションはAさんへ」「預貯金はBさんへ」といった、財産ごとの明確な割り振りが可能です。これにより、相続トラブルの防止にもつながります。お世話になった方がいるとき、法定相続人以外の方に相続して欲しいときは必ず記載が必要です。
遺言執行者の指定
遺言を確実に実現するために、遺言の内容を実行する人(遺言執行者)をあらかじめ指定しておくことができます(民法第1006条)。専門家を選任することで、手続きの円滑化にもつながります。
付言事項の記載(法的効力はないが、想いを伝えられる)
遺言書には「付言事項」として、葬儀の方針や大切な人への感謝の言葉などを自由に記すことができます。これは法的な効力を持ちませんが、受け取る側にとっては深い意味を持つ内容になることが多いです。
できないこと(他の契約や備えが必要な内容)
一方、遺言書だけではカバーしきれない内容もあります。
- 生前の生活支援の話(通院の付き添い・買い物代行など)
- 判断能力が低下した際の代理行為について(入院・施設契約など)
- 死後の事務手続き(主に葬儀・役所手続き・公共料金の解約など)
こうした場面では、次にご紹介する「生前契約」の併用が有効です。
生前契約とは?
遺言書が「死後の意思表示」を主にカバーするのに対して、生前契約は「生きている間の不安や支援」に備える手段です。特におひとりさまの場合、身近な支援者がいない状況でこれらの契約を活用することで、安心して暮らす土台が整います。ここでは代表的な4つの契約についてご紹介します。
任意後見契約
判断能力が低下したときに備え、あらかじめ信頼できる人に財産管理や契約の代理をお願いする契約です。公正証書で作成し、将来、判断能力が衰えたときに家庭裁判所の監督のもとで効力が発生します。
財産管理契約
判断能力があるうちから、財産の管理・生活支援を委任できる契約です。入院・施設入所時など、ご本人が不在になる場面でも柔軟に支援が行えます。
見守り契約
定期的に連絡を取り、生活の様子を確認してもらう契約です。安否確認や孤立防止の観点からも有効です。これ自体には法的拘束力があるわけではありませんが、他の契約(財産管理契約・任意後見契約)と併用されることが一般的です。
死後事務委任契約
死亡後に必要な手続きを他者に委ねる契約です。葬儀の手配や火葬・納骨、住居の片付け、行政手続き(住民票の抹消・保険の解約)など、遺族がいない、あるいは頼れない場合に極めて重要となります。