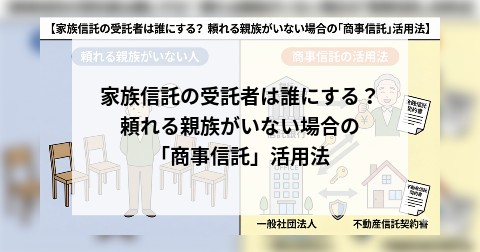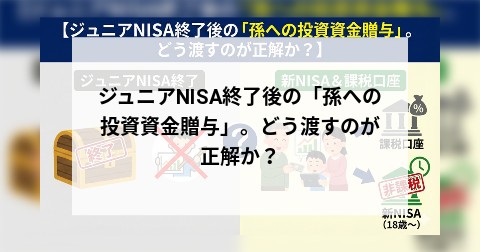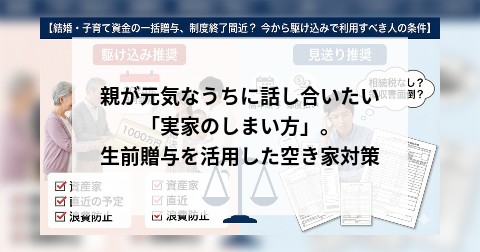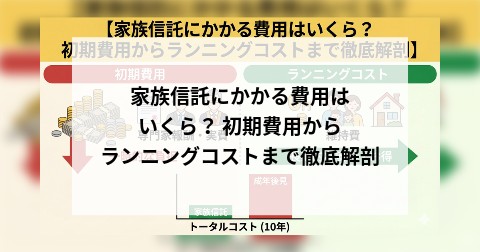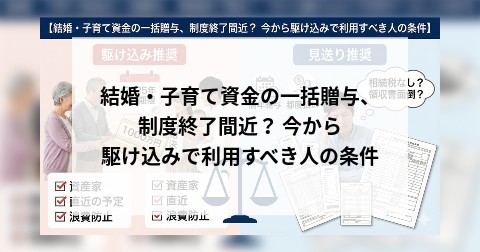贈与契約書は必須?生前贈与を法的に有効にするための注意点
家族や親しい人への資産の譲渡手段として、生前贈与を検討される方は少なくありません。しかし、「口約束だけで大丈夫?」「贈与契約書は必要なの?」といった疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
この記事では、生前贈与を法的に有効に行うためのポイントと、贈与契約書の重要性についてわかりやすく解説します。

贈与契約書がなくても贈与は成立する?
民法上、贈与は「当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる」と定められています(民法第549条)。つまり、法律上は口頭の約束だけでも贈与は成立します。しかし、口約束だけの贈与には大きなリスクが伴います。
そもそも贈与契約書とは?
贈与契約書は、生前贈与をする際に作成する書類です。
契約日・受け取る財産の内容・贈与の方法を記載し、贈与者(財産を渡す人)・受贈者(もらう人)の署名捺印を行うことで作成します。
贈与契約書は形式が定められておらず、個人で作成が可能です。
手書きでも作成できますが、署名捺印以外はパソコンで入力し作成してもかまいません。
贈与契約は口約束でも成立するため、生前贈与するだけなら贈与契約書の作成は必須ではありません。
しかし将来のトラブル防止のために作成する場合が多いです。
贈与契約書のメリット
贈与契約書があることで次に挙げるメリットが得られます。
- 公平な遺産分割
- 確実な贈与履行
- 税務調査対策
- 不動産登記の円滑化
公平な遺産分割が可能
贈与契約書があれば遺産相続のトラブルを防止することが可能です。生前贈与を受けた場合、遺産相続の際にほかの相続人が不公平に感じる場合があります。ほかの相続人からは、生前贈与された金額が明確には分からないからです。しかし、贈与契約書があれば生前贈与された具体的な金額を証明できるため、それをもとに公平な遺産分割を行えます。
確実に贈与を履行してもらえる
贈与は当事者間の口約束で成立しますが、贈与する人(贈与者)の気が変わって贈与の話がうやむやになる可能性もあります。口約束の場合、当事者のどちらかが言い出せば贈与を途中で中止することが法的に可能だからです。たとえば、500万円の贈与予定が100万円の贈与が行われた時点で撤回になることもあり得ます。
財産をもらう側(受贈者)が拒否した場合はともかく、贈与の中止はトラブルの原因になる可能性があります。贈与契約書があれば途中で贈与を中止できなくなるため、トラブル防止の意味でも作成しておくことをおすすめします。
税務調査対策になる
税務調査が入った場合に贈与契約書があれば贈与の事実を証明することが可能です。これによって正当な贈与であることを証明できます。
そもそもなぜ税務調査対策が必要かというと、名義預金(※1)や定期贈与(※2)を疑われて税務調査が入る場合があるからです。実際に基礎控除の範囲で贈与していたとしても、管理方法や贈与の仕方によっては税務署が贈与を認めず、名義預金や定期贈与とみなすことがあります。
不動産登記の手続きがスムーズ
贈与で不動産を取得する場合、贈与契約書があると不動産登記の手続きが円滑になります。不動産を取得したとき、名義変更のために所有権移転登記が必要になります。そのときに登記名義人を変更する理由の記載が必要になり、贈与契約書がその証明書類となります。そのため、事前に贈与契約書を用意しておくと、手続きがスムーズです。
贈与契約書を作成する際の注意点
ここでは贈与契約書を作成する際に気をつけたい注意点を4つご紹介します。
- 双方が納得した状態で進める
- 贈与の内容は詳細に書く
- 署名は手書きで行う
- 未成年が受け取る場合は親権者の署名捺印が必要
①双方が納得した状態で進める
必ず贈与者・受贈者の双方が契約内容を理解した状態で契約書を作りましょう。
特に以下の項目はお互いの認識にズレがないか注意が必要です。
- いつ財産を渡すのか
- 財産の内容(財産の種類・金額など)
- 贈与の方法
以上の契約内容の確認を怠ってしまうと、贈与者・受贈者間で[言った・言ってない]などのトラブルになるおそれがあるため双方が納得した状態で贈与契約書を作成しましょう。
②贈与の内容は詳細に書く
贈与契約書を作成する際は、具体的な契約内容になっているかが重要になります。
財産の内容を記載する際は以下の点に注意しましょう。
| 財産の種類 | 注意点 |
| 現金 | 金額は一の位まで正確に記載しているか |
| 株式 | 銘柄名と数量に加え、会社の住所や株式の種類の記載があるか |
| 不動産 | 登記事項証明書の通りに記載しているか |
贈与契約書はどんな贈与を行ったか証拠を残すための書類のため、財産の内容は詳細に記載しましょう。
③署名は手書きで行う
署名は必ず手書きで行うようにしましょう。手書きで署名することで、当事者本人が贈与契約書を作成したという証拠を残すことができます。
④未成年が受け取る場合は親権者の署名捺印が必要
未成年も生前贈与で財産を受け取ることができます。ただし、未成年が財産を受け取る場合、親権者の同意が必要です。
暦年贈与における3つの注意点
暦年贈与とは、贈与税の仕組み(暦年課税)を利用して非課税で生前贈与を行う方法です。
暦年贈与を上手に使うことで、贈与する人(贈与者)にとって有効な相続税対策となるだけでなく、贈与される人(受贈者)も贈与税を負担せずに済みます。
ただし、暦年贈与を行う際以下の点に注意しましょう。
- 定期贈与だとみなされないようにする
- 名義預金だと判断されないようにする
- 相続開始前7年以内の暦年贈与は相続財産に加算される(生前贈与加算)
定期贈与だとみなされないようにする
定期贈与とは、あらかじめ、まとまった財産を1人に贈与することを取り決めて行われた贈与のことを指します。
たとえば、Aさんが「孫であるBさんに600万円を贈与したいが、年間110万円を超えたら贈与税がかかる」と考え、6年に分けて100万円ずつの贈与を実行したとします。
この場合、税務署から「定期贈与」であるとみなされ、贈与額の合計に対して贈与税が課税される可能性があります。贈与者Aさんは暦年贈与をしているつもりでも、毎年同じ時期に・同じ金額を・同じ人に贈与しているからです。
定期贈与と判断されないためには、毎年、時期や金額を変えて贈与することが大切です。
名義預金だと判断されないようにする
名義預金とは、家族名義の銀行口座で、名義人とは異なる人が管理している預金のことを指します。
「相続対策はしたいけれど、子どもが使ってしまうのは避けたい。子ども名義の口座に振り込んでいくけど、通帳は自分が管理して贈与したことにしておこう」。このように考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、贈与は、あげた・もらったという関係が、贈与者と受贈者の間で成立することが必要(民法第549条)であり、贈与税の基礎控除(年間110万円)を適用するには、贈与契約そのものが成立していることが前提です。もし、贈与者が一方的に贈与をして受贈者がその存在を知らない場合や、実際に名義預金を管理しているのが贈与者であるなら、贈与そのものが成立していない状態です。
このように、贈与が成立していないお金が名義預金とみなされた場合、そのお金は贈与者のものであると判断され、贈与者の相続発生時に相続税が課税されてしまいます。
相続開始前7年以内の暦年贈与は相続財産に加算される(生前贈与加算)
相続開始までの一定期間内に行われた贈与は、相続時に相続財産に加算され、相続税の対象となります。
令和5年までに贈与される財産については、相続開始前3年以内に行われた贈与が相続財産に加算される対象になります。
令和6年以降に贈与される財産については、相続税の対象になる期間が順次延長され、最終的には相続開始前7年以内に行われた贈与が相続財産に加算される対象になります。
まとめ
生前贈与を行う際には、贈与契約書を作成することで、法的トラブルを未然に防ぎ、贈与の事実を明確にすることができます。特に、高額な贈与や不動産の贈与の場合には、贈与契約書の作成が推奨されます。贈与契約書を作成する際には、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします