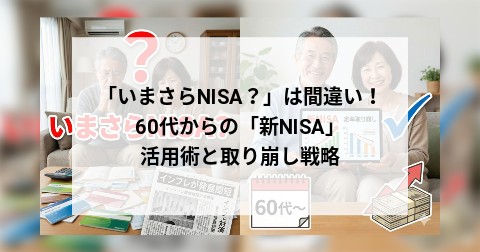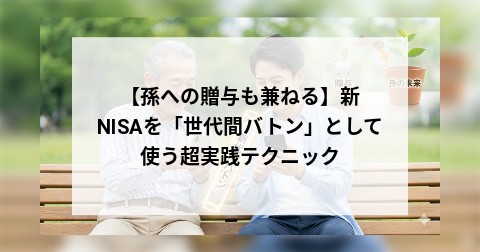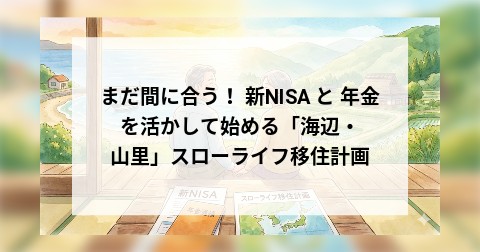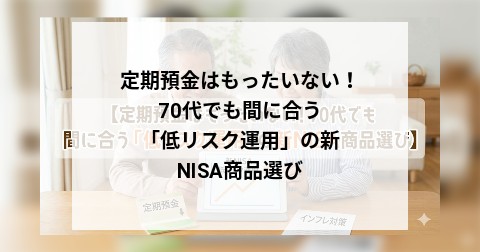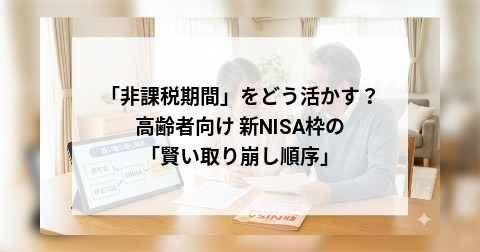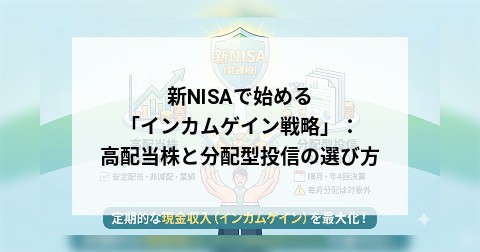シニアが絶対に避けるべき「危ない投資」とは?
定年後の資産運用では、「増やす」だけの運用よりも「守りながら育てる」という運用に重点を置くのがセオリーとされています。
生活資金を安全に確保しながら、老後資金を安定的に成長させるためには、安全性と成長性をバランスさせた資産配分が求められのでリスクが高い運用は避けるべきです。
本記事ではシニア世代で避けるべきリスクの高い投資について解説していきます。

老後の資産運用でやってはいけないこと
老後の資産運用でやってはいけないことをいくつかあげました。
以下のうち、年代によっては問題のないものもありますが、60代以上で老後に差し掛かった人は特に「やってはいけない」と認識しておくことが大切です。
①ハイリスク商品への投資
老後は「資産運用の時間があまりない」との考えから短期間で大きなリターンが狙えるような投資に目が向きやすい一面があります。
例えばFXの短期売買やバイナリーオプション(※)、暗号資産(仮想通貨)などはその典型です。
これらの投資は、短期的に資金を2倍、3倍にもできる可能性を秘めていますが、ハイリターン投資はハイリスク商品でもあります。
場合によっては、短期間に資産を全部失う恐れもあるため、老後の資産運用には適していません。
②退職金を活用した一括投資
老後を目前に控えた時期に、会社員や公務員など給与所得者として勤務してきた人のなかには退職金を受け取る人もいるのではないでしょうか。
特に何か事業をしていたり親族から遺産が入ってきたりする予定がない限り、退職金は実質的に人生最後の大金となります。
それだけに資産運用で増やし、老後の生活を豊かにしたいと考えるのはごく自然なことです。しかしその退職金を特定の投資商品に一括投資することは、おすすめできません。
仮にそれが資産運用法として適切であっても、一度に全額を投資してしまうとその投資商品と「心中」することになってしまいますので、退職金の一括投資は避けた方がいいでしょう。
③手数料負けしてしまう金融商品
「資産運用のことはよく分からない」という人に向けに運用を任せられる「ファンドラップ」「ロボアドバイザー」といったサービスがあります。しかしいずれも手数料の高さがデメリットです。
これらと同じ理由で、「テーマ型投資信託」「変額年金保険」なども手数料コストが高いことから、老後の資産運用には不向きといえます。
単純計算で利回り4%の運用ができても手数料が1%の場合、実質的な利回りは3%です。
しかも思うような運用利回りになっていない場合でも手数料は変わらず発生するため、利回りが低くなると手数料が高い分マイナスになってしまう可能性もあります。
手数料が高い投資商品は「手数料負け」のリスクがあるため、老後の資産運用としては「やってはいけない」と考えたほうがよいでしょう。
④現金化に時間がかかる投資
資産運用をする場合、商品によっては現金化に時間がかかったり、投資家の都合でいつでも現金化できなかったりするものがあります。
例えば現物不動産(アパートやマンションなど)は、買い手を見つけて売却する必要がありますし、仕組債(※)は満期まで原則途中解約不可といった具合です。老後は、自分や配偶者などが高齢になることで病気のリスクも高くなります。
将来的に「今すぐお金が必要」という事態になる可能性はゼロではありません。そのため資産運用の際は、一部の必要な現金を残しておくか、現金化に時間のかかる投資は避けたほうが無難です。
⑤不自然に利回りの高い投資
利回りの高い投資は、短期間に老後資金を増やせる可能性があるため、魅力的に見えます。しかし不自然に利回りが高いものは、詐欺の可能性が高く基本的に関わるべきではありません。
一般的に資産運用の利回りは数%から高くても10%程度が相場です。それを大きく上回るような利回りをうたっている投資商品は現実味がありません。
また資産運用の利回りは、年利で表示されるのが一般的です。それに対して月利で表示しているものは、高利回りを際立たたせるための「演出」の可能性が高く、やはり詐欺を疑うべきでしょう。
⑥たこ足ファンド
たこ足ファンドとは、分配金に投資家から集めた元本が含まれているファンド(投資信託)のことです。
高配当をうたう投資信託や毎月分配型の投資信託に見られる傾向で、タコが自分の足を食べることになぞらえて「たこ足ファンド」と呼ばれています。
元本を含めた分配金を出しているため、あたかも毎月多くの収入が得られるように見えますが、その一部は元本です。
分配金を出すごとに元本が減ってしまうため、投資信託の価格となる基準価額が下がってしまいます。自分のお金が払い戻されているだけの商品に手数料を支払うのは無駄になるため、たこ足配当を出しているような投資信託は老後の資産運用だけに限らず、おすすめできません。
⑦節税効果を目的とした投資
投資マンションの広告などによく登場する「節税効果」の文言を見たことはありませんか。
たしかに不動産投資には、節税効果があります。しかし、そもそも老後の資産運用をする人のうち節税が必要なほど本業の収入がある人は限られてしまうでしょう。
この場合、節税効果をうたい文句にしている投資はあまり意味がなく、むしろリスクのほうが高いため、避けるべきです。
シニアの資産運用で気をつけたいポイント
老後にかかる費用を明確にする
投資を始める前に、老後の収入や支出を明確にしておく必要があります
- 夫婦がもらえる年金額はいくら受け取れるのか
- 退職金・企業年金はいくら受け取れるのか
- 定年後の生活費はいくら必要となるのか
- 住居費(固定資産税・リフォーム代など)はいくらかかるのか
- 生活費以外の特別支出金(子供の結婚資金、孫へのお祝い、趣味、旅行、友人や近所との付き合いなどにかかるお金)はいくらかかるのか
など、これら収入・支出項目の概算金額を書き出したうえで、いくらまでならリスクを抑えて投資が可能なのかという金額を算出してみましょう。
目的に合った資産運用の方法を選ぶ
目的によって、最適な資産運用の方法は異なります。目的を踏まえたうえで資産運用の方法を選ぶと、達成する可能性も高くなります。目的だけでなく、投資に回せる資金、投資期間、許容できるリスクとリターンのバランスなども考慮して資産運用の方法を選択しましょう。
資産運用の方法を決めたら、その方法に関する具体的な知識や情報を収集します。ここでは、可能な限り幅広い知識や情報を得ることが大切です。準備が整い次第、実際に資産運用を開始してみましょう。なお、資産運用を始めた後も、定期的に戦略を見直す必要があります。
初心者であれば少額からスタートする
たとえ余裕資産が多くても、初心者は少額から資産運用を開始しましょう。少額から資産運用を始めれば、万が一うまくいかない場合でも損失を小さく抑えられます。初心者のうちは分からないことが多く思ったように運用できないこともあるので、一歩一歩確認しながら資産運用を始めましょう。資産運用には元本割れのリスクがある点を意識し、無理のない範囲で取り組むことが大切です。
また、少額で始めれば複数の資産運用の方法にもチャレンジできるため、経験や知識を増やせます。実績を積んで自信が出てきたら、運用する金額を少しずつ増やしていきましょう。
分散投資する
資産運用に取り組むうえでは分散投資も重要です。分散投資とは、複数の金融商品に投資する方法です。例えば、株式投資のみを行うのではなく、債券投資や投資信託なども同時に行うケースが当てはまります。
分散投資を行うべきなのは、特定の金融商品で損失が発生しても、他の金融商品で利益が出ていれば損失をカバーしやすいからです。複数の金融商品に投資すると、資産運用のリスクを抑えやすくなります。それぞれの金融商品の特徴を把握し、相性も考慮して選択しましょう。
まとめ
資産運用の方法としては様々なものがあり、特徴が異なります。初心者でも始めやすい資産運用の方法も多くあるため、自分にとって最適なものを選びましょう。繰り返しになりますが、そのためには、資産運用の目的を明確にすることが大切です。
また、資産運用では損失が発生する恐れがあるため、初心者の方は少額から始めましょう。長期的な視点で取り組み、分散投資も心掛ける必要があります。さらに、資産運用に関する知識も積極的に身に付けるといいでしょう。自分に合う資産運用の方法が分からない場合は、専門家にも相談しながら無理をせず取り組むようにしてください。