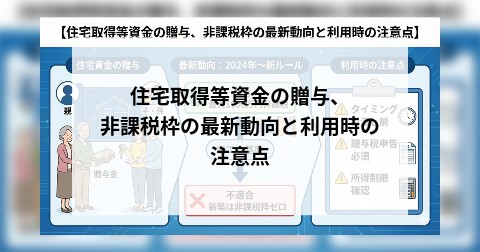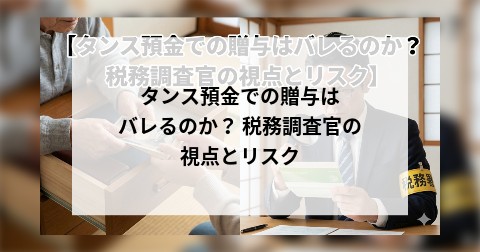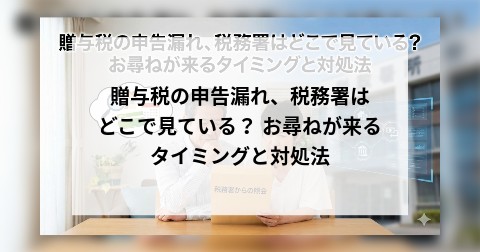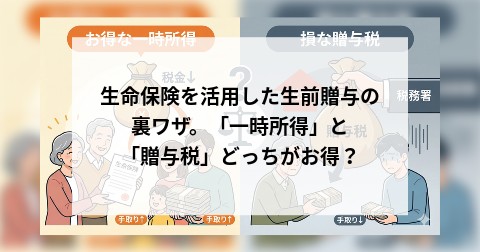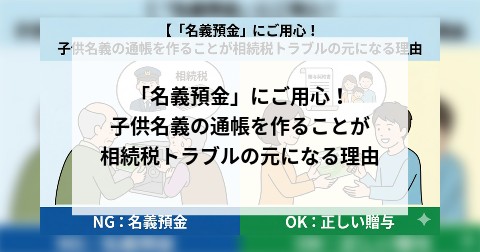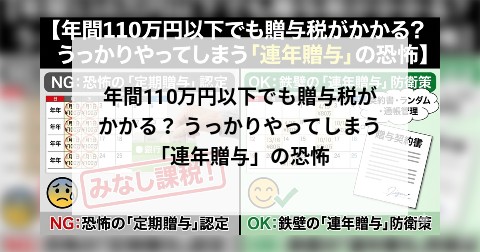漠然とした不安を解消!シニアが知っておくべき相続の基本と相談先
高齢化社会の進展に伴い、シニア層の相続問題がますます注目されています。相続手続きには専門知識が必要な場合もあります。
特にシニア層は自身の財産管理や相続準備に対する関心が高く、専門家へ費用を支払ってでも専門的なサポートを求める傾向があります。
そこで今回は、シニア世代に向けて相続に関する基本的な知識や行っておきたい相続対策を解説します。
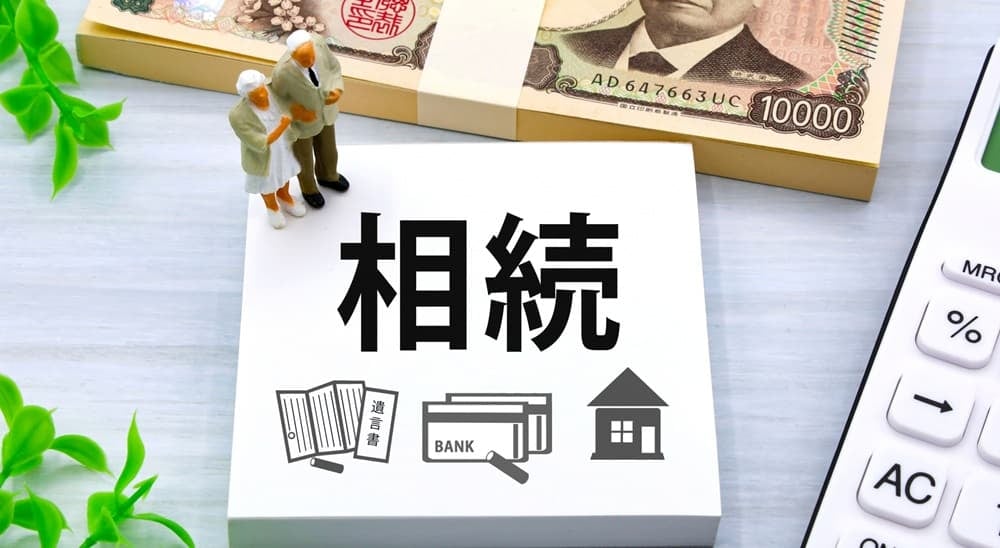
相続とは?
相続とは、相続人が被相続人(亡くなった人)から財産を引き継ぐことです。相続は法律上で相続することが決まっている法定相続人への相続と、法定相続人以外への遺贈があります。
まず、相続には大きく分けて「法定相続」と「遺言相続」があります。遺言書がある場合は、原則としてその内容が優先されますが、遺言書がない場合などには、民法の相続のルールに従って、遺産分割協議により、決められた人が決められた分を相続することになります。
法定相続とは?
民法に定められた相続人の範囲や順位、それぞれの相続分に従って相続することを「法定相続」といいます。
相続人
民法では相続できる人(相続人になれる人)の範囲を定めており、これを「法定相続人」といいます。法定相続人となるのは、亡くなった人の配偶者と一定の血族(子や父母、兄弟姉妹など血縁関係のある人=「血族相続人」)です。子には養子や法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子も含まれます。胎児も死産の場合を除き相続人に含まれます。
なお、内縁関係のように事実婚の状態にある人、離婚した元夫や元妻は法定相続人に含まれません。
相続人の範囲と順位
亡くなった人の配偶者は常に相続人となります。血族相続人には、民法で次のとおり相続人の範囲と順位が定められています。
相続人の範囲と順位については以下の記事をご参考ください。
相続分とは?
複数の相続人がいる場合、相続財産は相続人全員で共有することになります。相続分とは、相続財産に対する各相続人の持分(割合)のことをいいます。相続分には、「指定相続分」と「法定相続分」があります。
指定相続分
指定相続分は、亡くなった人が遺言によって相続分を指定したもので、法定相続分よりも優先されます。
法定相続分
法定相続分は、民法で定められた相続分のことで、どの相続人がどれだけ遺産を相続するのかの割合が次のとおり定められています。なお、これは相続人同士の遺産分割の話合い(遺産分割協議)で合意ができなかったときに適用される遺産の分割割合ですので、必ずこの割合で遺産分割をしなければならないわけではありません。
| 相続人 | 相続する割合 |
| 配偶者のみ | 配偶者:全部 |
| 配偶者と子 | 配偶者:2分の1、子(全員で):2分の1 |
| 配偶者と父母 | 配偶者:3分の2、父母(全員で):3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:4分の3、兄弟姉妹(全員で):4分の1 |
相続の方法
相続の方法には、大きく分けて「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。
単純承認
単純承認とは、相続人が被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことです。特に手続きを行わなければ、単純承認となります。
限定承認
限定承認とは、被相続人の債務がどの程度かわからず、財産が残る可能性もあるなどの場合、相続人が相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産の債務を引き継ぐ相続方法です。相続した財産以上に債務を引き受ける必要はありません。
相続はプラスの財産だけではなく、借入金や未払金などのマイナスの財産を引き継ぐこともあります。しかし、限定承認を行えば、相続財産の範囲内でマイナスの財産を引き継げばよいため、相続人は必要な財産を手元に残すことができます。
相続放棄
相続放棄は、相続人が被相続人の財産や債務を相続する権利を放棄することです。マイナスの財産が多く、引き継ぎたくない場合には、相続をすべて放棄することができます。
また、限定承認と同様、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。
遺言相続とは?
遺言は、ご自身が亡くなったときに財産をどのように分配するか等について、自己の最終意思を明らかにするものです。亡くなった人(被相続人)が生前に作成した遺言書が存在する場合は、基本的には遺言者の意思に基づいて財産が分配されます。これを遺言相続といいます。
遺言相続のメリット
- 遺言相続では、民法上相続人に含まれない人(内縁関係の人、血縁関係にない人や団体など)に遺産を分配することができる。
- 自分の意思で遺産の分配を決めることができる。
- 特定の遺産を特定の相続人に相続させることができる。
- 相続人同士の争いを避けることができる。
一般的に多く用いられる遺言の方法としては、遺言者自らが手書きで書く「自筆証書遺言」と、公証人(国の公務である公証作用を担う実質的な公務員)が遺言者から聞いた遺言の趣旨を記載し、公正証書として作成する「公正証書遺言」の2種類があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者本人が、遺言の全文、日付及び氏名を自ら手書きして押印します。なお、財産目録については、パソコンや代筆で作成することができます。ただし、その場合には財産目録の全てのページに署名と押印が必要になります。
また、偽造や改ざんを防ぐため、遺言書を保管していた人や遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、開封する前に家庭裁判所に遺言書を提出し、検認(※注3)を受ける必要があります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場等で2人以上の証人の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて、公証人がその内容を記載して作成する遺言書です。自分で書く自筆証書遺言と比べ、要件を満たしていないなどの理由で無効になるリスクが少なくなります。なお、遺言書の原本は、公証役場で保管され、家庭裁判所の検認は不要です。
相続手続きの流れ
身内のだれかが亡くなり、相続が発生したら、どんな手続きをどのような順番で行わなければならないか、相続に伴う必要な手続きとその流れをざっと確認しておきましょう。
| 1.死亡届の提出 [7日以内] ⇓ 2.健康保険・介護保険の資格喪失届、年金の受給停止などの届け出 [14日以内] ⇓ 3.遺言書の有無の確認、財産の洗い出しと財産目録の作成 ⇓ 4.(必要に応じて)相続放棄・限定承認の申述 [3カ月以内] ⇓ 5.被相続人の準確定申告 [4カ月以内] ⇓ 6.(遺言書がない場合)遺産分割協議 ⇓ 7.取得した遺産の相続手続き・名義変更など ⇓ 8.(必要に応じて)相続税の申告・納付[10カ月以内] |
まとめ
相続手続きは、思いのほか煩雑です。 しかし期限を過ぎてしまうと追徴金がかかってしまったり、権利を主張できなくなったりする場合もあります。
仕事で忙しい方や体調のすぐれない方、ご高齢で手続きが難しいと思われる方は、専門家の相続手続きサポートのご利用もご検討下さい。